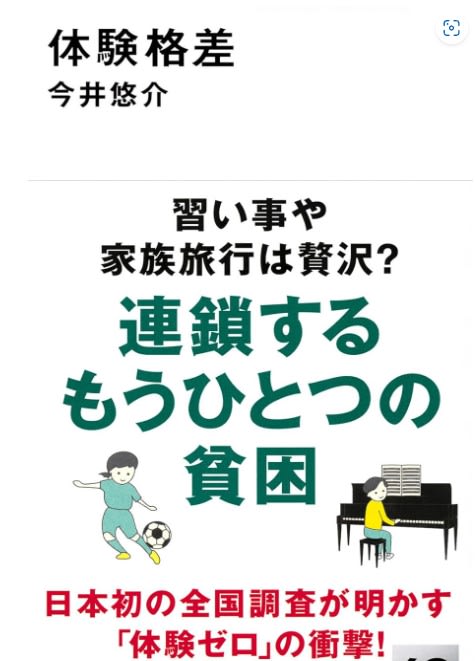自分の娘が小4のころ、2桁(けた)引く1桁、例えば13ー6=などを答え求めると指を使って計算した。そのに驚いて、算数特訓を何度もしたことを強く記憶している。
そこで小学校入学前の孫娘にも2桁引く1桁の同じような計算をいくつか出してみた。11-3や12-4などは即答するのだけれども、13-7や15-8などになるとちょっと時間がかかる。どうやって計算しているか聞いてみると15-8なら、8から5引いて3、10から3引いて7という答えを出していた(減減法:引き引き算)。そこで、15-8では、10から8引いて2、5に2を足して7になる(減加法:引き足し算)ことを説明した。こちらのほうが早く計算できると説明するが、「なに言ってるかわかんない」と拒否された。

しばらく日にちが立って、もう一度、15-8は?とたずねると7と即答するようになっていた。計算の練習をしたみたいで、ある程度答えを覚えたようであった。それが一番早い計算力増強と思っていたので、昔、娘にもそうやって覚える特訓をした。中学生や高校生、されに塾の保護者会などでは大人にも、この2桁引く1桁の計算スピードを実施してみた。やはり、このスピードが速ければ成績上位であることが明白になった。保護者には、計算スピードの遅いお子さんには、この<2桁引く1桁>特訓をお勧めした。
もう一度、孫娘に減加法:引き足し算を説明すると、簡単に理解できていた。6歳前後の学習能力の発達はすごいものだと感動した。
さて、「9歳まで決まる算数が得意な子になる本」を読んでみた。
この本でも、1年生の最大の難関が、「繰り下がりの引き算」と説明されていた。高学年になったり、中学、高校生になっても計算が遅い、または、間違える、それで数学が不得意科目になる、それで勉強が嫌になるという生徒を多く見てきたそうである。この「繰り下がりの引き算」の克服を親として見過ごすわけにはいかない。さもなければ大いなる禍根を残すことになる。
ちなみにわが娘は、単純な引き算特訓を実施した後、ぐんぐんと成績を伸ばし、国立大学に入学できるまでになった。

さて、次なる壁が九九である。小2の壁である。
この壁をじゅうぶんな訓練なく見過ごすと2桁割り算でつまづくことになる。この2桁割り算が小学校算数の最大の難関だとある。このつまづきが、算数嫌いの最大の原因の一つになる。そのための九九だが、単に暗唱できればいいと思っていたが、以下のような訓練方法が示されていた。
まず、「上がり九九」「下がり九九」(暗唱1分をめざす)さらに、「段ごとバラ)バラ九九」そして「完全バラバラ九九」(目標1分以内)で鍛える。

さらに、「割り算64問」(=バラバラの2桁割る1桁が64問)で九九のスキルアップ完璧となる。
なるほどと思うとともに、このようなトレーニングをしなかったが故の、自分自身の九九の不完全さが身にしみて、こたえた。

九九を完全に乗り切ることで、小3の壁「割り算」を簡単に乗り越えられるであろう。ちなみに、小5の壁は、「割合の文章題」だそうである。
「9歳まで決まる算数が得意な子になる本」には、算数ポスターが付録でついていたり、お風呂でかさ(リットル、デシリットル、ミリリットル)の実践的体験学習や野菜を切るお手伝いから学ぶ立体図形など面白そうな勉強法がたくさん示されていておもしろい。
新小学1年生を持つ保護者の方にぜひおすすめしたい1冊である。さらに、小中学生のわが子が、計算力が弱い、遅いと感じている保護者にも、早めの取り掛かりたい手引書、参考書として参考にしてほしと思う。