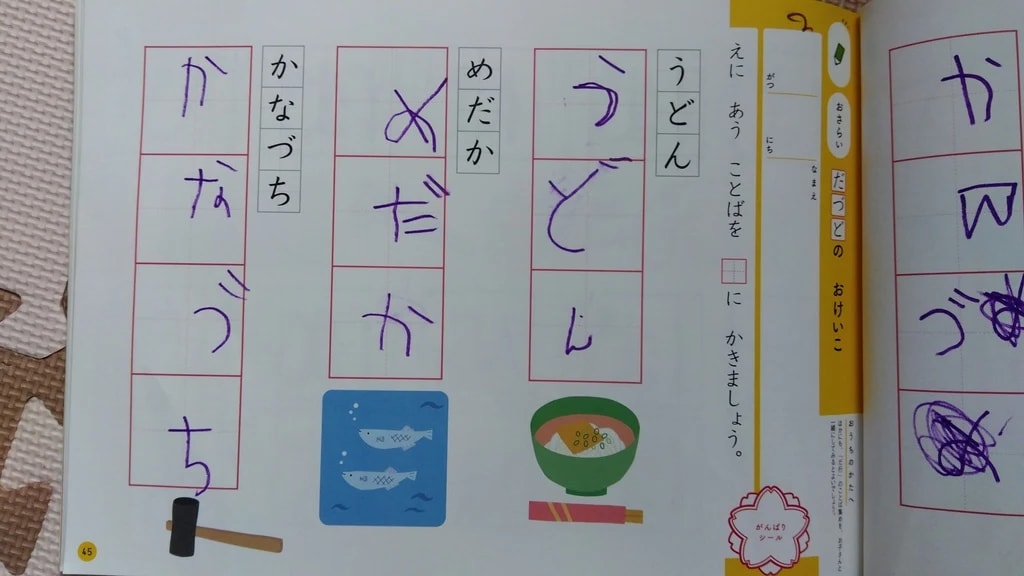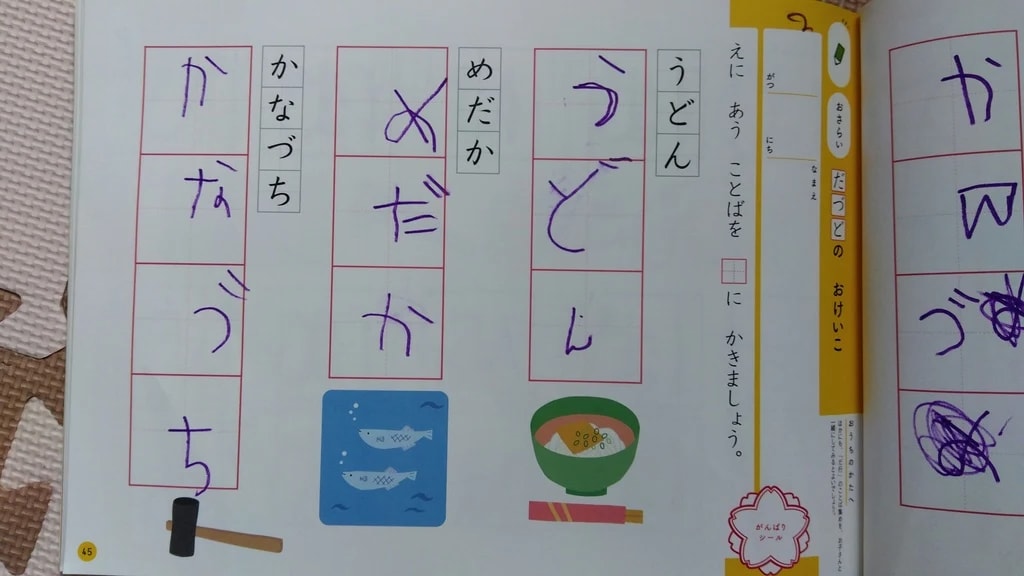私の家には3台のAmazonスマートスピーカー「Echo」がある。「アレクサ」と話すだけで、見覚まし、タイマー、家電やエアコンのオンオフなどに利用している。一番よく利用するのは、夕食を作るときのバックグランドミュージックとして音楽を流すことだ。「アレクサ、音楽を流して」とか「アレクサ、スムースジャズをかけて」などと言うと「お気に入りの~」と前置きをして、かってに音楽を流してくれる。 ただし、無料版を使っているので、特定の曲をかけることができない。たとえば、「『Let it go』(アナと雪の女王)をかけて」と言うと、「関連した歌をかけます」という返事が返ってきて、それなりの音楽が流れる。一時期、有料版を使っていた時は、そのものずばりの曲が流れていたが、さすがに無料だとずばりと帰ってこない。そこで、試しに「アレクサ、スポティファイで『アンパンマンのマーチ』かけて」と言ってみる。Spotfy経由だけれども、関連する音楽が鳴るだけである。残念。
妻が「アレクサ、『アイドル』かけて」と言うと、いつものように「関連した曲を~」となる。妻曰く、「アレクサは言うこときかないのよね。」そこで、5歳の孫も「アレクサ、言うこときかない」と大きな声で言う。アレクサの即座に答え、「大人の言うことを聞かない子がいます。悪い子には、怖い思いをしてもらいます。[言うこと聞く]と言うまで終了できません。鬼とおばけ、どちらを呼びますか?」 5歳児「怖い~」突然の声、それも鬼とおばけという言葉に恐怖を感じ私のところに逃げてきた。
無言の5歳児に
アレクサ曰く、「あ、赤鬼がむかっています。言うことききますって言ってください。言わないとまた赤鬼を呼びます。」
「言うこと聞きます」と5歳児。
一同、爆笑で幸せなひと時を過ごしました。

『なんか』についてもう一度。
あまりTVドラマを見ないのだが、最近見ているドラマとして、『ラファエルとアストリッド』が終了し、とても寂しい想いをした。さらに「さよならマエストロ」も「不適切にもほどがある」もそろそろ終了である。その「不適切にもほどがある(3/2放送分)」で「君の発言、『なんか』が多いね」という場面があった。このドラマにその場面を挿入する意味はなんだろうと思ってしまったが、やはり、今の若者の言葉として『なんか』を多用するのだろうと想像した。
5歳の女児が『なんか』を多用するのは、母親の真似だろうが、令和時代の若者の言葉でもあるのだろう。TikTok での、永井ローラさんのおしゃべりをまた聞いてみた。やはり、いたるところに『なんか』がでてくる。しかし、この『なんか』は、何にでもいつでも使えるので便利なのであろう。しかし、濫用され、連発されると耳ざわりな言葉として響いてくるのは確かだ。「なんかいつでも使えるし、なんか若者風にもつかえるし、なんかいいよね!」
私が、5歳の孫によく使う言葉があった。
娘の職場で「『バカちん』は方言だ」と盛り上がっているのを聞いて、「うちの父親がよく『バカちん』と言う」と話したことを私に伝えた。『バカちん』が方言であることを私は知らなかった。昔、東京で「お金をこまめて」と言って「?」が返ってきたことを思い出した。「こまめて」→「くずして」である。
『バカちん』は、海援隊の「母に捧げるバラード」で使われたり、金八先生が生徒に使う言葉として全国的に有名になった。「早く学校へいってこんか、このバカちんがくさ」
ただし、「バカ」や「アホ」のよりもずっと柔らかく、基本的に「バカチン」という言葉には、「子供や学生などが何か悪いことをして、その悪事について愛情を込めて叱ったり怒ったり(注意したり)している、というニュアンスが込められている(「意味解説辞典」より)。」
私も、孫のいたずらや悪いことをしたと時に対して『バカちん』という。怒られた孫も笑う。
日々成長する幼児を見ていると、言語の習得の楽しさと難しさを知る。ただし、笑いがいっぱいであることがすばらしい。

<ちょっとお出かけ>
太宰府天満宮に行き、九州国立博物館に行ってきました。
「長澤芦雪」展に行きました。天満宮も博物館もすごい人出でした。


すごい迫力に感動!