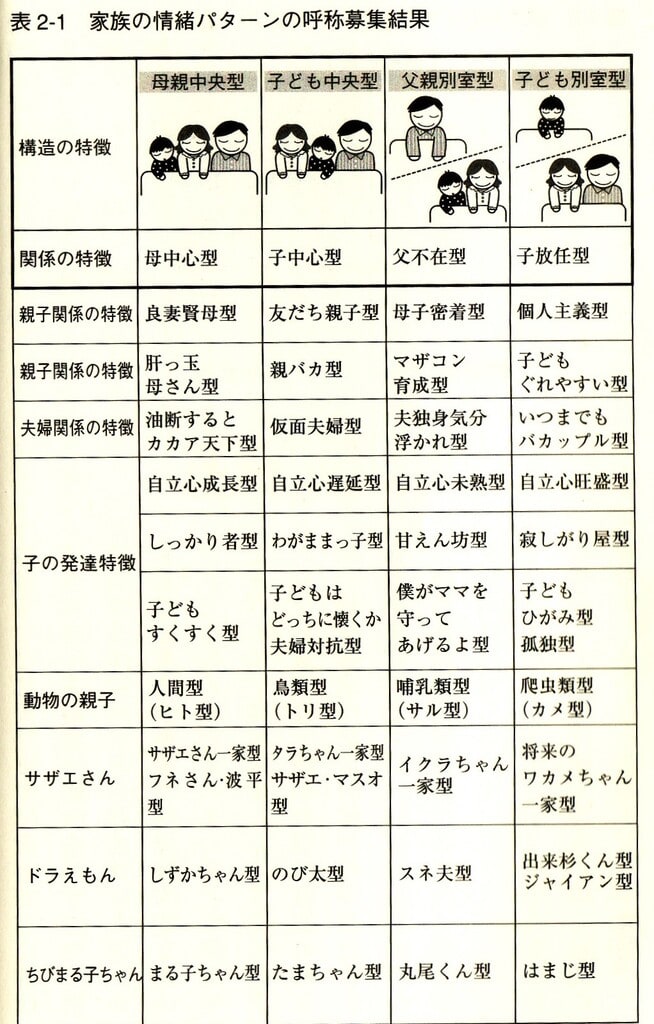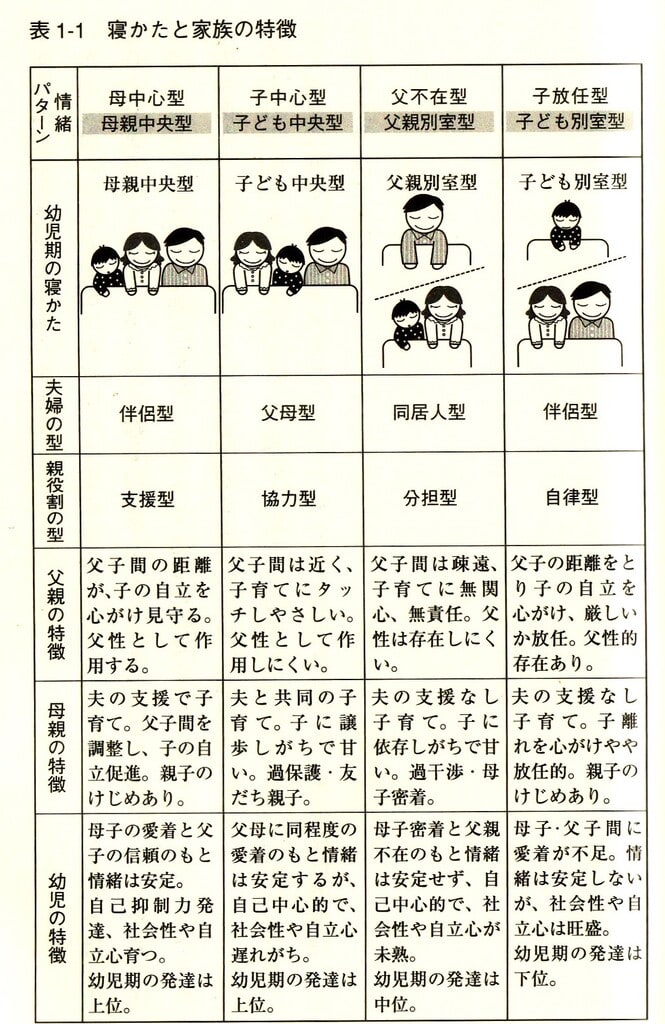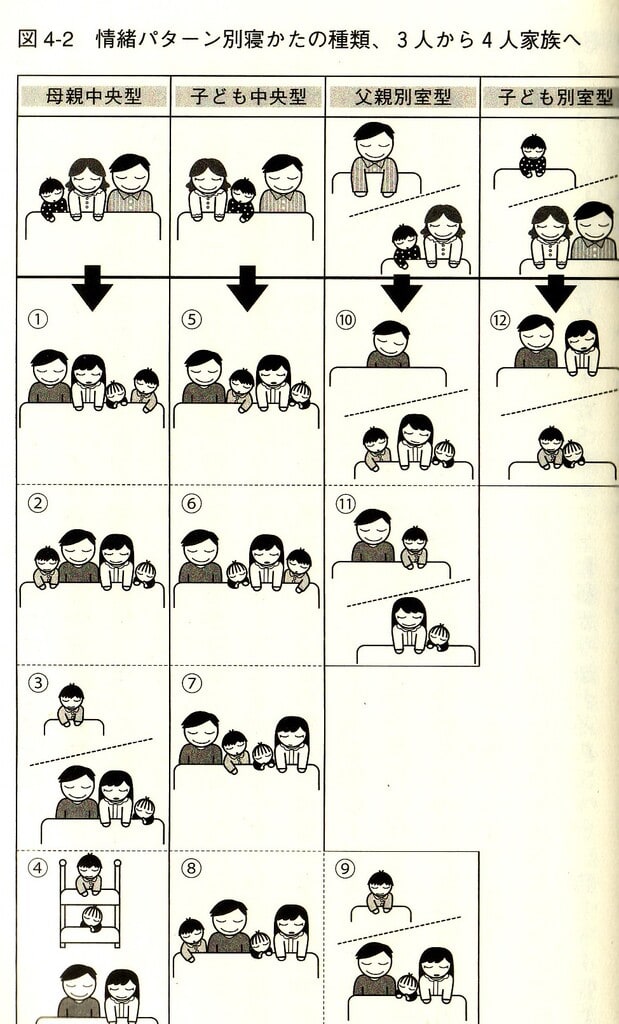Fラン大学でも東大に勝てる 逆転の就活=吉井 伯榮 (著) 2020
あるネットで、「Fラン大学」に行くのは、まったくの無駄と言い切る記事を見た。けっこう有名人の発言である。Fラン大学に行くぐらいなら高卒で働く方が有意義だと主張している。個人的に同感する部分も多い。
Fラン大学とは、偏差値ランキングに掲載されない大学のことで、偏差値が35以下の場合が多い。偏差値フリー、偏差値BF・ボーダーフリー大学、つまり、試験の点数によって入学ができないということがない大学、ある意味、誰でも入学できる大学のことを表している。(名前さえかければ合格できるとは、言えないので注意が必要である。)
この本では、そういう大学に入学した学生を100%一流企業を含め、多くの企業に合格させた実績・方法を詳しく述べてある。

指導の初期に、「日本の白地図に知っている県名を書け」というテストを出した。15名中、最高の成績が13県、最低では3県しか書けない学生がいた。小学生以下の知識量である。いわんや、日本で働く若者が、自分の近県しか知らないでは、働かせようにも働かせない。福岡県の公立高校入試では、九州人にとって最も疎い地方である関東の県名や県庁所在地が頻繁に出題された。中学生にも劣るこの学生たちを一流企業に送りこもうというゼミでの学習。夢のような話が実現するのだろうか。
このゼミでの主な戦略としては、以下のようなものが示される。
▼まずは、自分の価値を認め、自信を持つことから始める。自己肯定感が高まると、面接などでも堂々と自分の意見を伝えることができるようになる。
▼4コマ漫画を使ったエントリーシートを作成する。自分の経験やスキルを、わかりやすく4コマ漫画に仕立てて、企業にアピールする。視覚的に訴えることで、自分の印象を強く残す。
▼志望企業の絞り込み。自分の興味関心や強みに合った企業を12社に絞り込み、効率的に就職活動を行う。
▼面接対策。面接で求められているものを理解し、模擬面接などを通して、実際の面接に備える。
▼企業とのコミュニケーションを円滑に行うために、コミュニケーション能力の向上を目指す。
▼逆質問の活用: 面接の最後に、企業に対して質問をすることで、自分の熱意を伝えるとともに、企業への理解を深める。
以上のような訓練を大学3年生の初めから開始し、3年生の終わりからの就職活動に間に合わせる。
この本を読むことで、就職すること、自己実現すること、合格することなどに自信をもって進むことができるようになる。つまり、就職活動に対する不安を解消できるようになり、具体的な行動計画を立て、自信を持って就職活動に臨むことができる自信を獲得できるようになる。
塾講師として、高校への推薦入試の合格術を指導してきた。個人的には、ほぼ100%に近い合格者をだした。自分の指導には、自信を持っていたが、当時、この本を読んでいたら、違った指導を行うことができたのではないかと思ってしまった。わくわくさせる方法論がいっぱいである。
< 自己分析の方法 企業研究のポイント 面接での立ち振る舞い 内定獲得後の対応 >など高校入試や大学入試にも活用できるポイントが多くある。
Fラン大学生だけでなく、すべての大学生、そして、中学生や高校生にも是非読ませたい一冊である。私も大学生の時に読みたかったなぁ。