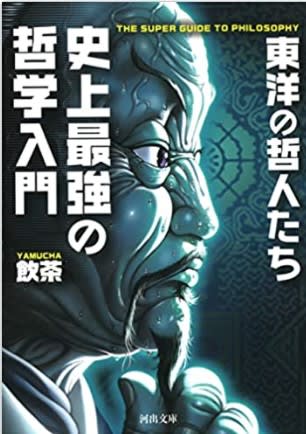「あした死ぬ幸福の王子」飲茶著を読んだ。 副題は、ストーリーで学ぶ「ハイデガー哲学」

この本を買いに走った理由は、2つ。
飲茶氏の著書、特に哲学に関する多くの本は、読みやすく、分かり易く、おもしろいとつくづく感じていたからだ。特に、『「最強! 」のニーチェ入門: 幸福になる哲学 』などは、勇気づけられた人も多いだろうと推測される感動の本だと思う。
もう一つの理由は、大学時代、若い教授にハイデガーの「存在と時間」を3回読めといわれて、懸命に3回読ん経験がある。その結果、わかったことは、2つ。ひとつは、何が書いてあるかほとんど理解できなかったこと。2つ目は、「お互いが理解できることは何か」をひとつひとつ確認しながら、一歩一歩話を進めるという途方もないしつこさを見せつけられたこと。
とにかく、わからないまま。その教授の次の示唆を待っていたが、翌年、教授は、アメリカへ留学し、結局、2度と会うことがなかった。

目次に目を通すと懐かしさがあふれてきた。
「「「「「「「「「「
< あした死ぬ幸福の王子 >
目次
序章 宣告
序章 宣告
第1章 死の哲学者
もし明日死ぬとしたら、何をする?
「死とは何か?」を考える前に
人間の思考の「限界」とは?
「存在」とは、思考の土台である
人はなぜ死を恐れるのか?
「死とは何か?」を考える前に
人間の思考の「限界」とは?
「存在」とは、思考の土台である
人はなぜ死を恐れるのか?
第2章 現存在
「人間とは何か?」ハイデガーの答え
人間は「いつか必ず死ぬ不幸な存在」なのか?
人間は「いつか必ず死ぬ不幸な存在」なのか?
第3章道具体系
人間以外は、すべて「道具」である
「道具」がなければ、私たちは生きていけない
では、人間も「道具」なのか?
人はみな、「幸福な王子」として生まれてくる
「道具」がなければ、私たちは生きていけない
では、人間も「道具」なのか?
人はみな、「幸福な王子」として生まれてくる
第4章 本来的生き方
多くの人間が「非本来的」に生きている
人間と動物の「決定的な違い」とは?
「他者の視線」で人生を決めていないか?
死が持つ五つの特徴
死がもたらす「思いがけない贈り物」とは?
人間と動物の「決定的な違い」とは?
「他者の視線」で人生を決めていないか?
死が持つ五つの特徴
死がもたらす「思いがけない贈り物」とは?
第5章 死の先駆的覚悟
大切な人の余命を知ったら、あなたはどうする?
死など忘れて、毎日楽しく生きてはいけないのか?
今この瞬間も「死」を覚悟して生きよ
死など忘れて、毎日楽しく生きてはいけないのか?
今この瞬間も「死」を覚悟して生きよ
第6章 良心の呼び声
「良心」がなければ、死とは向き合えない
あなたを襲う「無力感」の正体
何気ない日常の中で、目をそらしてはいけないもの
あなたにとって、「かけがえのない存在」とは?
「良心」がなければ、死とは向き合えない
あなたを襲う「無力感」の正体
何気ない日常の中で、目をそらしてはいけないもの
あなたにとって、「かけがえのない存在」とは?
第7章 時間(被投性と企投性)
「二つの時間」を比較する
過去とは、勝手に放り込まれた世界
未来とは、ひとつしか選べない世界
現在とは、無力さを突きつけられる世界
あなただけが選べる、たったひとつの可能性
人は「絶対に手に入らないもの」を求めている
過去とは、勝手に放り込まれた世界
未来とは、ひとつしか選べない世界
現在とは、無力さを突きつけられる世界
あなただけが選べる、たったひとつの可能性
人は「絶対に手に入らないもの」を求めている
第8章 世界内存在
「死の恐怖」とどう向き合えばいいのか?
終章 幸福の王子
終章 幸福の王子
エピローグ
」」」」」」」」」」」」」」
」」」」」」」」」」」」」」

まるで絵本を読んでいるような雰囲気で始まる。サソリに刺されて死ぬ運命の王子、「明日、自分が死ぬのだとしたら、それが〜」よくあるパターンの通俗小説のような出だしから、深刻さを増す限界状況を次々と経験し、物語が進行する。 ある老人との出会いから、ハイデガーの哲学を知る。物語が、哲学的になる。
うまくストーリーにのせて、難解なハイデガーの哲学を一般の読者に分かりやすく解説してくれて楽しくなる。もし、「死」や「生き方」みたいなところでモヤモヤしているなら読む価値は大きいと思う。
ーーー
今思うに、「存在」という認識論が、「死」を境に、「どう存在するか」、つまり、どう生きるかという「倫理」の問題にすり替わってしまっていると感じる。そのため、ハイデガーも当時の「実存主義」哲学者のひとりとしてくくられるのだろう。ただし、第一次世界大戦と第二次世界大戦での数百万の虐殺と戦死を背景にした時代であれば、当然の哲学だったかもしれない。そして、今、第三次世界大戦前とも言えそうな現在に「私たちの存在」をもう一度、立ち止まって考えよう、とハイデガーが伝えているのかもしれない。