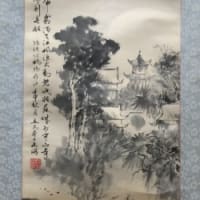孫子 九地第十一
孫子曰。凡用兵之法,~略~
故善用兵者、譬如率然。率然者、常山之蛇也。撃其首則尾至、撃其尾、則首至、撃其中、則首尾倶至。敢問、兵可使如率然乎。曰、可。夫呉人與越人相惡也。當其同舟而濟、遇風、其相救也、如左右手。是故方馬埋輪,未足恃也。齊勇如一、政之道也。剛柔皆得、地之理也。故善用兵者、攜手若使一人、不得已也。
~略~。

為時 敢て問う、兵は率然の如くならしむ可きか、と。
為時 では、ここから先は頼通様がお読み下さいませ。
頼通 (暗唱)曰く。可なり。夫れ呉人と越人とは相悪(にく)むも、その舟を同じくして済(わた)り、風に遇うに当りて、その相救うこと、左右の手の如し。
為時 お見事でございます。
(道長登場)
為時 左大臣樣。
頼通 父上。
道長 はかどっておる樣だな。
為時 やあ、ご聡明の程、驚くばかりございます。
道長 ははは。私の子とは、思えんなあ。