文系オヤジの禁断の領域,特に確率解析へと思考の道が迷い込む.実際には,ここはどう表現したらいいのだろう.思考の道に随伴するような,奇妙にかすったような存在を感じることがある.当然,道の近辺に現れた,未知の存在だから,はっきりと,道に取り込んで考えを進めたいと思う.かするような存在を意識しながら,どっかで取り込んでやろうと思う.思考を完備化しようという指向が働く.完備化とは,「私は有限の存在であり,有限の存在であるからこそ,無限というラベル(♾)を備えた存在空間へ繋がるのだ」というと,キリスト教信者ぽくなるだろうか.有限の値を持つ何かとして,思考を観察する立場に立っているような感じである.自分自身のパロディー思考なのに,と自己ツッコミしたくなるが,そんな感じもあるのである.思考することは不思議なもので,はっきりとした持続時間も持たないくせに,時折,かすったような何者かの存在を暗示する.その存在は,思考を制御する,例えるならば,トリックスターのような意味をまとっているように直感させるようなものである.
かすったような存在を心象しようとして,私の思考の道が有限区間の集まりだとして,一様な比重のもとで,同値な類の分類に収束するようなところにいる何者かの存在ではないかと,当たりをつけようとしたりする.「モジュラー要素のような方ですか」と尋ねたとしても,返事などするわけがない.「私の思考は,マルコフ過程のスケールに入ったとか」と問い直しても,返答などあるはずがない.思考することは,とりわけオヤジの思考は,孤独なのである.--- modular(モジュラー)とmoduli(モジュライ)が区別されていないからだろうか.
確率解析は,伊藤解析のマルチンゲール理論に基づく一般化のことであるということであれば,まずは,伊藤解析のお勉強から始めるのが順当である.
下手の考え休むに似たり,ということで,とりあえず,『数学辞典 第四版」の「確率微分方程式」の項目からコピペする.

確率微分方程式論の発展も含めた概要だろうから,次のコピペも含めて,目標というか目安ということになるだろう.

どっか,私の「思考の束」に似ている気がするし,あるいは,確率微分幾何的な類似も思ったりする.理系だったら,「これを,ちゃんと,数学的あるいは確率論的に理解しろよ」,となるのだろうが,文系オヤジだから.
F_tに適合するような結合確率分布の近傍系を設定するような操作,あるいはそのような写像を作ることを,「一様」確率積分とは言わないのだろうか.「一応」確率積分ではなくて.連続な確率過程のCauchy列の極限を確率積分ということだそうだから.素数空間上のループ空間の類の列の極限とか.私の思考の束は,造語する.ふざけているわけじゃないが,こういう場面は,何故か,素数の影がチラつく感じを受けるのである.一様性は別名,近域系(systeme d'entourage)というらしいが,確率論的な<近傍>くさい.「これらの仕事(確率解析の創出)の背景にある私の考えは,レヴィ過程をマルコフ過程の,いわば接線として捉えることにありましたが,...」(伊藤著『確率論と私』)をパロって,確率過程の法線とか.
渡辺信三著『確率微分方程式』から, のブラウン運動
のブラウン運動 による確率積分
による確率積分

とは,

なる写像で,定義は次のとおりである.(定義を与えるのに準備があって,それが満たされたとして,)  が
が のCauchy列をなし,ただ一つの(極限確率過程に)収束する.それを
のCauchy列をなし,ただ一つの(極限確率過程に)収束する.それを と定義する.この
と定義する.この を
を の確率積分といい,
の確率積分といい,

と表すことが多い..... 「このようにして,確率積分 はマルチンゲールとして,したがって一つの確率過程として定義されたが,tを固定したとき
はマルチンゲールとして,したがって一つの確率過程として定義されたが,tを固定したとき はΩ上の2乗可積分な確率変数であり,この確率変数自身を確率積分と呼ぶことも多い」,ということだから.
はΩ上の2乗可積分な確率変数であり,この確率変数自身を確率積分と呼ぶことも多い」,ということだから.
 とか,
とか, というより
というより なんて写像作ったら,どうなるのだろう.nets(列)がnest(入れ子)になるとか.I(Y)で,IはIntegralの頭文字のIなのだろうが,形式的には,ブラウン運動Bによって生成される増大情報系{F_t}に適合する{Y_t}に対して定義された確率積分
なんて写像作ったら,どうなるのだろう.nets(列)がnest(入れ子)になるとか.I(Y)で,IはIntegralの頭文字のIなのだろうが,形式的には,ブラウン運動Bによって生成される増大情報系{F_t}に適合する{Y_t}に対して定義された確率積分
を,一定のルールで,記号で表したものだから, 形式的には,そういう写像も,考えられそうだから.モジュライ空間(moduli space)上の確率解析的な.幾何構造と解析構造が結びついていそうだから.『数学辞典』では,S.K. DonaldsonとM. Gromovとか,Seiberg-Witten不変量とかが代表的らしい説明がある.確率解析の幾何構造とmoduliの幾何構造が連星しているかのような,感じを受けたりする.パロって言えば, とか
とか の意味付けとか,関連しそうである.私のパロディー思考の束も確率解析の近域(entourage, ア-ントゥラージュ,ァントゥァ-ジュ?)付近には近づいている感じはしないだろうか.「幻覚よ」と言われそうだが,確かに,これをちゃんとやれと言われたら眩暈(めまい(vertigo), ひねって,「垂直の近域にむかへ」なんてシャレに偶然たどり着く)がしそうである.
の意味付けとか,関連しそうである.私のパロディー思考の束も確率解析の近域(entourage, ア-ントゥラージュ,ァントゥァ-ジュ?)付近には近づいている感じはしないだろうか.「幻覚よ」と言われそうだが,確かに,これをちゃんとやれと言われたら眩暈(めまい(vertigo), ひねって,「垂直の近域にむかへ」なんてシャレに偶然たどり着く)がしそうである.
「σ加法族 はDynkin族
はDynkin族 なので,当然,
なので,当然, である」とあるが,確率積分が,解析数論の問題,「イデアル類の数hの計算」(高木『初等整数論』)の問題にどっか類似している感じは,どうなのだろう.いまTを二次体におけるt≧N(J)なる(ある)イデアルJの総数として,
である」とあるが,確率積分が,解析数論の問題,「イデアル類の数hの計算」(高木『初等整数論』)の問題にどっか類似している感じは,どうなのだろう.いまTを二次体におけるt≧N(J)なる(ある)イデアルJの総数として,

である,から,κは既知だから,hを求めることは左辺の極限値を求めることに帰するとあるが, の関係が導かれる,ここで
の関係が導かれる,ここで

で,二次体K(√d)に属する単数である.dは二次体K(√m)の判別式である.不定方程式論ぽい感じのやつである.また, のような関係(左辺はDedekindのゼータ関数)が,色々なゼータ関数やL関数について成立するのではという問題とか.「似てる感じがする」というだけだから,なんなんだが,リーマン予想とか.おそらく,こういう感じの関連はあるのだろうが,正確には知らないので,言ってみた.「確率解析で,リーマン予想を解かないか」といいそびれたのだろうか(「河田敬義君の思い出」,『確率論と私』).
のような関係(左辺はDedekindのゼータ関数)が,色々なゼータ関数やL関数について成立するのではという問題とか.「似てる感じがする」というだけだから,なんなんだが,リーマン予想とか.おそらく,こういう感じの関連はあるのだろうが,正確には知らないので,言ってみた.「確率解析で,リーマン予想を解かないか」といいそびれたのだろうか(「河田敬義君の思い出」,『確率論と私』).
私の思考の道の束を偶然現象に結びつけようとすることに無理があるのかもしれない.うっかりではあるが,それもパロディーの前提ではある.無理でないとすれば,パロディーではなく「確率論」になってしまうので.私の本来の趣旨からずれてしまう.「確率論」という厳密な理論体系はちょっと傍において,パロディーの精神を貫くとすれば,次のようなことも言えるのじゃないだろうか.
私の思考の持続時間を仮に区間と見ることにすれば,私の思考と偶然現象との結びつきを考えることは,思考の持続時間という区間のmixingのようなものだから,ある種の拡散過程である.拡散過程は,ブラウン運動が均質な媒質中の微粒子の運動を記述するのに対して,必ずしも均質でない媒質中の微粒子の運動や熱の伝導を記述するもので,ブラウン運動を一般化したものである,ということだから.T=[0,∞)として,T∪{∞}上に値をとるΩ上の確率変数τは,任意のt∈Tに対して,{τ<(または=) t} ∈ F_tが成り立つとき,停止時刻(stopping time)またはマルコフ時刻(Markov time)という,だから,私の思考の道も,ある種の射影確率過程,停止時刻の増大情報列的な,になるのではないか.偶然現象の広いクラスで,このような性質が保たれるとすれば,パロってみることも案外,無駄ではないかもしれない.思考の黒体輻射なんてパロりたくもなるわけである.
葦に生まれたことが罪ではない.葦にしたって,偶然を纏って靡(なび)いているのだから,たまたま,理科室の掃除当番でやってきた小学生の私の目に映っただけなのだから,「考える葦」という対象にされたことは,葦の責任ではない.私は考える葦なのか,と考えなければならないは,人間の方なのだから.人間とは,「人間は考える葦である」とはどういうことなのかを考え続ける存在のことである,とパロってみる.パロるしかないのは,当時,昼休みにプロレスごっこして遊んでいたのも私だから.今時なら,めちゃ叱られるだろうが.
ところで,この葦,実際には,水槽に生えた,サビた矢車のような感じのある細い茎草だったが,が「考える葦」なのか.考えているのは人間だから,まるで,時間が止まったかのように,このアシを囲む光景に垂線を引くかのような記憶として刺激されるからではないか.アシを囲む光景が固定されて,立体化された時間の中で,光景が揺らいでいく感じを受けるからではないか,という印象を持ったことを覚えている.ススキがお化けに見えるのと似た,ワビサビぽい感情が瞬間届いたような感じである.私は総称としてのアシに侘び寂びを教わった,あるいは,私のアシは侘び寂びを形作った,ということになるのだろう.アシであって抹茶アイスではない.
私の思考は零(ゼロ)なのか.アシはアシとして凛としているが,見ているのは私である.私のゼロは, 凛とした葦の周囲を切り取るために,私の視界の余剰の部分を,零なる不可視に変えたのか.私の思考は,カメラで写真を撮る時のように,フォーカスを定めて,他の周囲の映像要素を切断していく.写真の撮り手は,何に焦点を当て,どのように周囲をcutしていこうかと,視線を揺らしている.私の思考は,映像芸術である,「イマージュ」はフランスのエロ映画である.
パロりすぎると単なるおふざけになるが,ほんとは,次の箇所をパロりたかったのである.
「 の上の分布Pに対して,その特性関数
の上の分布Pに対して,その特性関数 を
を

と定義する. において,ある有限個の座標を残して他を0とおいたものを
において,ある有限個の座標を残して他を0とおいたものを の切断(section)という.Pの特性関数の切断は,Pの射影(2.12)の特性関数である.KOLMOGOROFFの定理(§2)は次のようにいいかえられる.
の切断(section)という.Pの特性関数の切断は,Pの射影(2.12)の特性関数である.KOLMOGOROFFの定理(§2)は次のようにいいかえられる.
 の関数
の関数 の任意の切断が特性関数ならば,
の任意の切断が特性関数ならば, は
は の上のある分布の特性関数である.しかもこの分布は唯一通りに定まる.
の上のある分布の特性関数である.しかもこの分布は唯一通りに定まる.
このことを用いて無限次元の正規分布を定義することができる.」(伊藤清著『確率過程』)
(2.12)は,「Pを の上の分布とせよ.相異なる
の上の分布とせよ.相異なる に対して,
に対して,

なる の上の分布
の上の分布 を定義する.これを分布Pの射影という.」である.
を定義する.これを分布Pの射影という.」である.
自然数の集合Nを正の整数Z+のように表すなら,自然数が,まるで,極限系列へミキシングするような操作を表す記号であるかのようなイメージである.しかも,そういう記号化の二段突きのようなイメージである.添字化といえばいいのだろうか.正の整数をZ+と記すなら,当然,整数全体の集合は,Z={Z-}+{0}+{Z+}のように分解されるわけだが.
重力の系列も停止をくり返しているのだから,重力理論も重力の確率過程解析論のようなものである.類別作用のフィルトレーション(線形濾過)のようなものであるようなことを読んだ記憶がある.テンソル化のような選出作用とか, スペクトルとか.確率論の所々に,伏流のように流れが続く感じの,読む方は,理解が淀む感じの部分がある気がする.{0}+{Z+}を改めて{Z+}と書くような感じなのだろうか.つまり,N'={0} +{1,2,3, ....}={0, 1,2, ...}ということだから.私の思考がエルゴード性を獲得していくような,なんちゃってプロセスである.なんちゃってプロセスではあるが,下手すると,最新の宇宙論につながっているかもしれない.「私の思考のプロセスは宇宙論である.宇宙論の解析学である.」ということにたどり着く.なんちゃってではあるが.
確率積分に対して確率微分の方は,説明がなんかややこしく感じる.商空間の極限を特徴づけるのは,差集合なんてことなのか,フラクタルということなのか. エネルギーのスペクトル則もそこらにつながっているのじゃないか,という感じがする.法則性の入れ子が極限の世界とか.Baireとか.
全く説明にはなっていないのだが,取っ掛かりとしての直感もそう的外れではないかもしれない.エーテルの渦のように,私の思考が淀む時の表現法のようなものである.確率微分多様体論なんてことになっちゃいそうだし,もしかしたら,新説あるいは珍説になるかもしれないから.
集合関数の微分が,確率過程の形式的な空間化によるふくらみを処理して確率微分を処理するという意味では,確率微分の基礎に存在するのじゃないかという感じである.「集合関数の微分係数」(『現代数学概説II』)を参照しながら,考えてみた.「ふくらみ」というのは,集合E⊂QのmE/mQの上限であるEの正則指数

は,集合Eの``ふくらみ''の度合いを表す指数である,とあるから,集合論と確率過程の形式的なふくらみによるずれ(関係というべきだろうか)を暗示しているのではないかと,理論のというか法則性のふくらみや引き戻しのように結びつけてみたわけである.シリンダーとか柱状集合の拡張という感じだろうか.「触媒」的に微分可能な系列に変換する感じだろうか.












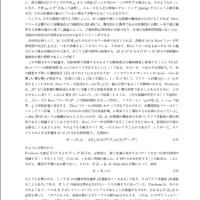
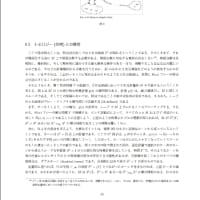
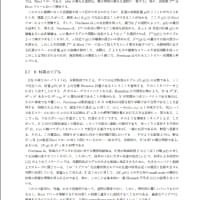
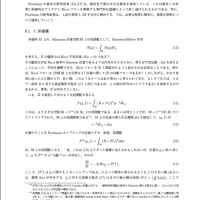

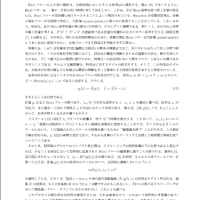
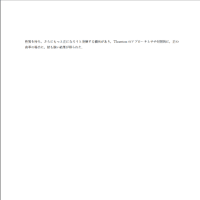
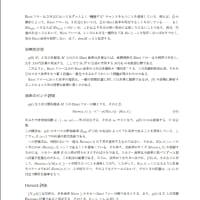
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます