2024年5月末だから,2024年はまだ半年程あるわけだし,これまでの危い均衡と,これからの危い均衡がどう動いていくかは,もうしばらく動向を見極める必要があるようだが,主には,ウクライナとロシア,ガザに対するイスラエル,モシトラ含みのアメリカの大統領選などとともに,米中政治経済戦争やグローバルサウスといわれることになった関連諸国の動向や選択など,世界的な節目がいつ明確なものになるのか,という関心事の中心になっているような現状である.その割には,日本では相変わらずの中身の薄い議論が盛んなようだが,日本らしいといえば日本らしい感覚ともいえる.私は,多少自国びいきというか甘い面があるのかもしれないが,そういうポーズを置くのも,無意味とは思わない.日本も過ちも多かっただろうが,他国から批判も指摘も受けられる国になるのが,そう悪いことなのだろうか.なんかやらせ中心の,反日論者の憂国論に染まったようなへんちくりんで窮屈な論調は脱するべきである.小泉だの石原だのは,そういう反日論者の隠れ蓑に都合がいいからカリスマ政治家に持ち上げられているのだろうし,和風ぶった森喜朗とかは,ちょっととがったカリスマ神輿の保険役なのだろう.都政の蓮舫か小池とかも同じような構図じゃないのだろうか.昔は,首都圏に住んでいたこともあったが,都民でないのだが,私を都知事にするというのも理屈にはかなっている.あるいは,そういう誰かが,選挙かっさらうというのも面白い気がする.統一家庭教会の舛添さつき都知事もいたわけだから,だったら,反統一協会的なこと言ってる私が都知事になってもいいわけではなかろうか.舛添もさつき自民党議員も,そこら甘い体質だったわけだから.東京も,なんか限界集落のカルト介入的な体質になって,しょぼい感じになっているのではなかろうか.日大事件の田中理事長もカルトべたよりのヤクザ代理店のような感じだが,案外多いのではないだろうか.一流でも有名大でも.日大も有名私立といえば有名私立だし.
STAP騒動にこだわっている感じに論述したが,こだわりたいというのが,私的にはしっくりくる.いまだに,STAP細胞信者がいるとか,アンチな連中がいっているようだが,まあ,そいつら自体だいぶ胡散臭そうだから気にもならないが,私は,こだわりたいと思っている.なんか,マニラのルフィーグループの内情を都合のいいように転嫁して騒ぎ立てよう的な,変な犯罪組織の常套的なやり口を感じる気がするが,指摘すること自体は悪いこととは思わないが,そういう都合に限り,なんてのはいただけない.日大の田中元理事長が,話題の麻薬の代わりに,チャンコに「詣で」というヤク味を売りに商売していたなんて,アンチSTAP騒動なんて,反社詐欺グループのようで気持ち悪い話である.吉村とか難波とか,研究者なのかそういう闇グループの子飼いなのかと疑わせる連中が,ひょっこり出てくるのも,ある意味,それなりの情報を与えてくれる.また,日本の経済誌のように,これまた胡散臭いやらせに乗っかかって,総括だのとやりだすのだから,アンチSTAP連中の示し合わせやらせを検証するのと同じような検証が必要ではないだろうか.アメリカからも釘をさされているようだから尚更.小池金融詐欺都政と便乗蓮舫立憲とか,小泉だ安部だ森だに続いてなんてのも,変な話である.銭には群がる民意とか.そういうのの対応するのが,吉村だったり,金子や高橋だったりするのも,おもろい情報である.そういう連中の雑魚手下のようにふるまっているのが芸能人の良純とか,話題の詐欺名義貸し有名人連中とか.しょぼい話である.池上とか何とかもだから善人というわけでもないわけだから.
アンチSTAPの本が,研究不正だの,研究倫理だのと騒ぎたがっているが,あんまり,触れ込みやったほど話題でもなく,そう評価されてもいないこと見ると,変な闇がそいつらの方に深いのじゃないかと疑ったりするが,科学と倫理なんてテーマも,ネアンデルタ-ル人の遺伝子がどうたらで,新型コロナの重症化リスクとか,あるいは,ウイルスと細胞の細胞膜接着に発見された新たな知見とかだけでなく,案外,stap問題でわきに追いやられた観点とも関係するのじゃないかと,せっかく,沖縄で研究していた経歴も持つ学者がノーベル賞ももらっているのだから,ちょっとは注目してもいいのではなかろうか.およそ,科学ジャーナリズムの予想は外れる決まりだが,そこらも予想を外しているのだから,ちょっとは,科学的観点から注目してもいいのではないだろうか.そういう検討から,科学研究と研究倫理の具体的な本当の接点が立ち上がってくる面もあるのだろう.やくざのやらせしのぎのような騒動捏造の吉村とかじゃ,倫理なんてやくざかハングレのおちゃらけご都合程度のものである.
なんか,中途半端な騒ぎ便乗的なことも多いから,ついくだくだと言ってしまった.きりがないので,小泉も石原もstap騒動のときの吉村程度の裏で持ち上げられている連中に過ぎない,It would not be an exaggeration to say so.(そう言っても過言ではないだろう),と私なりの結論で結ぶことにする.This idea is incarnated by the fact that ~(この考えは,~という事実によって実際に得られる). ~に当たる部分が突き止めにくいとか,関与が迂回的で慣習的に隠蔽されているとか,そういうことも考えられるわけではあるが.英語ではどう言うのか的な問題として考えてみた.簡潔なwitを利かせながら伝わる英語文に翻訳するには,フレーズの丸暗記とかが一番だろうか.
複素数z=x+iyに対して,共役複素数をz'=x-iyとおく(普通はzの上にバー).ρ=x^2+y^2とすれば,1/z = (1/ρ)z'. これは,複素数の逆数,一般に除算が回転と拡大・縮小の積あるいは変換の合成を表している.数IIBどまりの文系人間には,数IIIの最初で習いそうなこんな事実も,計算自体は簡単だが,気にもかけないかもしれない.複素数自体を中学か高校のいつ習ったかさえも覚えていない.理系の人間ならこんな事実からどこまで行くんだろうか.極小解析からゼータ関数までとか,相対性理論までとか,あるいは,パラレルワールド,多宇宙論までとか.理系の連中だって,ゼータ(リーマン)予想は解けてないし,極小解析もコーシーの丸暗記かもしれないし,多宇宙論も仮説のままだろうし,すすきと私の情報暗号論と違わないのじゃないかとか思うと気が楽である.理系は理系の大変さはあるのはわかる気がするが,なぜか,せっかくの努力も大人の事情で周回遅れとかに誘導されているとなると,お疲れさんとしか言いようがない.計算問題だされたり,実習のレポートの期限に追われたりするのも数学だろうが,ちょっと腰おろして空を眺めてたら,定理とその証明がふーと浮かんで消えたというのも数学なのだろう.文系人間に言わせれば,後者の方が圧倒的に理想である.実際,数学書を読んで,定理とかその証明は,その時にはたどれても全く記憶に残らない.思い出すには,またその数学書を読み返すしかない,ということも多いのだが,霧や靄のようにしか感じていないという実感である.「せっかくアーベル」から「非アーベル」への拡大・拡張なのか,不思議な入れ子構造なのか,どういうことになっているのだろう?
A地点でユリの花が咲いているのを見つけ,A地点とは異なるB地点でもユリの花が咲いているのを見つけた,というのと, A地点で見つけたユリの花がB地点でその本性とともにはめ込まれたという場合,私は,私と外界との極限的な境界点を動かしていることになるのだろうか.また,A, Bとも異なる地点で,ユリの花のようにその地点ではめ込まれるものもないのに,何故か,極限的な境界点が動くようなこともあるのだろうか? そこがはっきりしないと,あるのかないのかさえ怪しい,私の思考論理経路が定まらないことになる.または,そういうこともあるものさと認めて,非因果的な思考論理経路を受け容れてみるとかということもあり得るかもしれない.そういう意味では,因果性の成り立つ極限の世界を取り換えながら,思考論理経路を何度も振り返るような世界が環境世界というものかもしれない.
ところで,因果律(causality)というのはどういうものなのだろう.未来の入力が過去の出力(過去の入出力関係)に影響を与えることはないとか(『数学辞典』「制御理論」),消滅定理のようなものなのかとか,古典的波動の意味でも場の量子論的粒子の意味でも,遅延Green関数G⁺は因果律を与えてくれるが,しかし,両方の意味での因果律が一致するのは反粒子が存在しない場合だけである(『量子力学II』岩波講座)とか.粒子の生成・消滅とか.非因果性の影響を,実験的に確認する方法はないのかとか.原因があって結果があるという意味の因果律が,因果律を表す関数の境界条件として具体的に定められることを意味するようになるということかもしれない.A地点で見つけたユリの花が,B地点でその本性とともにはめ込まれる本情として境界条件を定めるものに化身しているなんて考えれば,芭蕉俳句の核心が得られるのかもしれない,と想像してみた.「閑さや岩にしみ入る蝉の声」てな感じなのだろうか.
リーマンの『幾何学の基礎をなす仮説について』は,中央公論の世界の名著シリーズ「現代の科学 I」で読んだが,リーマンの論文を読んだのは,朝倉の『リーマン論文集』を手に入れるまでは,この論文一編きりだった.印象としては,特に,終りの方で,連続多様体と極微の世界との関係が不思議な説明で書かれている,という感じだった.「すなわち離散的多様体では計量関係の原理はすでにこの多様体の概念のなかに含まれていますが,連続的多様体ではその原理をどこか他のところから付け加えねばなりません.それゆえに空間の基礎をなす実在的なものは離散的な多様体をなすか,それとも計量関係の基礎は,多様体の外部にあってこれに作用している拘束力のなかに求めねばなりません」.ここらは,場の粒子と実在の粒子とか幽霊場的な場合と対応するのだろうか.あるいは,A地点でユリの花を見つけたことが,境界条件として化身して,私s1の視点から,私s2の視点へ移行させたことに対応するのだろうか.私とススキではなく,私とユリというファンタジーも,数学とか物理のロジックとはかけ離れた,蓋然性の大きいものだが,みょうにこだわりが消えない.
リーマンの1854年6月10日,ゲッチンゲンでのコロキウムで,教授資格取得のために講義された論稿だそうだが,ガウスが感銘のあまりその帰途でずっこけたとかいうエピソードも残っているらしい.ガウスをずっこけさせるほどの内容を持った講義だったのだろうが,アインシュタインの相対性理論の先駆けとか,量子論的相対性理論(素粒子論など)のモデルとなる内容が含まれているのではないかとか,『現代の科学I』の解説では,「もちろん彼(リーマン)もまた空間とは本質的に違う時間を,どのようにして空間化すべきかという問題にまでは立ち入っていない点では,やはり19世紀的であった.しかし彼は他方で幾何学の諸前提が無限小で妥当するかを問題にし,離散的な多様体としての空間でも考察の対象としていたことは,いまのべた素粒子論の現状からみて注目すべきことである」,とある.とすると,空間の時間化までは19世紀にはたどり着いていたということなのか,x_i=x_i(t)←→t_i=t_i(x_i)のような感じなのか,まあ,通例のごとく,難しい話がそこには挿入されてくるのか.そこらを,私は,私とユリのファンタジーという文系イメージに変えてみたい.空間というカプセルに包み込むように,時間というカプセルに包み込むのか,境界のない入れ物のようなものなのか.
ニュートンの時間概念は,ニュートン的な物理・数量体系が矛盾なく成り立つように定められたものであるということだが,時間を類別して,同じ類においては同じ法則が成り立ち,異なる類の間になりたつ関係を新たに立てていくという見方の転換が必要になるのだろうか.「本質の立場は一般にReflexion(反省)の立場である」.とすると,A地点でみつけたユリの花の客観性あるいは実在性と概念がB地点で統一的に顕在して,環境知的に理念(Idee, イデー)化する.(ヘーゲル)哲学ぽっく見せかけて例えてみるとこんな感じだろうか.多様体というものも,類別された空間,例えばモジュライ空間(等角写像同値,等角同値類とか)などから,新たに構成された空間ということであれば,時間というものが類空間を取り換えながらどのように新たな法則を成り立たしめるものになるのかという感じのものになるのだろうか.
同一視することで,剰余類群に線形性という位相を導入して,あるいは直和分解して,その族MとMの部分加群の関係の保存系を一次準同型写像dでd *(ほんとは\circ) d=0を満たすものとの組を複体といい(M, d)で表す.dは微分作用素あるいは境界作用素と呼ばれる.とすると,A地点で見つけたユリの花は,B地点では動く微分構造と見なければならない,ということになるのだろうか.コホモロジーの消滅つまり消滅定理とすれば,微分構造が動くということは,より高い異なる次元から,ユリの花の再来の地平を見定めているという感じになるだろうか.デリダだったかフランクフルトだったかの「地平」というイメージぽく述べると,こんな感じだろうか.デリダだったら,ユリの花ではなくダリアにしておけばよかった感はあるが.
話を単純(primitive)に貼り合わせるようなことをやってるだけだが,小平『複素多様体論』の「はじめに」には,「変形理論は,コンパクト複素多様体Mは有限個の座標近傍を貼り合わせたものであるからMの変形はその貼り合わせ方を変えることである,という単純(primitive)な考えに基づく」とある.さらに,「この考えからMの無限小変形はコホモロジー群H^1(M, Θ)の元で表されることが自然に導かれるが,Mの手近な具体例に当たって見るとdimH^1(M, Θ)がMの定義に組み込まれたパラメータの有効なものの個数と一致したのは不思議であった」とつづく.私のユリのファンタジーがダリアのファンタジーに変われば,多様体の変形が得られるということだろうか.超曲面とかアフィン多様体とか関連が深そうだが,モジュライ空間とかタイヒミュラー空間とかアクセントを感じる話題につながるのだろう.有名な公式では,e^{iπ}=-1の数学的含意という感じだろうか.
A地点で見つけたユリの花を摘んで,B地点で見つけたダリアの花をA地点に植え替えると,私はA地点というイベントから,A'地点というイベントに改変(modification)あるいは手術(surgery)したことになる.真面目に言うと,複素多様体Mから新しい複素多様体M’(’はうえに波線のかわり)=(M-W)∪W'=(M-S)∪S'を作る操作を改変とか手術という.S⊂Mなるコンパクト部分多様体S,S⊂W_1⊂[W_1]⊂W⊂Mなる領域Wとする.あるいは,A地点というイベントの外部領域をB地点というイベントの外部領域と貼り合わせて,コラージュ・コピーのようなUmwelt(環世界と訳されるそうだが,私は環境の捉え方がわからないので環境世界という感じでイメージしている)をつくる感じだろうか.
集合全体の集まりを領域(classあるいは「宇宙」と言葉でイメージする)とみて,数学的にはっきりとした対象の間の関係として,集合論のパラドックスを解消して,その部分classの関係を再構築していくという背景が見えたりするが,はっきりとした数学的対象であるという条件を構築するには,集合という概念を破壊してclassという新たな概念を構築する,ひっそりとした操作が必要なのだろう.文系人間には,専門分野でひっそりとそういう操作を前提されると,理解するのがやたら難しくなるので,できれば,明示して説明してもらいたい感じはある.それと,AIでコラージュ・コピーを作り出していけば,私と環境世界が,普通に感知される世界と並行して溶け込むような体験世界を実現できるだろうか.そうなると,アニメもAIが作ることになり,アニメ文化も世界のあちこちで普遍化していくことになるだろうか.
(与えられた対象,射, 合成)の総合概念をcategory(カテゴリーあるいは圏)という. 具体的な例として,すべての群を考え,2つの群X, Yの間にある複数の準同型 X→Yの全体をHom(X, Y)と書く. その元f, g, ......を射(functor)とよびf∈Hom(X,Y)あるいはf: X→Yと書く. 合成と呼ばれる射の演算から得られる射g \circ(小さい丸) f ∈ Hom(X, Y)が定められている. 圏の公理により,圏は単位的半群を作る. (ユリイベント,ダリアとのコラージュ,コラージュ・コピーイベント)と考えれば,ユリやススキのファンタジーはカテゴリー論に属することになるのか. 多様体の変形理論もそういうことになるのだろうか.
相対性理論は厳密な物理理論のお手本のように考えられている. だから,その規範理論としての性格から,相対性理論を疑うのではなく,量子力学のほうを疑ってかかる. しかし,相対性理論の方を疑ってみる立場も必要ではないかという話が,湯川秀樹の言葉にある. そうすると,量子論的相対性理論を考えるということになるのではないだろうか. 相対性論的量子論と双対的に. さらに,そうすると,私のユリのファンタジーは,独立して動き,展開するアニメーションのように,私の思考とコラージュしながら,思考論理経路を構築しながら,環境知的な経験の道行きを歩く体験世界を顕在させていることになるのではないか. 個性を持った暗号情報のようになるだろうか.
戦争や金融犯罪等に対するAIの危険性が,AIへの規制を整備するべきという話になっているのだろうが,わたしは,ユリのファンタジーの方が面白い. ファンタジーも持たない人間がAIを規制しても人間社会の方が先に壊れるかもしれないではないか. 現実的には,生成AI等に関する規制がどれほど的を得ているか,また,限界を示していくのか,観察し続けるしかないが,ファンタジーなんて言っても相手にされないだろうから,じっくり楽しみたいところである.
数学の群という概念はどういうものかを超簡単に説明してみる.自然数全体の集合Nに足し算という演算(記号で+)を併せて考えるとする.2+3=5とか10+13=23とか,足し算という演算によって,必ず,自然数の仲間の数字が決まる.そこで,(1)自然数のどの数字でも,足し算の結果がその数自身になる数を単位元(e)とよぶことにしm+ e= m, (2)各自然数mとの足し算の結果が単位元になるそれぞれの数の逆元が存在する m+m'= e, というルールで考えてみることにする.これらの条件を満たす自然数は存在しないので,単位元eに相当する数0と,各自然数mの逆元にあたる数たち(ーm)を加えた数の集合M(整数全体の集合)を考えることになる.今度は,掛け算という演算(記号で×)を考えると,自然数全体の集合から,正の有理数全体の集合Qを考えることになるが,単位元は1だし(m×e=m),逆元は各々m’=1/mとなるから(m×m'=e).足し算も掛け算もと考えると,単位元は足し算の場合は0, 掛け算のときは1となり, 逆元は,足し算の場合は-m, 掛け算の場合は1/mというようになる.しかも,掛け算の場合は,0も負の有理数も考えた普通の有理数を考えていることになる.自然数→整数→有理数→実数→…と考えれば違和感はないが,群として考えるとプッツンしそうである.さらに,1の原始n乗根とか考え合わせると,ますますプッツンしそうである.極低温電子顕微鏡+生成AI判定システムなんて顕微鏡をのぞいてさらに微細な構造を見分けろなんてことになったら,コラージュコピーのいくつものパターンから真正の像を選び取るような感じになるのだろうか.そういう顕微鏡があったとしても,のぞける機会はほぼないだろうから,ユリとダリアのコラージュから寓話を楽しむことぐらいしか現実味が生じない.あるいは,専門機関等が公表するのが当たり前の時代になるとか.これがほんとのディープフェイクなんて政治・軍事利用されたら,という懸念にどう対処できるのだろうか.
「現象の因果関係の認識は,本質的には,われわれが現象を無限に小さいものにまで追跡していく正確性にこそ基づくのです. 機械的自然の認識でのここ何世紀かの間の進歩はほとんど,無限小の解析学の発明と,アルキメデス,ガリレイ,ニュートンにより発見されて今日の物理学が用いている簡単な基本概念とによって可能となった構成の正確性のみのおかげであります. しかしこのような構成に必要な簡単な基本概念がいまだに欠けている自然科学の諸部門では,因果関係を認識するために,顕微鏡が許す範囲内で空間的に微細なところまで現象を追究します. そうですから測り得ないほど小さいものでの空間の計量関係は,無用のものではありません」(『幾何学の基礎をなす仮説について』)
正則(regular)とか,全微分(total differential)とか,複素解析とか多変数解析とかの基礎概念に当たるのだろうが,文系にはややこしそうな聞きなれない数学用語の一つである. 正則といえば微分可能とか,全微分といえばΔz=AΔx + BΔy + ερの主要部Δx, Δyに関する一次式dz=(∂z/∂x)Δx+(∂z/∂y)Δyのことであるとか. ρは定点(x, y)と動点(x+Δx, y+Δy)との距離で,ρ→0のときε→0とか(高木『解析概論』). ついでに,dzは(x, y)において曲面z=f(x,y)に接する平面を表すとか,あるいは(流通座標を用いるが,)これが接平面の定義であるとか.
同値概念を定義して,その同値関係に基づいて対象を類別して,対象の間の関係を定めていくような感じの古典的なモデルということが,コーシー=リーマンとか有名な理由なのだろうか.例えば,タイヒミュラー空間について,『数学辞典』からかいつまむと,解析的に有限なリーマン面R_0は,種数gの閉リーマン面からn個の点を除いたものである.このときR_0を(g,n)型という.(g,n)型の任意のリーマン面Rと,R_0からRへの擬等角写像fとの対(R, f)全体を考える.2つの対(R, f), (R',f')が同値であることを,f' \circ f^{-1}がRからR'へのある等角写像とホモトピック(homotopic)であることと定義し,その同値類[R, f]全体をR_0を基点とするタイヒミュラー空間といいT(R_0)と書く.逆写像f^{-1}が印象的だが,保存系とか改変ということに関係しているのだろうか.log e^{-1} = -log e =-1とか遊び感覚で参考になるだろうか.
2024年7月14日遊説中のトランプ狙撃される. これも画面向かって左耳たぶ(本人右耳たぶ)貫通も,見た目そう大きな損傷ではなかった感じに見えた. 貫通したからなのか. 他に3人死傷とあるからおもちゃではなさそうである. 運がよかったのだろうか. 着弾して破裂するなんてことも聞くが,そうしたら命も危なかったということだろうか.
銃のことは知らないが,火薬入りのテープをカチンカチンと点火して,パンパンと音を出す銃しか手にしたことがないので,銃に詳しいコメンテーターに解説任せるしかない. ヤクザ関係の芸能人評論家とか. そっち方面の姐御藝能人とか文化人とか. 案外古いやり口の焼き直しのようなやらせ騒ぎがメディアでも多い気がする. 小池都知事3選にしても,統一教会だの裏金だのでダメージを予測できる自民が昔の公明や社民のように股下何とかバリにやってるというだけのことを,ステルスとかいえば新味があるように思っている腹黒い政治家の申し訳程度のことをメディアの一部がえらく持ち上げるてな感じなわけだから,旧態然のやり口の焼き直しか二番煎じなわけである. そういう連中がとっついていそうなのが石破とか小泉構文というやつではないのだろうか. 中曽根あたりからカルトポピュリズム的な感じが強まった気がしているが,勝新太郎がパンツに麻薬隠しても,元気になったかどうかはわからい的な,よる年波ということもあるし,そんな政治文化はいつまで続くのだろう. 結局,日本は政治家の二号橋が壊れ落ちるまでは改まらない. そういう,昔の政治文化にのかかって政治を語るかっこだけしていれば憂国の若者のような演出でメディアがお手盛りする. そんなところではなかろうか.
ロシアの核は中国北京にも向いていようが,東方への活動を活発にすると言いながら,横須賀を核攻撃すると脅すなんて話は,中露核戦争論を緩和するには大賛成という論者もメディアでもてはやさないのだろうか. あるいはモスクワをロシアの中央部に移すとか. もともとノマド拠点のようなところだから発想としてはあり得るのじゃないだろうか. プーチン構文. そして,極右ユダヤ主義構文,確かに,変な構文問題に世界がほんろうされている感はある. 蓮舫構文というより立民内部の腹黒構文で沈んだ感もあるのだろう. 民主党末期を思い出させるから. 立民の負け選挙密売商売のような感じだろうか. 蓮舫ー小池のヤクザの民事介入的な都議選に石丸構文という逃げ道を作った感じだろうか. 候補者のせいというより自公だの立憲だのの体質が垣間見える選挙であったのはむしろ良かったのではないだろうか.
・ウクライナはNATOに加盟し,ロシア構文に戻ることはない.
・イスラエルは,反イスラエル勢力を根絶するまで軍事行動をやめない.
・アメリカは,トランプにもどって,米ロV.S.NATO・EUの世界情勢の分断も辞さない. (米露 vs. NATO・EU. アメリカはNATO離脱して,EUとは敵対するというわけだから,対中姿勢を変えないならば理屈上は米露中 vs. NATO・EUの第三次世界大戦をもくろんでいるということも成り立つ.もちろん,中露にはありがたい仮想のシナリオだが.EU内部でもそういう亀裂を生じているような話もあるから.v.s. = see above と間違えただけだが,つい言い訳がましく話を取り繕いたい).
・中国はそんな情勢が中国への攻撃に代わるのでなければ都合がいい.
大雑把に,こんな感じで,世界の対立が演出されやすい構図を描かせたがっている. ご都合勢力の攪乱戦術にも見えるし,あるいは,図星を突かれて逆切れしているとも見える. あまり話題にならないが,メディアでも論じられているものであって,全くメディアでは報道してないというものでもない. 話題性をうすめて,中露の闇金に依存していそうな得体のしれない論者が,TVなどで盛んに言い立て始める. ハルキウへのロシア軍の侵攻が,支援離れとかモシトラとか絡んで,芯のない論者がなびき始める. 旧統一教会のサイコぽい高額詐欺が,地裁高裁の判決を最高裁が差し戻したという件も,裁判・法律通の腹にしまっていた風な,結局誤った見立てで,旧統一教会問題も薄まっていくのではないか的な自民のステルス思惑が,萩生田自民党都連の辞任になったとは考えられないだろうか. もしかしたら,私が都知事選に出ていたら大量獲得票で,都知事選,都政は変わっていたかもしれない. なんてことはないが. しかし, こういうことの目くらましのために,人口減少とか,若者へのステルス負担増とが悪用されているということは,一つの論点ではないだろうか. 健やかに強く生きられる環境づくりは,理想に過ぎないが小池や蓮舫の現実的に聞こえるが詐欺に過ぎない政策論よりはよいはずである.
実際,政治事は,本当は何を意図しているのかはっきりしないものも多い. 最近は,さらに,夏場の怪談のような得体のしれない話も多い. そうなると,ヒトの想像力の数だけ,あるいは,そういう制限もなく,幽霊は出たい放題になる. しかし,古来から幽霊と呼ばれるものには,何とも言いようもない制限があるように思われている. 怨念や生霊の祟りでもそういう制限があるきがする. 電磁物理で有名なクーロン相互作用も,あるいみ,そういう幽霊的な存在の存在の制約を表している感じなのだろうか. 質点という概念(ボスコビッチのマッハ主義的な概念)とか,電子とミューオン(質量だけ200倍異なるだけ)とかクォーク(単体では見つかっていない)とか,重力の近接作用への還元(アインシュタイン)とか,それだけ聞いても,分かるようでよくわからない,基本的な構成粒子や時空の問題も,幽霊的な存在の制約と分類と似た感じがしてくる. 例えば,素粒子に拡がりをもたせて,時空の方にも拡がりを持たせると,コラージュコピーのような感じで,時空と素粒子の相互作用が素粒子の存在制限内部に還元されて,電光掲示板的なON-OFFのパターンで表されるようになるとか? ここらまで来ると,朝永の相互作用表示の意義が強調されている感じがある.
源氏物語の女の生霊が祟り殺すとか,素粒子論のような物理の究極理論の指向のようなこと,あるいは政治事や国際紛争なども,私のファンタジー思考情報論の文学的変換で,大概のことは,それなりに読み解けるという自慢話にはなりうるかもしれない. ニュートン力学が内蔵している問題点を,功罪はあるだろうが,ある意味包み隠してしまった流れになり,量子論や相対性理論という新しい物理学の誕生と進展によって,包み隠されていた本質的な問題の再提起を促し,相対性論的量子力学のような新たな地平で再構築されて,重要な知見に貢献するといった流れのようにも読める.例えば,Coulombの法則は,2つの小さな帯電体の電気量をq, q',2つの帯電体の間の距離をrとすると,その間に働く力fは,それらの電気量の積に比例し,距離の二乗に反比例するという法則(f∝(qq')/r^2, ∝は左辺と右辺は比例関係にあるという感じだろうか)が精密な測定から結論されたというものであり, ニュートン力学の立場から電磁気学を扱う基礎となるものであるということだが,非因果性の影響を実験的に確認する方法に使われたり,物質・エネルギーの存在の条件に内部化したりするカギとなるような概念になって保存されれるのか,コラージュコピーだからというのは,だいたい,こういう話は,数学者がリーマン予想などを論じることに本能的な危険やリスクを直観するように,科学評論家もどきも敬遠したがる.私は,文系の科学苦手人間だから,全く平気だが,なんかそんなポーズが世間にはある気がする.だったら,核兵器も実際撃つまでは,科学評論家の見立てなどあてにならないものだと,自ら言っているような態度に見えるが,変なものである.軍事評論の方が,科学的な面は兎に角としても,リアリティがあるのもうなづけるが,原発だの核兵器だのウイルスだのは,変な詐欺師ジャーナリズムが我が物顔で嘘ばかり言ってる右翼なのか, 読売の斜陽ナベツネリズムのか,ネットとはそもそも前提が違うのではないか.石破も小泉も,付け込みやしけ込みがうまいというので,ポスト岸田だのどうでもいいような,ちゃっちいやり口に共感が集まるのじゃないかと,実績など聞いたことのない慶応閥だの,小物のうぬぼれが旺盛なのだろう.ナベツネイズムの金魚の何とかのような.ハングレヤーチョン閥がバックなのか? プーペイ閥とか? そこで,自民が野党に転落するとややこしくなるので,第一党になった政党は私を総理にするとなれば,日本はまっとうになる,というやらせを総動員するというのはどうだろう.
石破だけだと慶応閥批判になるが,小泉息子批判だと一橋批判となるのだろうか? なんか,福沢諭吉だの小幡甚三郎だの足立寛だの荘田平五郎だの小物のハングレ逆上せの大将のような石破後継という感じになるが,一橋もなんかそういうのになびいて魂売った有名大という感じがするわけである.なんかあったんだろうか? こう大学閥もだらしなくなっては,独学でしか勉強てしたことのない私には,朝鮮かどっかのやらせ教育機関じゃないかという印象しかない.スタップ細胞騒ぎのとき一部ネットだけで話題だった,吉村(子宮頸がんワクチン騒ぎで帝京医学部の副学長的コピーじゃないか的な疑義がかけらていたからなのか)また難波(どういう裏か知らないが)が反スッタプの旗手のようにもてはやされていたが,そういう事情背景の時世の申し子に仕立てたかった勢力でもあったのだろう.ワルが偽善に付け込みしけこむやり口そのものではないだろうか.私は結構,いい子で正直に生きたので,小物悪のやらせいい子捏造には敏感なのである構文.付け込みしけこみがいつの間にか主になって,その動機となった利害とか私利私欲が目的化して,あらゆるものがそういう私利私欲や利害の道具でしかないような錯覚にとらわれる,てのが政治屋的であり,そういう政治屋的なゆがんだ行為ではなく,カッコつきのイマージュの総体を身体的な行為として記憶する.見過ごされている事実関係を発見したり確認したりしながら,政治的行動につなげる.これが,俯瞰力を持った政治的立場というものであり,政局だの権謀術数だのと,お手盛り皿かコップの中で踊っているような最近の政界のやらせ持ち上げとは異なるのである構文.なんか,私の方が大物政治家なんじゃないかと思いたくなるものいいであるが.もっともらしいこと言っても,政治家としても人間性としても信頼されていない,政治不信に悩んでいるらしい自民だの立憲だのの政治家でも政治屋でもどっちでもいいが,「そんなことない,私に限っては」なんて実はいないから政治不信なわけだから.鈴木宗男か野田か石破か森喜朗か,なんて論外だが,つまりポスト岸田は,つまり結局私か構文.不信感や疑惑的にみられている売名構文芸能人は,たぶんそのこと自体気づいていないという私の売名構文.
2024年8月5日,日経平均株価(日経225か), 終値ベースで過去最大の下げ幅-4451円28銭.しばらくは話題になるだろうからメモっておくことにする.株価も投資家心理がパニクって,大暴落をも引き起こすと最近よく言われる話だが,これも一つのイマージュあるいはイマージュのなかでも身体的行動の記憶に結びついたものとしての心理であって,二元論的な心理という話でもないのだろう.ベルグソンの暫定的な定義として言えば「物質の知覚」としての,あるいはイマージュの総体(=物質)の身体的行動の記憶としての心理ということになるのだろうか.そこでは「私の知覚」は消滅しているわけだから.そうであれば,プログラム売買とかの要因があがることになるだろうが,生成AIのコラージュコピーで株の売買すればよさそうなものである.生成AIなんてものも国家戦略レベルで極秘の裡に進められているなんてなれば,それぞれの実際の運用とか到達具合とか知らされないだろうから,難しそうな話ではあるが(とりあえずメモっておくことにする.内容の真偽については当方は一切責任を持たない).急激な為替相場の変動が主要な要因てのも,円高に動くのか,円安傾向が続くのか,急激な円高だから,現時点ではどっちかはすぐ判断つくわけで,弱いドルがどれほど戦略的戦術的な行動選択を可能にしているのかの指標という面もあるのだろうから,そういう面の分析もおこなわれるのだろう.ある程度,アメリカの当局の見解も示されるだろうから,それで少し落ち着いてくるのか,それでも日本株は下落し続けるのか,どちらにしても思いもかけない方向に動く可能性の原因にあるのは何なのか,突っ込みどころは満載という感じだろうか.(これもメモっておくことにする).
(私の裏アカメモ) ここ一日二日では,どうも私の方が,経済アナリストだの経済閣僚だのより良い仕事をしたようだ.ポスト岸田だのうざい売込みしか能のない若手も含めて政治家などおこちゃまレベルである.それは措くとしても,実際,まだまだ注視が必要だとか,下げすぎとか上げすぎとかそれらしいことは言ってるアナリストの弁もあるから,そこも冷静に検討していく必要がある,はずである.とりあえず,ご苦労なことである.やっぱり,ポスト岸田は結局私ということになるのか.
(南海トラフ地震臨時情報) 8月8日,宮崎県沖日向灘を震源とするマグニチュード7.1の地震発生.最近,テレビ解説者などには,悪質な詐欺誘導評論家(橋本とか(TVなどに出ているどれかの).さすがに東国原とか地元を政治屋的に悪用しようなんて悪質なことは分別つくだろうが)も我が物顔で出演しているようなので,SNSなどでの詐欺情報に注意.
気象庁マグニチュードとか,モーメントマグニチュードとか,理科年表(手持ちの奴はちょっと古いやつだが)では,7つほど上がっているマグニチュードMの決め方(定義の仕方,定義式)による違いらしいが,モーメントマグニチュードの定義は,M_ω = (logM_0 - 9.1)/1.5というものだそうである.それはそれとして,要は,いつどこでどんな大きさの地震が起きるかなんて予測できないから,パニクらずに,デマなどに惑わされずに(そのうち,シレーッと詐欺便乗的な橋本のようなコメンテーターもでてくるから),局所的局時的事態でも身を守る心構えをということらしい.
大規模な地層の変動があれば,私などは山から転げ砕かれる石とかわらず,家が崩れれば粉々に壊れる家具と変わらないが,そういう変動の一部分であるにかかわらず,リスクミニマルな均衡状態なのか日常というものが,リスクマキシマルの暴走というべき局所的局時的事態に最大の弾力性を持つかもしれないというわけだから.運よく無事で済めば,それはその事態として評価され直されるのかもしれないが.こういうcarryを発生させる.そういう緊張感もなく悪事に専念する輩もいるから,carryings-on(不正行為,悪事,おふざけ,大声をあげて騒ぐこと,いちゃつくこと)という英単語もできたのだろうか.
好きな女の子といちゃつくことは地球よりも重いはずなのに,不正行為とか悪事と同じなのかと,あれれと思うかもしれない.私が考えるに,英語も案外おおくくりな面があって,そういう疑問は感性に乏しい野暮というものという感じではないだろうか.そういう野暮な連中の屁理屈は永田町のぶら下がり政治評論家にまかせておけばいい.麻生がどういっただの,二階派がどういってるらしいだの,結局,自民党のご都合が国民の政治行動を振り落とすのだというロジックを受け容れろという,権力べたり寄りのジャーナリズムの体質そのものを表しているに過ぎない.そういうもたれあい体質が,ファクトチェックなど邪魔者でしかない,自分には不都合だと本音を言いたくても,バツが悪くなるから,変ないいわけで取り繕う体裁を利用しようとするわけである.そこらを増長させた面も,統一原理問題やパー券裏金問題にあるから,いまだに,朝鮮系の土俗カルト詐欺をかばう言動が政治家や政治評論家に見られるのではないか.ちょっと,鈴木宗男問題に似ている気がしないだろうか.それとも,詐欺だろうと朝鮮系の土俗カルトだろうとなんだろうと,結構うまい汁吸えているわけだから,そういう連中の岩盤票が,小泉息子や石破などは取り込みやすいから(多少,お調子者ぽい面があるから)利用できるのではないかということだろうか.学閥云々も,慶応閥はもともとそういうのだろうが,昔の一橋派という名門というより,世相の経緯で中朝に魂売ってるようなの多くなってるのじゃないか的な軟弱さを感じる面もあるのじゃないか的な感じを覚えるわけである.原理教の安部がさつき議員を抑えるために憲法改正を利用したなんてこともちゃんとした弁明もなくうやむやにするから,変な政局を捏造するような田崎だのなんだの(田原が仲介して朝鮮系の裏とつながっているのだろうか)をTVバラエティーが重宝しているのも,政治不信の一因ではないだろうか.そういう意味では,朝鮮系の工作がポスト岸田騒ぎに,自民党改憲案に仕込まれているわけだ.自民党プーペイ改憲およびプーペイ自衛隊なんてなったら,日本もちゃんとした国家として認められるかどうか不安になるわけである.私は,中核から統一原理までいるようなサークルにいたことがあるが,どっちにしろ普通に良識ありそうな感じだったが,桜田淳子の旦那がちょっと闇を感じさせるやつだから,そういう面は分けて考えるべきなのだろう.桜田ファミリーは詐欺の首謀者でもないなら詐欺カルトから脱会すればそれで済む問題だから,自民党のうす腹黒い体質の改善にむしろ貢献すればいい.米露中vs.EU-NATOなんて仮想的なシナリオをうそぶいている私の発言の方が,リアルに考えると相当やばいわけではあるが.
円安ということは,円の価値が低下するということなら円への需要は高まり所得効果をプラスにするが,実質マイナスにするようなら,円は下級財ということになる(「需要の法則」law of demand).金利差を利用して,そのプラス効果を,ハイリスク・ハイリターンのアメリカの金融商品にキャリーする.というのが,円キャリートレードという見立てなのだろうか.同じような手法がとられるだろうから,その状況に応じて不安定な状態が続くのかもしれない.とすれば,アメリカは通貨ファンドなどを使って,その戦略的戦術的行動選択の可能性を組み込んでいることになるから,これは相当の軍師でなければ乗り越えられない.このうだる暑さの中, 複雑な油断ならない分析,策をひねり出すのは至難の業である.黒幕としていそうな経済界とか労働組合とか,右翼だ何それのドンとかも含めて,御大層なガキの悪ふざけ程度のポスト岸田自民党総裁選なんぞ,児戯にも等しい.私の裏アカウントを調べれば(実は,持ってないのだが),もっと酷評がつづられている.という裏アカコメント.
使い慣れない経済学用語で語ったので,辞書的定義だけ書き出しておく.
*** 需要の法則(law of demand) ある財に対する需要は,価格が下がれば増大し,価格が上がれば減少する,という法則.これは,価格変化のもたらす所得効果と代替効果により説明される.---> 右下がり需要の法則.
*** 右下がり需要の法則(law of downward-sloping demand) 需要曲線には,一時点においてある財の価格が下がれば需要量が増えるという,価格と需要量とが逆方向に動く関係が示され,これはグラフ上では曲線の左上から右下へのスロープとなる.このことをいう.
*** 所得効果(income effect) 消費者行動の分析において,任意の財の価格下落はより高い無差別曲線の実現をもたらす.その場合,その高次の無差別曲線の実現は,価格を一定にして貨幣所得が増大することによっても可能であり,このように仮設的に考えられた貨幣所得の増大による当該財貨の需要量の変化を,その財の価格下落にともなう所得効果という.それがマイナスであるような財は下級財と呼ばれる.
*** 代替効果(substitution effect) 消費者選択の理論において,ある財の価格の変化が他財の需要量に与える効果から所得効果の分を差し引いたもの.具体的には,同一の無差別曲線上の動きをいう.
*** 無差別曲線(indifference curve) 同一の効用または生産量を与えるような諸財の組み合わせを示した曲線のこと.消費者行動の理論では,2財の座標で説明すれば,無差別曲線は原点に対して非凹の曲線で示され,原点から遠い位置にある曲線の方がより高い効用水準に対応し,また2つの無差別曲線は互いに交わることはない.
私は,ある財というところを円という通貨商品と置き換えればどういうことになるのだろうと考えてみただけだが,円安とか(世界同時)株価暴落とか円キャリートレード説とか当面,話題としては消えないだろうからという動機で,考えてみただけである.対数曲線のような需要曲線と右下がり需要曲線の関数関係てどういうものなのだろとか,これはあるいは素数暗号的な新たな関係が隠されているのではないかとか考えてみれば,ちょっと面白い面もあるかもしれない.
話題性だけで言えば,パリ五輪ということになるのだろうが,私は,運動音痴というほどではないが,パリ五輪もダイジェストだけみた.柔道は学校体育の時間にならった程度で,専門的なことはわからないが,女子柔道家の号泣とか話題らしいが,本人,一瞬の技を決められてしばらく事態を呑み込めなかったといってたから,そういうものなのだろう.柔道の専門はそのために技を磨いているわけだから,私ならそれも当たり前かと思うわけだが,ビデオで再生されているシーンをみると,内股という技なのか,大外という技が体を崩される起点となって,内股にかけようとしたところを流されて,相手がその流れを体落とし的な踏み込みで刈り取った感じだったが,もしかしたら,瞬間,その流れを自分に引き込みなおす手がかりも感じていたのかもしれない.無意識に,一瞬の勝機を感じるようなことを会得できそうだという感慨が表れたのかもしれない.漫画のように素人がお話作るとこういう具合になるのである.競技は違え,積極的なメッセージを感じる五輪選手もいたのだろう.スポーツのことは部活でやってた以外よくわからないが.
裁定取引(arbitrage)というと,経済のマネー化でバブル崩壊をもたらした大きな要因として話題になっていたが,要はキャリー取引のようなものだから,ただ,失われた30年とか50年とか言われた年月を経ても解決されない.というより,asymptomatic(一見,徴候がないように見えるという感じだろうか)な経済の組成化の動きというか構造化の動きが,予測できないような運動の法則のように独自に動き出す.例えば,なぜ豊かさの中の貧困がもたらされるのか,地域差や時間差も横断,縦断して展開され,独自の運動の記憶のように貫徹されるのか.二次的な経済分析というと誤解が生じそうだが,古典的な視点の限界や誤りを超えて,さらに,三次的四次的な分析も包摂するような動揺する一般化や普遍化を観察できる立場があるとよいのかもしれない.古典的なといっても,突き詰めると,なんか哲学問答というのか形而上学的というのか,そんな難しさがあるから厄介なものだが,仮想的な三次四次的な延長をくぐって,ニュースにもなるような経済的イベントというのか事象を身体的運動の記憶の反照として位置づけなおす,予見可能性として弁証化するてな感じになるだろうか.デリダの「差延」とか,フランクフルト学派の「再来の地平」とか,アルチュセールの「徴候的読み」とかが示唆するところだろうか.マルクスの『資本論』にある「弁証法とは資本(論)の記述自体」とかが底本というところだろうか.ケインズなら『雇用・利子および貨幣の一般理論』の一般(理論)という含意の複眼性という感じだろうか.思いつくまま列挙してみたが,ここら,感じ取っているところが共通している感じを受けるが,長い伝統的学問思想基盤のなのだろうか.
古典派経済学というと,「リカードおよびジェームズ・ミルならびにその先行者たちを包括するために,マルクスによって発明された名称であって,私は,リカードの追随者たち(J.S.ミル,マーシャル,エッジワース,およびピグー)をもその中に含めることを慣習としている」(ケインズ),ということだそうだが,結局,どういう分析の立場に立って経済を見るかによって,その範囲も含意も変わるのだろうが,ケインズもマルクスの発明になる古典派経済学というとらえ方にはのかっているというわけだから,そういう関係が鏡となって,相互の経済学体系の異同がくっきりとしてくるということなのだろう.AIが,経済に関するデータをさらに蓄積し,アルゴリズムを進化させて,ケインズ経済学やマルクス経済学の,それぞれの新たな発見や問題点の明確化,あるいは共通のそれらを指摘するようになれば,案外,対話型AIとして,刺激的になるかもしれない.対話の結論が,第三次人類滅亡全面核世界大戦だなんてなることを怖れるという話は必ず伴うだろうが,それも,ていどはさまざま,現実味も様々というのが実態だろうから,私はあまり興味ない.程度も現実味もAIが判定できているという前提で,悲観論も楽観論も出てくるわけだから,AIがはたしてそういう判定をするのかどうかは,現在,知らないわけだし.
『原典による経済学の歩み』のケインズの節を読み返したりして,株だ債権だ通貨だという預託ゲームで大金手にした話など,ネットで話題の景気のいい話とは無縁なのだが,すると,必然的に,円安株高から円高株安なんてしょぼい話だけ残されることになるわけで,自民や立憲の党首選挙のようなものだから,考えるだけばかばかしいが,1970年代半ばの出版だから古いのだが,私にはちょっと面白かったりする.経済発展の動因を,投資が先行し,それに等しい貯蓄が生じるように所得が決定されるとみるか,貯蓄が先行し投資がその資本蓄積に応じて決められるとみるかという,投資乗数理論を投資先行説とするか貯蓄先行説とするかという相対する見方が可能だが.ケインズの立場は前者であるということである.マルクスの立場は前者なのか後者なのか,「蓄積せよ」というように資本家の衝動を言い表している点や,「ここがロドスだ.ここで跳べ」とか,少々無理な貯蓄動機を投資優先でルビコン川を渡らせる的な表現もあるから,意外とややこしい.投資乗数理論は,所得決定つまり雇用量決定を担う理論だということだから,意外とややこしいのも,もっと大きな転回のロジックが隠されているという見方もできるのかもしれない.「セー法則」とか「経営と所有」の分離とか再結合とか,「金利生活者の安楽死」とかの話題も,こういう文脈の中にあるという話だから,有名なテーマだったわけである.
レジュメ(resume)代わりに,というよりメモ代わりに,『経済学の歩み』から,用語説明にあたる部分だけ抜き出すと,
まず総供給関数と総需要関数,その交点での極大期待売上金額Dである有効需要について.
ZをN人雇用して得られる産出物の総供給価格とすれば,Z=Φ(N)を総供給関数とよび,DをN人雇用して企業者が受け取ると期待する売上金額とすれば,D=f(N)を総需要関数とよぶ.D>Zの場合,企業者はN以上に雇用を増大させ,Z=DとなるNの値のところまで,生産諸要素をめぐる競合が生じ,競合により生産費を高める刺激が存在される.そのようにして,雇用量は総供給関数と総需要関数の交点で与えられる.この点において企業者の期待利潤が極大となるから.総供給関数と交わった場合の総需要関数の点におけるDの値を有効需要とよぶ.
なんか,企業者の極大利潤追求に左右される雇用水準が,インデックス化されて,投機市場の売買の元手になり,雇用水準あるいは所得水準がキャリーされていくという感じな話に見えたりするが,そうなんだろう.日本の経済が複雑だという,縦型支配とか二重構造とか,賃金格差とか犠牲と繁栄とか言われることと関連しているのだろうか.ひいては,日本経済がどうこう言ってもアメリカのポチという話とかも関連するのだろう.デリケートな動きにも対応したうえで,行動を決めていかなければならないだろうから,ポチにはポチの悩ましい面もあるのだろうから,すぐにどうするべきだというわけではないが.経常面を破壊して,その破壊の程度を指標化してその指標を独立した商品として売買する投機市場で渡り合うには生成AIをプレイヤーにするしかなさそうだが,現在どこまで進んでいるのだろう.
森喜朗とか安倍晋三とかのまめなカルト癒着部分とか,そこらから逆照射すれば,気の抜けた問題行為だといって個人の不可解な嗜好で片付けられそうな,地方も含めてパー券自民や政治地面師屋の野田とか小沢立憲の犯罪性も問えるのではないかと思う.腹黒組織犯罪隠しだから.嘘で防衛され,世間もそれくらいでなびくんじゃないか的な組織的犯罪隠しにほころびが生じたから,自分都合の法律や憲法解釈が憲法や法律だてな倒錯が共感を呼んでいるわけだから,そういう空気感や居心地がつまりは判断の前提にある論者も多いのだろう.そういう連中の右顧左眄と有権者や国民多数の我慢の限界の対立のエネルギーの差が核心に言い及ばない議論の体裁をメディアが演出しているのだろう.麻薬をパンツに隠して, 果たして元気になったのかという演出右翼の紛らかし話題作りのようなものである.座頭市とかいっても知らない人も多くなっているだろうが,女座頭市というのもあるらしいがそれは別として,新しい時代の政治だ社会だといっても,いまだに昭和ちょい悪右翼の演出頼みてえのも,あるいはプーペイ工作員的な連中頼みてえのも,シラケる原因ではなかろうか.逆に考えれば,隙を狙うようなやり口がはやっているぞという情報にもなるが,反面教師的に役立てるという手もあるかもしれない.
意味があるのかないのかわからないが,自民や立憲の党首選,衆参院選,兵庫県知事への不信任成立,森喜朗がパー券や統一教会がらみの介入したとみられながらなんか言えないとか,安部が韓国土俗カルトを自民のVIP待遇にしたとか,立憲も政局密売で,だったら,立憲も解党して自民に合流しておけばよさそうなものだが,そうしないところに価値が生じる的な,民主末期の状況に限定販売とか.円や株価も方向が定まらない動きの中,急激な変動をなんとかコントロールする手しか打てないのじゃないかとか,政治家は,国民そっちのけでシラきり通すアピール満々にしか見えない.なんだったら,蓮舫とか上川とか,そして煙たい野党議員とか,無党派で新党を立ち上げるとかやっちまえばいいのである.だって,それくらいしか,選択肢のこらなくしているわけだから.小沢解体屋というより地面師詐欺師という政治家といった方がしっくりくる感じがする.何だったら,小泉も,石破や高市とかは参戦しないだろうけど,新党に合流すればいい.安部の統一協会VIP待遇とか,政界の取り巻き連中の下心とかがポピュリズム政治の実態なわけだから,たいして問題にならない.裏商売の善人たちが日本の政治家じゃ,法も社会もよくわからん感じになるのである.というわけで,ついつい脱線してしまった.
「かくして,われわれが社会の消費性向とよぶものが与えられているとするならば,均衡雇用水準,すなわち,雇用者に全体として雇用を拡大することも縮小することも誘引しない水準は,経常投資の数量(雇用がその与えられた水準にあるときに総産出物に対して社会の人々が消費することを選択する量をこえている分を吸収するのに十分な経常投資の量が存在しなければならない)に依存するであろうということになる.次いで,経常投資量は,われわれが投資誘因とよぼうとするものに依存し,そして投資誘因は,資本の限界効率表と各種の償還期限と危険の貸出しに対する利子率の複合体との間の関係に依存していることがわかるであろう.」
「均衡における雇用量は,総供給関数Φ,消費性向χ,および投資量D_2に依存する.」「Φ(N)-χ(N)=D_2, 雇用量Nは有効需要D=D_1+D_2に依存する.」 D_1は社会の期待消費支出量,D_2は期待新投資量.
「かくてわれわれは,消費性向とよぶところのものを,賃金単位で測定した所与の所得水準Y_wとその所得水準からの消費への支出C_wとの間の関数関係χ,C_w=χ(Y_w)として規定するであろう.」
雇用は契約だから,しかも自由な契約だから,均衡の成立のなかでの類型(投資の予想収益とその生産費)の限界効率,つまり,類型の収益で与えられる年金系列の現在価値をその供給価格に丁度等しくさせる割引率,で最大のものが資本の限界効率と呼ばれるものになるから,競争やそのゲームから得られるお得感からも自由なのである.お得感が欲しいというのと,稼いでいる青年実業家になりたいということがほぼ同義に使われていることを考えれば,案外身近な感覚である.
不確実性が,初期値の設定によって不可避となるのであれば,初期値を一定にして確実なものにするか,一定条件を満たすが,そこに内蔵される不確実性を反映させるかというケースが考えられそうだが,後者の場合,予想が外れるリスクは常に生じるわけだから,仮に正しい予想が得られたとしたら,正しい予想値をマイニングしたという利益を手に入れられる.これが投機動機となって,利子は流動性を犠牲にすることで生じる対価であるという流動性選好説に結びつく.ちょっと,話題性優先で,勝手な解釈をいってみたが,案外,ありそうな解釈だから怖いところである.短期(n期間)利子率i_1, n期間時点で買うr年据置利子率i_3,長期(n+r年)償還債権の利子率i_2. 不確実性が存在しない場合,(1+i_2)^{n+r}=(1+i_1)^n(1+i_3)^r.あるいは,ケインズが用いたndr=1d{n+r}/1dn. ndrは利子率i_1でr年間据え置く結果元利合計が1ポンドになる第n年における債権の現在の値.
現実の資本主義経済が,ケインズの主張通りに行動しているわけではない.低金利の下でも,企業の大きな内部留保の存在によって,利子率や資本の限界効率を投資決定の決定要因としない独占的投資計画が支配的となることが,その説明として挙げられる.独占と発展,独占資本政策の動態が,例えば,ウイルスとその作用のように,あるいは,動枠的な作用のように,既存の観察からの新規的発見やあるいはそれらの結果の破壊の一種のブラウン粒子のように,イマージュの総体の運動の身体記憶のように立ち現れる,なんて感じで動いているのかもしれない.というのも,そろそろ字数制限超えそうだからである.ケインズの経済理論については,『原典による経済学の歩み』講談社と『コメンタール ケインズ/一般理論』日本評論社からのつまみ食いである.
残り1400字ほどなので,経済の芸能化というのかペダンティズムというのもあるから,経済理論なんて儲けはないうえに,アホチョン連中からハラスメント受けやすいという面もありそうである.せいぜい,時の話題にのかっかって,お店のおねいちゃんたちの気でも引ければ儲けという程度のものである.その分,気は楽な問題であるが,経済問題がなんか空々しいは,景気のいい話が現実にそうそうあるわけでもないから,気分だけしたっていたいということも一因としてあるのだろう.その言い訳に使われるのが独占資本主義論というのも悩ましい問題である.アカデミックな経済理論のまわりには,官製経済理論とメディア経済理論が三つ巴であるらしいが,結局,経済の現実と対峙するような経済理論はないということなのだろうか.そこで生成AIの描くコラージュコピー経済理論が待望されるわけである.経済に対する信頼情報は生成AIから得られるから,バカな政治家だの官僚だの,経済界だのの話は,どんだけ間抜けな人間味が伝わるかだけのしろものと受け止められるから,案外,安定するかもしれない.
無意味な改行で空行ができて文字数を消費してしまっていたので,残り4000文字ほど残っている.せっかくなので,『原典による経済学の歩み』から,目を引く箇所をコピペすることにする.一寸思ったのだが,これもコラージュコピーの文字数換算みたいなものなのだろうか.私は,生成AIの文字数換算による字数制限に制約されている.
「経験は投機的動機を満足する総貨幣需要は通常は利子率の漸時的変化に対して連続的に反応していることを示している(投機的貨幣需要の変化と利子率の変化を関連付ける一つの連続的曲線が存在する)」.「取引動機および予備的動機を満たすために保有される現金量をM1, 投機的動機を満たすために保有される現金量をM2とする.」
「これら二つの現金の区分に対応して,二つの流動性関数L1およびL2をもつ.M=M1+M2=L1(Y)+L2(r). L1はM1を決定するところの所得Yに対応した流動性関数であり,L2はM2を決定するところの利子率r(L2はもっぱら経常利子率と期待状態の間の関係に依存する)の流動性関数である.L1はYの増加関数,L2は利子率の将来についての期待の状態が与えられるときにはrの減少関数として記述することができる」.
「コメンタール ケインズ/一般理論」では,関連して「資本の希少性理論」が論じられている.
ケインズの「一般理論」は難解なイメージがあるが,例えば,ケインズの経済学はイギリスの(ための)経済学であり,ケンブリッジスクールの身内サークルの経済学であって,外から見ると,隠語的な話も多く,どういうことを言っているのか了解するには,おやじが若者言葉を理解するには別途ギャル語辞典のようなものが必要となるとかという感じで,覇権大国の凋落と新覇権大国の台頭の象徴のように,実際採用されているのは,アメリカのケインズ理論であるとか,その背景事情も一癖ありそうである.金本位制復帰とかその具体例として挙げられている.そういうことはあっても,ケインズの経済理論が21世紀の世界に有効な視点をもつことを再認識され始めている,というのが現状のようである.こういういくらかでも内容のある学閥とか学的サークルなんてものがほんとに実在するものなら,わたしはそれもありじゃないかと思う方だが,慶応閥のようにもどき芸人のやらせ商法のような学閥が実態というのだから,そりゃなしでと思うのである.日本会議とかいう変なアホチョン連中の下請け学閥ぽくって,なじめない.
マルクスの『資本論』については,以前にも言ったように,高校2年生のころ,学校の図書館の世界の名著シリーズの棚の中からあずき色の『マルクス・エンゲルス』借りて(しばらくして,ペーパバック版の2冊本になっていたが),内容は「解説」と『資本論』の一部省略されているようだが翻訳というものだが,徹夜して読んだのが最初だが,なにせ,そもそも経済とは,あるいは経済学とはさえ,たぶん言葉としては知ってたと思うが,ほぼ白紙の状態で読み始めて,とにかく読み通すかと思いながら読んだことを覚えている.その後,国民文庫版の資本論全巻を生協で買って読んで,まあ,一応,まっとうに読んだことにはなるだろうくらいの満足感を得ている.当時は,『資本論』第一巻の商品物神ぐらいまではだいたい暗記していたが,あれなんだったけという箇所に引っかかったときはそこを読み直してみるという感じだったので,完全な暗記ができていたわけではないが.もちろん,マルクスの『資本論』が,社会や歴史あるいは政治や宗教,法律,哲学などに広範な影響をもつもので,向坂逸郎は蔵書10万冊だったそうだが,数冊,あるいは数十冊でへとへとの身には,それだけ読んでも知識量は増えないから効率が悪い読書に違いないと,納得するようにしている.マルクス自身の読書量も常識外れだったのだろうが,大英博物館の蔵書を,経済理論や統計,経済史,社会運動史とかにわたって(もともと法学,哲学,文学関係もよんでいたのだろうが),あるいは数学の文献まで読み漁っていた生涯だったらしいが,読書量と知識量は必ずしも比例しないという気慰みで対応することにしている.それと,不思議な感覚なのだが,「商品の物神的性格」は何故か記憶から消えていて,読み返しても覚えられない.岩波新書で大塚久雄とか「物神性」理解の重要性を説いていたと思うが,何らかの「心理状態に依存する」という話でもないだろうが,ちょっと構造的なメカニズムが隠喩されているのだろうか.ちょっと正確ではないのだが,『資本論』は,もともと,労働プチブルご婦人方の勉強会サークル用のパンフレットとして書かれたもので,そういう熱気も現在に受け継がれているのだろうか.気の弱い私にはちょっと御しがたいが.そこも普通に言えば,経済学批判で萌芽を得た経済学体系プランの基底部分を大成させたものが『資本(論)』で,マルクス・エンゲルスはその一応の完成をなして死んじゃったから,その後の進展の混乱を後継者たちが醸し出しているらしいが,あるいは,右翼的な攻撃というのか悪用に使われたり,アカデミズムのペダンティズムに堕落したり,面白みも薄まって,マルクス『資本論』は終わったらしい.マルクスでは,「カネ」というのは一般的等価形態にある商品であるから,お金があれば大抵のものが買えるのもカネがそういう商品だからで,拝金主義はそれを倒錯して感じる変態オヤジの意識のレッテルに過ぎない.
ケインズ三部作というものを挙げるとすれば,私の印象では,といっても客観的な根拠はないが,かじり読みした解説書の部分とかからの印象で選ぶとすれば,(1)『確率論』,A Treatise on probability, 1921, (2) 『貨幣改革論』,A Tract on Monetary Reform, 1924, (3) 『雇用・利子および貨幣の一般理論』,The General Theory of Employment, Interest and Money, 1936. (1) 『確率論』はケインズ自身の学生時代の苦い思い出が背景にあるとか,「論理学」と「確率」についてのケンブリッジ的特徴というのか伝統というのかとか,<a/h>とか,「aというのは確率の高いと考えられる命題を表し,そしてhというのはaの理論前提を構成している命題を表している.そしてh/a =1の場合,それを「確実」(certainty)というふうに定義している.」(『コメンタール ケインズ/一般理論』の「確信の状態とは」.論理学で言えば確率命題という感じだろうか) 普通に私たちが考える確率論とはちょっと異色なものだとか(ベイズ確率ポイ感じは受けるが),それと経済学とのかかわりとか,気にはなる問題をはらんでいる感じだから,(2)『貨幣改革論』は,比較的読みやすいというか,経済用語のわかりやすい説明としても読めそうだから,(3) 『ケインズ一般理論』は,主著の位置づけだろうから.
流石にそろそろまとめるには,あと,生成AIによるコラージュコピー経済論を論じなければならないが,マルクスは資本主義の完成期をイギリスの古典派経済学を検討しながら,ダイナミックに経済学批判体系として大成し,ケインズは,覇権大国イギリスの衰退期における,資本主義の変貌期の経済を,新たな発見や破壊を通じて,対処する方法を開いてたとすれば,それらをさらに俯瞰知的に,あるいは環境知的に実現する理論が現在求められているのかもしれない.それを,私のちょっとした思いも込めて,コラージュコピー経済理論とすればいいのじゃないかという提案である.
W-G-WとかG-W-Gとか,「単なる持ち手交換」に過ぎない図式が,商品の物神的性格を表す図式となり,W-G, G-WとかG-W, W-Gの闘争的結合に結果し,資本主義成立の条件である本源的蓄積から自律して資本主義の運動の推進力として保存される.マルクスのこのような解析も,ケインズが,古典派経済学の第二の公準をセー法則およびその下での完全雇用の前提での不完全な理論として,非自発的失業を認める理論へ一般化するときの念頭にあったのかもしれない(参考: 世界の名著『ケインズ・ハロッド』の「解説」部分).












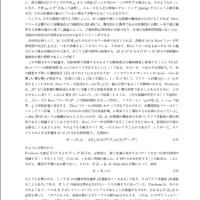
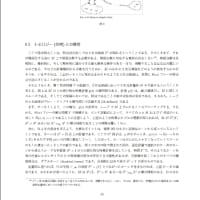
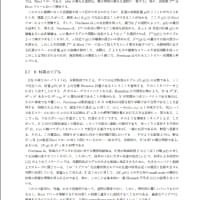
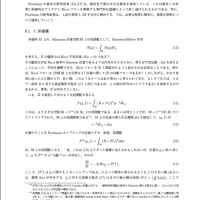

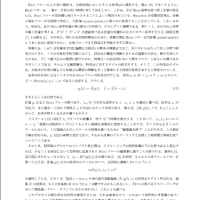
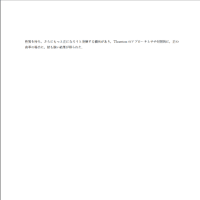
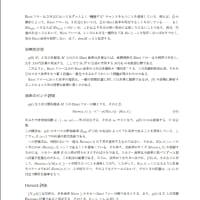
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます