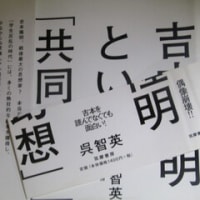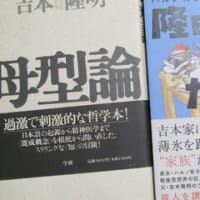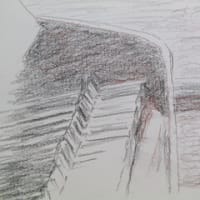夏目漱石を読むという虚栄
2000 不純な「矛盾な人間」
2400 「精神的に向上心がないものは馬鹿だ」
2410 文豪は悪文家
2411 「向上心が」「精神的に」「ない」
『こころ』で一番有名らしい文を読もう。
<『精神的に向上心のないものは、馬鹿だ』
(夏目漱石『こころ』「下 先生と遺書」四十一)>
「精神的に」の被修飾語が決まらない。〈「向上心」が「精神的に」「ない」〉なんて意味不明。〈「精神的に」「馬鹿だ」〉と考えても、やはり意味不明。〈「精神的」な「向上心」〉とやっても、やはり確かな意味はない。〈「精神的」方面「に」おいて「向上心のないものは、馬鹿だ」〉と補うと、やっと日本語らしくなるが、まだもやもやしている。〈肉体的方面にしか「向上心のないものは、馬鹿だ」〉という意味か。つまり、〈体育会系は馬鹿だ〉と言いたいのか、言ってもいいけど。
<よりよい方向を目指し自らを高めようとする心。
「―のない人」「精神的に―のないものは馬鹿だ〈漱石〉」
(『明鏡国語辞典』「向上心」)>
この説明と本文を合成すると、〈「精神的に」「よりよい方向を目指し自らを高めようとする心」「のないものは馬鹿だ」〉となる。この場合、「精神的に」の被修飾語は「よい」だ。この辞典によれば、本文では被修飾語が欠落していることになる。だったら、本文は悪文と判定してよい。ところが、『こころ』の作者がこれを悪文として表現している様子はない。だから、文豪Nは悪文家だろう。そうでないのなら、この辞典は間違っている。
<「問題の日本語」には、〈問題として出されている日本語〉〈問題になっている日本語〉などの意味と、〈問題のある、変な日本語〉という意味がありますが、「問題な日本語」には前者の意はなく、〈問題のある日本語〉の意に限定され、誤解なく伝わるという利点もあります。
(北原保雄『続弾!問題な日本語――何が気になる? どうして気になる?』)>
「問題な日本語」の「な」を、「のある、変な」と言い換えてわかったつもりになれるのなら、「問題な日本語」は問題な日本語ではないわけだ。しかし、「精神的に」は違う。「に」を弄った程度ではわかったつもりになれないのだ、私はね。
<私は先(ま)ず『精神的に向上心のないものは馬鹿(ばか)だ』と云い放ちました。これは二人で房州を旅行している際、Kが私に向って使った言葉です。
(夏目漱石『こころ』「下 先生と遺書」四十一)>
「馬鹿」の真意を知っているのは、Kだけだ。Sは知らない。作者は、どうか。
2000 不純な「矛盾な人間」
2400 「精神的に向上心がないものは馬鹿だ」
2410 文豪は悪文家
2412 立身出世
「向上心」というと、スマイルズの『向上心』が連想される。彼の『西国立志編』と訳された『自助論』は「西洋の個人主義的道徳」(『広辞苑』「西国立志編」)を説いたものだが、「しばしば立身出世の文脈で読まれた」(『日本史小辞典』「西国立志編」)という。
<当時のベストセラーであるスマイルズの『西国(さいごく)立志編』(1870~71)や福沢諭吉の『学問のすゝめ』(1872)は、人々に自らの才覚と努力で立身出世(=上昇移動)を勧める内容であり、また当時の個人レベルの立身出世はそのまま国家レベルの立身出世(=列強への追い付き)と重なり、立身出世は公的にも正当化された。その後明治後期からしだいに社会階層が固定化し安定化するようになると、社会的上昇移動のコースは学校や官僚制によって制度化され、それとともに立身出世の観念も当初の野性味を失い、形式化、矮小(わいしょう)化されるに至った。
(『日本大百科事典(ニッポニカ)』「立身出世」麻生誠)>
『それから』の代助の父の世代では、「個人レベルの立身出世」と「国家レベルの立身出世」が一致していたようだ。代助の世代では大義を失ったためか、彼は「nil(ニル) admirari(アドミラリ)の域に達して」(『それから』二)いた。〈ニル・アドミラリ〉とは、〈無関心〉とか〈無感動〉とかいう意味だ。この言葉は『舞姫』(森鴎外)に出ている。昭和中期に〈無責任〉が加わり、〈三無主義〉と言う言葉ができる。その後、〈ハレンチ〉が流行。その後、〈シラケ〉だ。
<我々は実際偉くなる積りでいたのです。ことにKは強かったのです。
(夏目漱石『こころ』「下 先生と遺書」十九)>
どんなふうに「偉くなる積り」だったのか、具体的に語られてない。ありふれた立身出世を願っていた様子はないから、「偉く」は意味不明。
「強かった」は、〈「積り」が「強かった」〉と解釈する。
<けれども天の与へた性質から言ふと、彼は率直で、単純で、そして何処か圧(おさ)ゆべからざる勇猛心を持つて居た。勇猛心といふよりか、敢為(かんい)の気象と言つた方が可からう。則ち一転すれば冒険心となり、再転すれば山気(やまぎ)となるのである。現に彼の父は山気のために失敗し、彼の兄は冒険の為に死んだ。けれども正作は西国立志編のお蔭で、此気象に訓練を加へ、堅実なる有為の精神としたのである。
(国木田独歩『非凡なる凡人』)>
Kの雑言に含まれた「精神的に」の「精神」は「堅実なる有為(ゆうい)の精神」とは違うようだ。むしろ、その逆で、「山気」だろう。〈Kは「山気のために失敗し」て「冒険の為に死んだ」〉と言える。ただし、その「冒険」は内向きであり、「精神的に」頑張っていただけだ。その非現実的な「向上心」を、Kは「精進(しょうじん)」(下十九)という言葉で美化していたらしい。
2000 不純な「矛盾な人間」
2400 「精神的に向上心がないものは馬鹿だ」
2410 文豪は悪文家
2413 「精神的に」しか「向上心のないもの」
Kに、スマイルズ風のポジティブな「向上心」があったろうか。
<寺に生れた彼は、常に精進(しょうじん)という言葉を使いました。そうして彼の行為動作は悉(ことごと)くこの精進の一語で形容されるように、私には見えたのです。私は心のうちで常にKを畏敬(いけい)していました。
(夏目漱石『こころ』「上 先生と遺書」十九)>
「彼」はKだ。この「常に」は〈しばしば〉などが適当。
<「梅雨時はいつも調子が悪い/梅雨時は常に調子が悪い」を比べると、「いつも」は“梅雨時になると毎年きまって調子を落とす”で、「常に」は“梅雨の期間中はずっと調子がよくない”である。
(森田良行『基礎日本語辞典』「いつも」)>
Kの「行為動作」の具体例は語られない。「悉(ことごと)く」は誇張。「私には見えた」には、〈私以外の人間には見えなかった〉という含意がある。Sは、Kの「精進(しょうじん)」芝居の唯一の観客だったようだ。Kは、Sに煽られて芝居を止められなくなっていたのかもしれない。
〈「私は心の」そとでは「常にKを」侮蔑していました〉という文が見え隠れする。
<こうして第一章で確認したように、近代国家の確立に伴う国家体制の整備・固定化により、一種の閉塞状況が青年層にもたらされた。「神経衰弱」という言葉がこの頃初めて使われ出したことに示される「煩悶青年」、「女学生との遊蕩に耽っている」と非難された「堕落青年」、他方では「一攫千金」を夢みる「成功青年」などの青年の諸タイプがこのアノミー状況に応じて登場してくる。そしてこれらの青年層向けに「努力による人格の修養」を第一義とする修養書が大量に書かれ、修養書ベストセラー時代が出現するのである。そしてさらにこのプロセスの中で修養主義が確立し、大正、昭和へと分極化しつつも受け継がれていくことになる。
(筒井清忠『日本型「教養」の運命―歴史社会学的考察』)>
Kは書淫つまり活字ヲタクだったようだ。活字中毒。本の紙魚。
<彼は寧ろ神経衰弱に罹(かか)っている位なのです。私は仕方がないから、彼に向って至極同感であるような様子を見せました。
(夏目漱石『こころ』「下 先生と遺書」二十二)>
「彼」はKだ。〈「精神的に」しか「向上心のないもの」〉は「神経衰弱」だろう。
静の存在とは無関係に、SはKを騙していたのだ。
(2410終)