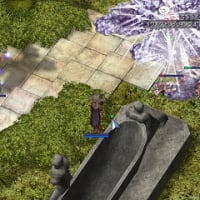それは、友人のすすめでジュノーのヴァルキリー神殿へお参りした後の帰国の途だった。
ファーシェというその友人は、私の祖国であるアマツを旅行したいと言うので、今度は帰郷がてら案内役をしていた。
港から石田公の座す城下町へ至る道中だった。
そろそろ宿を見つけようかと思っていた夜に、木々の鬱蒼とする道で私達は襲われたのだ。
大量の魔物の群れに。
完全に不意をつかれた。アマツの街道にまでこんな魔物の手が及んでいるとは思いもしなかった。
彼らと対峙した時、ふとシュバルツバルドの神殿で対面したヴァルキリーの言葉が頭をよぎった。
―あなたの人生には剣難のようなものが刻まれています。
とても言いにくいことですが、あなたはきっと人並みには長生きできないでしょう。
しかし、それが何年後になるのか、あるいは数日後になるかは、私にも見通すことはできません。
どうか、運命を恐れないで下さい。そしてその時が来たら、運命を受け入れて下さい。
心配はいりません。天にます主神(Odin)はあなたの新しい人生を約束しておいでです。
ともすればこの者達は、禍々しい形相ではあるものの、神の召された使いなのだろうか。
いずれにせよ、放っておけば近隣の村落にも被害が及ぶのは間違いない。
この場で排除する必要がある。さっと鞘を抜いた。
敵が距離を詰めてくる。ミズハもそれに突進していく。
もう若くはない年頃だが、剣の腕はまだまだ劣っていない。
群れの数は想像を遥かに超えていて、あっという間に周囲一面が魔物で埋め尽くされてしまう。
背丈は私達より頭三つ分ほども大きく、その姿形は狼に似ているようだが、二本足で立ち、全身を漆黒の毛が覆っている。
手足に生える爪や、口からのぞく牙は不釣り合いに長い。
手ごたえを確かめながら斬りつけていき、一つ、二つと屍を増やしていく。
これまで相手にした中ではだいぶ強い部類の魔物だが、いつもと変わりなく戦えるだろうと判断した。
そのつもりだった。
ところが、不意を突く形で大きな悲鳴が鼓膜を打ちならした。
気が付き振り向くと、ファーシェは強打を受け、姿勢を崩して尻もちをついていた。
深い傷はないようだが、魔物に四方を包囲されていてかなり危険な状況を呈していた。
その時ミズハははっとして、そして自分の浅はかさを深く悔いた。
私は村正を手にしてしばらくしてから、誰かと共闘することはほとんどなくなっていた。
その癖が身体に染みついたせいか、ファーシェのことをあろうことか忘れてしまっていた。
私は一人ではなかったんだ…。
その状況を見て思い直した。何かを守りながら戦うというのは、実にやりづらく難しいことだ。
もしかしたら私はここで死ぬかもしれない。そうだとしたら、思ったより随分と早い最期の訪れだ。
私はそれでいい。私は自分の運命を選択し、それを受け入れてきたのだ。
だがここにいるのは私一人じゃない。ファーシェがいる。
彼女を道連れにするわけにはいかない。
私は死ぬ。私はそれでいいが、彼女の命だけは守らねばならない。
この状況を打開するには、今までで最高の戦い方が求められていると感じた。
ここが私の死に場所となるなら、やはり己の力の限界を試さずにはいられない。
今がまさにその時に相応しい。きっとそうに違いない。
そう思うと、恐怖心が抜けていき、不思議なほどに冷静さを取り戻せた。
この剣が、村正が私の意識をしかるべき方向へ導いている、そんな気がするのだ。
ミズハは疾風になって、ファーシェのもとへ駆けだした。まさしく風だった。
まだ群がるように残っている魔物たちは、獰猛にその後を追いかける。魔物はさらに素早かった。
ミズハは彼らが追いつこうとすると、鮮やかに身を翻して斬り伏せ、走ってはまたそうやって斬り伏せる。
その太刀筋は恐ろしいほどに正確でいて、冷徹だった。
後頭部に眼があるのではないかと思うほど、背後に対する間合いの読みにためらいがない。
ファーシェに群がる敵へミズハは肉薄していき、稲妻のように隙間を縫って剣戟を加えていく。
そのほとんどは一筆の剣筋に致命傷を負い、その場に絶命していった。
ファーシェはふとその光景を目に入れた。まるでミズハが鬼神のように見えた。
ミズハが、初めて畏怖を抱かせる対象になった瞬間だった。
だが、この感情が単なる恐怖ではないことをファーシェは咄嗟に悟った。
私の中にある、身体でも心でもない別の存在が、その立ち合いを見て震えている。
その強さは尋常ではなく、恐怖を覚えたが、しかし美しかった。
恐ろしいほどに美しいと言うべきか、あるいは、美しいほどに恐ろしいと言うべきか。そう言ったほうが的を得ているかもしれない。
見ているうちに圧倒され、私は我を忘れた。
まるで自分の体が、あの妖刀を振り回している彼女と一体化したような感覚に陥る。
ファーシェを狙おうとした魔物たちの大部分はまだ目の前に健在だったが、
ファーシェはそれを不安だとは思わなくなっていた。
これこそが、境地に達した者が成せる業なのかと、そう思う。
「これが…村正とあなたの、本当の姿なのね…?」ファーシェは虚ろに呟いた。
その時のミズハは、まさに心を空にして戦っていた。
心頭を滅却すれば火もまた涼し、とはまさに今の自分のことだろうかと思っていた。
次第に、己の肉体の感覚が薄れている。
足や腕や、あらゆる関節が自分の意思では動いておらず、魔物を含めた周囲の景色が勝手に動き回っているように思えるのだ。
自分の体そのものが村正であるかのような錯覚を受ける。いや、もはや錯覚とすら感じられない。
ふと何かが縦横無尽に、自分の立ち回りに呼応して周囲を移動していることに気付いた。
実体はないが、確かにそこにある。私が魔物を斬るたびに、呼吸を合わせて次に向かうべき場所を指し示してくれているのだ。
「コノ剣ノ魂」か、とミズハは考えた。村正の魂が、獲物を求めて鋼の体躯から飛び出たがっている。
もはや全く理屈を踏み外しているが、そんな気がした。
さっきから胸のあたりがやたら熱い。この気持ちは何だろう。
私は似たような気持ちをこれまで何度も味わってきた。
だがその大きさはこれまでとは比較にならない。
自然の摂理から外れた存在達と戦って、楽しいと思ったことはない。
けれども、それでも私を、私の意識を駆り立てるもの。
そうだ、一体感だ。私は村正と一体になろうとしている。
お互いがその魂を求めあっているのだ。
村正の意思は使い手を求め、ヒトはあらゆるしがらみを断ち切るために、村正という利器を欲する。
人と剣が互いにその心を開き、その気持ちがめぐり合う瞬間、剣士という愚直な生き物はやっと自由になれる。
その一瞬だけ、自由な存在となるのだ。
あっという間にあたり一面は魔物の骸だらけになった。
死の奔流を浴びせ続けたミズハはその姿勢のままに、息も荒く周囲の状況を確認する。
その向こうに、一つの大きな影が立っている。群れの統率者、リーダー格の魔物だと察知した。
その双眸は静かに、しかし激しい怒りをこちらに向けているのを感じる。
すぐに襲いかかってくるという感じはしない。きっと、仲間を全滅させる力量を持つ私を警戒しているのだろう。
「その時」をうかがっている。
少しの間、張りつめた空気が両者の間に落ちていた。
これは難敵だと、ミズハは感じた。一寸たりとも油断できない。
私が攻撃動作に移るか、背中を向けようとすればたちまち襲ってくるだろう。
だが、それは相手にしても同じなのかもしれない。
隙を見せれば自分も仲間と同じく、この剣士に必殺の一撃をもらうだろう、と。
おそらく相手も同じ気持ちで、私の出方を貪欲に、じっとうかがっているのだ。
「…それなら。」
ミズハは身を正して、村正を空中に一振りして刀身の血を振り払い、…すかさず鞘におさめた。
それを見たファーシェは、ミズハがアマツの抜刀術を使おうとしていることに気づいた。
私が腰を低くして構えをとると、次の瞬間には案の定、敵は地面を激しく蹴ってこちらに突進してくる。
恐ろしい速度だった。どんな歴戦の剣士でもそうそう体験できない速度だ。
それでもミズハは少しも怯まず臆せず、ただ自分の間合いの感覚に全身全霊を傾ける。
再び、何かの存在を近くに感じた。村正の意思か。
私はそれに、自分の意思を重ねようと試みる。それは何の抵抗もなく私を受け入れてくれた。
もう一度、私は村正になる。村正は私になる。何も恐れることはない。
その時が来れば、しかるべく私は導かれ、この者を討ち取るだろう。
ミズハはもう、自分の肉体を感じなくなっていた。
ただ、二つの魂が一つとなって魔物と対峙しているのみだ。
ファーシェは立ったまま、凍りついたようにそれを見ていた。
世界から音が消える。一切の静寂。
魔物が迫りくる、刻一刻と。
魔物が不気味な大爪をこちらに付き出す刹那、ミズハにはその動きがやたら遅くなったように見えた。
同時に、目の前に現れた「何か」から、自分の体に電流のようなものが流れ込み、指先に向かっていく―。
「見える!見える!」
電流が村正の柄を経て、ついにその黒い刀身を打ちたたく時。
ガッと心地いい音が響き渡り、刀が鞘から目にもとまらぬ勢いで飛び出した。
その一瞬の息合いは、まさに葉から滴がこぼれ落ちる一瞬の如く。
目の前が真っ暗になり、衝撃が身体に襲い来る。
それと行き違うように、自分の腕が、剣が、微塵のためらいもなく魔物を一閃した。
骨肉が刃に抵抗する感触は少しもなかった。
だがミズハは確信した。斬った。この者の肉体を完膚無きまでに斬った―。
呻くように断末魔を張り上げたその巨躯の獣は、宙に舞う枯葉のように背後に倒れた。
目で見てはいない、気配で感じてはいない。しかし、何かが私にその実感をもたらしてくれていた。
私が勝った。無上の悦びだった。今まで感じることがなかった情熱のようなもの。
その時間は、永遠に続くかのように思われて、けれどもそうはならなかった。
夢心地に浸っていた私の意識は、静かに薄れゆこうとしていた。
「―ッ!!」
ファーシェは絶叫しようとした。が、あまりにも力が入り過ぎて声にならない絶叫だった。
ミズハの放った一撃は、魔物の右腕を切断し、右わき腹から食い込んで背中を突き破りながら、
右胸の下あたりにまでに達していた。
人が二人がかりで引っ張れば、たちまちにちぎれそうなほどに深く、残酷な致命傷だ。
まさに必殺必中の剣。だが、ファーシェはそれどころではなかった。
魔物が倒れ落ちると、ミズハの姿を視認できた。
村正を右上に振り切った姿勢のまま、彼女は石像のようにその場に固まっていた。
その彼女の胸を―斬り落とされた魔物の右腕が貫いている。
不思議な感触に気付いたミズハは、自分の胸元にゆっくりと視線を下ろす。
すると、二の腕の中ほどで切り離された魔物の右腕は、甲冑を破って自分の胸に突き刺さっていた。
禍々しく、人外に太い魔物の腕は、明らかに心の臓を食いちぎっているのがわかった。
(なあんだ、刺違えたのか―)
童心のように無邪気にそう思った途端、視界が歪み、のたうちまわり、目の前から消えた。
痛みは感じない。死への恐怖もない。何の感情も浮かんでこない。
文字通り、私の『心』の中は本当に空っぽだった。
自分の肉体の感覚は、もうほとんどなかった。
まるで元いた世界から、いきなり別の世界へ吹き飛ばされてしまったようだ。
ふと手元にあるはずの村正の気配がなくなっている事に気付いた。
(どこだ、どこだろう。)
おかしいな、さっきまで確かにこの手に握っていたのに―。
落としたのか。いや違う。村正はもっともっと遠くに行ってしまったように思えた。
目の前がふっと明るくなり、何かが現れる。霧のようにぼやけて掴みどころのないそれは、やがて人のかたちに変わった。
この顔を私は知っている。誰だろう。
母親のように見えるが違う。私に剣術を授けた恩師たちのうちの、誰でもない。
村正に呪われるまでは親しかった、昔の友人かなと思ったが、そうでもない。
いや、ファーシェか。ファーシェじゃないのか…とも思った。
ところが、次の瞬間にはファーシェでさえない、ある人間の面影がそこに映し出されていた。
これは自分だ―。しかも今の自分ではない。今よりずっと若い自分。
そう、ちょうど村正を手にしたくらいの頃の自分に見えた。
もう一人の自分は、手を差し出して私に呟くのだ。
「私達の魂は解放された。私達の魂は空に還ることになる。
さあ。次なる世界へ行きましょう。
私達の意識は間もなく消える。けれど、怖がることなんてない。
魂が―同じ時空を生きた私とあなたの魂が、導いてくれるわ。」
私達という言葉を聞いて、ミズハは目の前のもう一人の自分が、村正の心なのだと思い至った。
私がこれまで村正に投射してきた私の姿を、村正は己の姿として得ていたのだ。
きっと、そうなんだろう。きっと…。
魂は天空に、身体は大地を求めて還っていくものだ―そうファーシェはよく言っていた。
ミズハもいつしか、その言葉を信じるようになっていた。
私の魂もまた、村正と共に天の主神のもとへ召されるのだろう。
そして身体はきっと、アマツの地に還っていく。
私が倒れるこの土へ。愛する故郷の土へ。とても幸せな気分がした。
けど…、そうだ。ファーシェがいる。まだいる。そばにいるような気がする。
私は死ぬんだ。この世界にはもう戻ってこれない。それが死というもの。
ファーシェには、もうこの世界では二度と会えない…。
私は、もう一人の私の手に掴まれようとしている。あの世へ行こうとしている。
いや、ちょっと待って―ファーシェに何か言わなきゃ。
石像のように立っていたミズハは、唐突もなく崩れ落ちた。
その全身は血まみれなのだが、どす黒いものも混じっていて異様な色に染まっていた。
ファナはその脇に急いで走り寄る。頭の中は真っ白のまま。
「しっかりして―」
と言いかけて、傷を確認したファーシェはその凄惨さに絶望した。これでは確実に助からない。
心臓や肺は押しつぶされ、抉り取られて、ほとんど残っていないように見えた。
私が起こしうるどんな奇跡でも、
いや、大陸が誇るいかなる蘇生儀式をもってしても、彼女はもう救えないだろう。
言いようの知れない恐怖にファーシェは駆られた。
ミズハは仰向けのまま、唇を微かに動かして何かを言おうとしている。
だがこの体では、もうどうあがいても声を絞り出せると思えなかった。
ファーシェはその残酷な事実に打ちひしがれて、がっくりと顔を落とした。
もうこれまでだと思って目を閉じかけたその時、声が聞こえた。
またどこかで会いましょう―。
ファーシェははっとして、ミズハの顔を再び見やった。
が、彼女は瞼を下ろしたままで、もう二度と微動だにしなかった。
この声はどこから?ミズハの口から発したようには思えない。
私の錯覚か、あるいは彼女の声なき声か…。
ミズハは穏やかな顔をしていた。苦痛は感じてなさそうだが、かといって微笑んでもいない。
どこまでも穏やかで、安らかで、あらゆるものから抜け出している。そんな表情だった。
大陸の遥か東の世界に伝わる「ホトケ」のような顔だと、ファーシェは思った。
ふいに、何かが自分の中から湧き上がってきて、溢れ出そうになった。
それをせきとめたくて、私は思わず顔を両手で覆った。
力もなく、その場にしゃがみこんでしまった。
私は涙が止まらなかった。彼女のそばで、ずっと嗚咽していた。
ミズハさんは死んでしまった―いや、この言い方は嫌だからやめよう。
彼女の魂は解き放たれたのだ。解き放たれて別の世界へ行ってしまったのだ。
「ミズハさんは、行きたいところに行けたのか、な…?」
そう呟くと、すぐ近くで金属を小さく叩いたような音が聞こえた。
ふっとその方を見ると、そこには村正があった。
血を帯びて地面に横たわる村正の刀身は、…中ほどで真っ二つに折れていた。
かつてそれが宿した魔性の美しさは、もはや見当たらない。
ファーシェの問いに答えたと言わんばかりに、村正はその命を終えていた。
そうか。そうなんだ。この子も一緒に召されたんだ。
主人と一緒に最期の役目を果たして、この黒鉄の体から飛び出したんだ。
いい子だったのね、とファーシェは思った。
さらに涙が出てきて、どうしていいかわからずに泣いた。声を上げて。
ずいぶん長い間泣いていたと思った。
少しだけ落ち着いて、ファーシェはそこから周囲を見回した。
辺り一面が死体の山になっていた。もう何かが襲いかかってくるような気配はしない。
そよ風の音と、植物の葉が揺れてこすれ合う音しか聞こえない。それ以外は、全くの静寂。
東の空がもう明るい。太陽が地平線から顔をのぞかせている。
「水と日の満ちる国」と言われていた自分の故郷を離れ、
大陸で戦いに明け暮れていたミズハがいつも見つめていた、祖国の日の出だ。
ファーシェはゆっくりと、少しふらつきながら立ちあがった。
自分も、自分の道を歩いていこう。ミズハがあの陽光の橋を渡って行くように。
「また会いましょう、ミズハさん。どこかで…」
その後、ファーシェはミズハの遺体を彼女の故郷―天ツ出泉水国(イズミノクニ)で丁重に葬り、
それからシュバルツバルド共和国へ帰国した。
やり残したことがなくなったら、自分もヴァルキリーと対話して、転生の約を授かろう。
ファーシェはそう決意して、残りの生涯を過ごすことにした。
またいつどこかの世で、彼女の魂にめぐり会えることを祈って。
―数百年後
こんな言い伝えがある。
遥か昔、この国には呪われた刀が存在した。
徒に返り血を好むその刀は、その魔性の美しさゆえに使い手の人生までをも狂わせてきた。
かつて人々はみな、その銘を持つ刀を忌み嫌い、記憶からもこの地からも遠ざけていった。
ある時、異国の地でそのうちの一振りが名もなき剣士の手に渡った。
剣士も例に漏れずその狂気に魅せられ、いつしか孤独に陥ってしまう。
だが剣士は数多の魔物は殺したが、人は殺さなかった。
最期の瞬間まで刀を使い続け、ついに剣士と刀は互いに心を開き、そして共に命を落としたという。
その時から、刀はもう妖刀ではなくなった。
狂気も呪いも消え去り、常人に扱えるものになった。
初めて人を殺すためだけの凶器ではなくなったのだという。
その銘を、伊勢千子村正。
その剣士がいたおかげで、村正は名刀として伝えられてきたのだ、と。
―でも、それだけではないと思うのです。
かつて、望まずも妖刀を世に生み出してしまった刀匠の思い、
そしてそれに魅せられた多くの人々の人間模様があったことと思います。
この世に限られた本数しかないそれは、使い手たる人間がそれを望み、欲したからこそ、
見えない部分で形を変えながら、今も生きているんじゃないか…
村正の一振りを現代に伝える家の人間として、そんな気がするのです。
どれくらい昔のことなのかははっきりとはわからない。事実かどうかも定かではない。
けれど村正の物語は、昔の人の口伝から形を変えて、書物になって確かに今も存在しています。
(天ツ国卯年五月)
―私は今年、120年ぶりにアマツからミッドガルドへ派遣される使節団に加わることになった。
私に与えられた役目は大陸諸国の武人達との文化交流、そしてアマツ流剣術普及の一助になること。
修行し、色々なことから学び、自分を高め、その力を両国のために役立てたいと思う。
私の家は代々剣士を輩出している家柄で、この国のかたちが出来ていない大昔にも、
同じように君主の命を授かり、剣客として海の向こうへ渡った人がいるんだとか。
船へ乗船する直前に、私は祖父母から自分の一族に伝わる一振りの刀を授けられました。
由緒あるその刀は、名を村正というそうです。
いよいよ出港です。私は大陸の人々には、ミズハと名乗ります。
どうか、よい旅立ちになりますように。(完)
ファーシェというその友人は、私の祖国であるアマツを旅行したいと言うので、今度は帰郷がてら案内役をしていた。
港から石田公の座す城下町へ至る道中だった。
そろそろ宿を見つけようかと思っていた夜に、木々の鬱蒼とする道で私達は襲われたのだ。
大量の魔物の群れに。
完全に不意をつかれた。アマツの街道にまでこんな魔物の手が及んでいるとは思いもしなかった。
彼らと対峙した時、ふとシュバルツバルドの神殿で対面したヴァルキリーの言葉が頭をよぎった。
―あなたの人生には剣難のようなものが刻まれています。
とても言いにくいことですが、あなたはきっと人並みには長生きできないでしょう。
しかし、それが何年後になるのか、あるいは数日後になるかは、私にも見通すことはできません。
どうか、運命を恐れないで下さい。そしてその時が来たら、運命を受け入れて下さい。
心配はいりません。天にます主神(Odin)はあなたの新しい人生を約束しておいでです。
ともすればこの者達は、禍々しい形相ではあるものの、神の召された使いなのだろうか。
いずれにせよ、放っておけば近隣の村落にも被害が及ぶのは間違いない。
この場で排除する必要がある。さっと鞘を抜いた。
敵が距離を詰めてくる。ミズハもそれに突進していく。
もう若くはない年頃だが、剣の腕はまだまだ劣っていない。
群れの数は想像を遥かに超えていて、あっという間に周囲一面が魔物で埋め尽くされてしまう。
背丈は私達より頭三つ分ほども大きく、その姿形は狼に似ているようだが、二本足で立ち、全身を漆黒の毛が覆っている。
手足に生える爪や、口からのぞく牙は不釣り合いに長い。
手ごたえを確かめながら斬りつけていき、一つ、二つと屍を増やしていく。
これまで相手にした中ではだいぶ強い部類の魔物だが、いつもと変わりなく戦えるだろうと判断した。
そのつもりだった。
ところが、不意を突く形で大きな悲鳴が鼓膜を打ちならした。
気が付き振り向くと、ファーシェは強打を受け、姿勢を崩して尻もちをついていた。
深い傷はないようだが、魔物に四方を包囲されていてかなり危険な状況を呈していた。
その時ミズハははっとして、そして自分の浅はかさを深く悔いた。
私は村正を手にしてしばらくしてから、誰かと共闘することはほとんどなくなっていた。
その癖が身体に染みついたせいか、ファーシェのことをあろうことか忘れてしまっていた。
私は一人ではなかったんだ…。
その状況を見て思い直した。何かを守りながら戦うというのは、実にやりづらく難しいことだ。
もしかしたら私はここで死ぬかもしれない。そうだとしたら、思ったより随分と早い最期の訪れだ。
私はそれでいい。私は自分の運命を選択し、それを受け入れてきたのだ。
だがここにいるのは私一人じゃない。ファーシェがいる。
彼女を道連れにするわけにはいかない。
私は死ぬ。私はそれでいいが、彼女の命だけは守らねばならない。
この状況を打開するには、今までで最高の戦い方が求められていると感じた。
ここが私の死に場所となるなら、やはり己の力の限界を試さずにはいられない。
今がまさにその時に相応しい。きっとそうに違いない。
そう思うと、恐怖心が抜けていき、不思議なほどに冷静さを取り戻せた。
この剣が、村正が私の意識をしかるべき方向へ導いている、そんな気がするのだ。
ミズハは疾風になって、ファーシェのもとへ駆けだした。まさしく風だった。
まだ群がるように残っている魔物たちは、獰猛にその後を追いかける。魔物はさらに素早かった。
ミズハは彼らが追いつこうとすると、鮮やかに身を翻して斬り伏せ、走ってはまたそうやって斬り伏せる。
その太刀筋は恐ろしいほどに正確でいて、冷徹だった。
後頭部に眼があるのではないかと思うほど、背後に対する間合いの読みにためらいがない。
ファーシェに群がる敵へミズハは肉薄していき、稲妻のように隙間を縫って剣戟を加えていく。
そのほとんどは一筆の剣筋に致命傷を負い、その場に絶命していった。
ファーシェはふとその光景を目に入れた。まるでミズハが鬼神のように見えた。
ミズハが、初めて畏怖を抱かせる対象になった瞬間だった。
だが、この感情が単なる恐怖ではないことをファーシェは咄嗟に悟った。
私の中にある、身体でも心でもない別の存在が、その立ち合いを見て震えている。
その強さは尋常ではなく、恐怖を覚えたが、しかし美しかった。
恐ろしいほどに美しいと言うべきか、あるいは、美しいほどに恐ろしいと言うべきか。そう言ったほうが的を得ているかもしれない。
見ているうちに圧倒され、私は我を忘れた。
まるで自分の体が、あの妖刀を振り回している彼女と一体化したような感覚に陥る。
ファーシェを狙おうとした魔物たちの大部分はまだ目の前に健在だったが、
ファーシェはそれを不安だとは思わなくなっていた。
これこそが、境地に達した者が成せる業なのかと、そう思う。
「これが…村正とあなたの、本当の姿なのね…?」ファーシェは虚ろに呟いた。
その時のミズハは、まさに心を空にして戦っていた。
心頭を滅却すれば火もまた涼し、とはまさに今の自分のことだろうかと思っていた。
次第に、己の肉体の感覚が薄れている。
足や腕や、あらゆる関節が自分の意思では動いておらず、魔物を含めた周囲の景色が勝手に動き回っているように思えるのだ。
自分の体そのものが村正であるかのような錯覚を受ける。いや、もはや錯覚とすら感じられない。
ふと何かが縦横無尽に、自分の立ち回りに呼応して周囲を移動していることに気付いた。
実体はないが、確かにそこにある。私が魔物を斬るたびに、呼吸を合わせて次に向かうべき場所を指し示してくれているのだ。
「コノ剣ノ魂」か、とミズハは考えた。村正の魂が、獲物を求めて鋼の体躯から飛び出たがっている。
もはや全く理屈を踏み外しているが、そんな気がした。
さっきから胸のあたりがやたら熱い。この気持ちは何だろう。
私は似たような気持ちをこれまで何度も味わってきた。
だがその大きさはこれまでとは比較にならない。
自然の摂理から外れた存在達と戦って、楽しいと思ったことはない。
けれども、それでも私を、私の意識を駆り立てるもの。
そうだ、一体感だ。私は村正と一体になろうとしている。
お互いがその魂を求めあっているのだ。
村正の意思は使い手を求め、ヒトはあらゆるしがらみを断ち切るために、村正という利器を欲する。
人と剣が互いにその心を開き、その気持ちがめぐり合う瞬間、剣士という愚直な生き物はやっと自由になれる。
その一瞬だけ、自由な存在となるのだ。
あっという間にあたり一面は魔物の骸だらけになった。
死の奔流を浴びせ続けたミズハはその姿勢のままに、息も荒く周囲の状況を確認する。
その向こうに、一つの大きな影が立っている。群れの統率者、リーダー格の魔物だと察知した。
その双眸は静かに、しかし激しい怒りをこちらに向けているのを感じる。
すぐに襲いかかってくるという感じはしない。きっと、仲間を全滅させる力量を持つ私を警戒しているのだろう。
「その時」をうかがっている。
少しの間、張りつめた空気が両者の間に落ちていた。
これは難敵だと、ミズハは感じた。一寸たりとも油断できない。
私が攻撃動作に移るか、背中を向けようとすればたちまち襲ってくるだろう。
だが、それは相手にしても同じなのかもしれない。
隙を見せれば自分も仲間と同じく、この剣士に必殺の一撃をもらうだろう、と。
おそらく相手も同じ気持ちで、私の出方を貪欲に、じっとうかがっているのだ。
「…それなら。」
ミズハは身を正して、村正を空中に一振りして刀身の血を振り払い、…すかさず鞘におさめた。
それを見たファーシェは、ミズハがアマツの抜刀術を使おうとしていることに気づいた。
私が腰を低くして構えをとると、次の瞬間には案の定、敵は地面を激しく蹴ってこちらに突進してくる。
恐ろしい速度だった。どんな歴戦の剣士でもそうそう体験できない速度だ。
それでもミズハは少しも怯まず臆せず、ただ自分の間合いの感覚に全身全霊を傾ける。
再び、何かの存在を近くに感じた。村正の意思か。
私はそれに、自分の意思を重ねようと試みる。それは何の抵抗もなく私を受け入れてくれた。
もう一度、私は村正になる。村正は私になる。何も恐れることはない。
その時が来れば、しかるべく私は導かれ、この者を討ち取るだろう。
ミズハはもう、自分の肉体を感じなくなっていた。
ただ、二つの魂が一つとなって魔物と対峙しているのみだ。
ファーシェは立ったまま、凍りついたようにそれを見ていた。
世界から音が消える。一切の静寂。
魔物が迫りくる、刻一刻と。
魔物が不気味な大爪をこちらに付き出す刹那、ミズハにはその動きがやたら遅くなったように見えた。
同時に、目の前に現れた「何か」から、自分の体に電流のようなものが流れ込み、指先に向かっていく―。
「見える!見える!」
電流が村正の柄を経て、ついにその黒い刀身を打ちたたく時。
ガッと心地いい音が響き渡り、刀が鞘から目にもとまらぬ勢いで飛び出した。
その一瞬の息合いは、まさに葉から滴がこぼれ落ちる一瞬の如く。
目の前が真っ暗になり、衝撃が身体に襲い来る。
それと行き違うように、自分の腕が、剣が、微塵のためらいもなく魔物を一閃した。
骨肉が刃に抵抗する感触は少しもなかった。
だがミズハは確信した。斬った。この者の肉体を完膚無きまでに斬った―。
呻くように断末魔を張り上げたその巨躯の獣は、宙に舞う枯葉のように背後に倒れた。
目で見てはいない、気配で感じてはいない。しかし、何かが私にその実感をもたらしてくれていた。
私が勝った。無上の悦びだった。今まで感じることがなかった情熱のようなもの。
その時間は、永遠に続くかのように思われて、けれどもそうはならなかった。
夢心地に浸っていた私の意識は、静かに薄れゆこうとしていた。
「―ッ!!」
ファーシェは絶叫しようとした。が、あまりにも力が入り過ぎて声にならない絶叫だった。
ミズハの放った一撃は、魔物の右腕を切断し、右わき腹から食い込んで背中を突き破りながら、
右胸の下あたりにまでに達していた。
人が二人がかりで引っ張れば、たちまちにちぎれそうなほどに深く、残酷な致命傷だ。
まさに必殺必中の剣。だが、ファーシェはそれどころではなかった。
魔物が倒れ落ちると、ミズハの姿を視認できた。
村正を右上に振り切った姿勢のまま、彼女は石像のようにその場に固まっていた。
その彼女の胸を―斬り落とされた魔物の右腕が貫いている。
不思議な感触に気付いたミズハは、自分の胸元にゆっくりと視線を下ろす。
すると、二の腕の中ほどで切り離された魔物の右腕は、甲冑を破って自分の胸に突き刺さっていた。
禍々しく、人外に太い魔物の腕は、明らかに心の臓を食いちぎっているのがわかった。
(なあんだ、刺違えたのか―)
童心のように無邪気にそう思った途端、視界が歪み、のたうちまわり、目の前から消えた。
痛みは感じない。死への恐怖もない。何の感情も浮かんでこない。
文字通り、私の『心』の中は本当に空っぽだった。
自分の肉体の感覚は、もうほとんどなかった。
まるで元いた世界から、いきなり別の世界へ吹き飛ばされてしまったようだ。
ふと手元にあるはずの村正の気配がなくなっている事に気付いた。
(どこだ、どこだろう。)
おかしいな、さっきまで確かにこの手に握っていたのに―。
落としたのか。いや違う。村正はもっともっと遠くに行ってしまったように思えた。
目の前がふっと明るくなり、何かが現れる。霧のようにぼやけて掴みどころのないそれは、やがて人のかたちに変わった。
この顔を私は知っている。誰だろう。
母親のように見えるが違う。私に剣術を授けた恩師たちのうちの、誰でもない。
村正に呪われるまでは親しかった、昔の友人かなと思ったが、そうでもない。
いや、ファーシェか。ファーシェじゃないのか…とも思った。
ところが、次の瞬間にはファーシェでさえない、ある人間の面影がそこに映し出されていた。
これは自分だ―。しかも今の自分ではない。今よりずっと若い自分。
そう、ちょうど村正を手にしたくらいの頃の自分に見えた。
もう一人の自分は、手を差し出して私に呟くのだ。
「私達の魂は解放された。私達の魂は空に還ることになる。
さあ。次なる世界へ行きましょう。
私達の意識は間もなく消える。けれど、怖がることなんてない。
魂が―同じ時空を生きた私とあなたの魂が、導いてくれるわ。」
私達という言葉を聞いて、ミズハは目の前のもう一人の自分が、村正の心なのだと思い至った。
私がこれまで村正に投射してきた私の姿を、村正は己の姿として得ていたのだ。
きっと、そうなんだろう。きっと…。
魂は天空に、身体は大地を求めて還っていくものだ―そうファーシェはよく言っていた。
ミズハもいつしか、その言葉を信じるようになっていた。
私の魂もまた、村正と共に天の主神のもとへ召されるのだろう。
そして身体はきっと、アマツの地に還っていく。
私が倒れるこの土へ。愛する故郷の土へ。とても幸せな気分がした。
けど…、そうだ。ファーシェがいる。まだいる。そばにいるような気がする。
私は死ぬんだ。この世界にはもう戻ってこれない。それが死というもの。
ファーシェには、もうこの世界では二度と会えない…。
私は、もう一人の私の手に掴まれようとしている。あの世へ行こうとしている。
いや、ちょっと待って―ファーシェに何か言わなきゃ。
石像のように立っていたミズハは、唐突もなく崩れ落ちた。
その全身は血まみれなのだが、どす黒いものも混じっていて異様な色に染まっていた。
ファナはその脇に急いで走り寄る。頭の中は真っ白のまま。
「しっかりして―」
と言いかけて、傷を確認したファーシェはその凄惨さに絶望した。これでは確実に助からない。
心臓や肺は押しつぶされ、抉り取られて、ほとんど残っていないように見えた。
私が起こしうるどんな奇跡でも、
いや、大陸が誇るいかなる蘇生儀式をもってしても、彼女はもう救えないだろう。
言いようの知れない恐怖にファーシェは駆られた。
ミズハは仰向けのまま、唇を微かに動かして何かを言おうとしている。
だがこの体では、もうどうあがいても声を絞り出せると思えなかった。
ファーシェはその残酷な事実に打ちひしがれて、がっくりと顔を落とした。
もうこれまでだと思って目を閉じかけたその時、声が聞こえた。
またどこかで会いましょう―。
ファーシェははっとして、ミズハの顔を再び見やった。
が、彼女は瞼を下ろしたままで、もう二度と微動だにしなかった。
この声はどこから?ミズハの口から発したようには思えない。
私の錯覚か、あるいは彼女の声なき声か…。
ミズハは穏やかな顔をしていた。苦痛は感じてなさそうだが、かといって微笑んでもいない。
どこまでも穏やかで、安らかで、あらゆるものから抜け出している。そんな表情だった。
大陸の遥か東の世界に伝わる「ホトケ」のような顔だと、ファーシェは思った。
ふいに、何かが自分の中から湧き上がってきて、溢れ出そうになった。
それをせきとめたくて、私は思わず顔を両手で覆った。
力もなく、その場にしゃがみこんでしまった。
私は涙が止まらなかった。彼女のそばで、ずっと嗚咽していた。
ミズハさんは死んでしまった―いや、この言い方は嫌だからやめよう。
彼女の魂は解き放たれたのだ。解き放たれて別の世界へ行ってしまったのだ。
「ミズハさんは、行きたいところに行けたのか、な…?」
そう呟くと、すぐ近くで金属を小さく叩いたような音が聞こえた。
ふっとその方を見ると、そこには村正があった。
血を帯びて地面に横たわる村正の刀身は、…中ほどで真っ二つに折れていた。
かつてそれが宿した魔性の美しさは、もはや見当たらない。
ファーシェの問いに答えたと言わんばかりに、村正はその命を終えていた。
そうか。そうなんだ。この子も一緒に召されたんだ。
主人と一緒に最期の役目を果たして、この黒鉄の体から飛び出したんだ。
いい子だったのね、とファーシェは思った。
さらに涙が出てきて、どうしていいかわからずに泣いた。声を上げて。
ずいぶん長い間泣いていたと思った。
少しだけ落ち着いて、ファーシェはそこから周囲を見回した。
辺り一面が死体の山になっていた。もう何かが襲いかかってくるような気配はしない。
そよ風の音と、植物の葉が揺れてこすれ合う音しか聞こえない。それ以外は、全くの静寂。
東の空がもう明るい。太陽が地平線から顔をのぞかせている。
「水と日の満ちる国」と言われていた自分の故郷を離れ、
大陸で戦いに明け暮れていたミズハがいつも見つめていた、祖国の日の出だ。
ファーシェはゆっくりと、少しふらつきながら立ちあがった。
自分も、自分の道を歩いていこう。ミズハがあの陽光の橋を渡って行くように。
「また会いましょう、ミズハさん。どこかで…」
その後、ファーシェはミズハの遺体を彼女の故郷―天ツ出泉水国(イズミノクニ)で丁重に葬り、
それからシュバルツバルド共和国へ帰国した。
やり残したことがなくなったら、自分もヴァルキリーと対話して、転生の約を授かろう。
ファーシェはそう決意して、残りの生涯を過ごすことにした。
またいつどこかの世で、彼女の魂にめぐり会えることを祈って。
―数百年後
こんな言い伝えがある。
遥か昔、この国には呪われた刀が存在した。
徒に返り血を好むその刀は、その魔性の美しさゆえに使い手の人生までをも狂わせてきた。
かつて人々はみな、その銘を持つ刀を忌み嫌い、記憶からもこの地からも遠ざけていった。
ある時、異国の地でそのうちの一振りが名もなき剣士の手に渡った。
剣士も例に漏れずその狂気に魅せられ、いつしか孤独に陥ってしまう。
だが剣士は数多の魔物は殺したが、人は殺さなかった。
最期の瞬間まで刀を使い続け、ついに剣士と刀は互いに心を開き、そして共に命を落としたという。
その時から、刀はもう妖刀ではなくなった。
狂気も呪いも消え去り、常人に扱えるものになった。
初めて人を殺すためだけの凶器ではなくなったのだという。
その銘を、伊勢千子村正。
その剣士がいたおかげで、村正は名刀として伝えられてきたのだ、と。
―でも、それだけではないと思うのです。
かつて、望まずも妖刀を世に生み出してしまった刀匠の思い、
そしてそれに魅せられた多くの人々の人間模様があったことと思います。
この世に限られた本数しかないそれは、使い手たる人間がそれを望み、欲したからこそ、
見えない部分で形を変えながら、今も生きているんじゃないか…
村正の一振りを現代に伝える家の人間として、そんな気がするのです。
どれくらい昔のことなのかははっきりとはわからない。事実かどうかも定かではない。
けれど村正の物語は、昔の人の口伝から形を変えて、書物になって確かに今も存在しています。
(天ツ国卯年五月)
―私は今年、120年ぶりにアマツからミッドガルドへ派遣される使節団に加わることになった。
私に与えられた役目は大陸諸国の武人達との文化交流、そしてアマツ流剣術普及の一助になること。
修行し、色々なことから学び、自分を高め、その力を両国のために役立てたいと思う。
私の家は代々剣士を輩出している家柄で、この国のかたちが出来ていない大昔にも、
同じように君主の命を授かり、剣客として海の向こうへ渡った人がいるんだとか。
船へ乗船する直前に、私は祖父母から自分の一族に伝わる一振りの刀を授けられました。
由緒あるその刀は、名を村正というそうです。
いよいよ出港です。私は大陸の人々には、ミズハと名乗ります。
どうか、よい旅立ちになりますように。(完)