今まで、基本的には、1つの都道府県が都内に アンテナショップを置き、
そこを拠点として、地方の特産物や観光情報等を発信していくやり方を
行っているアンテナショップを主に取り上げてきました。
今回、新たな取組みを行っている台東区の「ふるさと交流ショップ」を紹介いたします。

台東区が地方経済の活性化と商店街振興事業の2つを目的として、区内商店街の空き店舗を
借り上げて、8つの姉妹友好都市のほか、全国の自治体が出店のできるアンテナショップを
開設しています。
【取組みの内容】
台東区が開設した「ふるさと交流ショップ」に姉妹友好都市や全国の自治体が、
1週間から4週間程度の期間を区切って出店し、特産品販売や観光案内等を行っている。
その際に店舗の借上げ料及び什器借上げ費、光熱水費の費用は、台東区が負担し、
店舗内のレイアウト、物産の販売内容、販売員の確保については、出店する自治体が
企画し、その費用を負担しているようです。
出店自治体の商店街のイベント参加や地域住民との交流を通じて、物産品の販路拡大を
図るとともにあわせて、活性化が課題となっている近隣商店街への誘客狙いのようです。
【導入・実施にあたり工夫した点とその対処法】
他のアンテナショップと違い、最低1週間で出店自治体が入れ替わるため、
各自治体は短期間での成果が求められる。区として、出店調整など出店自治体に
対するきめ細やかな対応や、ショップを広くPRし効果的に周知を図ることに
苦慮した。2か月ごとにチラシを作成し、町会回覧を行うなど区内全体への
周知に努めている。
【今後の課題と展開】
商店街の活性化に向けて、今後出店自治体とどのように連携して共存共栄を
図っていくか、その仕組みづくりが課題である。
今後、出店自治体と商店街理事会・青年部との意見交換や出店自治体同士の
情報交換できる機会を設けていく。
―上記取り組みをみて―
1つの都道府県がアンテナショップを都内に置くことは、経費の負担はかなり大きいが、
長期的に情報を発信できるメリットがあり、通年を通しての販売データ等を
取ることも可能です。
「ふるさと交流ショップ」のような仕組みでは、1市町村が気軽に出店ができることは、
大きなメリットだと思う一方で、短期間というのは、PRの面で弱いので、デメリット
とも考えられます。
その為、細やかな周知等のサポートの必要性やイベントを出店自治体と商店街が
一緒に行うことが大事だと思います。
何よりも事業として、空き店舗を活用して、人を集客することができれば、
地域の商店街の活性化にも役立つのではないでしょうか。
調べたところ、適用される支援措置として、地方創生推進交付金が
使われているようでした。
こういう取組みが、都内の他の区にも波及していくと良いと思います。
http://www.city.taito.lg.jp/smph/index/kusei/shimaitoshi/oshirase/0157790500.html

















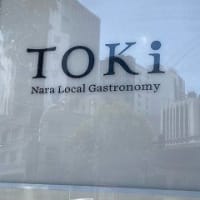


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます