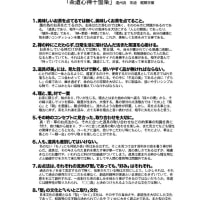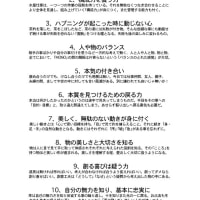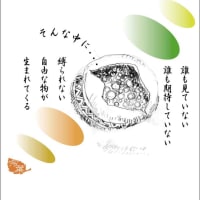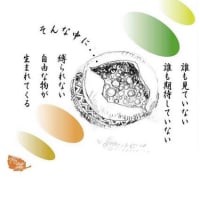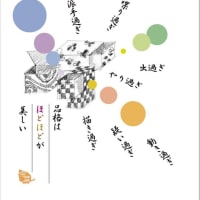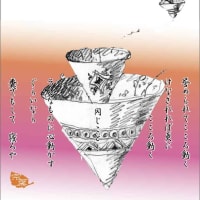平常心是道 平常心(びょうじょうしん)是れ道(どう)
人生には喜怒哀楽があって、一喜一憂、悩んだり苦しんだり、泣いたり笑っ
たりしながら心は揺れ動くのが常である。嬉しいときは喜び、悲しいときは
涙するのは人として当然のことである。この揺れ動く自分のその心そのもの
が我が心のそのときの真実の心であり、さまざまな状況、状態に応じて変化
し現れるのが、人の心であり人間としての自然の姿である。
むしろ上がり緊張している我が心こそ、今の自分の真実の姿であり、ありの
ままの心なんだ、ということを素直に認め受け入れることである。
「平常心」は普段のまま、現在の煩悩心のそのままではない。道元禅師の言わ
れる「ただわが身も放ち忘れて仏のいへになげいれて、仏の方より行われ、
是に従い行くとき ちからも入れずこころもついやさずして 生死を離れて
ほとけとなる」とある。要は仏のいえ、大自然の運行、自然法爾のままに、
一切を御仏にお任せするその心そのままが平常心なのである。
一華開五葉 結果自然成 一華(いちげ)五葉を開き 結果自然(じねん)に成る
一華開く・・・心の花を開く=仏性(ぶつしょう)に目覚めること。清浄無
垢な心に立ちかえること。心華が開けばやがて自然に仏果菩提の実を結ぶ。
また、五葉とは五弁の智慧花びらに当てられる。
大円鏡智 清浄な人間の心―――大きな円鏡はすべてのものをその
まま映しとる智慧。
平等性智 周りにあるものすべてをわけ隔てなく平等に仏心をあら
わす智慧。
妙観察智 優れた観察力をあらわすことの出来る智慧。
成所作智 仏の智慧のよりあらわれる行い。所作。
法界体性智 一切の存在、世界のすべて仏の心の顕現であるとする智。
茶禅一味と言うように、茶席の花は「一花五葉」を活けるといわれる。茶花
など茶席の花は単なる活け花でも、床の間の装飾でもなく、「心の華を開け
よ」という教えでもある。
喫茶去 (きっさこ)
相対する分別、取捨、過去・現在、あちら・こちらと分かつ一切の意識を断
ち切った、絶対の境地のあらわれに他ならない。そこには、凡聖、貴賎、男
女、自他等の分別は無く一切の思量の分別の無い無心の境地からの「喫茶去」
なのだ。この無心の働きからでるところに、茶道家はこの「喫茶去」の語を
茶掛けとして尊んで自ら無心に茶を点て、貧富貴賎の客を択ばず無心に施す
心を養ってきたことだろう。私たちはおうおうにして、好きな人や、金持ち
や身分の高い人が来れば鄭重にもてなし、嫌いな人や貧しい人にはいい加減
な対応をしてしまいがちである。分別を入れず、誰に対しても計らい無く、
真心から接して行きたいものである。
自浄其意 (じじょうごい)
「仏教の根本の教えとは何か」と質問した。道林和尚は即座に「諸悪莫作、
衆善奉行」即ち、悪いことをするな、善きことをせよと答えたのだった。
あまりにも平凡な答えに白楽天はあきれて「そんなことは三歳の童子でも知
っていることではありませんか、馬鹿にしないでください」反発したところ
「三歳の童子でも知っているであろうが、八十の老人でさえ行うことは難し」
と平然と答えたという。
寒時寒殺闍黎 熱時熱殺闍黎
寒時(かんじ)は闍黎(しゃり)を寒殺(かんさつ)し、熱時(ねつじ)は
闍黎を熱殺(ねっさつ)す
『寒いとか暑いとか言うのは暑さ寒さを分別比較して、寒いといい、暑いと
いって嫌い避けようとして、結局、寒暑に振り回されてしまうから愚痴にな
ってしまうのだ。寒いときは寒さになりきり、暑いときは暑さに徹して逃げ
ようとか避けようとするのでなく、暑さに任せておけばいいじゃないか、何
で迷うことがあろうか』と洞山禅師が示された言葉である。
ただし、これは僧が問うた寒暑とは単なる暑さ寒さのことでなく、心のうち
の苦悩煩悩のことであり、苦しいとき辛いとき悲しい時の悩みをただ避けた
り、一時逃れるするのでなくありのままに受け止め、そのこと、その事柄に
徹しなりきることによって煩悩苦悩から解放されることなのだという教えで
ある。
徳不孤 必有隣(論語) 徳は孤ならず 必ず隣有り
人はおうおうにして、自ら学び得たことや、技量が世間に省みられず、認め
られないことは耐え難いことである。ところが、それまで己の主義主張や心
操を曲げて、世間に妥協し世間に迎合してしまいがちになることも少なくな
い。しかし、意志堅固に道を求め続け、学において究め続けていれば、身に
光は備わりおのずから理解者は現れ、支持する人も出てくるものなのだ。
陰徳陽報ということばがあるが、目立とうが当が目立つまいが、人の嫌がる
ことや、避けて終いがちなことでも、喜んでさせていただく下座行、陰徳の
行を修めることによって自ずから身に光は備わり徳は高まり、人々は慕い集
ってきて孤にしてはおかないものである。
鶏寒上樹鴨寒下水 鶏(とり)は寒うして樹に上り 鴨は寒うして水に下る
お釈迦様の説法は皆に対して同じであっても、聞く側の、理解力、関心の対
象の違いによって受け止め方も違いがあり、膨大なご説法の理解、解釈が違
えば、その伝え方も自ずと異なるのは仕方がないことである。このように、
一つの真理、一つの教えにも、修行者の感性、境地によって教意と見るか、
祖意と見るかにわかれて行くことを、巴陵和尚はのべ、また、敢えて教意だ、
祖意だと分別する必要も無く、教禅一如であることを示された言葉でもある。
放下著 〈ほうげじゃく〉
修行者は苦修錬行、ちょっと道理がわかり、いささかの境地が得られると既
に大悟したかのように、悟りの境地に迷う。俗にいう「味噌の味噌臭きは上
味噌に非ず」というように禅でも悟りの悟り臭きは上悟りに非ずといい、真
の悟りとしては評価されない。更に放下し、捨て去り、その悟りの臭みをも
抜ききってこそ本来無一物の境涯を得られたといいうるのだ。
東山水上行 東山(とうざん)水上(すいじょう)を行く〔雲門広録〕
私どもは常に、一般的に抱く常識的、相対的認識の世界にあって、 動とか静、
善とか悪、生とか死、苦とか楽などの二相に分別しているから、 その分別妄
想を起こし、執着し、迷いあるいは苦しみ、業を重ねているもの である。そ
ういう二元対立、ニ相分別の観念を打ち砕き、私どもの常の概念 とする常識
や理屈の殻を突き破らしめる禅匠としての雲門禅師の境涯が 伺える。
是非、善悪、愛憎、動静の分別を起こさず、山と静とを対比せず、山は山そ
のもの姿を見、水は水の姿 そのものを見れば、動、不動の分別二相の発想は
起こらない。あるいは自らが山になりきり、また水その ものになりきっての、
純粋認識である。そこに諸仏の無碍自在の境地がある。
青山元不動 白雲自去来 (せいざんもとふどう)(はくうんおのずからきょらい)
超然とした青山は周囲の雲がどのように去来し、覆おうが青山の本来の面目
は何ら変わるものではない。私たちの生活においてもこのようでありたいも
のだ。煩悩妄想の雲は必ずかかる。これが人の世の常なのである。
しかし是非得失、愛憎、悲喜、苦楽等分別相対の世界に暮らす現実の社会に
あっても、人間本来の面目たる仏から賜る佛性をしっかり見据えていれば、
煩悩妄想の雲には惑わされない。
深林人不知 明月来相照 (唐詩選) 深林人知らず 明月来って相照らす
人は物に満たされても心までは満たされない。だから多くの人は生きがいを
探し、生きる価値をさがしもとめるが、それは遠く求めてもえられないかも
しれない。“秋風やなすことなくて心足る”の句を隣寺の老僧から頂いたが、
まさに孤独の中に合っても、自然の中に身をおいて、自然の悠久の時間に遊
び、秋風を喜び、月の照り来るを喜べるところに生きがいなんていらない。
より豊かな生活がここにあるのだ。
采菊東籬下 悠然見南山 菊を(と)る(とおり)のもと 悠然として南山を見る
この庵のある山合い風光はなんともいえず心を休ませてくれる。鳥も空に浮
かんで自然に溶け込み、その中に私も同化してしまったよ。もう煩悩だ妄想
だということさえなく、悟りという臭みさえ忘れ果てたし、執着だ、無執着
だということさえない。そんな心境だ。
主人公〈しゅじんこう〉(無門関)
禅の目指すところは「己事究明」による「見性成仏」である。己の内心を究
明し究明して、生まれながらに頂いている仏性への目覚めに修行の眼目があ
るのだ。坐禅の「坐」の字は土の上に人が向き合って対話する形から成り立
っているが、その人とは己れ自身ともう一人は別なる自分、すなわち内心の
自分、魂の自分のことである。主人公と叫ぶ己と、、と応えるもう一人の自
分である。主人公と叫ぶ自分と、応える主人公の自分が互いに主人公になり
きりった尊い姿を見なければならない。
便是人間好時節 (無門関) すなわち是れ人間の好時節
禅的に言うところの自然(じねん)は、おのずから、そのようにとか、真理
のままにというような有らしめられている現実そのものを言い、単なる自然
(しぜん)とはちがうし、ここでは自然(しぜん)を賛えることの言葉だけ
の意味ではない。
とかく人間というものは、三毒五欲の煩悩に迷い、閑事の、どうでもよいこ
と、つまらぬこと、むだごとに囚われて、嘆いたり悲しんだりである。そう
いう閑事にとらわれたり、迷い、己を見失うことがなければ、春夏秋冬いつ
でも人間の好時節なのである。それは自然(じねん)法爾(ほうに)の中に
いきることであり、生かされてあることなのだろう。それがすなわちそのま
ま仏の道であり、そのままであることが平常心なのである。
風定花猶落 鳥鳴山更幽 (風定まって花猶落ち 鳥鳴いて山更に幽なり
すべての動きが止まった単なる静けさではなく、静かさの中に穏やかな温も
りと時の動きを感じる静けさである。全くの無音状態が静かとは限らない。
無音は却って不気味さ不安さを感じさせ心穏やかならず、決して静寂さを味
わうことは出来ないものである。
茶室の静寂も茶釜が奏でる松音によって一層引き立つようなものである。
「鳥鳴いて山更に幽なり」の語もやはり静かさの中のひとつの鳥の叫びが却
って静寂さを際立たせる効果を生む。いずれも「動中の静、静中の動」の境
をを表す言葉として面白く禅者は好む
人生には喜怒哀楽があって、一喜一憂、悩んだり苦しんだり、泣いたり笑っ
たりしながら心は揺れ動くのが常である。嬉しいときは喜び、悲しいときは
涙するのは人として当然のことである。この揺れ動く自分のその心そのもの
が我が心のそのときの真実の心であり、さまざまな状況、状態に応じて変化
し現れるのが、人の心であり人間としての自然の姿である。
むしろ上がり緊張している我が心こそ、今の自分の真実の姿であり、ありの
ままの心なんだ、ということを素直に認め受け入れることである。
「平常心」は普段のまま、現在の煩悩心のそのままではない。道元禅師の言わ
れる「ただわが身も放ち忘れて仏のいへになげいれて、仏の方より行われ、
是に従い行くとき ちからも入れずこころもついやさずして 生死を離れて
ほとけとなる」とある。要は仏のいえ、大自然の運行、自然法爾のままに、
一切を御仏にお任せするその心そのままが平常心なのである。
一華開五葉 結果自然成 一華(いちげ)五葉を開き 結果自然(じねん)に成る
一華開く・・・心の花を開く=仏性(ぶつしょう)に目覚めること。清浄無
垢な心に立ちかえること。心華が開けばやがて自然に仏果菩提の実を結ぶ。
また、五葉とは五弁の智慧花びらに当てられる。
大円鏡智 清浄な人間の心―――大きな円鏡はすべてのものをその
まま映しとる智慧。
平等性智 周りにあるものすべてをわけ隔てなく平等に仏心をあら
わす智慧。
妙観察智 優れた観察力をあらわすことの出来る智慧。
成所作智 仏の智慧のよりあらわれる行い。所作。
法界体性智 一切の存在、世界のすべて仏の心の顕現であるとする智。
茶禅一味と言うように、茶席の花は「一花五葉」を活けるといわれる。茶花
など茶席の花は単なる活け花でも、床の間の装飾でもなく、「心の華を開け
よ」という教えでもある。
喫茶去 (きっさこ)
相対する分別、取捨、過去・現在、あちら・こちらと分かつ一切の意識を断
ち切った、絶対の境地のあらわれに他ならない。そこには、凡聖、貴賎、男
女、自他等の分別は無く一切の思量の分別の無い無心の境地からの「喫茶去」
なのだ。この無心の働きからでるところに、茶道家はこの「喫茶去」の語を
茶掛けとして尊んで自ら無心に茶を点て、貧富貴賎の客を択ばず無心に施す
心を養ってきたことだろう。私たちはおうおうにして、好きな人や、金持ち
や身分の高い人が来れば鄭重にもてなし、嫌いな人や貧しい人にはいい加減
な対応をしてしまいがちである。分別を入れず、誰に対しても計らい無く、
真心から接して行きたいものである。
自浄其意 (じじょうごい)
「仏教の根本の教えとは何か」と質問した。道林和尚は即座に「諸悪莫作、
衆善奉行」即ち、悪いことをするな、善きことをせよと答えたのだった。
あまりにも平凡な答えに白楽天はあきれて「そんなことは三歳の童子でも知
っていることではありませんか、馬鹿にしないでください」反発したところ
「三歳の童子でも知っているであろうが、八十の老人でさえ行うことは難し」
と平然と答えたという。
寒時寒殺闍黎 熱時熱殺闍黎
寒時(かんじ)は闍黎(しゃり)を寒殺(かんさつ)し、熱時(ねつじ)は
闍黎を熱殺(ねっさつ)す
『寒いとか暑いとか言うのは暑さ寒さを分別比較して、寒いといい、暑いと
いって嫌い避けようとして、結局、寒暑に振り回されてしまうから愚痴にな
ってしまうのだ。寒いときは寒さになりきり、暑いときは暑さに徹して逃げ
ようとか避けようとするのでなく、暑さに任せておけばいいじゃないか、何
で迷うことがあろうか』と洞山禅師が示された言葉である。
ただし、これは僧が問うた寒暑とは単なる暑さ寒さのことでなく、心のうち
の苦悩煩悩のことであり、苦しいとき辛いとき悲しい時の悩みをただ避けた
り、一時逃れるするのでなくありのままに受け止め、そのこと、その事柄に
徹しなりきることによって煩悩苦悩から解放されることなのだという教えで
ある。
徳不孤 必有隣(論語) 徳は孤ならず 必ず隣有り
人はおうおうにして、自ら学び得たことや、技量が世間に省みられず、認め
られないことは耐え難いことである。ところが、それまで己の主義主張や心
操を曲げて、世間に妥協し世間に迎合してしまいがちになることも少なくな
い。しかし、意志堅固に道を求め続け、学において究め続けていれば、身に
光は備わりおのずから理解者は現れ、支持する人も出てくるものなのだ。
陰徳陽報ということばがあるが、目立とうが当が目立つまいが、人の嫌がる
ことや、避けて終いがちなことでも、喜んでさせていただく下座行、陰徳の
行を修めることによって自ずから身に光は備わり徳は高まり、人々は慕い集
ってきて孤にしてはおかないものである。
鶏寒上樹鴨寒下水 鶏(とり)は寒うして樹に上り 鴨は寒うして水に下る
お釈迦様の説法は皆に対して同じであっても、聞く側の、理解力、関心の対
象の違いによって受け止め方も違いがあり、膨大なご説法の理解、解釈が違
えば、その伝え方も自ずと異なるのは仕方がないことである。このように、
一つの真理、一つの教えにも、修行者の感性、境地によって教意と見るか、
祖意と見るかにわかれて行くことを、巴陵和尚はのべ、また、敢えて教意だ、
祖意だと分別する必要も無く、教禅一如であることを示された言葉でもある。
放下著 〈ほうげじゃく〉
修行者は苦修錬行、ちょっと道理がわかり、いささかの境地が得られると既
に大悟したかのように、悟りの境地に迷う。俗にいう「味噌の味噌臭きは上
味噌に非ず」というように禅でも悟りの悟り臭きは上悟りに非ずといい、真
の悟りとしては評価されない。更に放下し、捨て去り、その悟りの臭みをも
抜ききってこそ本来無一物の境涯を得られたといいうるのだ。
東山水上行 東山(とうざん)水上(すいじょう)を行く〔雲門広録〕
私どもは常に、一般的に抱く常識的、相対的認識の世界にあって、 動とか静、
善とか悪、生とか死、苦とか楽などの二相に分別しているから、 その分別妄
想を起こし、執着し、迷いあるいは苦しみ、業を重ねているもの である。そ
ういう二元対立、ニ相分別の観念を打ち砕き、私どもの常の概念 とする常識
や理屈の殻を突き破らしめる禅匠としての雲門禅師の境涯が 伺える。
是非、善悪、愛憎、動静の分別を起こさず、山と静とを対比せず、山は山そ
のもの姿を見、水は水の姿 そのものを見れば、動、不動の分別二相の発想は
起こらない。あるいは自らが山になりきり、また水その ものになりきっての、
純粋認識である。そこに諸仏の無碍自在の境地がある。
青山元不動 白雲自去来 (せいざんもとふどう)(はくうんおのずからきょらい)
超然とした青山は周囲の雲がどのように去来し、覆おうが青山の本来の面目
は何ら変わるものではない。私たちの生活においてもこのようでありたいも
のだ。煩悩妄想の雲は必ずかかる。これが人の世の常なのである。
しかし是非得失、愛憎、悲喜、苦楽等分別相対の世界に暮らす現実の社会に
あっても、人間本来の面目たる仏から賜る佛性をしっかり見据えていれば、
煩悩妄想の雲には惑わされない。
深林人不知 明月来相照 (唐詩選) 深林人知らず 明月来って相照らす
人は物に満たされても心までは満たされない。だから多くの人は生きがいを
探し、生きる価値をさがしもとめるが、それは遠く求めてもえられないかも
しれない。“秋風やなすことなくて心足る”の句を隣寺の老僧から頂いたが、
まさに孤独の中に合っても、自然の中に身をおいて、自然の悠久の時間に遊
び、秋風を喜び、月の照り来るを喜べるところに生きがいなんていらない。
より豊かな生活がここにあるのだ。
采菊東籬下 悠然見南山 菊を(と)る(とおり)のもと 悠然として南山を見る
この庵のある山合い風光はなんともいえず心を休ませてくれる。鳥も空に浮
かんで自然に溶け込み、その中に私も同化してしまったよ。もう煩悩だ妄想
だということさえなく、悟りという臭みさえ忘れ果てたし、執着だ、無執着
だということさえない。そんな心境だ。
主人公〈しゅじんこう〉(無門関)
禅の目指すところは「己事究明」による「見性成仏」である。己の内心を究
明し究明して、生まれながらに頂いている仏性への目覚めに修行の眼目があ
るのだ。坐禅の「坐」の字は土の上に人が向き合って対話する形から成り立
っているが、その人とは己れ自身ともう一人は別なる自分、すなわち内心の
自分、魂の自分のことである。主人公と叫ぶ己と、、と応えるもう一人の自
分である。主人公と叫ぶ自分と、応える主人公の自分が互いに主人公になり
きりった尊い姿を見なければならない。
便是人間好時節 (無門関) すなわち是れ人間の好時節
禅的に言うところの自然(じねん)は、おのずから、そのようにとか、真理
のままにというような有らしめられている現実そのものを言い、単なる自然
(しぜん)とはちがうし、ここでは自然(しぜん)を賛えることの言葉だけ
の意味ではない。
とかく人間というものは、三毒五欲の煩悩に迷い、閑事の、どうでもよいこ
と、つまらぬこと、むだごとに囚われて、嘆いたり悲しんだりである。そう
いう閑事にとらわれたり、迷い、己を見失うことがなければ、春夏秋冬いつ
でも人間の好時節なのである。それは自然(じねん)法爾(ほうに)の中に
いきることであり、生かされてあることなのだろう。それがすなわちそのま
ま仏の道であり、そのままであることが平常心なのである。
風定花猶落 鳥鳴山更幽 (風定まって花猶落ち 鳥鳴いて山更に幽なり
すべての動きが止まった単なる静けさではなく、静かさの中に穏やかな温も
りと時の動きを感じる静けさである。全くの無音状態が静かとは限らない。
無音は却って不気味さ不安さを感じさせ心穏やかならず、決して静寂さを味
わうことは出来ないものである。
茶室の静寂も茶釜が奏でる松音によって一層引き立つようなものである。
「鳥鳴いて山更に幽なり」の語もやはり静かさの中のひとつの鳥の叫びが却
って静寂さを際立たせる効果を生む。いずれも「動中の静、静中の動」の境
をを表す言葉として面白く禅者は好む