真の茶道は草庵小座敷 現代、茶道が盛んですが、様々な人
々から現代の茶道は、千利休の精神を忘れて形だけになって
いると批判されています
茶の湯について二つあると言っている。
二つの茶の湯
●書院台子の茶の湯
広い書院で台子(だいす)を用いる。名物の茶器を用いる。
大勢が参加する。
台子は茶道具を飾る棚
●草庵小座敷の茶
露地の中に独立した狭い草庵で、台子を用いない。小人数で
行う。
利休は繰り返し、草庵、小座敷の茶の湯しか、本心に至りえ
ないと述べている。なぜだろうか。書院台子の茶の湯は、禅
寺の法事のごとく、草庵小座敷は、坐禅と独参のごとしです。
仏道を志す者が、法事ばかりやって、坐禅も師匠との問答も
しなかったら、仏道を得らないのと似ているだろう。法事の
最中に師匠は弟子に仏法指導はできない。
茶道が[人間とは何か][道とは何か][自己とは何か]
[心とは何か]を究めるものであるならば、茶の師匠と弟子
がその根本に立ち向かう草庵での会にこそあるのは当然であ
る。たとえ作法を覚えた人でも、朝夕工夫をすると「心に至
る」はずである。
書院の茶は世間、草庵の茶は出世間
書院台子の茶は世俗の行事作法であり、草庵の茶は仏道であ
り、自己を悟るのが目的である。得道とは禅の言葉で、悟り
を得る、世間の自我を離れること。悟りの時、自我を忘れる
こと、無になること、こういう禅体験がここに記述されてい
る。だから利休の茶の目標は茶の湯をとおして悟りを得るこ
とである。趣味や芸術や友達つきあいを楽しむだけのもので
はない。
作法規矩からはいって、そこを離れた境地まで至ると、茶の
湯が遊びや趣味や小遣いかせぎでなく、[道]となる、という。
特に小座敷の茶の湯は仏道そのもの
「小座敷の茶の湯は、第一、仏法をもって修行得道する事な
り。家居の結構、食事の珍味を薬とするは俗世の事なり。家
は漏らぬほど、食事は飢えぬ程にて足る事なり。是れ仏の教
え、茶の本意なり。水を運び薪をとり、湯を沸かし茶をたて
て、仏に供え、人にも施し我も飲み、花をたて香をたき、皆
々仏祖の行ひのあとを学ぶなり。」
悟道の利休の茶の精神(形や作法や美学でなく)は悟道の人
でなければ真に理解できないのかもしれない。茶を行う主体
は禅的真人である、ということである。もし、茶人が禅を実
践すれば独創的な茶道、現代に本当に生きる新しい茶道がで
きると思われる。それを千利休、千宗旦、柳宗悦、久松真一
などが強く説いたはずである。
自由自在、我がなく、自分の誤りをかくすことなく、他人の
よいところを認める、というのは[無我]つまり我のないこ
とのあらわれで、禅の悟りを得たことが明白。自他の差別な
く、心にかけるのはただ[道]のことであった。茶人は、こ
れを手本として一歩でも近づきたいと願い、努力をする人で
あろう。
真の茶道は出離の人のもの
「茶一道、もとより得道の所、濁りなく出離の人にあらずし
てはなしがたかるべし。未熟の人の野がけふすべ茶の湯は、
まねをするまでのことなり。手わざ諸具ともに定法なし。定
法なきがゆへに、定法、大法あり。その子細はただただ一心
得道の取りおこない、形の外のわざなるゆへ、なまじゐの茶
人構えて構えて無用なり。天然と取行ふべき時を知るべし。」
真の茶道は出離の人でなければできないから、特に野がけ
は得道の人以外はしないほうがよい、という。出離、得道の
人とはどういう人をいうか、よくよく検討すべきであろう。
々から現代の茶道は、千利休の精神を忘れて形だけになって
いると批判されています
茶の湯について二つあると言っている。
二つの茶の湯
●書院台子の茶の湯
広い書院で台子(だいす)を用いる。名物の茶器を用いる。
大勢が参加する。
台子は茶道具を飾る棚
●草庵小座敷の茶
露地の中に独立した狭い草庵で、台子を用いない。小人数で
行う。
利休は繰り返し、草庵、小座敷の茶の湯しか、本心に至りえ
ないと述べている。なぜだろうか。書院台子の茶の湯は、禅
寺の法事のごとく、草庵小座敷は、坐禅と独参のごとしです。
仏道を志す者が、法事ばかりやって、坐禅も師匠との問答も
しなかったら、仏道を得らないのと似ているだろう。法事の
最中に師匠は弟子に仏法指導はできない。
茶道が[人間とは何か][道とは何か][自己とは何か]
[心とは何か]を究めるものであるならば、茶の師匠と弟子
がその根本に立ち向かう草庵での会にこそあるのは当然であ
る。たとえ作法を覚えた人でも、朝夕工夫をすると「心に至
る」はずである。
書院の茶は世間、草庵の茶は出世間
書院台子の茶は世俗の行事作法であり、草庵の茶は仏道であ
り、自己を悟るのが目的である。得道とは禅の言葉で、悟り
を得る、世間の自我を離れること。悟りの時、自我を忘れる
こと、無になること、こういう禅体験がここに記述されてい
る。だから利休の茶の目標は茶の湯をとおして悟りを得るこ
とである。趣味や芸術や友達つきあいを楽しむだけのもので
はない。
作法規矩からはいって、そこを離れた境地まで至ると、茶の
湯が遊びや趣味や小遣いかせぎでなく、[道]となる、という。
特に小座敷の茶の湯は仏道そのもの
「小座敷の茶の湯は、第一、仏法をもって修行得道する事な
り。家居の結構、食事の珍味を薬とするは俗世の事なり。家
は漏らぬほど、食事は飢えぬ程にて足る事なり。是れ仏の教
え、茶の本意なり。水を運び薪をとり、湯を沸かし茶をたて
て、仏に供え、人にも施し我も飲み、花をたて香をたき、皆
々仏祖の行ひのあとを学ぶなり。」
悟道の利休の茶の精神(形や作法や美学でなく)は悟道の人
でなければ真に理解できないのかもしれない。茶を行う主体
は禅的真人である、ということである。もし、茶人が禅を実
践すれば独創的な茶道、現代に本当に生きる新しい茶道がで
きると思われる。それを千利休、千宗旦、柳宗悦、久松真一
などが強く説いたはずである。
自由自在、我がなく、自分の誤りをかくすことなく、他人の
よいところを認める、というのは[無我]つまり我のないこ
とのあらわれで、禅の悟りを得たことが明白。自他の差別な
く、心にかけるのはただ[道]のことであった。茶人は、こ
れを手本として一歩でも近づきたいと願い、努力をする人で
あろう。
真の茶道は出離の人のもの
「茶一道、もとより得道の所、濁りなく出離の人にあらずし
てはなしがたかるべし。未熟の人の野がけふすべ茶の湯は、
まねをするまでのことなり。手わざ諸具ともに定法なし。定
法なきがゆへに、定法、大法あり。その子細はただただ一心
得道の取りおこない、形の外のわざなるゆへ、なまじゐの茶
人構えて構えて無用なり。天然と取行ふべき時を知るべし。」
真の茶道は出離の人でなければできないから、特に野がけ
は得道の人以外はしないほうがよい、という。出離、得道の
人とはどういう人をいうか、よくよく検討すべきであろう。













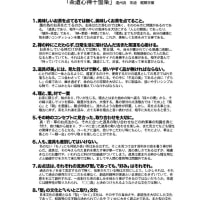
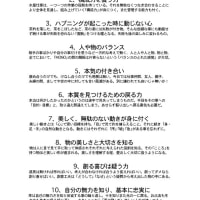
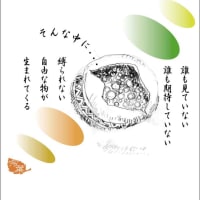

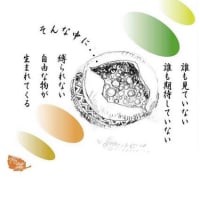
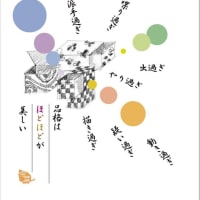
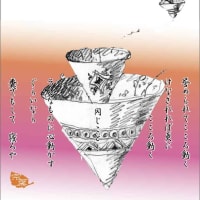

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます