
確か1年半前ぐらいにやはりガレージバンドの音楽制作のキッズワークショップに参加して、その時は「クリックとは?」「ドラッグとは?」といったところからヒビキには初体験という状況だったのだが、今年はめでたくそういう面倒がないうえに、レクチャーをしているスタッフの方が見本でやっているところと、はいやって!というところがあるのをヒビキがちゃんと聞き分けて進めていけるのとで、親としては非常に落ち着いて(つまり口出しせずに)参加というか見学することができた。
いやあ、「身内にパソコンを教える」というのはなかなかキビシイ経験であるが、相手がコドモとなるととたんに親の特権で次々「メイレイ」してしまったりするから要注意なのである。
参加者のコドモたちは総勢11名(1名欠席)で、半数が音楽のレッスンをしていない、残りの半数がなんとピアノのレッスンをしている子供たち。(うーん、ピアノを習うというのはやはり今でも音楽レッスンの中で最もポピュラーなのか、それともピアノと音楽制作というものにより深いつながりがあるのだろうか?)残りの1がドラムとバイオリンを習っています!という変則ワザのヒビキであった。
毎回とても応募の多いアップルストアのキッズワークショップなので、過去に参加していながらまた参加するのはどうかとも思ったのだが、実際に参加してみると、たぶんガレージバンドという音楽制作ソフトそのものも進化しているものとみえて、たいへん有意義であった。
前回のレクチャーは、趣旨としては大きく「豊富なプリセット音源で選ぶだけでかっこいいサウンド作品のできあがり」といったもので、とにかくいろんなプリセットパーツを選んでトラックに載せて、繰り返したり、ボイス(セリフ)を録音したりしてできあがり、という流れだった。つまり別に音楽を作ろうという気がなくても、画像や映像になんか音を足したいな、という時などに、誰でも簡単に音が作れる、という感じだったのだ。
それと比べると、今回は音楽を作りたいと思ったら、こういうことをしたいよね、それにはガレージバンドではこうしたらできるんだよ、という流れが感じられた。それはかなり本音で自然な要求の流れであり、その実現の仕方としてマシンの機能がうまく説明されるのが、またわかりやすかった。
どちらがよくてどちらが悪いというのではなくて、ユーザにとってガレージバンドがどういうソフトかというところが変化したのだと思う。また面白いことに、ソフトの進化に応じてレクチャーも前回よりも今回のほうがアドバンスドなのかというと、内容的にはそうであるはずなのだが、逆に言うと、どうすればいいかがかなり指示された形になるために、コドモたちが自分でどういうアイデアを思いつけばいいのかがわかるので、それらしく高度なものになる確率は100倍ぐらい上がっているのである。前回はどちらかというとやり方はわかったけれども、単に組み合わせにしてもじゃあどうすればいいのか、アイデアがない子供たちが多かったように思う(単に周囲のコドモを見回して、聞こえてくる音とか、できあがりのトラック数の少なさとかいったレベルだが)。今回は知っている歌を吹き込んだり、ナレーションを付けたりしているコドモもいて、自分なりのアイデアを盛り込んでいる様子が伝わってきた。(つづく)
[Apple Store 新春キッズワークショップで音楽制作を体験 2009]
| 1 | 2 | 3 |












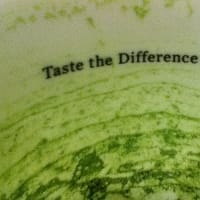





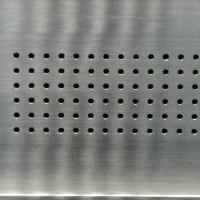

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます