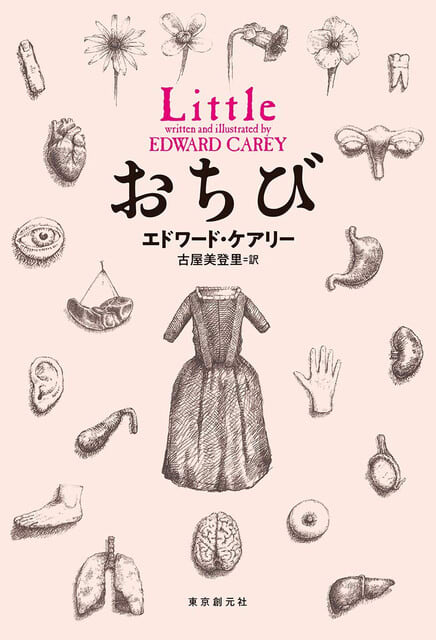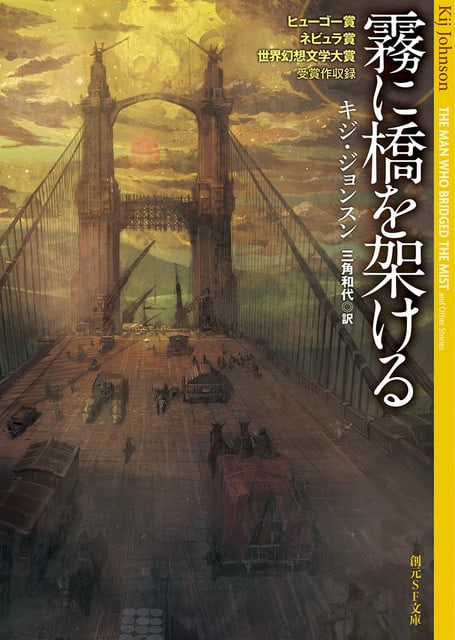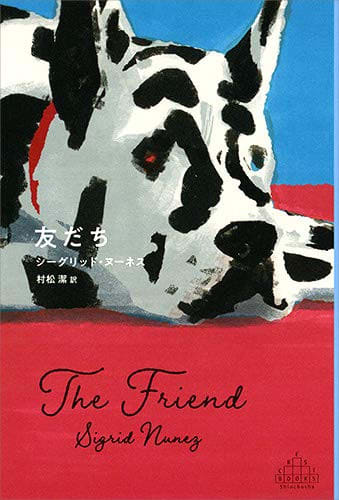コロナ禍において、ペットを飼う人が増えたといいます。室内での遊び相手という意味合いのほか、暗く苦しい状況下にかわいい犬や猫がいてくれるだけで心が和み、明日への活力が湧いてくることもあるでしょう。
今回ご紹介する小説『おちび/エドワード・ケアリー著・古屋美登里訳』にも、厳しい状況下におかれた人々が一匹の犬に心を癒やされる場面が出てきます。ただ、それはラスト近くでの話。まずはこの壮大な物語全体をご紹介しなければなりません。
ロンドンに行かれた方はご存知かもしれませんが、マダム・タッソー蝋人形館という観光名所があります。俳優、政治家、スポーツ選手などの有名人をそっくり模した蝋人形が飾られている施設です。この館の創始者であるマダム・タッソーが実に数奇な運命をたどった女性で、彼女にまつわる史実をもとに、巧妙かつ奇天烈な創意を盛り込んで書かれたのがこの小説なのです。
マダム・タッソーの元の名はマリー・グロショルツ。アルザス地方に生まれたマリーは、スイスのベルンに住むクルティウスという医師の元に雑用係として雇われます。成長しても142cmほどしかなかったマリーは、みんなから「おちび」と呼ばれていました。
クルティウスは患者に病状を伝えるため、人間の臓器を蝋細工で作っていましたが、その仕事に嫌気がさしていました。代わりに彼は頭の模型を作ることに夢中になり、マリーも彼からその技術を学びます。やがてクルティウスは借金がかさんでベルンを追われ、マリーと共にパリに移り住みます。
パリでは仕立て屋の未亡人の元で暮らすことになりました。クルティウスは蝋細工を作り、マリーは使用人として働きます。未亡人は意地が悪く、なにかにつけマリーに冷たく当たります。クルティウスの作った街の名士の胸像は評判となり、商売になると踏んだ未亡人は新たに大きな館を借り、大々的に胸像の展示を始めます。
1700年代という不安な時代、人々は公開で行われる処刑を見世物として楽しんでいました。そこに目をつけた未亡人の発案で、クルティウスとマリーは処刑された殺人犯の型を取り、蝋の全身像を作ります。これが人気となったため、同様に不気味な蝋人形が次々に作られ、館は大繁盛していきます。
そんな折、館を訪れたエリザベート王女(ルイ16世の妹)に気に入られ、マリーは彫刻教師としてヴェルサイユ宮殿で暮らすことになります。王女の召使い達に冷たくあしわられながらも、マリーは王女の寵愛を受け、王女の教育係としての毎日を楽しんでいました。ところが、宮殿にやってきたクルティウスと未亡人が騒動を起こし、マリーは宮殿を去らなくてはいけなくなります。
蝋人形館に戻ると、館はさらに繁盛しており、今ではパレ・ロワイヤルでも展示をおこなうほどでした。やがてフランス革命が勃発し、権力者たちが次々と処刑されていきます。蝋人形館には処刑された首が届けられ、クルティウスとマリーは、なんと斬られた生首から型を取り、蝋人形を作成することになります。
王党派に近いとされる者は難癖をつけて処刑される世情のなか、しだいにマリー達の立場も危うくなっていきます。ルイ16世をはじめ、権力者たちの蝋人形を展示していることから危険人物とみなされ、ついにマリーは監獄に捕らえられてしまいます。
お待たせしました。ようやく犬の登場です。マリーは監獄で様々な人と出会うのですが、そのなかにローズという印象的な女性がいました。彼女は、今いちばん会いたい相手として、夫でもなく息子や娘でもなく、フォルチュネという名のパグ犬を挙げるのです。ローズは守衛を籠絡し、週に一度フォルチュネを監獄に連れてくるよう段取りをつけました。フォルチュネと触れ合うことは、ローズだけではなくマリーやほかの収監者たちにとっても、大いなる慰めとなります。そのシーンがとても素晴らしいので、やや長いのですが下記に引用します。
〈 フォルチュネは愉快な子犬で、ご主人に懸命に尽くし、わたしたちは彼に会うのが本当に愉しみだった。ここに無垢なものがいる、という感覚。黒い悲しげな顔に心配そうな目をした無邪気な小さな命は、わたしたちの窮状がわかっているかのようだった。彼はわたしたちをとても喜ばせてくれた。彼の小さな声。その大らかさ。純真さ。彼が足取り重く去っていくのを見るのは悲しかった。そして、翌週彼に会うときまで生き永らえていますように、と願った。〉
じつはここで出会うローズは歴史にも名を残す女性なのですが、彼女が誰なのか、どうぞ小説を読んでたしかめてみてください。
その後マリーは処刑寸前まで追い詰められながら、蝋人形を作る技術を持っていたため、館に返されることになります。彼女はフランス革命を生き延び、さらにはナポレオンと対面するなど、強運と押しの強さで運命を切り開いていきます。
クルティウスや未亡人をはじめ、登場人物たちはみなそれぞれが長所と欠点を抱えた人間臭い人ばかりで、型通りの”いい人”は一人もいません。マリーもけっして素直ないい子ではなく、清廉な女性でもありません。そんな彼女が逆境にもめげず、時には人に逆らい、時には人に従い、フランス革命前後の激動の時代を生き抜いていくさまは圧巻です。事実と創造が見事に融合したこの大傑作、ぜひ一読をおすすめします!