夏の猛烈な暑さがようやく過ぎ去りました。今年は新型コロナの一件もあり、なかなか厳しい夏となりましたが、ようやくペットシッターの依頼もぽつぽつと入るようになってきました。このまま収束へと向かい、人々が普通の日常を取り戻すことを強く願っています。
さて今回は、夏のぎらぎらした暑さを味わわせてくれる犬の小説、『異邦人/カミュ著・窪田啓作訳』をご紹介します。有名な作品ですので、読んでなくても大まかなストーリーをご存じの方は多いのではないでしょうか。窪田啓作氏による冒頭の訳文、「きょう、ママンが死んだ」も有名ですね。既読の方は、「え? これって犬、出てきたっけ?」と思われるかもしれませんが、ちゃんと出てきます。ただしその前に、小説のおおまかなご紹介をしておきますね。
本作はよく、不条理小説と紹介されます。僕もこの小説を20年以上前に初めて読み、よくわからない小説だったという記憶だけ残っていました。今回、再読してまず思ったのは、さほど理解しづらい作品でもないこと、そして、本作を不条理小説と言って終わりにするのは非常にもったいないということです。
舞台はアルジェリアの首都アルジェ界わい。とにかく暑い地域です。主人公のムルソーは母の死に際し、とくに悲しむ様子も見せず、翌日に女友達と海へ遊びに行き、情事にふけります。その後、彼は隣人レエモンとアラビア人との諍いに巻き込まれ、殺人を犯してしまいます。法廷でその理由を聞かれた際、「太陽のせいだ」と答える、これもまた有名なシーンでしょう。ムルソーの行動は、“普通の”人々からは理解されず、非情な人間だと判断され、死刑を宣告されてしまうのです。
裁判ではしきりに、ムルソーが如何に普通と違っているかが取り沙汰されます。母親が死んだら悲しむべきだ、その直後に女性と海に遊びに行き、コメディ映画を見、女性と関係を持つなど、すべてが非情で非人間的な行為だ、と検事から責め立てられるのです。しかし、どうでしょう。ムルソーのしたことはそれほど非道なおこないでしょうか。彼は本当にそうした不条理な、人の心を持たないような人間なのでしょうか。僕はこの小説をつづけて二度読みましたが、殺人を除き、彼の行動にはさほど違和感を感じませんでした。母親が死んで悲しむ様子を見せない人だっています。その直後に遊びに行き女性と関係を持ったとしても、とくに非難されるようなことでもありません。殺人についても、ナイフを持った相手に対する正当防衛の意味合いが強く、とても死刑に値するとは思えません。
検事や陪審員たちは、「人は必ず母親を愛し、母親が死んだら悲しむものだ」という先入観を持っています。そして、誰かが自分の想像できない言動をとっただけで不条理と判断し、切り捨てようとする。そのほうがよほど不条理だと僕には思えます。
そんなムルソーですが、意外に人づきあいは活発で、マリイという女友達のほか、アパートの同じ階に住むサラマノ老人たちと行動を共にします。サラマノ老人は八年前からスパニエル犬を飼っており、犬は皮膚病のため体中がかさぶただらけです。狭い部屋で暮らしていると似てくるのか、老人もまたかさぶただらけの肌をしており、互いに鼻づらを突き出し首を伸ばした猫背の姿勢で歩きます。彼らは同族のようでいて、互いに憎み合っています。散歩で犬の引きが強すぎたり、部屋でおしっこをしたりすると、老人は犬を叩き、ののしります。犬も老人に無理やり引っ張られる時には唸って抵抗します。こうした描写がたびたび出てきて、ムルソーはなにかこの老人と犬に興味を惹かれるようです。
その後、散歩中に犬がいなくなり、老人はパニックになってしまいます。ムルソーは老人を部屋へ入れてやり、相談に乗ってあげます。のちに老人は裁判で証言する際、ムルソーに親切にしてもらったことを強調し、ムルソーと母親のことも弁明してみせます。はた目からは、ムルソーと老人との関係は慈愛に満ちた美しいものに思えます。ムルソーが老人に親身になってあげたのは、老人と犬とが互いに憎み合いながらも互いを必要としている、その関係に共感を覚えたせいかもしれません。
さて、第二部の大半は法廷劇となるのですが、思えば裁判制度というものも不条理に満ちています。本来なら正義と真実を見極める場であるはずの裁判が、検事と弁護士の単なる技術合戦になっているからです。また、ムルソーがラストで雄たけびをあげることになる、司祭との対立。すなわち、キリスト教も大いなる不条理に満ちています。神がいることを疑いもせず信じ、祈り、救いを求める行為は、神を信じないムルソーにはまったく意味が見出せませんし、キリスト教徒以外のすべての読者(僕も含む)も同じ思いにかられることでしょう。司祭の並べる“有り難い”お言葉に、ムルソーが珍しく激高するのもむべなるかなと思えます。
この小説を再読したのは、参加する読書会の課題本となったからでした。読書会では様々な意見が飛び交い、話し合うポイントが多岐にわたることを確認しました。読めば読むほど味わい深く、いろんなことを考えさせてくれる、とてつもない名作だと思います。どうか「不条理」という評判に負けず、どなたにも手に取っていただきたい一冊です。











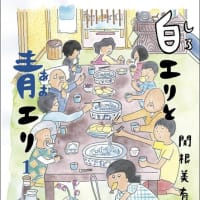
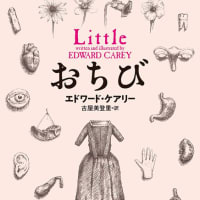
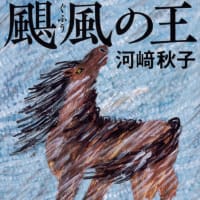
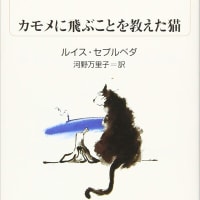
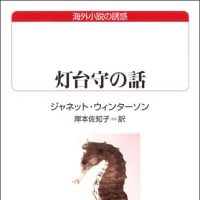
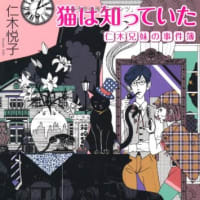
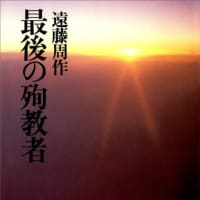
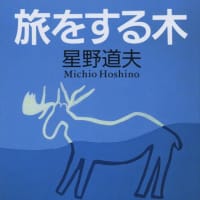
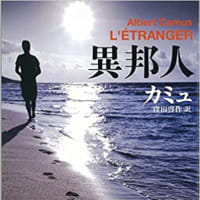
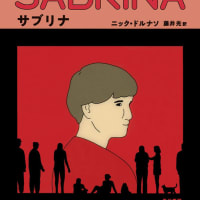
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます