猫ちゃんのシッティングで訪問する際、警戒心の強い子だと隠れて出てこないことがあります。そうした場合、室内を探したほうがいいか探さないほうがいいかを、事前に必ず飼い主さんに確認しておきます。ペットの安否を確認するためには探したほうがいいのですが、探し回ることでペットにストレスを与えてしまったり、家の中をうろうろされることを好まない飼い主さんもいらっしゃるので、そこはご要望にお任せすることにしています。
たまにひやりとするのは、猫がどこにも見当たらない時。探しても探しても見つからないと、だんだん焦りがつのってきます。たとえばゴミ捨てや水やりなどで室内外を出入りする際、窓の開け閉めのわずかな隙をついて外に出てしまうこともあり、もちろんそこは十分に注意するのがペットシッターの基本なのですが、可能性としてゼロではありません。どうしても見つからないとき、窓から外に出たのだろうか、玄関の出入りの際に出てしまったのだろうかと不安が心をよぎります。
でも十中八九、室内のどこかに隠れています。根気よく探していると、まさかここに、というほど狭い隙間や背の高い家具の上で見つかることがあります。テレビ台の下にDVDプレイヤーなどが置いてあり、正面の扉が閉まった状態でも、背面から入り込むことがあります。ソファ底部の袋状になったところや、意外に見落とすのが冷蔵庫の上だったりします。事前に隠れそうな場所をいくつか聞いておくことも、ペットシッターの仕事を遂行する上で重要です。
さて、今回ご紹介する小説『猫は知っていた/仁木悦子』でも、妙なところに隠れたりまた姿を現したりする猫が出てきます。江戸川乱歩賞が公募となった最初の回で見事、受賞作に選ばれたのが本作。なんと1957年の作品です。著者の仁木悦子さんは、日本のミステリ史で最初に登場する女性作家であり、日本のアガサ・クリスティとも呼ばれました。
小説の主人公は、著者と同じ名前の仁木悦子という女性と、その兄の雄太郎。この二人が移り住んだ先で、連続殺人事件が起こります。大学で植物学を専攻する雄太郎は頭脳明晰で、事件の謎を追い、真相を解き明かしていきます。悦子も素人捜査の一員として兄に付き添い、彼らはさながらホームズとワトソンのような活躍を見せるのです。
本作の特徴の一つは、古き良きミステリの味わいを堪能させてくれるところです。兄妹が病院の一室を間借りするところから物語は始まりますが、この導入部からして時代感満載です。本作が書かれた1957年当時でも、戦争の爪痕はまだ各地に残っていました。二人は戦災のためか住む場所を失い、ようやく病院の一室を住居として借りることになりました。病室に兄妹で住む、というのは今となってはなかなか考えづらい状況です。さらに、病院の敷地内に当たり前のように防空壕跡があるのもこの時代ならでは。この防空壕が本作で重要な役割を果たします。
そしてもう一つ重要な存在が猫です。最初に老婦人が殺されるとき、猫の姿が見当たらなくなります。前述したとおり、猫はいつの間にかどこかに行ってしまうものですが、本作でも意外なところで見つかります。さらにラストの謎解きでもう一度、猫が深く関わってきます。解き明かされた真相を知れば、猫好きの人はにやりとするはず。どう関わってくるのか、どうぞ本作を読んでお楽しみください。











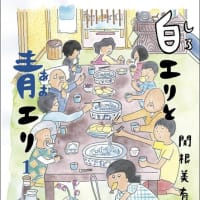
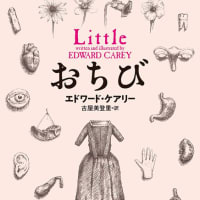
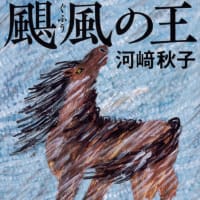
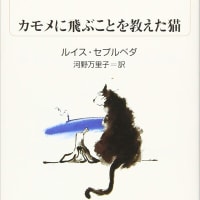
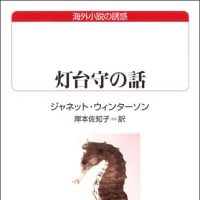
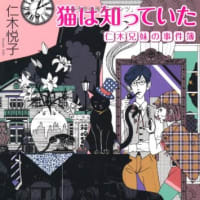
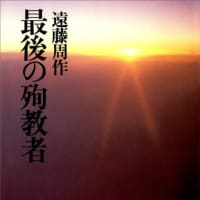
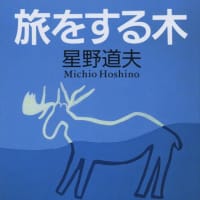
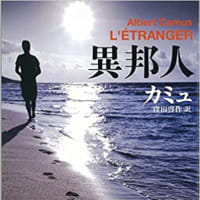
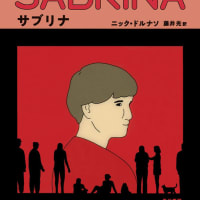
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます