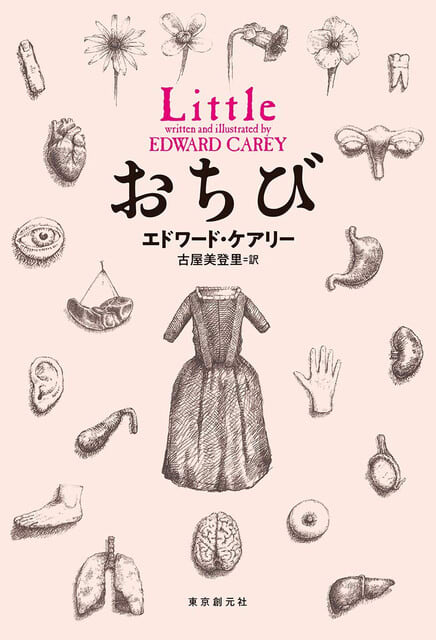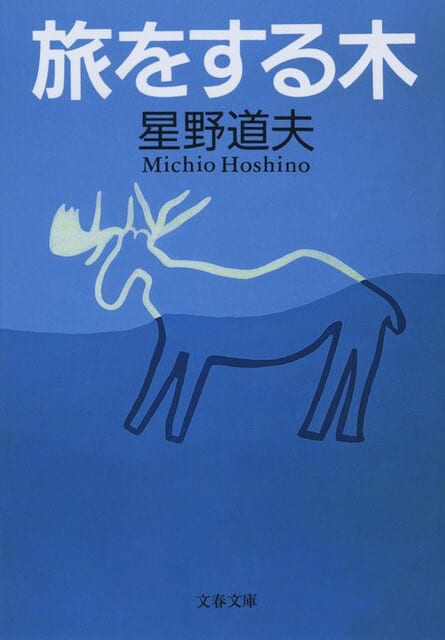愛知県に出された緊急事態宣言に伴い、やや増えてきたかなあと思えた仕事の依頼はふたたび激減しました。ただ、ワクチンの接種も少しずつではありますが進んでいる状況ですので、これが最後の我慢だと思っています。
コロナ禍において、あらためて自分の仕事を見つめ直した人は多いと思います。飲食店、映画館や美術館、旅行関連などは、仕事を存続させるだけで大変です。そうでない場合も、デスクワークなら自宅でのリモート作業に切り替わるなど、環境が大きく変化したことでしょう。
僕にとっても、ペットシッターという仕事についてじっくり考える機会となりました。旅行や出張がなくなっても、入院やどうしても外せない用事で外出される場合はありますから、ペットシッターの需要はゼロにはなりません。この状況下でも、「早くどこかにでかけたい」という声は日に日に高まっているのを感じますので、収束が近づくにつれ、仕事の依頼も増えていくものと思います。なにより僕はこの仕事が大好きですので、辞めるという選択肢はありません。これからもこの仕事を続けていくでしょうし、仕事を続ける喜びを感じられるのは幸せなことだと思っています。
今回ご紹介するのは、仕事について考察をめぐらせる漫画です。『白エリと青エリ』という変わったタイトルの短編集で、表題作は、大家族の中で暮らす高校生の少女・エリの日常を描いた連作短編集。エリは進路に悩み、家族や周囲の人々との交流のなかで、自分の生きていく道を探っていきます。簡素な絵柄で、見た目は『サザエさん』にも近いようなほのぼの系漫画ですが、身近な中にはっとさせられるような言葉や考え方が提示され、とても読み応えのある作品となっています。
動物の出てくる作品を紹介するブログなのに、今回はネタ切れかと思われた皆さん。そんなことありませんよ。本書には表題作の他に3つの独立した短編が収録されています。
「わたしのしごと」は、子ブタのリボンちゃんが主人公。リボンちゃんは人間の少女から「あなたのしごとはなに?」と訊かれ、戸惑います。考えたすえ、「トンカツになることかしら?」と答えると、少女は「それはしごとじゃないわ。運命よ」と返します。なんともシュールな会話です。その後、リボンちゃんはことあるごとに自分のしごとについて思いを巡らせます。やがて時は流れ、大きくなった少女にリボンちゃんが伝えた言葉とは--。
そして、僕がもっともぐっときたのが「飛ぶな、猿」という一編。地球が猿に支配された世界で、猿の吾作が飛行機を発明します。彼が危険な実験をおこなったおかげで飛行機が実用化され、猿の世界は豊かなものになりました。彼はいつも洗濯ばかりしている母親に、あるときこう伝えます。「お母さん。命は大切だと言わないでいてくれてありがとうございました」と。
命を大切に、なんてことは誰にでも言えます。母親は、誰よりも心配していただろうにそれを口に出さず、おかげで吾作は実験を成功させ、猿の世界に大きな一歩を踏み出すことができたのです。前述の吾作の言葉は僕の胸に突き刺さりました。そして、そんな吾作に母親の返した言葉がまた凄い。最後の最後の一コマです。これを読んで僕は涙があふれました。その言葉はここでは紹介しません。ぜひぜひ、この一編だけでも読んでみてほしいのです。16ページほどの、ほんの短い漫画ですので。