ペットのシッティング期間中、 ペットシッター自身が体調を崩したらどうなるのか、と聞かれることがあります。普段から体調管理に努めることはもちろんなのですが、それでも不測の事態に陥る可能性はあります。ペットシッター・ジェントリーでは、近隣に複数のスタッフが在籍していますので、基本的にはそのスタッフ達が代わりにシッティングを実施することになります。スタッフは全員、パソコンの同じツールを使っており、作業用のデータはオンラインで簡単にやりとりができます。通常よりも時間はかかるかもしれませんが、体調不良でシッティングに行けない場合でも、別スタッフが対処することは可能です。
もっと緊急の事態、たとえばシッターが交通事故に遭い、意識を失ってしまったとしたらどうでしょう。この場合、即座に対応することは難しく、解決は容易ではありません。ただ、当方のスタッフは全員、緊急時対応カードを財布などに入れて保持しています。カードには、ペットシッターという仕事をしており、自分がいないとペットの身に危険が及ぶため、このカードを見たらすぐ連絡をして下さい、という旨が書かれ、裏面には別スタッフや家族の連絡先が一覧になっています。つまり、誰かがそのカードを見た段階で、別スタッフに連絡をしてもらうという想定です。現時点ではこのくらいの対処しか考えられませんが、最悪の事態でも、考えられるかぎりの備えはおこなっているつもりです。
しかし、ペットシッターと違い飼い主の皆様が体調を崩された場合、事情はもっと深刻です。すぐに治る程度ならよいのですが、長期の入院となったり、そのまま治らず亡くなってしまった場合、ペットはどうなるのか。これまた簡単な問題ではありません。
今回ご紹介する小説『ティンブクトゥ/ポール・オースター著・柴田元幸訳』でも、死にゆく飼い主と犬との別れが描かれます。ただ、ポール・オースターという作家はひねくれた小説を書く人で、本作においてもいくつか特徴があります。いちばんは、語り手が犬だということ。犬の一人称で、犬から見た人間や世界の姿が描かれるのです。かといって「~だワン!」みたいに、わざとらしく犬の語りを際立たせるわけではありません。
主人公となる犬のミスター・ボーンズは、7年ほど前から、ウィリーという男性とニューヨークで暮らしています。ウィリーは幼い頃に父親を亡くし、口うるさい母親と二人で生きてきました。何かにつけ母親に反抗し、青年期に入るとドラッグに手を出した挙げ句、精神を崩壊させて病院に入ります。放蕩のすえ、あるときテレビから神の啓示を受け、自らをサンタクロースだと名乗りはじめます。その後は、詩作にふけったり、危険を顧みず暴漢から市民を救ったり、かと思えばアルコールに助けを求めたり、奔放な日々を送ります。身の回りに敵が増えるなか、ボディガードとして飼い始めたのがミスター・ボーンズでした。
こうして年月が過ぎたあと、ウィリーは重い病気にかかり、命の炎が尽きようとしていました。彼は、かつて自分の文学的才能を見出し、支えてくれた女教師のもとを訪ねるため、ミスター・ボーンズを連れてボルチモアへと向かいます。願いは二つあって、一つは書き溜めた膨大な文章を託すこと。もう一つは、ミスター・ボーンズの世話を引き受けてもらうことでした。
さて、オースター作品のもう一つの特徴は、物語が一本調子に進まないことです。現在の状況を語るなかでミスター・ボーンズの回想が混じり、当初の目的だった女教師に会う計画もすんなりとは進みません。ミスター・ボーンズが見た夢の話があり、夢の中の犬がまた夢を見ていたりして、いったいいつの時代の出来事なのか、いま起きているのは真実なのか空想なのか、判然としなくなってきます。物語は読者の予想を外れ、意外なほうへと進んでいきます。
訳者あとがきによれば、著者のオースターは、現実の犬の思考や感情を再現しようとしたつもりは毛頭ないのだそうです。それでも僕は、自分が犬だったらどう考えるか、目の前の出来事をどう捉えるのかと、著者が真摯に向き合って描いた気がしてなりません。もちろん、犬が本当にどう思っているのかは知るよしもありませんが、少なくとも本書を通して鼻白む箇所は一つもなく、ミスター・ボーンズに対する愛着は読むごとに深まっていきます。犬に対する興味や愛着がなければ、こうは書けないでしょう。
やがてミスター・ボーンズはウィリーのもとを離れ、各地を渡り歩くこととなります。様々な人と出会い、幸せも不幸せも経験していきます。果たして最後に行きつく先はどこなのか、そして、タイトルの「ティンブクトゥ」とはいったい何なのか。ぜひ読んで確かめてみてください。一風変わった犬小説ですが、読み終えた後にはとても素直で清々しい感動が待っています。そして、ミスター・ボーンズのことを心から愛おしく思えることでしょう。











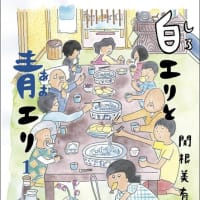
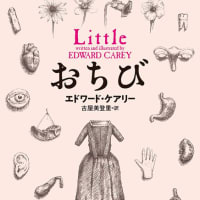
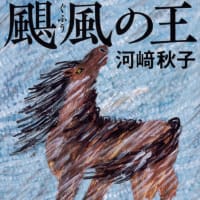
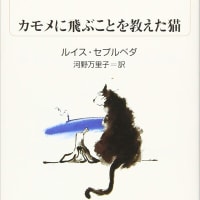
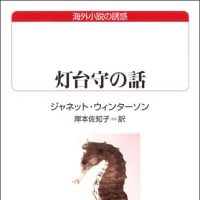
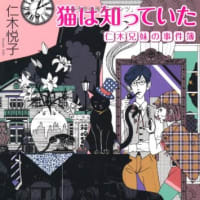
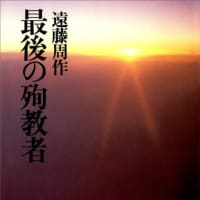
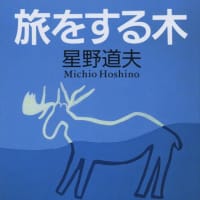
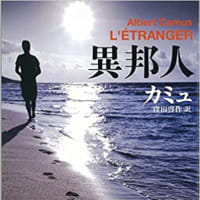
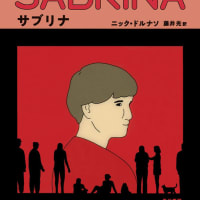
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます