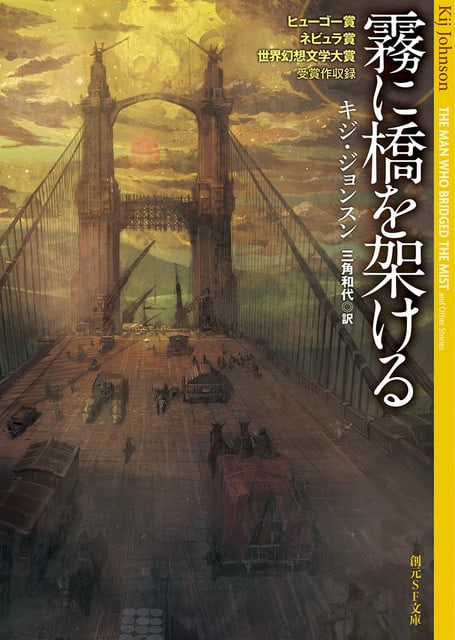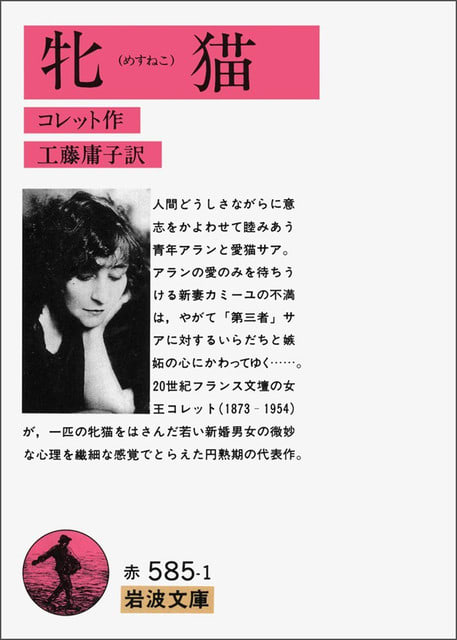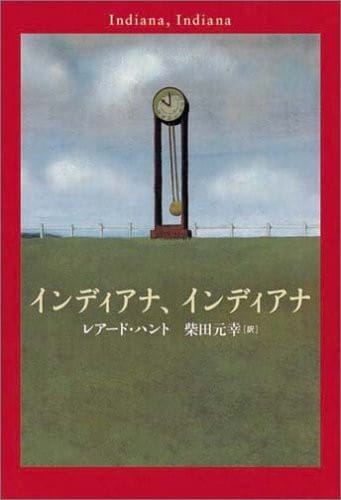猫や犬など、いろんな動物が仲良く暮らしているのを見るのは微笑ましいものです。ただ、ペットシッターの仕事でそうしたケースに遭遇することは少なく、やはり異なる種類のペットを一緒に飼うことは実際には大変なのでしょう。
たとえば犬と猫を比べると、犬が人間や他の動物とも積極的に仲良くしようとするのに対し、猫は自分のペースを守るのを重視する傾向にあります。(もちろんこれは一般論なので例外は多数ありますが。)小説などのフィクションでも同じように描かれることが多く、どうしても猫は気まぐれで意地悪なキャラクターにされがちです。
今回ご紹介する小説『カモメに飛ぶことを教えた猫/ルイス・セプルベダ著・河野万里子訳』にもたくさんの猫が出てきますが、やはりマイペースで個性的な猫ちゃんばかり。そんな彼らが力を合わせて一羽のカモメを救おうとするのが、このお話です。主人公はゾルバといういう名の、ふとった真っ黒な猫。ドイツの港町ハンブルクでのんびりと暮らしています。ある日、ゾルバが日光浴を楽しんでいたバルコニーに、一羽のカモメが落ちてきます。海で原油にまみれながら、力を振り絞ってここまで飛んできたのです。カモメはゾルバに三つの願い事をします。これから生む卵をけっして食べないこと、卵をヒナに孵すこと、ヒナに飛ぶことを教えること。カモメは卵をゾルバにたくし、息を引き取ります。
そこからゾルバの苦難が始まりました。卵を食べないのはなんとか我慢することでしのげたものの、自分の子供すら育てたことのないゾルバに卵をかえす方法などわかりません。彼は町に住む猫に助けを求めます。〈困っている者に力を与えることのできる、不思議な助言の能力〉を持つ、年齢不詳の猫〈大佐〉。やせてひげも二本しかない野良猫の〈秘書〉。ゾルバが話をすると、二匹は彼を〈博士〉の元へ連れていきます。灰色猫の〈博士〉は、老水夫の集めた膨大なコレクションの展示館に住み、日々百科事典の研究にいそしんでいます。〈博士〉は百科事典をひもとき、ゾルバに解決策を授けようとしますが、それだけではうまくいかないこともあります。彼らはどうやってカモメを救うのでしょうか。
〈大佐〉は尊大な割に物を知らず、〈秘書〉は〈大佐〉の言葉に口を出して怒られてばかり。〈博士〉は百科事典を信奉するあまり本質を見失いそうになります。街に出ればちんぴらの野良猫が行く手をはばみ、〈博士〉と同居するいやみなチンパンジーや中庭の通行権を求めるネズミなど、多彩なキャラが猫たちを悩ませます。本書の対象年齢は8歳から88歳まで、と言われているようですが、カモメとの約束を果たそうとするゾルバの冒険話に、子供なら胸を躍らせること間違いなしです。
いっぽう、大人は話の寓意性に目を向けることでしょう。〈秘書〉や〈大佐〉など、身近な誰かに似ている気がしてきますし、彼らとのやりとりはまさに人間社会を写したものに思えてきます。
本書の根底には人間のおこないに対する強い戒めが感じられます。カモメが飛べなくなったのは人間が海に垂れ流す重油のせいです。猫たちは他にも、人間が海に捨てる殺虫剤の缶や古タイヤなどに頭を悩ませています。イルカやライオンなどさまざなま動物を人間が手なずけ、もてあそんでいることも著者は批判しています。それでも、ラストの展開には人間に対するかすかな希望もうかがえます。
著者のルイス・セプルベダ氏は、2020年4月、新型コロナ感染により亡くなりました。また、作中で引用される「カモメ」という詩は、同じく2020年に日本で刊行され話題となった『アコーディオン弾きの息子』の著者ベルナルド・アチャーガ氏によるものです。そしてなにより、様々な動物たちが自分の意見を主張し、いがみあい、違いを認識しあい、それでも同じ世界に住む様を描き出しているところは、現在の多様化する社会の見本といえます。
様々な意味で現代性を感じる作品です。短くてすぐに読めますので、一家に一冊、食卓にでも置いてみてはいかがでしょう。親子で読んで感想を披露しあうのもきっと素敵な体験になることと思います。