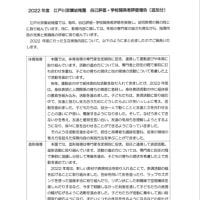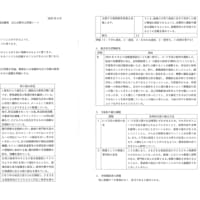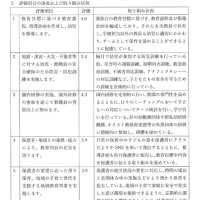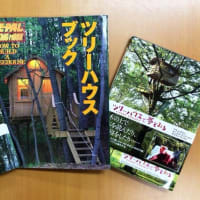はじめに
幼児期は、子どもの成長において人生の中で最も大切な時期と言われています。しかし、なぜ大切なのかについてはあまり知られていません。ここでは、幼稚園で過ごす子どもたちの事例を通して、子どもたちのこころの中に育っているものについて考えてみたいと思います。
ある新入園児のおはなし
ある年の4月です。新入園児3歳の男の子で、毎朝玄関で泣いている子どもがいました。仮にA君としておきます。お母さんと徒歩で登園してくるのですが、幼稚園の玄関に着いて、お母さんが帰ろうとすると泣き始めます。しかし、お母さんにしがみつくでことはありません。そこで、主任の先生がその子を抱っこします。抱っこしていると次第に落ち着き、泣きやみます。しかし、靴をはきかえたり保育室に行ったりはしません。先生が下におろそうとすると、また泣き始めるので、先生は一日その子を玄関で抱っこして過ごします。入園したてで午前保育ですから、2時間ちょっとぐらいの間、ずっと抱っこして過ごします。
先生はA君を抱っこしたまま、他の子どもたちを話をしたり、園庭で遊ぶ子どもたちの様子を見てA君に話しかけたり、保育室の方を覗いてみんなが何をしているのかをA君に話したりします。毎日そのように過ごしていました。
4月後半のある日、いつものようにA君はお母さんと一緒に登園してきました。玄関を入るなり、今日も泣きそうな顔をしています。先生は思わず、「甘えたいの?」と聞いてみました。するとA君は、「うん」と大きくうなずいて、手を広げて抱っこを求めました。先生はにっこり笑っていつものように抱きあげ、また玄関で一日過ごしました。しかし、その日は大きな変化がありました。A君が泣かなかったのです。
次の日、また変化がありました。登園してきたA君は、玄関から入り主任の先生の顔を見つけると、一言言いました。
「甘えたい。」
主任の先生は思わず笑ってしまったのですが、「そうなの、甘えたいの?」と言って抱っこしました。それから、A君は毎日登園してくると先生に「甘えたい」と言うようになりました。そしてもう泣かなくなりました。
そのうちに、先生に抱っこしてもらいながらであれば、靴を替えて保育室に入ることもできるようになりました。また、先生のエプロンにつかまっていれば、抱っこされないでもいられるようになりました。そしてさらに、先生が見ていてくれれば、先生から離れて友達と遊ぶこともできるようになりました。
5月のある日、A君はいつものように登園してきましたが、「甘えたい」と言わずに先生の前を通り過ぎて靴を替えました。先生は心配になり、「今日は甘えないの?」と聞きました。すると、A君は「今日はいい」と言って行ってしまいました。次の日も先生は「今日は甘えないの?」聞きました。するとA君は、「今日は甘える」と言って抱っこしてもらい、しばらくすると降りて遊びに行きました。
しばらくの間は、先生は毎日、「今日は甘えないの?」と聞いてみました。A君はその日によって、「今日は甘える」と言ったり、「今日はいい」と言ったりしていましたが、ある日、「もうそんなこと聞かないでくれよ」というような恥ずかしそうな顔をして、保育室の方へ行ってしまいました。先生は、もう大丈夫だと思い、その日から、「今日は甘えないの?」とは聞かなくなりました。A君はそんな風にして、幼稚園生活に馴染んでいきました。
A君の気持ち
さて、それではA君のこころの中では、何が起こっていたのでしょうか。A君が泣いていたのは、幼稚園が嫌いだったのでしょうか。それとも、お母さんと離れるのが嫌だったのでしょうか。幼稚園が嫌いだったのであれば、家を出るときに泣いていたはずです。お母さんと離れるのが嫌だったのでしたら、お母さんが帰るときにしがみついて泣いていたはずです。しかし、A君はそのどちらでもありませんでした。
先生はA君のおかれた状況や表情その他の様子を見て、「甘えたいの?」と声をかけました。A君は、お母さんに代わって自分を甘えさせてくれる人が欲しかったのでしょう。先生のその言葉に大きくうなずき、そこからA君は変わってきました。
それまでのA君は、泣くしかありませんでした。幼稚園に行きたくないわけではない。お母さんと離れるのが嫌なわけでもない。だけど、お母さんに代わって甘える相手が欲しいということを言葉にして伝えるようなことはまだできません。それどころか、こころの中で気持ちが整理されているわけでもありません。
そんな時、先生が「甘えたい」という言葉をかけてくれたのです。A君は、自分の今のこころの状態とその言葉がぴったりということに気付きました。A君が「甘える」という言葉を以前から知っていたかどうかはわかりませんが、自分の気持ちとその言葉がぴったり結びつくことに気付いたのです。そして、その言葉を使って、新しい世界に一歩踏み出すことができたのです。
気持ちを理解されるということ
A君のこころの中では、次のようなことが起こっていたと思われます。
・気持ちを理解されることによって安心した
・自分で自分の気持ちがわかった
・気持ちを表す言葉を手に入れた
・自分の気持ちを伝えることができるようになった
大人でも、自分で自分の気持ちがよくわからなくなることがあります。身近な人に、「本当はこうなんじゃないの?」と言われて、ドキッとしたりスッキリしたりすることもあります。
大人は言葉の習得が一応終わっており、日常的に使われる言葉はすべて知っています。それでも、自分の気持ちが言葉にできないことがあります。
子どもはまだ言葉を知りません。聞いたことがあってもまだ意味がわからない言葉もたくさんあります。しかし、こころの中では、すでに色々なことを感じています。そして、そこで感じていることやこころの中で起こっていることが何なのか、わからないままでいます。そんな時、涙が出てきます。
気持ちを表す言葉
子どもが言葉を覚えるとき、最初に覚えるのは、たいていはモノの名前です。「ママ」や「パパ」が多いようです。たとえば、パパがいるときにママがパパを指差してパパと言いますので、子どもにとっては、目の前にいる男の人とパパという言葉が結びつき、その言葉を覚えます。「ワンワン」も同じです。目の前に犬がいるとき、周りの大人が「ワンワンいるね」とか「ワンワンかわいいね」と何度も言うので、目の前にいる生き物とワンワンという言葉が結びつき、ワンワンという言葉を覚えます。
では、「嬉しい」とか「悲しい」などの、気持ちを表す言葉は、どのようにして覚えるのでしょうか。
「嬉しい」というものは、この世の中にはありません。目にも見えませんし触ることもできません。では、どのようにして子どもに教えたらいいでしょうか。「嬉しい、嬉しい…」と10回ぐらい言わせたらいいでしょうか。
子どもがうれしいと思ってるときに、「嬉しいね」と声をかけると、子どもはその時感じている心地よい思いと「嬉しい」という言葉が結びつき、嬉しいとい言葉を覚えます。「悲しい」も「楽しい」も「さびしい」も同じです。気持ちを表す言葉を獲得するのは、自分の気持ちを理解し共感してくれる人がそばにいて、その時の気持ちを言葉にしてくれた時ということになります。つまり、自分を理解し共感してくれる人がいて初めて、言葉を覚えることができるのです。
もし、自分の気持ちをだれも理解してくれなかったら。たとえば、子どもがさびしいと思っているとき、だれも理解してくれなかったら、子どもは今感じている不快で辛い気持ちが何なのか、わからないままです。そして泣くことしかできません。しかも、泣いているだけではだれも自分の気持ちをわかってはくれません。
しかし、だれかが理解してくれて、「さびしいね」「さびしかったね」と声をかけてくれたら、きっとわかってもらえたことで安心し、今自分が感じているのは「さびしい」という気持ちなんだということがわかり、次に同じ気持ちを感じた時には、気持ちを分かってほしい人に「さびしい」と伝えることができるようになります。
世の中には、いろいろな環境で育つ子どもたちがいます。中には、小さなころにだれにも気持ちを理解されず共感されずに育つ子どもたちもいます。こころの中のモヤモヤが自分でも整理することができず、言葉にすることも人に伝えることもできない子どもたちもいます。そのために、周りの人にますます理解され難くなり、苦しい思いをしていたりします。そのようなこともあることをお心にとめていただければ幸いです。
人生の最初のところで、気持ちをわかってくれる大人に出会えたかどうかで、子どものその後の人生は大きく変わってきます。大人が子どもの気持ちを理解するということは、子どもにそれほどの影響を与えるのです。
おわりに
人間は感情の生き物です。どんなに良い環境に置かれても、どんなにお金持ちになっても、こころが満たされていなければ、幸せを感じることはありません。人に理解され理解し合う関係というものは、お金では買えませんし、学歴も知識も関係ありません。
人生で一番大切なことは、親子関係の中にあり、そして最初に社会に出る幼稚園生活の中にあります。子どもたちの幸せのためにも、この時期を大切にしていきたいと思います。
幼児期は、子どもの成長において人生の中で最も大切な時期と言われています。しかし、なぜ大切なのかについてはあまり知られていません。ここでは、幼稚園で過ごす子どもたちの事例を通して、子どもたちのこころの中に育っているものについて考えてみたいと思います。
ある新入園児のおはなし
ある年の4月です。新入園児3歳の男の子で、毎朝玄関で泣いている子どもがいました。仮にA君としておきます。お母さんと徒歩で登園してくるのですが、幼稚園の玄関に着いて、お母さんが帰ろうとすると泣き始めます。しかし、お母さんにしがみつくでことはありません。そこで、主任の先生がその子を抱っこします。抱っこしていると次第に落ち着き、泣きやみます。しかし、靴をはきかえたり保育室に行ったりはしません。先生が下におろそうとすると、また泣き始めるので、先生は一日その子を玄関で抱っこして過ごします。入園したてで午前保育ですから、2時間ちょっとぐらいの間、ずっと抱っこして過ごします。
先生はA君を抱っこしたまま、他の子どもたちを話をしたり、園庭で遊ぶ子どもたちの様子を見てA君に話しかけたり、保育室の方を覗いてみんなが何をしているのかをA君に話したりします。毎日そのように過ごしていました。
4月後半のある日、いつものようにA君はお母さんと一緒に登園してきました。玄関を入るなり、今日も泣きそうな顔をしています。先生は思わず、「甘えたいの?」と聞いてみました。するとA君は、「うん」と大きくうなずいて、手を広げて抱っこを求めました。先生はにっこり笑っていつものように抱きあげ、また玄関で一日過ごしました。しかし、その日は大きな変化がありました。A君が泣かなかったのです。
次の日、また変化がありました。登園してきたA君は、玄関から入り主任の先生の顔を見つけると、一言言いました。
「甘えたい。」
主任の先生は思わず笑ってしまったのですが、「そうなの、甘えたいの?」と言って抱っこしました。それから、A君は毎日登園してくると先生に「甘えたい」と言うようになりました。そしてもう泣かなくなりました。
そのうちに、先生に抱っこしてもらいながらであれば、靴を替えて保育室に入ることもできるようになりました。また、先生のエプロンにつかまっていれば、抱っこされないでもいられるようになりました。そしてさらに、先生が見ていてくれれば、先生から離れて友達と遊ぶこともできるようになりました。
5月のある日、A君はいつものように登園してきましたが、「甘えたい」と言わずに先生の前を通り過ぎて靴を替えました。先生は心配になり、「今日は甘えないの?」と聞きました。すると、A君は「今日はいい」と言って行ってしまいました。次の日も先生は「今日は甘えないの?」聞きました。するとA君は、「今日は甘える」と言って抱っこしてもらい、しばらくすると降りて遊びに行きました。
しばらくの間は、先生は毎日、「今日は甘えないの?」と聞いてみました。A君はその日によって、「今日は甘える」と言ったり、「今日はいい」と言ったりしていましたが、ある日、「もうそんなこと聞かないでくれよ」というような恥ずかしそうな顔をして、保育室の方へ行ってしまいました。先生は、もう大丈夫だと思い、その日から、「今日は甘えないの?」とは聞かなくなりました。A君はそんな風にして、幼稚園生活に馴染んでいきました。
A君の気持ち
さて、それではA君のこころの中では、何が起こっていたのでしょうか。A君が泣いていたのは、幼稚園が嫌いだったのでしょうか。それとも、お母さんと離れるのが嫌だったのでしょうか。幼稚園が嫌いだったのであれば、家を出るときに泣いていたはずです。お母さんと離れるのが嫌だったのでしたら、お母さんが帰るときにしがみついて泣いていたはずです。しかし、A君はそのどちらでもありませんでした。
先生はA君のおかれた状況や表情その他の様子を見て、「甘えたいの?」と声をかけました。A君は、お母さんに代わって自分を甘えさせてくれる人が欲しかったのでしょう。先生のその言葉に大きくうなずき、そこからA君は変わってきました。
それまでのA君は、泣くしかありませんでした。幼稚園に行きたくないわけではない。お母さんと離れるのが嫌なわけでもない。だけど、お母さんに代わって甘える相手が欲しいということを言葉にして伝えるようなことはまだできません。それどころか、こころの中で気持ちが整理されているわけでもありません。
そんな時、先生が「甘えたい」という言葉をかけてくれたのです。A君は、自分の今のこころの状態とその言葉がぴったりということに気付きました。A君が「甘える」という言葉を以前から知っていたかどうかはわかりませんが、自分の気持ちとその言葉がぴったり結びつくことに気付いたのです。そして、その言葉を使って、新しい世界に一歩踏み出すことができたのです。
気持ちを理解されるということ
A君のこころの中では、次のようなことが起こっていたと思われます。
・気持ちを理解されることによって安心した
・自分で自分の気持ちがわかった
・気持ちを表す言葉を手に入れた
・自分の気持ちを伝えることができるようになった
大人でも、自分で自分の気持ちがよくわからなくなることがあります。身近な人に、「本当はこうなんじゃないの?」と言われて、ドキッとしたりスッキリしたりすることもあります。
大人は言葉の習得が一応終わっており、日常的に使われる言葉はすべて知っています。それでも、自分の気持ちが言葉にできないことがあります。
子どもはまだ言葉を知りません。聞いたことがあってもまだ意味がわからない言葉もたくさんあります。しかし、こころの中では、すでに色々なことを感じています。そして、そこで感じていることやこころの中で起こっていることが何なのか、わからないままでいます。そんな時、涙が出てきます。
気持ちを表す言葉
子どもが言葉を覚えるとき、最初に覚えるのは、たいていはモノの名前です。「ママ」や「パパ」が多いようです。たとえば、パパがいるときにママがパパを指差してパパと言いますので、子どもにとっては、目の前にいる男の人とパパという言葉が結びつき、その言葉を覚えます。「ワンワン」も同じです。目の前に犬がいるとき、周りの大人が「ワンワンいるね」とか「ワンワンかわいいね」と何度も言うので、目の前にいる生き物とワンワンという言葉が結びつき、ワンワンという言葉を覚えます。
では、「嬉しい」とか「悲しい」などの、気持ちを表す言葉は、どのようにして覚えるのでしょうか。
「嬉しい」というものは、この世の中にはありません。目にも見えませんし触ることもできません。では、どのようにして子どもに教えたらいいでしょうか。「嬉しい、嬉しい…」と10回ぐらい言わせたらいいでしょうか。
子どもがうれしいと思ってるときに、「嬉しいね」と声をかけると、子どもはその時感じている心地よい思いと「嬉しい」という言葉が結びつき、嬉しいとい言葉を覚えます。「悲しい」も「楽しい」も「さびしい」も同じです。気持ちを表す言葉を獲得するのは、自分の気持ちを理解し共感してくれる人がそばにいて、その時の気持ちを言葉にしてくれた時ということになります。つまり、自分を理解し共感してくれる人がいて初めて、言葉を覚えることができるのです。
もし、自分の気持ちをだれも理解してくれなかったら。たとえば、子どもがさびしいと思っているとき、だれも理解してくれなかったら、子どもは今感じている不快で辛い気持ちが何なのか、わからないままです。そして泣くことしかできません。しかも、泣いているだけではだれも自分の気持ちをわかってはくれません。
しかし、だれかが理解してくれて、「さびしいね」「さびしかったね」と声をかけてくれたら、きっとわかってもらえたことで安心し、今自分が感じているのは「さびしい」という気持ちなんだということがわかり、次に同じ気持ちを感じた時には、気持ちを分かってほしい人に「さびしい」と伝えることができるようになります。
世の中には、いろいろな環境で育つ子どもたちがいます。中には、小さなころにだれにも気持ちを理解されず共感されずに育つ子どもたちもいます。こころの中のモヤモヤが自分でも整理することができず、言葉にすることも人に伝えることもできない子どもたちもいます。そのために、周りの人にますます理解され難くなり、苦しい思いをしていたりします。そのようなこともあることをお心にとめていただければ幸いです。
人生の最初のところで、気持ちをわかってくれる大人に出会えたかどうかで、子どものその後の人生は大きく変わってきます。大人が子どもの気持ちを理解するということは、子どもにそれほどの影響を与えるのです。
おわりに
人間は感情の生き物です。どんなに良い環境に置かれても、どんなにお金持ちになっても、こころが満たされていなければ、幸せを感じることはありません。人に理解され理解し合う関係というものは、お金では買えませんし、学歴も知識も関係ありません。
人生で一番大切なことは、親子関係の中にあり、そして最初に社会に出る幼稚園生活の中にあります。子どもたちの幸せのためにも、この時期を大切にしていきたいと思います。