皆様、おはようございます。中小企業診断士の福田徹です。1月24日土曜日、今朝2時の東京・小平は晴れ、気温は8℃です。
今日は、放送大学大学院の単位認定試験を3科目受けてきます。これを書いている午前2時現在、これまでの勉強不足を痛感し反省モードになりつつあります。
そんなわけで、試験結果への展望は悪くなりつつありますが、昨日に続き受講科目についてお話しさせていただきます。
今日ご紹介するのは、西川泰夫先生の「認知行動科学~心身の統合科学を目指して」という講義です。
認知行動科学とは、これまで心理学などにより考えられ続けてきた「心の科学」と、進化論、生物学、から最新の脳神経科学などによって解明されてきた「身体の科学」の統合を目指すものです。
心と身体の統合的理解を目指す旅はデカルトの心身二元論から始まります。デカルトは、人の「心」のみを特別のものとして扱い、一方で「心」以外の人の「身体」、動物などを含む森羅万象については物質として捉えました。
ここに「非物質である心が物質である身体を制御可能か、また逆に物質である身体が非物質である心を制御可能か」という「心身問題」が発生します。
講座は、この「心身問題」の解決をめぐって、カント、ホッブスなどを引きながら進んでいき、やがて現代記号論理学により、心は計算機であるということの確証を得るに到ります。
その後、心を外側から捉える行動論が花開き、パヴロフやワトソン、スキナーが活躍し、観察による客観的な心の研究が進みます。
さらに、1940年代以降の情報科学の進展、コンピュータの実現、脳神経科学の進展により、1960年代には認知論が台頭し、心を記号の処理操作システムとして捉えるパラダイムにシフトする。
ここに、人間は情報処理システムと捉えられるようになる。このながれは、1980年代に入りデカルト以来の心身問題に取り組む「認知行動科学」へとつながっていきます。
その「認知行動科学」は、意識、知性、思考、言葉、情熱、成熟・発達現象などの考察とともに、物資州から生命が生成した経緯、さらに生命を持つ物質からいかにして心が生成されるのかを問う幅の広い分野です。
そして講義の最後は、「認知行動科学」対する異論を検討し争点を整理します。また、結論としてこの分野の思索と検証がまだまだ終局には程遠いことを示すとともに、将来像を描くためには講義で示した各パラダイムを歴史的経緯の中で位置付け理解を深めることが必要と説きます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
以上が、概要です。とても難しいと感じています。
※当ブログおすすめ記事の紹介
内部留保についての誤解を解こう
自分の電子証明書をみる:公的個人認証サービス
「ピンチはチャンス」の年が始まります
最新の画像[もっと見る]
-
 青色決算&確定申告&弊社決算&法人税等申告
11年前
青色決算&確定申告&弊社決算&法人税等申告
11年前
-
 金沢出張
12年前
金沢出張
12年前
-
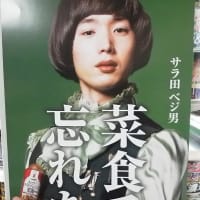 西友「バスプラ」シリーズ
13年前
西友「バスプラ」シリーズ
13年前
-
 西友「バスプラ」シリーズ
13年前
西友「バスプラ」シリーズ
13年前
-
 3年ぶりの三香温泉
13年前
3年ぶりの三香温泉
13年前
-
 蛙の大合唱@オンネトー
13年前
蛙の大合唱@オンネトー
13年前
-
 ぶりステーキ@ゆうじ
13年前
ぶりステーキ@ゆうじ
13年前
-
 三田製麺所@有楽町
13年前
三田製麺所@有楽町
13年前
-
 青葉@甲府
13年前
青葉@甲府
13年前
-
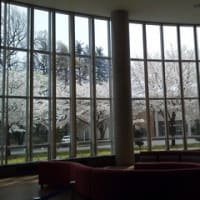 学生証を更新しました@放送大学
13年前
学生証を更新しました@放送大学
13年前









