
石居進 『 カエルの鼻 』を読んで、すっかり里心がついたところに、
子供が学校でJ.S.バッハの小ーガト短調 (YouTubeのコープマン演奏にリンク) を習ってきた話をするもんだから、
子供の期末前にもかかわらず、
映画を観てきた翌日でくたびれているにもかかわらず、
どうしても生のオルガンを子供たちに聴かせたくなってしまったわけだ。
自分の過去をつまびらかにする趣味はないはずなんだけれどねぇ。
かつて大学1年のとき、大学の宗務部の掲示板のポスターにふと目がとまって、
オルガン講座のオーディションを受けたら受かってしまって、
それでパイプオルガンを習うことができたのだ。
そのつてもあって、コンサートに行ってきた。
あそこは東京都だけれど草木生い茂る三鷹なので、車で行ったほうが楽だ。
それで、国道299号線のくねくね道をひた走り、
国道16号線に入り、新青梅街道を走り…、野川公園の横の大学に行った。
昔に比べたらずいぶん道がよくなって、3時間半~4時間くらいで着いた。
大学は懐かしいけれど、子供たちになんら思い出があるわけでもなし、
道が増えたり建物が増えたり壊していたり建てていたりして、
自分の歳を感じます。 約20年経つんだもんなぁ。
奏者はわたしが卒業してから新たにオルガン講師/奏者に加わった先生なので、
直接面識はない。
演目にも小フーガト短調は入っていない。
そんなんでも、いいのだ。
なにか突発的に行動するようだ、わたしは。
だってこの機会を逃したら、
わたしの子供たちはきっと一生、オルガンの演奏を生で観ることはないだろう。
ちょうど興味を持った今しかない!
いや、わたしがなんか行きたくなってしまっただけ!!
演奏はよかったです。
なんてでっかい楽器なんだ、パイプオルガンは!
あれを独りで操作するっていうのは、支配者になったようないい気分だ、と感じたことを思い出した。
おおげさにいえば、教会全体が楽器、だからなぁ。
演目の前半はバッハ、後半は現代もの、特に日本人の作曲が多かった。
バッハの方が安心して音楽に乗れるなぁ。
やっぱりオルガンは強烈に教会と結びついてしまっているんだなぁ。
溝上日出夫 「雲中供養菩薩」楽 は、涅槃の曲らしい。
そういう意味では宗教的だ。
オルガン講座で単位は取れないし、大規模なものではなかったので、
同期はわたしを入れて3人しかいない。
後輩達とは連絡も取り合っていないし、
わたしはキリスト教信者でもなければ教会に通っておらず、オルガンを続けているわけでもない。
勇んで行ったはいいが、まあ知り合いもいないだろうと思っていたのだ。
ぶっちゃけ奏者が全く見えず、音しかなかった代わりといってはなんだが、コンサートが終わると
リュックポジティブ (壇上の十字架の後ろの箱、あそこにもパイプが入っている) に
隠れている、鍵盤やらストップやらを見せてもらえる。
それを見に行こうとしたら、かつてのオルガンの先生に声を掛けていただいた。
年賀状は毎年出していたけれど、お会いしたのは20年ぶりくらい!?
話が弾んで、たいそう楽しかった。
行ってよかった。
そうそう、夫は行かなかった。

バカ山という。
この梅の木の下で、さんざ昼寝をしたものだ。 とっても気持ちよかった。 だから落ちこぼれなんだよ。 くぅ。
梅の木もすっかり大きくなった。

メタセコイアの下に、こんなキノコがいっぱい生えていた。
いいにおいがしたよ。 キシメジ?
食べられる?




















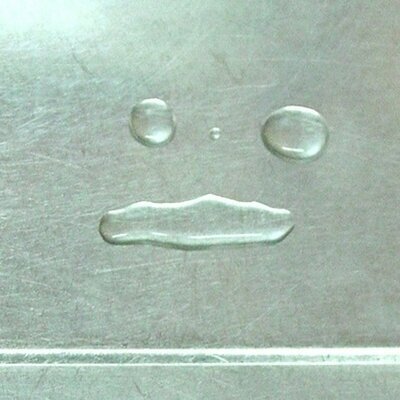




『カエルの鼻』、無事に誕生日を迎えた1号が今ハマって読んでます(^^)やっぱり面白いみたい。ふふふ。
建物自体が楽器になっていて、共鳴がうまく行くように建てられていて関心しますよね。
教会によって音色も違うし。
日本で行ったことが無いんですけど、ちーさんの通った大学には有るんですね、素晴らしい
『 カエルの鼻 』 が面白いとは、なかなか見所がありますねぇ。
いいなぁ。行ったことありません。
最近は、日本でもパイプオルガンが増えましたよ。
キリスト教系の大学や、北大や東大など、けっこうあるみたいです。
もちろん、教会にも。