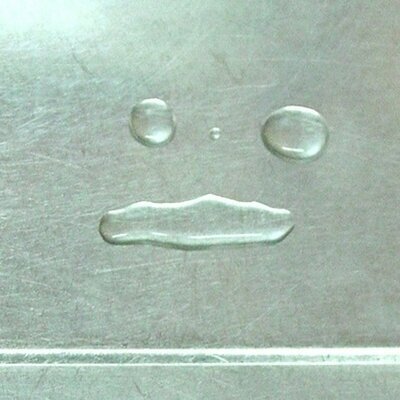76cmのムカデ(織り付けソーチ、ともいう)が来たので、
もう一度経糸を取り付けて、織り始めました。
経糸(たていと)がすぐに付くし、幅がちゃんと合ったので、織りやすい!
滝長さんありがとう。
昨日のはなし。
おとといは朝から晩まで出掛けていて、昨日も完全にダウンしていた。
こういう日は何をしてもうまくいかない、ってことも知っている。
だけど、何もしないともっと落ち込むし、そんなに時間に余裕があるわけでもない。
年賀状でまちがい連発をするよりは、まだ機(はた)や糸車の前に座っているほうがましだろう。
と思い、緯糸(よこいと)を入れ始めたわけだ。
経糸を機にかけているときは、糸さえかけてしまえばこっちのもん、
みたいな気分でいたが、いざ織り始めると、やっぱりそんなものではないのである。
そうだった、この前の布を織ったときもそうだった、と今さら思ってももう遅いんだ。
杼(ひ、シャトルともいう)をちゃんと投げられない。
少しうまくなったかな、というところで、前回は経糸が尽きたんであった。
それから、早1年以上経っている、忘れているよなー。
しかも、今回は前回よりも布幅があるから、もっと難しい。
杼を飛ばすことや、耳を気にしていると、今度は打ち込みの密度がムラになっている。
だいぶん前の部分の糸が飛んでいることに気が付く。
こんな、織りムラ、織りキズだらけじゃ、ダメダメだっ!
なんだかすごく、落ち込んでくるんだ。 はぁ~。
今日はもうダメだ、と思い、今度は糸車の前へ。
すると、やっぱり糸が切れるんである。
でも、しばらくはがんばって糸を紡いだよ。
とうとう機織りと糸紡ぎを断念して夕食の準備を始めたが、こちらは勝手に頭と体が働く。
機織りや糸紡ぎより、食事を作るほうがよっぽど上手だ!
毎日毎日多少の工夫を凝らして(凝らさない日もある)作ってるんだから、
当たり前といえば当たり前なんだけど。
それはそれで、またしても落ち込んだのであった。
先日スライバーを計ってみた。
50cmで2gだった。
その日は2時間半で10g紡げた。 つかれたー。
余分な力が入っているのが分かるので、首を左右に揺さぶっている。
我ながら、すごく変。
糸紡ぎが様になるには、まだまだ修練がいるんだろうなあ。
機織りも、「目指せ100反!」 とnunogotoさん はのたまうが、
ほんと、わたしもがんばらねば!
織りキズだらけじゃいやだー!
といいつつ、年賀状がわたしを待っている。

今日は雨。
庭のリンゴの枝に、水滴がついた。