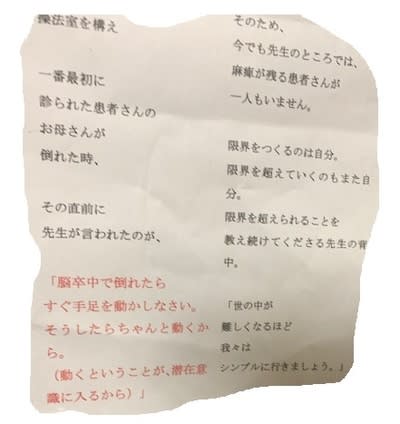井本整体とはまた違いますが、谷本道哉教授が、テレビから誘ってくるので、今まで敬遠していたスクワットをついやってみる気になりました。

膝の痛みがかなりよくなったと言っても、スクワットは無理でしょうと、はじめは思ったのですが、、、
「つま先より前に膝が出ない」という約束事が、難なくできて、お尻がしっかり後ろに下げられて、腰椎がしっかりとS字を作って、下までしゃがむことができました。
膝が痛くない!!!
やったー!嬉しい、嬉しい。
谷本先生の「からだすこやか、うれしい、うれしい」その言葉のまま。
マッチョな体で教える体操は、マッチョな人向きなのかと思ったら、不調を抱える人に、優しい、嬉しい体操だった。
「超体操」も、とても理にかなった動き方をして、嬉しい、楽しい。
これから、残りの、不要不急生活がおわっても、その先にも、欠かせないものと思います。

膝の痛みがかなりよくなったと言っても、スクワットは無理でしょうと、はじめは思ったのですが、、、
「つま先より前に膝が出ない」という約束事が、難なくできて、お尻がしっかり後ろに下げられて、腰椎がしっかりとS字を作って、下までしゃがむことができました。
膝が痛くない!!!

やったー!嬉しい、嬉しい。
谷本先生の「からだすこやか、うれしい、うれしい」その言葉のまま。
マッチョな体で教える体操は、マッチョな人向きなのかと思ったら、不調を抱える人に、優しい、嬉しい体操だった。
「超体操」も、とても理にかなった動き方をして、嬉しい、楽しい。
これから、残りの、不要不急生活がおわっても、その先にも、欠かせないものと思います。














 今日は、いつも凝り固まっているところが、ほぐれて、穏やかになっていたらしい。
今日は、いつも凝り固まっているところが、ほぐれて、穏やかになっていたらしい。