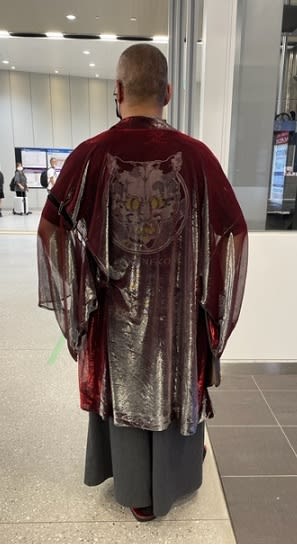息を吐く。吐き切ろうとしている時、どこが緊張していますか。
山田先生に質問されました。
このあたりと両手のひらで触ってみる。
斜腹筋ですね。そして、ここもと指摘されたのは、背筋です。
その時、私が自分で意識してなかったのですが、背筋にも緊張があったようです。
そう言われれば、という感じです。
先生は、背筋の力が弱いから自分では意識しにくいのだそうです。
今、巻き肩(先生はその表現は使いません)が少しずつ改善しているところです。
それには、背筋の力が必要ですが、先生のご指導は、あくまでも気持ちが良い
というところで肩甲骨やその周りを動かしましょうと、おっしゃいます。
いろんな場面で、「気持ちが良い」とおっしゃいます。
無理やりグイっとと動かしても、その反動で、元に戻ってしまうからです。
穏やかにやり続けることによって、気が付いたら、正しい位置にあった。
そんなやり方が、いつも山田先生のおっしゃる方法です。
そんな穏やかなやり方でも、今まで、動かすことを忘れていたところの筋肉が
動き始めると、筋肉痛になります。
その痛みを、症状の悪化ととらえてはもったいないことになります。
「痛みは、信号」と先生はおっしゃいます。
「その信号を正しく受け取って、正しく次のステップに移る」そのヒントを
毎回の施術の中で、身につけてきました。
話が井本整体になりました。今日のテーマの自分では動けない横隔膜を動かす
には、その二つの大きな筋肉を使って機能させることが必要です。
私は、斜腹筋のとらえ方を間違って伝えていました。
これからは、斜腹筋と間違いなく言います。
腹斜筋と背筋と横隔膜が、具体的にどのように動いて息を吐き、息を吸い、
声を出し、声を支えているのか、これから、試行錯誤です。
今は、どの言葉を使っても私の横隔膜の理解をすることが出来ません。
斜腹筋と背筋とが、どのように関係しあっているかを観察して観察して
観察します。
整体施術後のカラオケでは、それまでより、軽く弱い声が出たような気が
しました。
先生のおっしゃったことを言葉ではなく、感覚で受け止めました。
この感覚が消えないうちに、体に定着させることが大事です。
なかなか、わかったつもりでもするりと逃げられるのです。
意識しすぎてはいけません。作為的になってしまわないように、声を出して
観ました。
「八」と「水」の音程が、たぶん今までよりも響きのあるゆとりのある声で
出たようなきがします。
こんな時、一人カラオケは、寂しい。
2人カラオケでも、もしかしたら、寂しいかもしれないなぁ。
どういう形で、私の成果を知ることが出来るのかな?
あるいは、成果を上げてないことを、知るのかな?