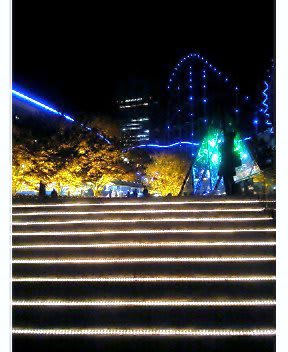ドライブ

なぜかここフジテレビへ

22Fフォーラムへのエレベーターに乗るには、45分待ち。(平日午後3時頃、これ以降には、かくっと行列減少)
「東京めちゃイケランド」体験クルーズに参加するには、2時間待ち。
(当日整理券必要、これは無料だけど、1day passportは必要)
(整理券を入手するのに、2時間待ち。その後、22Fに着いてからも、会場前で列を作って待つもよう)

たどりついたょ、めちゃイケランド。
でも、テレビみたことないけど。
 ←目玉はこちららしい。
←目玉はこちららしい。
 売れたらちょっとおもしろい。
売れたらちょっとおもしろい。
人気だそうです。↓めちゃイケグッズの品々
 美術館?にはつきもの。絵葉書セット。
美術館?にはつきもの。絵葉書セット。
 緑のTシャツ、他2デザインあり。この〈三角すい〉だけS&Lサイズは品切れ中でした。
緑のTシャツ、他2デザインあり。この〈三角すい〉だけS&Lサイズは品切れ中でした。
 食品です。
食品です。
 これはぎょうざ味。他にナポリタン、カツ丼、茶碗蒸し、ポテトチップス味があり。
これはぎょうざ味。他にナポリタン、カツ丼、茶碗蒸し、ポテトチップス味があり。
 くばってました。
くばってました。


なぜかここフジテレビへ

22Fフォーラムへのエレベーターに乗るには、45分待ち。(平日午後3時頃、これ以降には、かくっと行列減少)
「東京めちゃイケランド」体験クルーズに参加するには、2時間待ち。
(当日整理券必要、これは無料だけど、1day passportは必要)
(整理券を入手するのに、2時間待ち。その後、22Fに着いてからも、会場前で列を作って待つもよう)

たどりついたょ、めちゃイケランド。
でも、テレビみたことないけど。
 ←目玉はこちららしい。
←目玉はこちららしい。 売れたらちょっとおもしろい。
売れたらちょっとおもしろい。人気だそうです。↓めちゃイケグッズの品々
 美術館?にはつきもの。絵葉書セット。
美術館?にはつきもの。絵葉書セット。 緑のTシャツ、他2デザインあり。この〈三角すい〉だけS&Lサイズは品切れ中でした。
緑のTシャツ、他2デザインあり。この〈三角すい〉だけS&Lサイズは品切れ中でした。 食品です。
食品です。 これはぎょうざ味。他にナポリタン、カツ丼、茶碗蒸し、ポテトチップス味があり。
これはぎょうざ味。他にナポリタン、カツ丼、茶碗蒸し、ポテトチップス味があり。 くばってました。
くばってました。




















 東京ドーム
東京ドーム