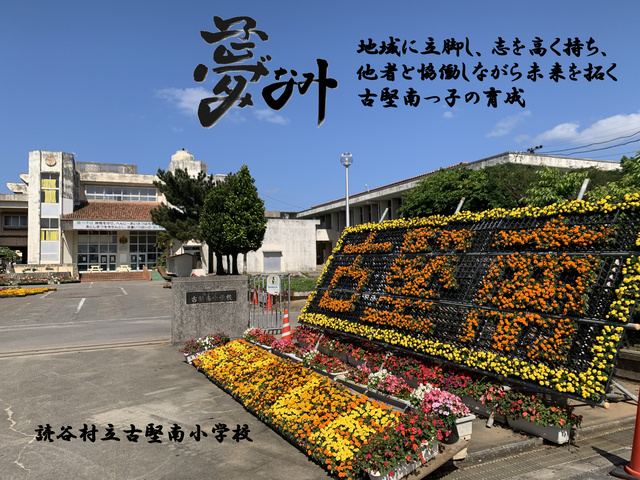牛乳、あわごはん、ソーキ汁、いんげんのおかか和え、納豆
 おかかについて
おかかについて
おかかとはかつおぶしのことです。
かつおぶしは、江戸時代に広く使われるようになりましたが、高価なものだったそうです。
料理やで料理に使う分だけ削る時は、かつおぶしの端を引っかくしたそうです。
そのため「御掻き端」(おかきはし)と呼ぶようになり、それがつまって「おかか」になったそうです
もう一つの説は、昔天皇の住む宮中に仕える女の人(女官)を、女房といいました。この女房たちが、衣服や、食べ物ことを言うときに、自分たちだけにわかる、独特の言葉を使って言い表していました。たとえば、水を「おひや」、髪を「かもじ」などどといったのです。
かつおぶし、または、かつおぶしをけずったものは、「かか」といいました。「かか」に接頭語「お」をつけて「おかか」といったのです。
それが普通の人たちも使うようになったと言われています。
















 」と自分たちが植えた花が生長しているのを喜んでいました
」と自分たちが植えた花が生長しているのを喜んでいました