命題A⇒Bと同値なのは対偶命題¬B⇒¬Aだけだとするのが対偶論理学です。
そこからは¬A条件にとって命題A⇒Bが真なのは対偶命題¬B⇒¬Aが成立するときだけだということを雄弁に論証することが出来ました。Aという条件が封じられたら対偶しか無くなるという仕組みです。その意味において記号論理学の計算は目安に過ぎないとも考えられましょう。記号論理学では(A⇒B)⇔(¬A∨B)なのですが対偶論理学では(A⇒B)⇒(A∧B)∨(¬B∧¬A)なんです。この集合で完全論理学による命題A⇒Bの定義式((A⇒B)⇒B)⇒Aを計算しますと結果はAと出ます。これはこの定義によって自明で真であるのは前提条件であるAだけだということが分かります。
完全論理学では対偶を自明で同値だとは致しません!
さて記号論理学における「否定されなければ真」だとする計算も妥当性を尊重しなければならないとして、問題は「否定されない」という条件が二重否定にあたるのかどうか、という課題です。記号論理は¬A⇒(A⇒B)を恒真として¬A∧(A⇒B)を¬Aと同値とするややこしい学問です。その計算をすると完全論理学の定義式は逆命題と同値と出ます。宜しい・・、逆命題を意味するというのならば(B⇒A)⇒(A⇒B)を計算して進ぜましょう。そうするとA⇒Bと同値だと出ます。
(((A⇒B)⇒B)⇒A)⇒(A⇒B))⇔(A⇒B)なんです!
この文章は「完全論理学の定義に沿ってA⇒Bを導くことはA⇒Bに等しい」ということで完全です。その代わりとして一たん定義してしまったら元に戻すということはしません。こうしたら完全論理学の集合計算では定義式はA⇒(A⇒B)を意味した上でA∧Bになります。ですから対偶と同値だという定理もなくなります。対偶と同値であるためには¬Aと¬Bとが存在しなければなりませんから非存在の可能性が有るならば定義しないのが完全論理学です。対偶論理学の記号計算などをまとめてみましょうか?
【対偶論理学】
(X⇒Y)⇔(¬Y⇒¬X) かつ (X⇒Y)⇒((X∧Y)∨(¬X∧¬Y))
(注)記号計算は同値ではないので集合から論理式に戻すことはデキマセン!
【完全論理学】
((X⇒B)⇒A)⇒(A⇒B)⇔X=(A⇒B)
また、カリー命題はT⇒Aとゴク単純に表現することができました。対偶を取れば¬A⇒Fですから「Aでなければ嘘だ」というような駄々子のような意味だと受け取ればいいでしょう。記号論理学によってカリー命題CについてC⇔(C⇒A)を計算したときに得られるC∧Aという論理式が期せずして完全論理学による結果と一致しているというのも面白い現象ですね?対偶が存在すれば根本的なパラドクス(Aでなければこの命題は間違いだ)に陥るというのも「対偶は自明で真ではない」という完全論理学の公理によって説明されます。嘘つきパラは両面パラドクスでしたがカリー命題は正直パラとも言えるかと存じます。「私は正直です」はもっともらしいのですが「正直でなければ私ではない」は成立しません!“嘘つきでかつ自分ではない”なんていう意味を持った亡霊命題なんです。しかし完全論理学では立派な命題です。
比べると嘘つきパラは「幽霊ですらない」といえるのかもしれないですね?
そこからは¬A条件にとって命題A⇒Bが真なのは対偶命題¬B⇒¬Aが成立するときだけだということを雄弁に論証することが出来ました。Aという条件が封じられたら対偶しか無くなるという仕組みです。その意味において記号論理学の計算は目安に過ぎないとも考えられましょう。記号論理学では(A⇒B)⇔(¬A∨B)なのですが対偶論理学では(A⇒B)⇒(A∧B)∨(¬B∧¬A)なんです。この集合で完全論理学による命題A⇒Bの定義式((A⇒B)⇒B)⇒Aを計算しますと結果はAと出ます。これはこの定義によって自明で真であるのは前提条件であるAだけだということが分かります。
完全論理学では対偶を自明で同値だとは致しません!
さて記号論理学における「否定されなければ真」だとする計算も妥当性を尊重しなければならないとして、問題は「否定されない」という条件が二重否定にあたるのかどうか、という課題です。記号論理は¬A⇒(A⇒B)を恒真として¬A∧(A⇒B)を¬Aと同値とするややこしい学問です。その計算をすると完全論理学の定義式は逆命題と同値と出ます。宜しい・・、逆命題を意味するというのならば(B⇒A)⇒(A⇒B)を計算して進ぜましょう。そうするとA⇒Bと同値だと出ます。
(((A⇒B)⇒B)⇒A)⇒(A⇒B))⇔(A⇒B)なんです!
この文章は「完全論理学の定義に沿ってA⇒Bを導くことはA⇒Bに等しい」ということで完全です。その代わりとして一たん定義してしまったら元に戻すということはしません。こうしたら完全論理学の集合計算では定義式はA⇒(A⇒B)を意味した上でA∧Bになります。ですから対偶と同値だという定理もなくなります。対偶と同値であるためには¬Aと¬Bとが存在しなければなりませんから非存在の可能性が有るならば定義しないのが完全論理学です。対偶論理学の記号計算などをまとめてみましょうか?
【対偶論理学】
(X⇒Y)⇔(¬Y⇒¬X) かつ (X⇒Y)⇒((X∧Y)∨(¬X∧¬Y))
(注)記号計算は同値ではないので集合から論理式に戻すことはデキマセン!
【完全論理学】
((X⇒B)⇒A)⇒(A⇒B)⇔X=(A⇒B)
また、カリー命題はT⇒Aとゴク単純に表現することができました。対偶を取れば¬A⇒Fですから「Aでなければ嘘だ」というような駄々子のような意味だと受け取ればいいでしょう。記号論理学によってカリー命題CについてC⇔(C⇒A)を計算したときに得られるC∧Aという論理式が期せずして完全論理学による結果と一致しているというのも面白い現象ですね?対偶が存在すれば根本的なパラドクス(Aでなければこの命題は間違いだ)に陥るというのも「対偶は自明で真ではない」という完全論理学の公理によって説明されます。嘘つきパラは両面パラドクスでしたがカリー命題は正直パラとも言えるかと存じます。「私は正直です」はもっともらしいのですが「正直でなければ私ではない」は成立しません!“嘘つきでかつ自分ではない”なんていう意味を持った亡霊命題なんです。しかし完全論理学では立派な命題です。
比べると嘘つきパラは「幽霊ですらない」といえるのかもしれないですね?










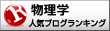







また、((A⇒B)⇒B)=Bであるのに(((A⇒B)⇒B)⇒A)=Aなんですが、これは確かに「導きたいものを導き得ている」証拠だと思っています。
ですから、
((((A⇒B)⇒B)⇒A)⇒(A⇒B))=(A∧B)
だって確かだと予想しています!