
暑い中,林著も第4章「2オーバー1レスポンスの後の展開」Ⅱ「オープナーのリビッド」まで読み進みました.
2/1FGシステムで覚えなければならないのは,
1にFNT,
2にメジャー・レイズ.
3,4が無くて
5に2/1レスポンスの後.
だと思いますが,その見方からすれば,ここまでで林著とハーディの基本的相違は十分明らかにされたと思います.
(一つのビッディング・システムを理解するにはメジャー・[オープン~]レイズのシステムを最初に確認すべきですが,上の順序は覚えるべき内容の分量とその重要度を考慮した上での実感です.)
林著はこの先Ⅲ「ビッドの展開」以降,全て解答・解説付きの練習問題を含め,p85までの実に30ページ以上を,この2/1レスポンスの後に当てて居ます.
これは,この本の見掛けの厚さ(むしろハンディな薄さ)に比べて,非常に貴重な部分の一つだと予想します.おそらく著者御本人の実戦経験と,中上級者を指導・教育された経験の集大成を簡潔に表現して居る.
では本の読み方としてどうすればよいか?1回目としてはここで次章以降,というより,上の順位を考えて,思い切って
第7章「メジャーのレイズの後の展開」
を先に読んだ方が,「システムそのものの理解と比較」の能率は上がるでしょう.(FNTについては競り合いの場合を除いて第3章で完全になっている.) このブログ・シリーズの目的は第1にブリッジ入門者のためなので,ここでハーディと比較しつつⅢを精読するのと,それを後回しにするのと,果たしてどっちが賢明だろうか,考えているところです.
2/1FGシステムで覚えなければならないのは,
1にFNT,
2にメジャー・レイズ.
3,4が無くて
5に2/1レスポンスの後.
だと思いますが,その見方からすれば,ここまでで林著とハーディの基本的相違は十分明らかにされたと思います.
(一つのビッディング・システムを理解するにはメジャー・[オープン~]レイズのシステムを最初に確認すべきですが,上の順序は覚えるべき内容の分量とその重要度を考慮した上での実感です.)
林著はこの先Ⅲ「ビッドの展開」以降,全て解答・解説付きの練習問題を含め,p85までの実に30ページ以上を,この2/1レスポンスの後に当てて居ます.
これは,この本の見掛けの厚さ(むしろハンディな薄さ)に比べて,非常に貴重な部分の一つだと予想します.おそらく著者御本人の実戦経験と,中上級者を指導・教育された経験の集大成を簡潔に表現して居る.
では本の読み方としてどうすればよいか?1回目としてはここで次章以降,というより,上の順位を考えて,思い切って
第7章「メジャーのレイズの後の展開」
を先に読んだ方が,「システムそのものの理解と比較」の能率は上がるでしょう.(FNTについては競り合いの場合を除いて第3章で完全になっている.) このブログ・シリーズの目的は第1にブリッジ入門者のためなので,ここでハーディと比較しつつⅢを精読するのと,それを後回しにするのと,果たしてどっちが賢明だろうか,考えているところです.












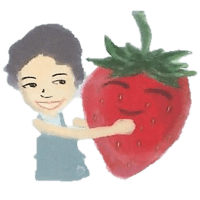

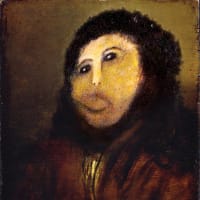

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます