 (3/25〜26未明)
(3/25〜26未明)〝お父さん、オジさん、オバさまのための数学〟
(サービス講義)
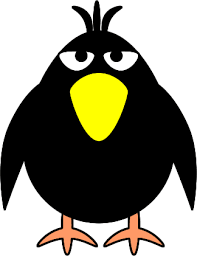 子供の頃に教わって、日頃何気無く使って居る四捨五入ですが、実はブリッジプレイヤーの誰彼さん👨👩同様に⁉️相当な曲者です。
子供の頃に教わって、日頃何気無く使って居る四捨五入ですが、実はブリッジプレイヤーの誰彼さん👨👩同様に⁉️相当な曲者です。
先ず四捨五入の意外な真実を表すお話を。
何処かの楽園では、「VP」が通貨の単位である。1VPは日本の千円に換算される。正式名称は橋牌(「嬌牌」や「狂牌」と揶揄されることも有るようだ。)なのだが、普通は〝無(ブ)理強い〟とか〝無(ブ)理爺〟とかと呼ばれて親しまれている高度に知的な競技のリーグ戦が行われて居り、1試合毎に20 VP、つまり2万円の賞金を得点(IMP)に応じてどう分け合うかを決めて居る。
以下円で語ると、20-0の完勝だと2万円与えられる。アベレージは1万円。全5戦の賞金額は完勝チームだと十万円。アベレージは5万円である。
賞金授与のための精算は日本紙幣の千円札のみで行うのだがが、暇人が多い国だしプライドが高い人種だから、タテマエとして 宗主国から作って貰ったVPの百分の一、日本円で十円玉相当まで細かく刻んだ賞金表が有って、マイナンバーカードのように推奨されて居る。しかしコンピューターが無かった時代からの慣行🗡もあり、煩瑣だし、なまじ小数点が有るだけに数学臭も敬遠され、細か過ぎて、却って実感が湧き難いから、誰も顧みない。
2022-2023年春季、と言ってもこの国の季節は春と夏しか無いのだが、楽園リーグで1位のAチームと2位のBチームの5戦①〜⑤の成績は次の通りだったという。
(Bチーム成績の[ ]は参考値※ 文末見よ)
回次 A チームのIMP差と賞金 B チーム同
- 2 11(千円=VP) -2 9(千円=VP)
- (同上)
- (同上)
- 44 18 34 16
- 11 13 53[43] 18[17]
合計 64(千円=VP) 61[60](千円=VP)
AとBは初戦で当たって居て、上のようにA勝ちだった。Aチームの文句無しの優勝…と皆が受けとった筈だった。
しかし、異議申し立てが

Bチームにはプレイヤーでないキャプテンが居た。そして優勝は正規のルールに従えば、AチームでなくBチームだと指摘したのだ。
彼の主張は次のようなものだった。
⑴ 千円単位の粗い計算でなく、十円単位で賞金を計算すべき。賞金授与のための精算は千円単位でもいいが、少なくともレッドポイント🗡🗡に関わる順位はそれで決めるべきだ。
Aチームのキャプテン、こちらはプレイヤーだった、が嘲けるように言った。3千円(3VP)も差があるのだから、今更順位が変わるわけじゃない。負けたからと言って妙なイチャモンを付けず、潔く結果を受け入れるべきだと。これにはリーグ役員を含め他の皆が同調した。
しかしBチームのキャプテンは、静かに次の計算結果を示した。
⑵ 回次別の両チームの十円単位の賞金額は、
Aチーム Bチーム
- 10,500(円) 9,500(円)
- (同上)
- (同上)
- 17,580 16,380
- 12,540 18,470[17,470]
合計 61,620 63,350[62,350]
順位の逆転は明らかだし、これを VPに戻すと、62対63となり、やはり逆転する‼️
つまり余裕の3VP差で勝って居たはずのチームが、実は1VP負けて居たと言うわけだ。十円単位なら1,730円。差し引き4VP、むしろ5VPにも近い大逆転だ‼️ 1位と2位だけでなく、他でも同点や1〜2 VP差はザラに起こる。全部見直したらどう違って来るか分かったものではない。
彼等が、その後この問題をどう解決したかは伝わって居ない。…が、タテマエの十円単位の賞金計算方式(連続=小数値VP)と、慣行の千円単位方式(離散=整数値VP)とでは、順位決定上は全く別のルールの競技になって居ることは共通理解になったことだろう。
※ [ ]内の値は、Bチームが最終戦で、1 VP少なかった場合には十円単位でもピッタリ千円下がる、それはタテマエ表が偶然この場合だけそうなって居るに過ぎぬのだが、それ故 元々4VP差で負けていた方が VPで同点になる場合で、しかもタテマエ点だと余裕で逆転する一つの面白い現象を示したものだ。
🗡 半世紀あまり「ペア戦」と言えばマッチポイント・ペア戦だけだったのも、コンピューターが一般に使えなかった時代の産物。6テーブルくらいから先のIMP ペア戦などとても出来るものではなかった。
つくばのクラブでも、ウィークリーやCCGの一部をIMP ペア戦にする提案に対して、総会で「聞いた事が無い。」とゲテモノ呼ばわりした反対発言が有って、苦労させられたものだ。(下の国際IMPペア戦から既に15年ほど経っていたにも拘らず。)
因みに筆者が折原博士と組んで優勝した香港(返還直前)での第2回極東ブリッジ・コングレスでは、各国から、70ペア近くが出場して居り、高性能の「ミニコン」(何とも懐かしい名前だ。)が会場に運び込まれて居たものだ。
🗡🗡 RP と書かれる。MP (マスターポイント)・インフレで、技量とMPやそれに基づくライフマスターの称号が釣り合わなくなった対策として導入された。
CCG以上2セッション以上の試合で与えられる上級のMPで、通常の(黒)MP の他に、一定のRPが無いとライフマスターになれないようにした。IMPリーグ戦は、地方クラブではRP獲得に最も向いて居る試合である。
確かアメリカには全く同じ制度は無く、日本独自のものだったと思う。その後似た事情で更にSPも考案された。但しこの場合はMP上位者の高齢化に伴う技量低下にも対応して居る。羽生がソータ君に負けるようなもの。












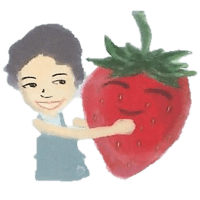

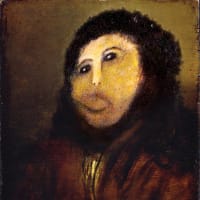

*20.00は同率順位を防げ
PC採用の現在では当然の事。
程度の感覚でとらえていましたが、更に奥の深い問題指摘素晴らしいです。
理想の試合形式と採点方式は???
1.単純ノックアウトは紛れが無いが
対戦組み合わせの決定に不満?
2.ダブルノックアウトなら多少緩和出来るが、日程と満足度に疑問。
3.予選後、ノックアウト、大多数がこの方式だが今度は、ボードのPLAY順序は?
3-1.観客は、OR、CRが
ドイツ番号をPLAYする方が結果の推測が容易で面白い。
3-2.但し選手も当然推測が出来るので終盤のボードが博打的闘い
に成ってしまう。
等と運営も含めたBEST方式は今の採点スケールだけでは無理かも
AIの推奨との一致度のような評価基準が必要に成るのかも、そこはPCの処理能力が上がっているので、見えないカードを覗かずあくまで分布確率での正解を重視するような配慮も可能に成っているように思えます。
ただ、ORとCRの辺りから、意味が分からなくて、これまでコメントが返せずにいました。
ORは光学リーダー、CRはカードリーダーでしょうか? まさか前者はオペレーションズ・リサーチでは無いですね。
もう少し詳しくお話しいただければありがたいのですが。
オープン・ルームだけの場合でも、見物人規定では、興味のあるボードについて行くことは禁止だし、6〜8ボードでは時間的に、見物人の移動は難しい。同一ボード同一順序でプレイしたら、無論どちらか一方しか観られません。
IMPリーグで6ボードずつ交換するときは、付いて行っても許されるかも知れませんが?
なお自分が所属するチームの観戦は、主催者の許可が有れば可と言うルールは、案外知られていない様です。
以上nishida様の論旨とは更に外れたかもしれませんが、再コメントお待ちします。
CRはクローズドルーム
の積もりで書きました。
6~8ボードで行われる試合では見物人は関係有りませんがプレイヤーはボードが終わる毎に、ビッドシステム、オープニングリード、カードの配置、等の全てについて結果を評価して、
運も含めて旨くいった、と思えばその後無理はせず、セーフティプレイ
気味な行動を選び、逆なら敢えてスラムを狙ったり、或いは故意に押さえたり、アンチパーセンテージプレイを選んだり、する亊が考えられその事が折角ボード数を増やして運の要素を減少しようとしている基本方針の妨げに成る、との思いでした。
只、ミスを早い順番のボードでやるか、遅い順番のボードでやるかはいずれにせよ残る運の問題で、仕方無いかもしれません。
背景としては会報投稿で少し触れた
アジア大会ーOPENチーム
準決勝の最終ラウンド16番ボード
を1Hに売り渡すかどうかの判断に通じる問題です。
登った記憶が有りますが、玉稿までとなるとさすがにむずがゆく悶えております。冗談はさておき
2023-3ー4号41ページです。