加藤周一氏が去る5日午後に亡くなられました。享年89歳。
戦後を代表する知識人として、新聞紙上の追悼記事にも「稀有な知性の人」「ぶれぬ視点で自由を貫く」と、すぐれた評論をはじめとするその活動に対して、敬意をこめた愛惜の追悼文が掲載されていました。
朝日新聞に月1回掲載されていた「夕陽妄語」(せきようもうご)は、今度は何が取り上げられるかと、楽しみに待った記事でした。夏以来途絶えていました。
私は40代半ば、「日本文学史序説」で初めてその著述に接しました。ものを見る目に、このような捉え方があるのかと驚き、多くの啓蒙を受けた方です。増鏡をあらためて読み直したのを思い出しています。
医者とし東京大空襲の被災者の救済に当り、敗戦の日を迎えたのが25歳の時。 広島に原爆調査団の一員として入りその惨状を身をもって経験したことが、ご自身も言及されるように、その後のあらゆる著述や社会的活動の原点にあったようです。
幅広い知識は夕陽妄語で余すところなく展開されて、古今、東西にわたり、文学、宗教、政治、とあらゆる分野に広がり、絵画でも、若冲、抱一、蕭白もとりあげられていました。
特にしばしば言及されていた「日本文化の雑種性」と、平和憲法を守ろうと、4年前に大江健三郎氏、小田 実氏らと設立された「九条の会」の呼びかけ人となっておられたのを忘れることはできません。
行動する本物の知識人と私には映っていました。
すぐれた業績を持つ人が、また今年も年の終わりに妄語どころか、多くの提言を残して消えてゆきました。
私の敬愛する方はなぜか12月に旅立ってゆかれるようです。白洲正子さん、石垣りんさんもでした。
折りしも今日は無謀な太平洋戦争へ突入していった開戦の日です。当時の軍国少女だった私達の世代も次第に欠け始めました。 この残日の薄明かりの境涯では、一段と寂しさが冬の木枯らしの中で身にしむことです。

戦後を代表する知識人として、新聞紙上の追悼記事にも「稀有な知性の人」「ぶれぬ視点で自由を貫く」と、すぐれた評論をはじめとするその活動に対して、敬意をこめた愛惜の追悼文が掲載されていました。
朝日新聞に月1回掲載されていた「夕陽妄語」(せきようもうご)は、今度は何が取り上げられるかと、楽しみに待った記事でした。夏以来途絶えていました。
私は40代半ば、「日本文学史序説」で初めてその著述に接しました。ものを見る目に、このような捉え方があるのかと驚き、多くの啓蒙を受けた方です。増鏡をあらためて読み直したのを思い出しています。
医者とし東京大空襲の被災者の救済に当り、敗戦の日を迎えたのが25歳の時。 広島に原爆調査団の一員として入りその惨状を身をもって経験したことが、ご自身も言及されるように、その後のあらゆる著述や社会的活動の原点にあったようです。
幅広い知識は夕陽妄語で余すところなく展開されて、古今、東西にわたり、文学、宗教、政治、とあらゆる分野に広がり、絵画でも、若冲、抱一、蕭白もとりあげられていました。
特にしばしば言及されていた「日本文化の雑種性」と、平和憲法を守ろうと、4年前に大江健三郎氏、小田 実氏らと設立された「九条の会」の呼びかけ人となっておられたのを忘れることはできません。
行動する本物の知識人と私には映っていました。
すぐれた業績を持つ人が、また今年も年の終わりに妄語どころか、多くの提言を残して消えてゆきました。
私の敬愛する方はなぜか12月に旅立ってゆかれるようです。白洲正子さん、石垣りんさんもでした。
折りしも今日は無謀な太平洋戦争へ突入していった開戦の日です。当時の軍国少女だった私達の世代も次第に欠け始めました。 この残日の薄明かりの境涯では、一段と寂しさが冬の木枯らしの中で身にしむことです。











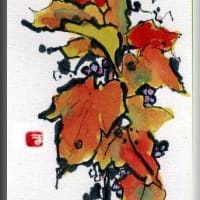





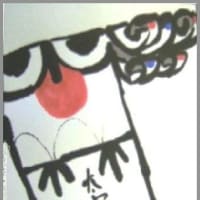

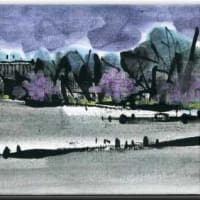
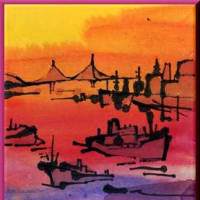
訃報に接し、スクラップにしていた10数枚を読み直す事で哀悼の意を表す代わりとした次第。
夕陽妄語も当初は難解な文章でしたが、ここ数年は頓珍漢読者にも読解できる明快さがあり
楽しみにしておりました。
そう言えば、いろんな企業のトップの謝罪会見でのお詫びの言葉に関して論じておられた記事を思い出しますね。
①このような事が起こらないように努力する。
②このような事を起こさないように・・・・。
主語と目的語+自動詞と他動詞の使い分けは、日本の伝統的文化や無責任社会の背景や
”和”を貴ぶ価値観に関わる云々。
その後もテレビで謝罪会見が繰り返されていますが、画面に現れれば、直ぐにチャンネルを変えてしまうので(そう、アホらしくて)
言葉のチェックをしておりませんが。
ところで、
現在の世界的金融不安問題に関して、専門家でない加藤氏ならどのような切り口で記されるか?
期待しておったのですが、残念ですね。
そうそう、”医者は社会的常識の欠如云々”に
どのような反論を医者の立場で???。
聞きたかったですよね。
朝日新聞が出している「夕陽妄語」ももう8冊目でしょうか。最近のものは持っていません。スクラップの知恵もなくて残念なことでした。
同様に哀悼の思いをこめて私も本棚から取り出して読み返しています。
珠玉の言葉は、切り口の鋭さに反して、時に温もりさえ感じます。同じ後期高齢期を生きる生き方のこのギャップをなんとしましょう。
また、ゆっくり記事にしたいと思っています。
もっともっとお伺いしたい社会の諸相が山積していますね。
明日から庭の手入れに植木屋さんが参りますのを期に師の著「日本の庭」思い出し展開してみたいと思います。
「万葉集」の主な主題の一つは自然である。万葉の詩人は、海を歌い、山を歌い、野と森と季節の移り行きを歌った。シナ文学にない繊細な感受性、インドヨーロッパ文学にない感覚的な鋭さをもって、美しい自然を描いた。その美しさは、自然そのものの中でなく、その自然を美しいものとしてとらえ、表現し、鑑賞するという日本文化そのものの中に理由がある。その美しさは、「枕草子」の感受性の鋭さ、「今昔物語」「徒然草」の観察の細かさ、「新古今集」の美的な自然哲学、能の象徴主義「花」、茶の芸術的生活「さび」に受け継がれたが、伝統として固定化され生命を失う。その後、「奥の細道」「鶉衣」「黄葉夕陽村舎詩」でよみがえりながら次第に衰えて言った。明治になって子規を通じて私小説の世界に流れ込む。しかし、日本文化固有な自然感情や自然の意識が、観察と感受性と表現力において、総合的本質的に現れた「調和」の庭である。
武蔵野の庭に自然がどの程度取り入れる事ができるか俄か芸術家の挑戦して見ようと思います。
その自然観の基盤にあるものが少し覗けた気がします。時折拝見する広がりのある「調和」の、さりげなさの秘密のようなものを感じました。
作庭にはそこに住む人の人生観が要約されると思っています。何よりもの作品でしょう。「武蔵野」のテーマを、紫のひともとに、「みながら」表現なさる楽しみとご苦心の程を遥かに楽しみ偲んでいます。
加藤さんの死去は、常の喪失感より深いものを感じて寂しい思いをしています。