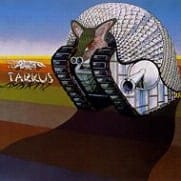~ 名盤になりそこねた一枚 Motion / Lee Konitz
変態ベース
京都の木屋町通りに呼人(よびと)という店があった。雑居ビルの2階にあったその店は、殆んど人目に付かない。昼はジャズ喫茶、夜はスナック。知る人ぞ知るといったお店で、ジャズ通にも殆んど認知されていなかったように思う。私の友人が、昼のジャズタイムにその店でアルバイトをやっていたのだが、たいてい客は入っていなかった。そんな訳でいつも昼間は私達、つまり軽音楽部の連中の貸し切り状態。コーヒーは只、好きなレコードを大きな音で、かけたい放題、聴きたい放題。学生のやることだから、遠慮を知らない節度をわきまえない。思い返せば汗顔ものだが、幸せな時代だった。
そんなある日、リー・コニッツの『Motion』が店でかかったことがあった。それ迄このアルバムについて全く知識がなかった(というよりリー・コニッツその人を、あまり聴いたことがなかったと言うべきか)。その時友人と交わした会話(論争というほどのものではなかったが)は、このアルバムの演奏方法についてだった。アルバムには有名なスタンダードナンバーが何曲か取り上げられている。そのいくつかは、テーマ部分は演奏されない。つまり、いきなりアドリブが始まり、そのまま終わってしまうのだ。
「これでは一体何の曲をやっているのか解からない。」
「いや、ジャズにとってアドリブこそ生命であって、アドリブ・インプロヴィゼーションが充実していれば、テーマはどうだっていいんじゃないか。」
「そもそもジャズにとってテーマって何?」 「テーマは必要なのか?」
そんな結論が見えそうにもないことを、夜を通して語り合ったのである。はたから見ればばかばかしいが、幸せな時代だった。
ヴァーヴのコニッツと言えば、藤田さんご推奨の『Very Cool』(57年5月5日)が真っ先に思い浮かぶ。音のハリやイマジネーションの豊富さ。リー・コニッツというミュージシャンのユニークさが凝縮された素晴らしいアルバムだ。ドン・フェラーラ(tp)、サル・モスカ(p)、ピーター・インド(b)、シャドウ・ウィルソン(ds)。知名度という点でサイドメンは少し地味な感じもするが腕前は確かだ。トリスターノ楽派のつわものが勢ぞろいしたと言っても過言ではない。ウィットに富んだ会話をご堪能頂けることと思う。実にセンシティヴな作品だ。コニッツというミュージシャン(トリスターノ楽派の人はおおむねそうだが)はひねくれているというか、フレーズをリズム通り素直に吹かない。弱起(1拍目から入らない)を多用し、アクセントやビートを裏返したりする曲者だ。『Very Cool』は、そのトリッキーさが嫌味にならず程よく刺激的だ。聴けば聴くほどに、奥深い作品と感嘆させられる。

その次に思い出されるのは、上記の『Motion』(61年8月)だろう。薄暗い背景に、ライトに浮かび上がったコニッツの顔が朱に染まっている。「赤のコニッツ」。私にはそういうイメージがある。編成は、サックスによるワンホーン・トリオ。ロリンズがお得意としていた楽器編成だ。ピアノのような和音楽器が抜けると、演奏に「間」が生じる。漫才で言えば、合いの手、ツッコミがいなくなった状況だろう。俄然ベーシストの役割が重要になってくる。つたないベースランニングではそれこそ「間」が持たない。本作のベーシスト、ソニー・ダラスは堅実なプレイでその大役をこなしている。しかしながら、ピアノを欠くと、演奏が解かりづらくなることも確かだ。前述の通りテーマの提示がないので、漫然と聴いているとどんな曲を演奏しているのか解からなくなる。また集中して聴かないと小節を見失うことになる。素人には勿論のこと、経験のあるリスナーにとっても聴力、スキルが試される踏み絵のようなアルバムなのだ。
『Motion』のセッションは、最初ニック・スタビュラスがドラムスを叩いていた。しかし出来栄えに満足できなかったためか、エルヴィン・ジョーンズに替えて再び収録が行われた。それが最終的にアルバムに収録されるテイクとなったのだ。後に全セッションを網羅した完全盤が発表されたが、それはCDにして3枚にものぼる膨大な量になってしまった。スタビュラスの入ったセッションもそんなに悪いとは思えない。それでも延々とセッションに重ねたのは、コニッツ自身納得行かないところがあったからだ。リスナーにとって些細なことでも、ミュージシャンには譲れないこともあるのだ。
御存じのようにエルヴィン・ジョーンズはロリンズのヴィレッジ・ヴァンガード(サックストリオ)にも参加していた。コニッツがそのジョーンズを指名したのは、やはりあの演奏が意識の片隅にあったからではないだろうか。同世代のロリンズやコルトレーンの活躍は、大いにコニッツを刺激したと思う。この時期を境にして、コニッツの演奏は次第に変容していった。それはライバルに水を開けられまいという焦りや葛藤だったのか。それとも彼の好奇心が次の時代に吸い寄せられていたからだろうか。

ジャズには音遊び的な実験とユーモアの精神が必要だ。リー・コニッツはいつも探究心に溢れ、ジャズの魅力を最大限に体現するミュージシャンだ。テーマをとばしていきなりアドリブに突入するパフォーマンスも、彼一流のユーモアと実験精神の表れなのかもしれない。誤解を恐れずにもの申すならば、ジャズに過大なロマンスや感傷を求めるのはお門違いと言うものだ。私はジャズから受ける感動とは、元来そのようなセンチメンタルなものとは少し中身が異なるように思う。打ち震えるような感動を求めるならば、もっと美しい旋律や叙情性豊かな詞を持つ音楽の方が適している。
それではジャズを聴いても全く感動が得られないかと言えばそんなことはない。ただ感動の種類が違うのだ。ジャズのアドリブなんて、そんなロマンティックな感情のこまやかさを表現するには遠回し過ぎるし歯痒くもある。痛快でもっと人の機知・洒落やユーモアのセンスに根ざした音楽。それがジャズの楽しみなのだ。ジャズは興奮だ。
リー・コニッツの演奏などはまさにその典型。コニッツの演奏は、ジャズと云う掴みどころのない音楽の象徴でもあるのだ。もしこのアルバムにとっつきにくい要素があり、それが本作を名盤の呼名から遠ざけたとしたら少々残念だ。しかしその解かりにくさや取っつきにくさこそが、ジャズ本来の魅力でもあるのだ。若い頃に友人と繰り広げたジャズ談義。いまだにその結論の糸口さえ見えないが、『Motion』を聴くと、あの頃のことがほろ苦く想い出されるのだ。