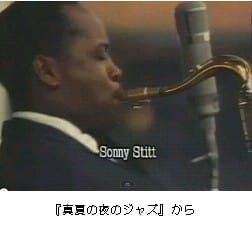アーリー・エバンス その3
The Blueswalk
ビル・エバンスのピークはスコット・ラファロを擁したトリオでの『ポートレート・イン・ジャズ』に始まる一連の1959年以降の作品だと思われるが、その1年前のマイルス・デイビス・グループへの参加によってその萌芽がまさに開花し始めたといっても差し支えない。
よく知られているように、ジョン・コルトレーンやレッド・ガーランドの例を持ち出すまでもなく、マイルス・デイビスは新人を発掘することに掛けてはジャズ界随一の嗅覚とセンスを持っていた。当時、マイルスはプレスティッジからコロンビアへ移籍した直後で、新しいサウンドを求めていた時期に当たる。コルトレーンを外すわけには行かないが、レッド・ガーランドやフィリー・ジョー・ジョーンズのリズム・セクションではとうに先は見えている。そこで、ここに新しいピアノ・サウンド・クリエイター候補としてビル・エバンスに白羽の矢が当てられたわけだ。その結果として、「コード進行(ハーモニー)の束縛から解放した(コード進行に囚われない)自由なアドリブ」奏法として《モード手法》が生まれたのだが、これは瓢箪から駒などといわれるような偶然の結果では決してなく、ビル・エバンスというピアニストでなければなしえなかった産物だろう。マイルス・デイビスの慧眼には恐れ入るべしだ。

ビル・エバンスの参加した最も古いマイルス・デイビスのレコードは1958/5/17録音の『ライヴ・イン・ニューヨーク』のようだが、その10日後のスタジオ録音『1958マイルス』(1958/5/26)が最も重要だ。ジャケット・デザインは池田満寿夫氏による、1979年日本編集のレコードだが、このようなすばらしい演奏がオクラになっていたとは驚きだ。メンバーもこのレコーディング以降は黄金のカインド・オブ・ブルー・セクステット(マイルス・デイビス、ジョン・コルトレーン、キャノンボール・アダレイ、ビル・エバンス、ポール・チェンバース、ジミー・コブ)だ。
特に1曲目の“オン・グリーン・ドルフィン・ストリート”における、ビル・エバンスの耽美的なイントロとそれに続くポール・チェンバースの思索的なベースの妙、その後のマイルス、コルトレーン、キャノンボールの各ソロ、全く非の打ち所のない演奏だ。さらに、“フラン・ダンス“、“ステラ・バイ・スターライト“、“ラヴ・フォー・セール“と続く4曲(1曲“リトル・メロネエ“は別メンバーでの1956年録音)はマイルス・デイビスの数多い演奏中トップ・クラスにあげられる。
すでにこの作品において《モード手法》への方向性がはっきりと意識されていることがわかる。『カインド・オブ・ブルー』が《モード手法》を取り入れた完成形の作品とするなら、この『1958マイルス』はその原型として高く評価すべき作品である。マイルス・デイビスのレコードで僕が最も多くターン・テーブルに載せているレコードだ。

このあと、マイルスのグループではライヴ録音が続くが、まずは『アット・ニューポート1958』が楽しい。ライヴ録音なので、前作のようなビル・エバンスのピアニズムを鑑賞するというわけには行かないが、エバンスも意外と根性があったんだと再認識させてくれる一枚だ。レコードではマイルス・デイビス・グループ(1958/7/3録音)とセロニアス・モンク・グループ(1963/7/4録音)と全く脈絡のない2つのセッションのA、B面カップリングであった(もちろんジャケットも異なる)が、CDではコンプリートとして個々に独立させたバージョンになったので買う立場からは改善されたようだ。演奏は前作と同じメンバーだが、メンバー紹介でのビル・エバンスへの拍手が少ないのが当時を物語っている。マイルスを除いての一番人気はもちろん、キャノンボール・アダレイに決まり。1曲目のチャーリー・パーカーのビバップ曲“アー・リュー・チャ”、マイルスの急速長調のオープン・トランペット、キャノンボールの火を吹くようなアルト・サックス、コルトレーンのシーツ・オブ・サウンドを髣髴とさせるテナー・サックスに対し、ビル・エバンスがどう対峙したか、そう、音なしの構えとはこのこと、こんな奴らに付き合っていられるかとソロなし(取らせてもらえなかった?)だ。他の曲ではきっちりソロしているので、御大マイルスがいようがいまいが自分に合わない曲ではソロしないと自己主張しているようで面白い。

『ジャズ・アット・ザ・プラザ』はプラザ・ホテルでの1958/9/9ライヴ録音。同じライヴ演奏ながら、こちらは屋内ということで落ち着いた演奏であるが、1曲目の“イフ・アイ・ワー・ア・ベル”でマイルスのトランペットがところどころでオフ・マイクになっている部分があるのが惜しい。ビル・エバンスを筆頭に全員快調に演奏しているのでなおのこと録音の不味さが本作を台無しにしている。カインド・オブ・ブルー前の黄金カルテットの記録という意味以上の価値はないので、マニアのみもっていればよいアルバムだろう。1973年発売だから、マイルスが発売を渋った結果に違いない。

この間、ビル・エバンスのリーダー作として、『エヴリバディ・ディグズ』(1958/12/15録音)と『グリーン・ドルフィン・ストリート』(1959/1/19録音)がある。いずれもフィリー・ジョー・ジョーンズがドラムスで参加したピアノ・トリオの演奏だ。ベースは前者がサム・ジョーンズ、後者がポール・チェンバース。マイルス・グループではモードに向かって突っ走っているビル・エバンスだが自己リーダー作ではかなり楽しんでやっているという感じがする2作である。いずれもスタンダード中心で、バラードあり、心地良いスウィングするものありでハツラツとしたビル・エバンスが聴ける。演奏曲がバラエティに富み、飽きが来ない作りをしている。前者では、ピアノ・ソロの“ピース・ピース”、バラードの“テンダリー”が聴き物だろう。後者ではタイトル曲と“あなたと夜と音楽と”で美しさが際立っている。ビル・エバンスとフィリー・ジョーとが合うなんて意外と思われるかもしれないが、案外ビル・エバンスにはハードボイルド的な側面があるのでウマがあったのかもしれない。スコット・ラファロ、ポール・モチアンとのトリオ演奏と較べたら色々批評も出てくるだろうが、これはこれでかなり質の高い(ビル・エバンスに質の低いのはないけれど・・・)演奏記録である。

さて、『カインド・オブ・ブルー』(1959/4/22録音)である。これについては僕にはあまり付け加える言葉もないのだが、やはり世紀の大傑作というしかない。ジャズファンを自称して持っていない、聴いたことがないという方はすぐ買って聴いてください。そして、1曲目の“ソー・ホワット”を聴いてください。イントロのビル・エバンスのピアノとポール・チェンバースのベースのユニゾンを聴いてください。これが、モード・ジャズです。ジャズに美的なものを求めるとするならこのレコードしかない。気を静める、気を落ち着かせる、静かにジャズに浸るといった場合にはこの上ない盤である。だが、ジャズを聴いて楽しむ場合にはたしてこのレコードを一番に推薦できるかというとはなはだ疑問が残る。実際、今回取り上げたビル・エバンス関連のレコードで見ても、僕は『1958マイルス』を一番好んで聴いているのだから。