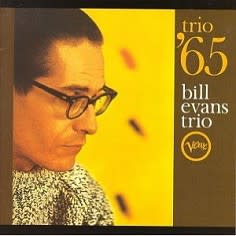ROCKIN' in RHYTHM
By 変態ベース
Fragile ~ Close To The Edge
KJSの会員にはクラシックの隠れファンもいらっしゃるようだが、驚いてはいけない、何を隠そうこの私も少しはクラシックを嗜むのだ。クラシック歴(そんなご大層なものではないが)は、さかのぼることジャズを聴き始めたころと重なるので、キャリアだけはそこそこ長い。但し皆様ご推察の通り、ほんの冷やかし程度のリスナーなので、あの指揮者がどうの、この演奏家がこうのと、いっちょ前の口が叩けるほどは解っていない。
私が最初に好きになったのは、ストラヴィンスキーのバレエ音楽『春の祭典』だ。近代音楽の傑作とされるが、複雑なリズムと不協和音が特徴的だ。どう考えても、初心者が手を出すような代物ではないように思える。しかし好きになってしまえばアバタもエクボ。あのエネルギッシュな響きが、頭からこびりついて離れない。最初に聴いたレコードはバーンスタイン指揮、ニューヨークフィルハーモニーの演奏だった。それ以降もブーレーズ、カラヤン、ショルティ等々を聴き比べたが、それぞれ微妙に楽器の響きやテンポが異なっていて面白い。クラシックの楽しみを垣間見たような気がしたものだ。あのまま順風満帆にクラシックにのめり込んでいれば、私も今頃は一端のクラシックファンとなり、或いはKJSの皆様ともお会いする機会がなかったかもしれない。そんな運命のいたずらを、ため息交じりに残念がる方がいらっしゃらないことを、心から祈るばかりである。
さてストラヴィンスキー以降も、気が向けばちょろちょろレコードを手にしていたわけだが、そもそもクラシック(ついでにジャズも)に興味を持つようになったのは、イエス/Yesというロックグループとの出会いがきっかけだった。イエスは、キング クリムゾンやピンク フロイドと肩を並べる、イギリスの代表的プログレシブ ロックバンドだ。プログレシブ(Progressive)には、先進的、前衛的という意味がある。つまり従来のロックが、ジャズやクラシック等々の影響を受け、どちらかと云えば技巧的で、ポピュラリティーよりアルバムのトーナリティやアーティスティックな面に重きを置く、ちょっと進んだコンセプトを持つグループの総称である。それまではローリング ストーンズ、レッド ツェッペリン等の所謂ハードロック系のバンドにしか関心がなかったけれど、イエスを聴く機会を得て自分のミュージックライフが大きく展開していったのだ。

『Fragile/こわれもの』を聴いたのは、高校生の頃だった。『Fragile』は彼等の4枚目のアルバムで、イエスの名前をロックファンの間に知らしめた重要な作品だ。Roundabout、Heart of Sunriseといった彼等の代表曲に、各メンバーのソロナンバーをちりばめた快作だ。キーボードプレイヤーにリック ウェイクマンが加入し、サウンドも大きく変貌を遂げた。ステージ上でもウェイクマンはひときわ目を引く。グランドピアノ、ハモンドオルガンの上にシンセサイザーやメロトロンを積み上げ、キーボード類に囲まれた風情はさながらワンマンオーケストラのごとく、シンフォニックサウンドの要となっている。因みにメロトロンと云うのは、ストリングスの録音テープが鍵盤を押さえることで再生する仕組みになっている。高価で複雑、運搬調整に手間がかかり、ツアー中にトラブルを起こしたらこんな厄介なものはない。ストリングス以外にもフルート、コーラス(混声)が切り替え選択できる。巨大なテープ再生機であり、果たして楽器と呼べる代物かどうか怪しいものだ。ミュージシャンのユニオンからは仕事を侵害されるとの理由からクレームが付き、訴訟沙汰にまで発展したらしい。
話がそれた。イエスのクラシカルな部分、つまりオーケストラ的な音空間を支配するのがリック ウェイクマンだとしたら、ジャズ的な側面(イエスの音楽はそんなにジャズっぽくないと感じる人もいるようだが)をリードするのが、ドラマーのビル ブラフォードである。ブラフォードは小さい頃からジャズに興味を示していたという。イギリスの音楽業界は、ロックとジャズの境目が曖昧で、相互間の交流も盛んである。つまりロック系ドラマーにもジャズの素養を持った人が少なくないってことだ。ブラフォードもそんな訳で当初はジャズミュージシャンを志していたのだが、募集に応じてアンダーソン等に合流したのだ。その素質はこのアルバムを聴けば解って頂けると思う。特に難曲Heart of Sunriseでは、彼のジャージーなセンスが随所に感じ取れるはずだ。

ブラフォードはロックドラマーとしては独創的である。クリアーなシンバルレガートと変則的なスネア奏法は、ジャズドラミングを研究した成果が窺える。最高傑作の誉れ高い5作目『Close To The Edge/危機』を最後に、彼はキングクリムゾンに引き抜かれてしまった。それは、イエスの音楽に方向性の違いと限界を感じてしまった結果と思う。彼の脱退と共に、イエスの音楽も急速にポテンシャルを失いこわれてしまったのではないだろうか。私は彼の演奏を聴いてジャズに強く惹かれるようになった。ある時期、彼に心酔していたと言っても過言ではない。初来日の時、ドラマーがアラン ホワイトに代わっていたのには、本当に落胆した。ブラフォードの抜けたイエスに対し、私は急速に興味を失ってしまった。しかし彼のドラミングの才能も、イエスと共に開花・熟成したことを忘れてはならない。彼の演奏が最もセンシティヴだったのは、イエスに加わっていた数年だったと私は思っている。特に『Fragile』以降の頭脳的なドラミングは他に比類する人物が浮かばない。そんなブラフォードも六十歳を機に、早々と演奏活動から身を引いてしまった。以前なら、大慌てしたようなニュースだが、平然と受け止めてしまった自分に少し驚いている。
クリス スクワイアはイエス結成以来のメンバーで、分裂解散後もイエスの名義を繋ぎグループを統率している。ベースギターを弾きながら複雑なコーラスも担当する。大変難しいパートをいとも簡単にこなす優秀なプレーヤーだ。リッケンバッカーのベースギターが彼のトレードマークだ。ディストーションの利いたトーンで、まるで2本目のリードギターのように、ステージ狭しと弾きまくる。その一端はソロナンバーFishで窺い知ることが出来る。深海から湧き上がってくるような不思議なサウンドは、すべて彼のベースから生み出されたものだ。因みにフィッシュと云うのは彼のニックネーム。5人の中では最もストレートなハードロッカーぶりを披露する。

ロックギタリストと云う人種は、たいていボディーの平べったいソリッドギターを使うものだ。ギブソンのレスポールやフェンダーのストラトキャスターといった名器がそれだ。スティーヴ ハウは、珍しくフルアコースティックボディのギターを愛用する。彼はジャズからクラシックまで幅広くトレーニングをしてきたが、その影響でギターもフルアコに慣れてしまったのだろう。ハウは3枚目の作品『The Yes Album』から、グループに加入した。彼のバーサタイルなプレイは、間違いなくイエスの重層的な構成に貢献している。ソロナンバーMood For A Dayではフラメンコタッチの演奏を披露する。South Side Of The Skyのオブリガートは、ダイナミックで並のギタリストには真似できない。凄腕のテクニシャンという称賛と、センスが悪い、ヘタクソだという悪口が交錯して、世間の評価はマチマチだ。確かに聴いていてルーツのさかのぼれない、最もロッカーらしくないロックギタリストだ。
フレディー マーキュリーが亡くなった後、ポール ロジャースを入れてクイーンが再結成されたと聞いた時は耳を疑った。そんなクイーンなんてあり得ないだろうというのが感想だったからだ。同様にジョン アンダーソン抜きのイエスもあり得ないだろうと思っていたが、最近のツアーでは彼に代役を立てて回ったというから驚きだ。ハスキーで声に独特の透明感がある。声量はないし、シャウトするタイプではない。少なくともハードロックには向いていないと思う。しかしイエスの成功は彼のユニークさに頼るところが大きいはずだ。思索的で自然愛好志向が強く、シーシェパードのようなテロリストではないが、優しくクジラを殺してはいけないよと説くタイプ。もちろん原発のような自然の摂理に反するものには、基本的にネガティヴな姿勢を貫く、と自由気儘にアンダーソンの人物像を想像してみたが、本当はどんな人なのかよく知らない。哲学的でイエスの精神的支柱となる人物だが、グループの中で一番浮いているようにも思える。でも彼の代わりはどうしても考えられない。アンダーソンが抜けたらイエスではなくなるだろう。
『Close To The Edge』はイエスの最高傑作で、プログレの名作として彼等の名前を決定的なものにした。私もこのアルバムには完全にノックアウトされたひとりなのだ。あまりにも上質で気品があって、ロックビートのイージーリスニングみたいな悪口も囁かれる。クリムゾンファンのイエスに対する上から目線は、おおむねそんな優等生面に対する当てこすりなのだ。しかしイエスファンは、そんなやっかみを取り合わないことにしている。
奇跡のような演奏は、傑出した五人のミュージシャンが結束したからなし得たことだ。A面一曲、B面二曲からなるこのコンセプトアルバムは、歌詞カードの対訳を読んでも哲学的で何を歌っているのか実のところさっぱり解らない。シンフォニックロックの最高峰として完成度が高く、テクニカル面でもメンタル面でも、グループがぎりぎりまで張りつめたピークの状態にあったことは間違いない。それに対し、編曲が複雑かつ精緻で、ロックの演奏としては余りにも制約も多く、技術的には金縛り、がんじがらめの酸欠状態にあったことも確かだ。ブラフォードの脱退も、そんな閉塞的状況を克服できなかったからだ。
『Fragile』と『Close To The Edge』の成功は、皮肉なことにライヴでの彼等をも、身動きできない状態にしていた。それはこれらのアルバムを崇拝するファンが、ステージでもアルバムの音楽がそっくりそのまま再現されることを期待していたからだ。グループの誰もがその無言の圧力をひしひしと混じていたに違いない。しかしこのアルバムの音楽はスタジオでリハーサルとダビングを繰り返し出来上がったものである。いかに五人がテクニシャンで優れたミュージシャンだったとしても所詮は生身の人間、アルバムそのままを再現することは不可能である。(またそのようなこと ――つまりアルバムを完璧に再現することに―― 全精力を注ぎ込むことが音楽本来の目的であるかと云えば、疑問を感じるのだが。)

そんな彼等のステージを捉えたアルバムが、LPにして3枚組の大作『Yessongs』である。イントロ部分、彼等がステージに登場する場面では、会場にストラヴィンスキーの『火の鳥』が流れる。御察しの通り私がストラヴィンスキーに興味を覚えるようになったのは、このレコードを聴いたからである。
アルバムの評判は概ね好評のようだ。野性的でストレートなロックビートを取り戻したと、巷では評価されているようだが、私には粗悪な駄作にしか思えない。確かにドラマーのアラン ホワイトは、短い期間で複雑な曲をよくコピーしているし、リズム感も安定している。しかし、ブラフォードの精密さを期待すると、裏切られた気分になるのはどうしようもない。救いはブラフォードの叩いた演奏が、このアルバムに数曲収録されていることだ。特にPerpetual Changeは録音もクリアーで、ギターソロからドラムソロに至るプレイも溌剌としている。これこそロック本来のパワーと即興性を兼ね備えた名演だと思う。このテイクを聴いてから、他にも彼が入っていた頃のライヴテープが残されているのではと期待しているのだが、今まで発表された記憶がない。

『Tales From Topographic Oceans/ 海洋地形学の物語』は壮大な駄作だ。『Close To The Edge』を聴いた人は、首を長くしてこの作品を待ち望んだものだ。LP二枚組、各面に一曲ずつを配した超大作のふれ込みに、発売前から期待が膨れ上がり話題を呼んだが、これだけものの見事に期待を裏切ってくれたレコードも珍しい。退屈で内容がなく、曲を練った痕跡もなし。レトルトのスープを水で薄めて過ぎ、やけくそで手当たりしだい調味料を放り込んで、訳の分らない味付けになってしまったとでも言うか。前作が超傑作だっただけに、メンバーのプレッシャーも大変だったことは想像がつく。急に売れ出して、ゆっくり音楽を吟味推敲する時間もなっかたのでは。イエスも終わったな。ダメ出しになった記念すべきアルバムだ。
今もイエスはメンバーを補強して演奏活動を行っている。しかし残念なことに過去のヒット曲と栄光にあやかった、メモリアルバンドのようになってしまった。往年のイエスファンとしては何とも歯がゆい話である。