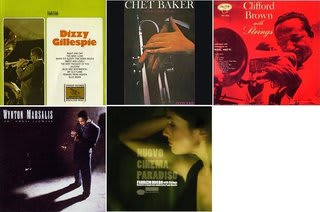ハンク・ジョーンズを偲んで
By The Blueswalk
ハンク・ジョーンズさんが2010年5月16日、91歳で亡くなられた。最晩年まで精力的に活動され、天寿を全うされたといってもいいだろう。最も日本を愛し、日本人に愛され親しまれたジャズ・マンの一人ではなかったのではないだろうか。それは、特に晩年は日本を何回も訪れたことでも判るし、とくに関西・神戸を愛していたようである。温厚で、品が良いジェントルマンであった。また、明快でかつ歯に衣を着せない語り口には僕たちジャズ・ファンも溜飲を下げたことも多かった。
ご存知の通り、ジョーンズ3兄弟の長兄として、早くからジャズ界で活動されたのだが、次兄のサド・ジョーンズはトランペッター、サド・メル・オーケストラのリーダーとして、末弟のエルヴィン・ジョーンズはジョン・コルトレーン・グループのドラマーとして脚光を浴びてきたのに対し、長兄のハンク・ジョーンズはなかなかジャズの第一戦での活躍が目立つ存在ではなかった。どちらかというと、バイ・プレイヤー、歌伴ピアニストのイメージが強い。トミー・フラナガンを名盤請負人バイ・プレイヤーとして最大評価している向きがあるが、ハンク・ジョーンズも負けてはいない。1946年には、スタン・ゲッツの『オパス・デ・バップ』に参加して以降、数多くの名盤に参加するとともに、エラ・フィッツジェラルドの歌伴奏者として、コンスタントにレコーディングを続けている。ただ、不幸にも穏やかな性格が災いしてか、なかなか自己名義のレコードでインパクトのある作品が作れていないのは事実であった。
僕らが知っている初期の代表作は1955年録音の『カルテット&クインテット』となろう。非常に趣味のいいピアノを聴かせており、なかなかの秀作である。聴けば聴くほど味の出る作品とはこういうレコードを指すのだろう。しかし、これとてもトランペットのドナルド・バードが目立っており、どうしても主役としては影が薄いのは否めない。
ハンク・ジョーンズが脚光を浴びたのは、すでに還暦に差し掛からんとする1977年のグレート・ジャズ・トリオによる『アット・ザ・ヴィレッジ・ヴァンガード』である。何と遅咲きであることか。ロン・カーターのベースにトニー・ウイリアムスのドラムスという、当時の最強のリズム陣を得て、二人に負けないくらいの圧倒的な迫力でもって聴衆を凌駕している。その、前年には同じ布陣で渡辺貞夫の『アイム・オールド・ファッションド』を録音しており、このセッションがハンク・ジョーンズのバップ魂に火を注いだのではないかと推測するのである。そして、これを機に怒涛の快進撃をはじめるのだから、人間いつどう変わるか判らないものである。大器晩成とは云えないが、それまでの不遇を補ってお釣りが来るほどの活躍なのだ。
ハンク・ジョーンズの趣味の良さが味わえる小品が1994年にチャーリー・ヘイデン(b)と録音した『スティール・アウェイ』だ。邦題は“スピリチュアル”となっており、黒人霊歌、賛美歌などを演奏しており、静謐なピアノとベースの音が心に響いてくる。僕はキリスト教ではないので、クリスマスで何かするということはないのだが、毎年このCDの最後の賛美歌メドレーを聴いて過ごすことにしている。これは、これからもずっと続くことになるだろう。ハンク・ジョーンズさん、安らかに眠ってください。