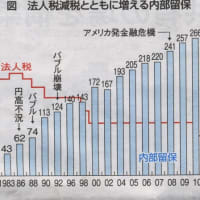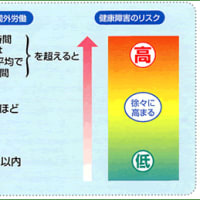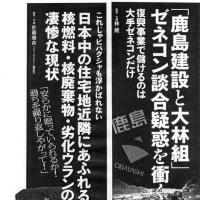●[註6]は、同法第63条によると、裁判員は刑の言渡しの公判日には出頭しなければならないとなっているが、但し書きで「裁判員が出頭しないことが、当該判決又は決定の宣告を妨げるものではない」という。
要するに裁判員が出頭しなくても判決は宣告され裁判員の任務は終わる。
この事は、判決書に裁判員が署名捺印しないことを意味する。
この点については、最高裁判所のHP「裁判員制度Q&A」において、明確に回答されています。
Q:判決に裁判員の名前は載るのですか。
A:判決書末尾には裁判官が署名・押印しますが、これに加えて裁判員が判決書に署名・押印することはありません。
この様にみてくると、裁判員の立場からすると裁判員は軽くみられていると思われるし、被告人の立場からすると、この様な裁判員制度に命を委ねるわけには行かないでしょう。
少なくとも、取調べの可視化や調書裁判・人質司法の弊害を改善される事がこの制度の実施に当っての前提条件でなければならないと思います。
本来の刑事裁判は、「疑わしくは被告人の利益に」という大原則が貫かれなければならず、その精神は、人権の尊重と冤罪の防止にあります。
光市(母子殺害)事件において、本村洋さんの手記(Will-2008年6月号)によるとその当時、取調べに当っていた警察官が一冊の本(※A)を本村さんに渡し、“「一冊は君、一冊は僕の分だ。この本を読んで、一緒に少年事件や少年法のことを勉強しよう」と、言ってくれた。”と告白しています。正しく警察は被害者の仇討ち役を演じようとしているのであり、この傾向は検察官にも見られると云われています。(※B)
この事件以降、マスメディアも含め加害者より被害者の人権が声高に叫ばれ、振り子が極端に180度振れた現状においては、裁判員の量刑判断が重い方へ傾くのではないかと危惧されます。
※A:警察官が手渡した一冊の本とは、神戸の通称酒鬼薔薇事件での被害者 土師淳君の父親が書いた『淳』(新潮社刊)とのことです。
※B:土居 公献氏(元日本弁護士連合会会長)によると、
→被害者から見れば犯人(とされた被告人)は憎いので報復感情が先に立つ。それを代弁するのが検察官だとすれば、公益の代表者とされる検察官の本来の使命が失われてしまう。
被害者側の仇討ちを禁ずる代りに国がこれを代行するという粗末な考え方が罷り通る現状は歎かわしい。被害者(遺族)の悲しみと怒りは、国による物心両面にわたる手厚いケアによってこそ癒されるのである。
裁判官と裁判員に有罪の確信を抱かせるための立証の責任を負うのは訴追側の検察官なのであるから、裁く側から見れば検察官の立証に少しでも怪しさや穴が無いかを鵜の目、鷹の目で調べなければならないのであり、裁かれる相手は被告人ではなく検察官なのである。
裁判官不在の席での陪審員の全員一致評決と異なり、裁判官を交えた多数決では、とかく有罪認定に傾き易くなるのも予想できる。
官僚裁判の弊を避けるどころか、裁判員が却って官僚裁判をたすける「隠れ蓑」になる危険を免れないのである。
-えん罪を生む裁判員制度(現代人文社刊)- より(一部分抜粋)
要するに裁判員が出頭しなくても判決は宣告され裁判員の任務は終わる。
この事は、判決書に裁判員が署名捺印しないことを意味する。
この点については、最高裁判所のHP「裁判員制度Q&A」において、明確に回答されています。
Q:判決に裁判員の名前は載るのですか。
A:判決書末尾には裁判官が署名・押印しますが、これに加えて裁判員が判決書に署名・押印することはありません。
この様にみてくると、裁判員の立場からすると裁判員は軽くみられていると思われるし、被告人の立場からすると、この様な裁判員制度に命を委ねるわけには行かないでしょう。
少なくとも、取調べの可視化や調書裁判・人質司法の弊害を改善される事がこの制度の実施に当っての前提条件でなければならないと思います。
本来の刑事裁判は、「疑わしくは被告人の利益に」という大原則が貫かれなければならず、その精神は、人権の尊重と冤罪の防止にあります。
光市(母子殺害)事件において、本村洋さんの手記(Will-2008年6月号)によるとその当時、取調べに当っていた警察官が一冊の本(※A)を本村さんに渡し、“「一冊は君、一冊は僕の分だ。この本を読んで、一緒に少年事件や少年法のことを勉強しよう」と、言ってくれた。”と告白しています。正しく警察は被害者の仇討ち役を演じようとしているのであり、この傾向は検察官にも見られると云われています。(※B)
この事件以降、マスメディアも含め加害者より被害者の人権が声高に叫ばれ、振り子が極端に180度振れた現状においては、裁判員の量刑判断が重い方へ傾くのではないかと危惧されます。
※A:警察官が手渡した一冊の本とは、神戸の通称酒鬼薔薇事件での被害者 土師淳君の父親が書いた『淳』(新潮社刊)とのことです。
※B:土居 公献氏(元日本弁護士連合会会長)によると、
→被害者から見れば犯人(とされた被告人)は憎いので報復感情が先に立つ。それを代弁するのが検察官だとすれば、公益の代表者とされる検察官の本来の使命が失われてしまう。
被害者側の仇討ちを禁ずる代りに国がこれを代行するという粗末な考え方が罷り通る現状は歎かわしい。被害者(遺族)の悲しみと怒りは、国による物心両面にわたる手厚いケアによってこそ癒されるのである。
裁判官と裁判員に有罪の確信を抱かせるための立証の責任を負うのは訴追側の検察官なのであるから、裁く側から見れば検察官の立証に少しでも怪しさや穴が無いかを鵜の目、鷹の目で調べなければならないのであり、裁かれる相手は被告人ではなく検察官なのである。
裁判官不在の席での陪審員の全員一致評決と異なり、裁判官を交えた多数決では、とかく有罪認定に傾き易くなるのも予想できる。
官僚裁判の弊を避けるどころか、裁判員が却って官僚裁判をたすける「隠れ蓑」になる危険を免れないのである。
-えん罪を生む裁判員制度(現代人文社刊)- より(一部分抜粋)