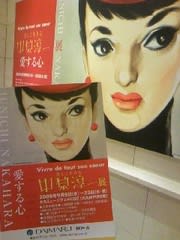「卒業式の袴」再考
2010年1月7日の朝日新聞に「高額の袴レンタルに違和感」と題された投書が掲載されました。投稿者は22歳の女性。彼女はこの3月に卒業予定。彼女の大学では、女子学生は袴を着用するのが多数だそう。彼女も袴のレンタル店に下見に行ったものの、高額だったために着ようという気持ちにならなくなってしまったとのこと。そのように考える友人が彼女の周囲にいなかったけれども、同じように高額な袴(や成人式の着物)のレンタルに違和感を抱く同世代がいるだろうと、「一人じゃないし、間違ってないよ」と呼びかけました。
その投書を受けて、1月12日には「晴れ着レンタル」と小見出しがついた投書二つが彼女への返答として掲載されました。ひとつは「なぜ着るか 考える姿勢大切」という46歳女性の投書、もうひとつは「思い出残ればどんな服でも」28歳の女性の投書でした。前者は「お金の価値や自分の価値観をどう子どもに伝え、育てていくか自問自答している親の一人」で、「なぜ着るのか」を考えることはとても大切、と応援しています。後者は、「投稿者とおなじ思いを学生時代に持ち、袴を着なかった一人」で、卒業式はスーツで出席したそう。そして「どんな服装でも」「自分自身が満足のできる形の出席であれば、思い出に残る卒業式になると思」う、と女子学生を応援しています。
この三つの投書を読み、わたしも全体的には賛成したいと思います。
ただ、女子学生の最初の投稿のなかには「2年前の成人式は行かなかった」とあって、その理由に、「振り袖を着たら」と言ってくれる両親に負担をさせたくなかった」からだと書かれていたことは気になります。振り袖を着ないと式に出席できないわけではないので、式に行かなかった理由を振り袖のためにするのはどうでしょうか(この部分は朝日新聞の担当者さんの文章短縮がこうさせたのだと思いたいところです)。大学の卒業式も同じように、袴姿でしか出席できないものではありません。自分が式にふさわしい服装だと思うもので出席するのが一番納得できるでしょう。もしくは、あえて政治的にふさわしくない服装で出席する、ということもひとつのアピールになるかもしれません。ただ、それを他の人が見てどう思うか、ということも考えるべきでしょう。ジャンパーで出席できないところには行かない、という姿勢を貫いた今和次郎先生ではないですが、自分の信念(や価値観)と他人のそれとは違う、と認識し、自分の行動に責任を持つこともまた大切だとわたしは考えています。
けれども、わたしが考えているのはここだけではないのです。「なぜ袴を着るのか」、という部分。現在では、卒業式の袴というものは、形骸化されて単なるひとつのコスプレでしかないかもしれません。明治・大正時代の、懐かしの「女学生」スタイルとして。「はいからさん」っぽいスタイルとして。しかし、「なぜ着るのか」をもう少し深く考えてみると、この「女学生」スタイルも、その成立過程には今の袴の議論よりももっと熱い議論がたくさんありました。近代的な教育を受ける女学生にどのような服装をさせるのかという問いは、そのころの婦人雑誌でもさまざまな意見が交わされています。着物を改良して動きやすい服装にしたらどうかという改良服の提案がなされたり、実際に制服を作った学校の校長先生からは、その制服の意義がわざわざ説かれたりしました。
一方でそうした新しい試みには、どちらかというと美感という、感情に訴える批判が多くなされました。曰く、妙齢の女子に袴を着せるなんて、何を考えているんだ!女性の着物は、肩から帯にかけてが一番美しいのに!(袴をつけたら帯は締めないので残念) 後ろ姿の柔らかなラインこそ美しいのに!(袴をつけたら隠れてしまうところなので、こちらも魅力半減) などなど。そうした批判をした人にとっては、今まで見慣れていた女性の美しさを奪われた気分になったのでしょう。その気持ちはわからないではありません。ただし、その批判の真意には、服装が変わることによって女性の行動にも変化が生じる可能性を意識的に(あるいは無意識的のうちに)見ていて、むしろそちらに警戒していたことも多いことを付け加えておきます(これについては、小山有子「和服改良論と「女性美」――明治後期の女性の服装とその規範性をめぐって」荻野美穂編著『〈性〉の分割線』青弓社 2009年を参照。ウフフ、宣伝☆)。
こういうことは、形骸化した袴姿としか認識されない現在では、知ったところでどうなるわけでもありません。でも、「なぜ着るのか」という問いに答えるものでもありたいと思います。たとえ形ばかりの袴であっても、現在に伝えられることはもっとあるのではないかしら。わたしたちの周囲には、今もなお「なぜ着るのか」考える問題にあふれているのになぁ、と、今回の投書は考えさせてくれました。
* * * * *
ちなみにわたしが卒業した当時の日本女子大学では、卒業式の案内に「華美な服装は慎むこと」という注意書きがあって、式には振り袖での出席は不可でした(謝恩会には振り袖でもOK)。
その頃はまだ、明治期の雑誌が目白にあるなんて知りもしない頃でしたが、増渕宗一先生の授業などで聞いていたかつての女子大の校風を思い描いて、「こんな注意書きがあるなんて、さすがだなぁ~☆」と感じたことでした。
今でもそうなのかしら。
なんとなくそうであってほしいけれど。
(今度文化学科の淵江先生に聞いてみよう)
2010年1月7日の朝日新聞に「高額の袴レンタルに違和感」と題された投書が掲載されました。投稿者は22歳の女性。彼女はこの3月に卒業予定。彼女の大学では、女子学生は袴を着用するのが多数だそう。彼女も袴のレンタル店に下見に行ったものの、高額だったために着ようという気持ちにならなくなってしまったとのこと。そのように考える友人が彼女の周囲にいなかったけれども、同じように高額な袴(や成人式の着物)のレンタルに違和感を抱く同世代がいるだろうと、「一人じゃないし、間違ってないよ」と呼びかけました。
その投書を受けて、1月12日には「晴れ着レンタル」と小見出しがついた投書二つが彼女への返答として掲載されました。ひとつは「なぜ着るか 考える姿勢大切」という46歳女性の投書、もうひとつは「思い出残ればどんな服でも」28歳の女性の投書でした。前者は「お金の価値や自分の価値観をどう子どもに伝え、育てていくか自問自答している親の一人」で、「なぜ着るのか」を考えることはとても大切、と応援しています。後者は、「投稿者とおなじ思いを学生時代に持ち、袴を着なかった一人」で、卒業式はスーツで出席したそう。そして「どんな服装でも」「自分自身が満足のできる形の出席であれば、思い出に残る卒業式になると思」う、と女子学生を応援しています。
この三つの投書を読み、わたしも全体的には賛成したいと思います。
ただ、女子学生の最初の投稿のなかには「2年前の成人式は行かなかった」とあって、その理由に、「振り袖を着たら」と言ってくれる両親に負担をさせたくなかった」からだと書かれていたことは気になります。振り袖を着ないと式に出席できないわけではないので、式に行かなかった理由を振り袖のためにするのはどうでしょうか(この部分は朝日新聞の担当者さんの文章短縮がこうさせたのだと思いたいところです)。大学の卒業式も同じように、袴姿でしか出席できないものではありません。自分が式にふさわしい服装だと思うもので出席するのが一番納得できるでしょう。もしくは、あえて政治的にふさわしくない服装で出席する、ということもひとつのアピールになるかもしれません。ただ、それを他の人が見てどう思うか、ということも考えるべきでしょう。ジャンパーで出席できないところには行かない、という姿勢を貫いた今和次郎先生ではないですが、自分の信念(や価値観)と他人のそれとは違う、と認識し、自分の行動に責任を持つこともまた大切だとわたしは考えています。
けれども、わたしが考えているのはここだけではないのです。「なぜ袴を着るのか」、という部分。現在では、卒業式の袴というものは、形骸化されて単なるひとつのコスプレでしかないかもしれません。明治・大正時代の、懐かしの「女学生」スタイルとして。「はいからさん」っぽいスタイルとして。しかし、「なぜ着るのか」をもう少し深く考えてみると、この「女学生」スタイルも、その成立過程には今の袴の議論よりももっと熱い議論がたくさんありました。近代的な教育を受ける女学生にどのような服装をさせるのかという問いは、そのころの婦人雑誌でもさまざまな意見が交わされています。着物を改良して動きやすい服装にしたらどうかという改良服の提案がなされたり、実際に制服を作った学校の校長先生からは、その制服の意義がわざわざ説かれたりしました。
一方でそうした新しい試みには、どちらかというと美感という、感情に訴える批判が多くなされました。曰く、妙齢の女子に袴を着せるなんて、何を考えているんだ!女性の着物は、肩から帯にかけてが一番美しいのに!(袴をつけたら帯は締めないので残念) 後ろ姿の柔らかなラインこそ美しいのに!(袴をつけたら隠れてしまうところなので、こちらも魅力半減) などなど。そうした批判をした人にとっては、今まで見慣れていた女性の美しさを奪われた気分になったのでしょう。その気持ちはわからないではありません。ただし、その批判の真意には、服装が変わることによって女性の行動にも変化が生じる可能性を意識的に(あるいは無意識的のうちに)見ていて、むしろそちらに警戒していたことも多いことを付け加えておきます(これについては、小山有子「和服改良論と「女性美」――明治後期の女性の服装とその規範性をめぐって」荻野美穂編著『〈性〉の分割線』青弓社 2009年を参照。ウフフ、宣伝☆)。
こういうことは、形骸化した袴姿としか認識されない現在では、知ったところでどうなるわけでもありません。でも、「なぜ着るのか」という問いに答えるものでもありたいと思います。たとえ形ばかりの袴であっても、現在に伝えられることはもっとあるのではないかしら。わたしたちの周囲には、今もなお「なぜ着るのか」考える問題にあふれているのになぁ、と、今回の投書は考えさせてくれました。
* * * * *
ちなみにわたしが卒業した当時の日本女子大学では、卒業式の案内に「華美な服装は慎むこと」という注意書きがあって、式には振り袖での出席は不可でした(謝恩会には振り袖でもOK)。
その頃はまだ、明治期の雑誌が目白にあるなんて知りもしない頃でしたが、増渕宗一先生の授業などで聞いていたかつての女子大の校風を思い描いて、「こんな注意書きがあるなんて、さすがだなぁ~☆」と感じたことでした。
今でもそうなのかしら。
なんとなくそうであってほしいけれど。
(今度文化学科の淵江先生に聞いてみよう)