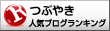土曜日の利用者は、いつもより少なく感じました。
今日の演奏曲は「故郷の空・もみじ・昭和枯れすすき・りんご村から・
別れの一本杉・船頭小唄・休憩(お話)・村祭り・柿の木坂の家・山の吊橋・
星のフラメンコ・骨まで愛して・荒城の月・別れ船・アンコールは赤とんぼ」以上でした。
はじめの挨拶で・・・
「皆さん・・今日もご存じの歌がありましたら歌って下さいね!」と申しますと・・
いつもの問題児?のオバァさんが・・
「そんなモン・・歌いたぁないわぁぁ~あ!」と絶叫!!!
職員さんが慌てて口をふさぐ様子が可笑しくて思わず笑ってしまいましたが、
演奏が進行するにつれておとなしくなり最後には笑顔で帰って行きました。
ご本人にとって”楽しかったのか・・悪かったのか・・」・・・・
認知症のアタマの中は誰にもわかりません(ー_ー)!!
しかし、何時もの通り無事に演奏が終了出来て良かったです。
今月は小休止のところでお祭りについてのお話をしていますが
信州飯田の「七九里神社裸まつり」について
写真をお見せしながら説明しました。

裸祭りの由来・・・・
氏子の七つ平より一人づつ力自慢の若者が選ばれ、
前日より身を清め、裸身となって腰に太注連縄を締めお神酒樽に注連縄をめぐらして、
これを頭上高く掲げて掛け声勇ましく振りきおひます。
宵祭りの花形となったこの若者は、奉納煙火の天下一切の責任者となります

三国花火に点火・・降りしきる火の粉を浴びて樽を振る姿は、
男の中の男として憧れの的になります
太注連縄に火がついて燃え上がることもあり、
傍にいる氏子が水をかけて消します
三国とは・・甲州・信州・駿州を意味し・・
花火とは書かず”煙火”と書いて"はなび"と読みます。
これは戦国時代、武田信玄が筒煙火を神前に奉納し、必勝祈願をしたためで
のろしとして使われていたので「三国煙火」となったそうです。
例祭には必ずこの「三国煙火」を奉納しなければならない習わしとなりました。
最後は七人が揃って火の中で桶を振ります
こんなお話をさせて頂きましたが
演奏を飽きさせないためにはこんな工夫も必要かな・・と思います。
今日の演奏曲は「故郷の空・もみじ・昭和枯れすすき・りんご村から・
別れの一本杉・船頭小唄・休憩(お話)・村祭り・柿の木坂の家・山の吊橋・
星のフラメンコ・骨まで愛して・荒城の月・別れ船・アンコールは赤とんぼ」以上でした。
はじめの挨拶で・・・
「皆さん・・今日もご存じの歌がありましたら歌って下さいね!」と申しますと・・
いつもの問題児?のオバァさんが・・
「そんなモン・・歌いたぁないわぁぁ~あ!」と絶叫!!!
職員さんが慌てて口をふさぐ様子が可笑しくて思わず笑ってしまいましたが、
演奏が進行するにつれておとなしくなり最後には笑顔で帰って行きました。
ご本人にとって”楽しかったのか・・悪かったのか・・」・・・・
認知症のアタマの中は誰にもわかりません(ー_ー)!!
しかし、何時もの通り無事に演奏が終了出来て良かったです。
今月は小休止のところでお祭りについてのお話をしていますが
信州飯田の「七九里神社裸まつり」について
写真をお見せしながら説明しました。

裸祭りの由来・・・・
氏子の七つ平より一人づつ力自慢の若者が選ばれ、
前日より身を清め、裸身となって腰に太注連縄を締めお神酒樽に注連縄をめぐらして、
これを頭上高く掲げて掛け声勇ましく振りきおひます。
宵祭りの花形となったこの若者は、奉納煙火の天下一切の責任者となります

三国花火に点火・・降りしきる火の粉を浴びて樽を振る姿は、
男の中の男として憧れの的になります
太注連縄に火がついて燃え上がることもあり、
傍にいる氏子が水をかけて消します
三国とは・・甲州・信州・駿州を意味し・・
花火とは書かず”煙火”と書いて"はなび"と読みます。
これは戦国時代、武田信玄が筒煙火を神前に奉納し、必勝祈願をしたためで
のろしとして使われていたので「三国煙火」となったそうです。
例祭には必ずこの「三国煙火」を奉納しなければならない習わしとなりました。
最後は七人が揃って火の中で桶を振ります
こんなお話をさせて頂きましたが
演奏を飽きさせないためにはこんな工夫も必要かな・・と思います。