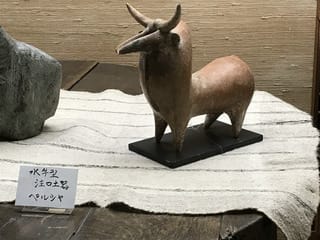軽井沢でゴルフをしてから軽井沢駅近くの大賀ホールの前に最近できた「軽井沢安東美術館」に行ってみた。この美術館は投資ファンド会社の経営者安東泰志氏とご夫人が創設した日本のみならず世界でも初めての藤田嗣治の作品だけを展示する個人美術館である。入場料は一人2,300円。

安東泰志氏は長年にわたって藤田の作品を蒐集し、自宅の壁にかけて慈しんできたコレクターである。夫妻が個人的に蒐集した藤田作品が多くなり、将来夫妻が亡くたった場合にその作品の散逸を防ぐために、その作品を展示する美術館を創設したとある。もともと夫妻の自宅に飾ってあったコレクションをもとにした美術館なので、美術館のコンセプトは来場者に安東夫妻の自宅に招かれたような気持になる場所にするという考えで作られている。


展示室に入っていくと直ぐに右側にサロン・ル・ダミエがある。この部屋では藤田の来歴や展示作品の説明のビデオ10分が流れており、鑑賞を前に事前勉強が可能となっている。椅子とテーブルがあり、コーヒーの無料サービスもあるのでコーヒーを飲みながらビデオを見て予習ができるのは素晴らしい。また、室内のインテリアもフェルメールの絵を思い起こさせるような床のデザインなど大変おしゃれな感じとなっている。


その後、順路に従って展示室を見ていくと、展示室は全部で4つに分かれており、藤田の来歴に従って作品が展示されている。最初は一般的な風景画などもあるが、その後、乳白色の裸婦像、聖母子像、子供の肖像画、猫の絵などが多く展示されている。部屋ごとに壁紙の色が異なっており、まるでイギリスのナショナル・ギャラリーに来ているような錯覚に陥る。


順路の中には当館の建設の全工程を記録した映像が見れる場所があり、また、安東夫妻のご自宅に絵があった当時の様子を記録したビデオと写真の展示もあったりして参考になる。全体的にインテリアはおしゃれでセンスが良く、ご夫妻の趣味の良さがにじみ出ている。


特記すべき点としては写真撮影のことだ、説明によれば写真撮影はOKだが、一つの写真には3つ以上の展示作品が写るようにするのが条件となっていることだ。例えば、1枚の絵だけを被写体として取る写真は許可されない、ということだ。これは著作権の関係があるためだと思われるが、ありがたい対応である。思わず写真に収めたくなる素晴らしさがある美術館だからだ。


さて、藤田嗣治であるが、彼は世界で有名になった後、日本で活動したいと思って日本に一時期滞在していたが、戦時中に戦争画を書いたことについて周囲の無理解により不愉快な思いをし、フランスで生きていくことにした、そしてフランス国籍も取得して、最後は夫人と一緒にフランスの地に眠ることになる。藤田は「自分が日本を捨てたのではなく、日本が自分を捨てたのだ」と終生語っていたそうだ。近藤史人著「藤田嗣治、異邦人の生涯」を読むとその間の経緯が詳しく書かれており、藤田の思いがよくわかる。戦前、戦中には保守的なことを言っていた学者が戦後節操もなく進歩的な学者に転向したことを書いた松本清張の小説を以前紹介したが(カルネアデスの舟板)、似たような例はいたるところにあったのだろう。

鑑賞を終わって、仕事に成功して金持ちになった人の金の使い方としては有意義なものだと感じた。若くして株式上場などで巨額の金を手にした実業家がグルメやヨットなどに成金趣味のように金を使っているのに比べれば、安東氏の金の使い方は立派なものだ。もちろん、税金対策とか実利的な面もあるだろうが、芸術や伝統芸能というものは税金ではなく金持ちの支援などでやっていくべきものだと思う。身銭を切って作品を蒐集する人には審美眼が備わっていくものだ。その意味でもこの美術館創設は有意義だと思う。
ゆっくり1時間ちょっと鑑賞して美術館を後にした。観覧料は若干高いが観に行く価値は十分あると思った。