将来、何になりたいか。私がこれを思い描いたのは小学校中学年ころ。呆れるくらい多様にありました。では中学校を卒業したらどうするかを具体的に考えたのは、やはり小学校高学年。十二歳の卒業間近な時期。中学校での過ごし方がその先の進路を左右するという雰囲気があったからだと思います。昭和四〇(一九六五)年の三月頃です。
それから二十年さかのぼる昭和二〇年五月十五日に、佐藤忠男さんが十五歳になる年です。高野山海軍航空隊に入隊します。高等小学校を卒業して二か月ほどたってからのことでした。なぜ予科練を志願したのか、その個人的な動機については先に述べました(映画評論家・佐藤忠男の予科練体験)。もう少し広く「進路として予科練」を考えてみると、当時の少年たちは進路をどのように考えていたのか。佐藤さんの記述を紹介します。
・・・戦争のない時代には、軍隊に志願しても戦死の危険という実感はないから、普通の進学や就職とあまり違いはないし、戦争の時代になってしまえば、志願しなくてもいずれは兵隊にとられて生死の境に立たされるのである。どうせそうなるなら、志願兵のほうが位が上で、殴られる側ではなくて殴る側だからまだマシだ、ということになる。/だいたい、予科練の制度があった時代というのは、今日とは比較にならないくらい、進学率は低かった時代なのである。中学への進学者は一〇㌫から三〇㌫の範囲だろう。大多数は小学校だけの学歴である。なにしろ日本全体がまだ貧しかった時代で、貧乏だから学力があっても中学へ行けないという少年たちは、自分とおなじか、あるいは自分より成績の悪い同級生たちが進学して上層階層へのパスポートを手に入れてゆくのを、歯ぎしりしながら、横目で睨んでいたものである。/しかし、いっぽう、そういう時代にはそれなりの教育機関もあった。たとえば師範学校である。教員養成のためのこの学校は入学金や授業料を取らないだけでなく、寄宿舎に入れて生活を保障したうえに、わずかではあるが小遣いまで支給した。その代わりとして卒業後は少なくとも何年か、教員になる義務があったが、小学校高等科卒業で受験することができたから、貧しいために中学へ進学できない少年たちにとっては願ってもないようなありがたい学校だった。もちろん、それだけに狭き門であり、競争率は高かった。/師範学校ほど、れっきとした学歴にはならないけれども、他にも公費で勉強させてくれる施設はいろいろあった。国鉄の職員養成所である鉄道教習所、おなじく逓信省の逓信講習所、軍に所属する兵器工場であった陸軍工廠や海軍工廠の工員養成所、などなどである。/(中略)/彼らのその特殊な学歴はそれぞれの役所や企業に内部でしか額面通りには評価されなかったから、彼らは、その役所や企業の子飼いの忠実な中堅技術者になったのである。/こうして、貧しさゆえに進学できないで口惜しがっている優秀な少年のエネルギーを汲みあげ、それぞれの役所や企業の忠実な戦力として役立てる、傍流の進学コースが多様にあったのである。そして、そのひとつが陸海軍の少年兵だった。/以上のような各種のコースは、自ずからその将来性によってランクづけられており、その順位は時代によって変化している。しかし、だいたいにおいて、師範学校と予科練あるいは陸軍少年兵がそのトップのエリート・コースであったと言えるだろう(「わたしの実感としての〝予科練〟」二六二~二六三頁)。
予科練や陸軍少年兵が傍流の進学コースにおけるエリートコースだったという指摘。ここでも私の予科練イメージは変わらざるをえません。当時の写真をみると必ず感じてきた少年たちの誇らしい表情の理由が氷解したからです。また十二~十四歳少年たちの進路についての思いは、ことのほか現実的であり選択的だったと思えることです。選択肢が多様なら将来の自分を客観視できる可能性が高まります。ここがダメならそこというふうに考えることができるからです。にも拘らず予科練に志願して入隊して行った中には、生真面目に皇軍兵士としての自画像にこだわっていた少年も確実に存在したと思えます。エリートとして「選ばれた」という自覚こそは、「特攻」を求めた軍部の<崩れ>を敏感に察知したにちがいないからです。














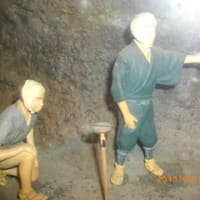




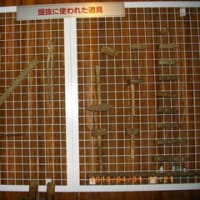
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます