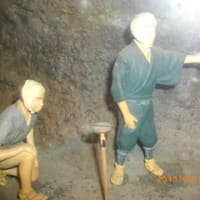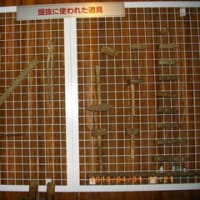前回(昨日)は、コトワザは「表象」と位置づけることができるという、哲学者言語学者・三浦つとむの助言を庄司はどう受けとめたのかを考えました。そこを要約しますと、表象とは論理性と感覚性の両方を伴った認識(シルエットのようだ!)の一つのかたちであると自覚したことは、「前論理学的段階」にあるというコトワザの性格をより鮮明にしていきました。一つはコトワザの感覚性は経験的段階へ、その論理性は論理学的段階へ繋がっていくことで、コトワザを、異なる段階との関連のなかで研究する方向を決定づけていきます。二つはコトワザを、経験的認識と論理学的認識のあいだに位置する「過渡的」段階とみることで、コトワザを認識発展論として研究する方向性を手にするわけです。今回は、三つ補足します。
このような見通しを得た庄司は、おそらくその日(九月二九日)のうちに、三浦のもとに携えて行った資料③「言語教育と科学教育についてのMemo」と資料④「テキスト:試案」を一挙に書き改め、資料⑤「言語教育の体系化への歩み」へと仕上げていったものと考えられます。このようなパワフルな行動を可能にしたのは、いうまでもなく、コトワザ論を「表象論」として展開できるという手応え、そのさきに「自分認識理論の創造」への見通しを得たことです。果たしてそれがどれほどの感動であったのか。以下の引用がこれを雄弁に語っています。
≪この表象論=コトワザ論をいかに展開するかに、自分が自分となるか、他人様の尻にくっついてしまうか、自分の理論をもつ主体的な人間になるかどうか、にかかわる問題といってよいのである。「よいのである」というなまぬるい問題ではない。重にして要なる課題なのだ。コトワザ論という形での表象論は自分の研究の生き死ににかかわることがらなのである。自分の認識理論を構築するキイポイントであり、前段階を統一的につかむ所業なのだ。思えばえらいところにつきあたったものである。自分が真の意味においての人間誕生にかかわる重大事に直面しつつあるという自覚をわたしはもつ。解説家・資料展示者・単なる人様の讃美者・普及者になりおわってしまうかどうか、本ものの思想家となりうるかどうか、という一大時期にさしかかっていることをまざまざと思わざるをえない。≫(「認識理論の創造への出発」、本書八頁)
もうひとつここで記しておきたいことは、これまでも指摘してきたことです。たとえば、ある山頂に立って前方に広い眺望を得たとします。後方をふりかえったとき、登っているときは気付かなかったけれど、斜面がいく筋もの谷川によって削られている風景を目の当たりにすることがあります。そして大きく見れば、どの谷川もその先端が頂上付近に集まっている(正確には頂上付近から発している)ことに改めて気付くのです。庄司の場合にかぎらず、一般になにか新たに研究上の見通しを得たときには、過去の研究蓄積の再編集が一箇所に集中してはじまるのではないでしょうか。このことは、これまでは庄司の論文から拾い出した断片によって確かめてきたのですが、ここでは庄司自身が直接書いているのでぜひ紹介しておきたい。
≪仮説実験授業の体験以前に、はいまわり的にちくせきしたぼう大な児童言語、様々な授業メソッド、大ぎょうにかまえた種々なるりくつ等を瓦礫と化してしまうか、それともつきざる泉として宝の貯水池となしてしまうかそこへ深いかかわりをもつ。そればかりではない、仮説実験授業ならびに予想授業や科学史授業のもつ論理をダイナミックなものとしてとらえて構想する「科学教育」、ひいては「教育」を“学”たらしむるか否かにもじゅうぶんなかかわりをもつ。≫
こうしたかかわりの中枢にあるのがコトワザ論を表象論として展開していく研究ですが、表象について復習するつもりで、三浦つとむの名著『認識と言語の理論(第一部)』に収められている「表象の位置づけと役割」(三浦つとむ選集第三巻『言語過程説の展開』勁草書房 一九八三)に目を通してみました。読んで、「表象」はそもそも認識の能動的な役割を担っていたことに改めて気付かされました。そう、表象は認識の一つのかたちだったのです。しかし、表象的認識は表現されない限り私たちの感覚にふれないわけですから、つい関心は「表現としての表象」に集中してしまいます。でも、これはたいへん多様な世界であることはすこし調べてみれば分かります。
なぜ、「認識としての表象」を忘れていたのかと問われれば、多様性が生みだす面白さにひきずられてきたのかもしれません。また、私の授業実践おいても「表現としての表象」は、子供たちの認識上の「のぼりおり」に重要な役割を果たしていることも分かってきたつもりですが、子供たちにどんな表象を提示すればいいのかと考えてきたことをふりかえると、やはり「表現としての表象」ばかりに気をとられて、「認識としての表象」という根本的な視角を忘れてしまったのだという気がしています。三浦つとむは上記に論文の終りで、「(表象)のような重要な認識の形態が従来の認識論においては軽視され、あるいは無視されている理由はどこに求められるか」を以下のように書いています。これが今回最後に書いておきたいことです。
≪第一に、表象それ自体が矛盾した不明瞭な存在だというところにある。感性的認識か理性的認識か、あれかこれかと割り切ってしまう形而上学的な考え方をすると、表象はいわば中間的な存在であるから、どちらにも入らない中途半端なものは切りすてようということになりかねない。第二は、個々の単純な表象を断片的に扱ったところにある。断片的に他から切りはなしてとりあげるかぎり、感覚にくらべて感性的なものを相当多く失ったその意味で抽象的な認識であるというにとどまってしまう。表象として複雑な発展したありかたを、認識のダイナミックな過程に位置づけてとりあげなければ、その有用性をとらえることができない。第三は、実践との関係で理解しようとしなかったところにある。科学の応用という実践の過程を具体的に検討してみるだけでも、表象の果す役割の重要性はほぼ納得できるのであるが、哲学者もそして心理学者も、認識の発展の中に構造的に実践を含めてとりあげる姿勢を欠いていたのであった。≫(三浦前掲書 四八頁)
表象が軽視されてきた三つの理由が述べられていますが、庄司のコトワザ=表象研究は、すでにこの三つの理由をクリアーしていることが分かります。第一は、表象の「矛盾した不明瞭さ」です。庄司はこの矛盾した不明瞭さを、自分のコトバで「ヌエ的性格」「人魚的性格」「アイノコ的性格」と覚書に連ねています(「認識理論の創造への出発」、本書八頁)。コトバを重ねてその矛盾した不明瞭さを意識立てていることに気付かれると思います。言ってみれば、「表象」のもつあいまいさを、表象的ネーミングによって逆に浮き彫りにしています。曖昧だからこそ面白いとさえ感じていたかも知れません。これも庄司のコトワザ研究の方向性の一つとして数えておきたいと思います。
第二の理由は、表象を断片的に扱ったことです。庄司は表象としてのコトワザを異なる段階との関連において研究しようとしています。これでは表象を軽視も無視もできないはずです。第三の理由は、実践との関係で理解しようとしなかったことを挙げています。庄司は小学校の教室を現場とする研究者です。研究方向の一つである「認識の発展」という問題意識は、目前の子供たちに対する教育実践を構想し計画し実践するという力動的な認識活動のなかに必然的に実現されていきます。ここにも表象の役割は大きかったはずです。
次回から、資料⑤「言語教育の体系化への歩み」(一九六五、九月二九日)に戻り、その言語教育の実践構想や授業後の小学生の感想などから、庄司のコトワザ研究=表象研究の三つの方向、(1)曖昧さの「自覚」、(2)異なる段階との関連性、(3)認識の発展性、の三つがどう実現されていったのか。これを読みとっていきます。庄司のコトワザ研究の始まりにおける「原初のかたち」というゴールが、うすぼんやりと見えてきたようです。