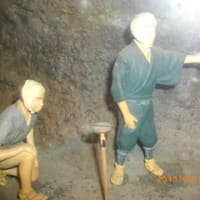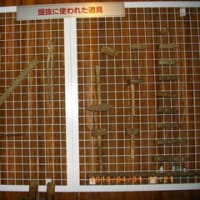今回は残りの(エ)庄司図式の「諺・金言」は、「表象」と位置づけられること、「表象」概念をハッキリ教えた三浦の助言について考えます。ここでまず「表象(ヒョウショウ)」という用語の意味が気になると思われます。ここでは、簡単に以下のように押さえもらえばいいと思います。庄司自身が徐々にこの「表象」概念を深めていく過程を追跡するつもりだからです。まず「表象」とは、私たちがある対象を認識するときに自分で思い浮かべたり、ひとから与えられたりするシルエット(影絵)のような画像だと考えておいて下さい。表象は頭や心に在って人間の認識活動に利用されるのですから、表現されない限り外部からは見えません。また「シルエット(影絵)」といえば、かたち(輪郭)は分かるけれど、それ以外はただの黒い影になって見えません。これに似たものが私たちの頭や心の中で活躍しているのです。このぐらいにして、庄司は、三浦つとむの助言をどう受けとめたのか、彼の叙述から探っていきましょう。
(エ)コトワザは「表象」として位置づけられる
≪さらに、三浦氏は、諺・金言というものを、論理学・認識論的には前論理学的段階であり、それ〔諺・金言というもの〕は無体系であるとともに感性的なものが残っているということにおいて、そのように〔論理学・認識論的には前論理学的段階として〕理解しうるといい、それ〔諺・金言というもの〕のもつ論理は表象としてとらえられているものだ、という。≫
先ず上の長い一文の前半です。「論理学・認識論的には前論理学的段階であり」とはどういう意味でしょうか。まず「論理学」とは、人間思考の法則性(と前に書きましたがここで訂正します)を含んだ、すべての個別学問(科学)に共通な法則性を扱う学問です。コトワザ(諺・金言)は、その前段階に位置するということが「前論理学的段階」ということの意味です。とすれば論理学も前論理学も、結局人間が何かを認識するときに利用される論理(知識)であり、一つの道具ということができます。「認識論的」とは、そういう観点を意味すると考えます。
次に、一文の後半です。このコトワザ(諺・金言)は、「無体系であるとともに感性的なものが残っているということにおいて、そのように理解しうるといい、それのもつ論理は表象としてとらえられているものだ、という。」とあります。コトワザ(諺・金言)は、高次の論理学大系からいえば、たしかに無体系です。たとえば「大は小をかねる」といえば、「しゃもじは耳かきにならぬ」と互いに否定するような表現がたくさんあります。つまり多様な「ものの見方・考え方」が互いに一匹オオカミ的であるために体系にはならないわけです。
また、殆どのコトワザが物事の感覚的なありようを扱った表現になっていることに注目すると、コトワザらしさに心づきます。たとえば「猿も木から落ちる」と「どんなすぐれた人でも失敗することがある」を比べてみれば明瞭ですが、コトワザらしいのは前者でしょう。後者はそれを抽象化したもので、前者の意味を表現するふつうのコトバ使いにすぎません。つまり感性的なものがくっついている論理だというのがミソ(コトワザらしさ)なのです。そして大事なことは、このような「感性+論理」という二重性格をもった認識は「表象」と呼ばれる、とまずは、このように三浦の「表象」論を受けとったことです。このような表象という概念を獲得することによって、コトワザ自体の輪郭をハッキリさせ、庄司のコトワザ研究に方向性がでてきたからです。続きをみていきましょう。
≪つづいて、その〔諺・金言というもの、の〕論理は特殊性の中でとりあげられたものであり、具体的なくらしということでは日常生活に使う道具の論理というすがたで問題になってくる、すなわちコトワザというものは、一方では経験とつながっているからとらえやすいし、他方では論理としてすぐに使えるだけに抽象されていることになる、という。≫
「表象」としてとらえられたコトワザの二重性格を改めて見直すと、コトワザが掬いとった経験則は、体系的な論理学のように広い範囲を扱いそこから普遍的な法則を掬い上げた学問とは異なり、たしかに生活経験という特殊性から導き出された論理です。だからこそ、「日常生活に使う道具の論理」と呼ばれるわけです。たとえば、やってもやっても効果の上がらない作業をしている者たちに、「ざるで水をくむ」というコトワザを使ったとすれば、これは「効果のないことをする」ことへの警告や批判を意味しますが、これは一方で経験則として高次の論理学的段階に繋がります。他方で「ざるで水をくむ」という感性的な側面は、そのような作業をしている経験の世界に繋がっていきます。すなわち、庄司は表象としてのコトワザを、論理への道と経験への道の両極との関連性において理解していることが分かります。最後です。
≪要するに、中間位にある表象、過渡的な段階の表象、そしてそれをこのようなかたちでとらえられている論理なのだ、という。実に示唆に富む、私の図式化への、逆転的で激烈な指針を導入してくれたというわけなのである。≫(以上、「認識理論の創造への出発」、本書七~八頁)
上のひとつの結論は、庄司をしてコトワザとは、「中間位にある表象」だと書かせています。これはだれにでも気づかれることでしょう。もう一つが重要だと思われます。それは「過渡的な段階の表象」だという受けとめです。ここには「認識の発展」という問題意識の端緒が見えます。
まとめますと、三浦のコトワザを「表象」だと指摘した助言は、コトワザの性格を、感性と論理の中間位にあることから、両者の関連性において研究すべきことを自覚させました。またコトワザが、感性と論理のあいだにあって「過渡的」だという受けとめは、コトワザを「認識の発展」という問題意識の中で研究すべきことを促しました。コトワザを「表象」と位置づける三浦の助言は、その庄司のコトワザ研究を、前後の「関連性」に配慮し、「認識発展」の芽を見ていく、二つの方向に決定づけたと考えられます。(つづく)