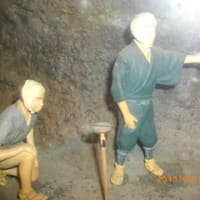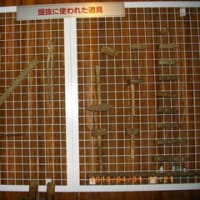前四回のブログで、「三浦つとむからの学び、その核心」(上・中・下・補)と題して、庄司和晃が三浦つとむの助言から学んだ四項目──①「諺・金言」に限定されたもの、②それは「前論理学的段階」、③「コトワザ研究をやってみたら」、④コトワザは「表象」──を「核心」とよび、庄司が獲得したコトワザ研究の方向性を三つ──①コトワザの「矛盾したあいまいさ」の自覚、②コトワザを異なる段階との関連性で研究すること、③コトワザを「認識の発展」という問題意識で研究すること──に整理してみました。そのうえで改めて資料⑤の「言語教育の体系化への歩み」(一九六五、九・二九)を読んでみようと思ったわけです。
これまで私は、庄司が一九六五年の九月二九日に、三浦つとむ『弁証法とはどういう科学か』から得た着想を図式化したもの(A「経験」──B「諺・金言」──C「弁証法」)を含めた資料①「科学の論理形成にさおさすもの」(一九六五、八・十二記)、②「言語教育と科学教育の周辺」(一九六五、九・二二記)、③「言語教育と科学教育についてのMemo」(一九六五、九・二九記)、④「テキスト:試案」(一九六五、九)を携えて、直接三浦のもとを訪ねたという仮定のもとで、庄司のコトワザ研究の始まりを追跡してきました。その根拠は、
≪その後、上記の諸論文とテキスト試案を、三浦つとむ氏にお渡ししたところ、Bの「諺・金言」のことがらについて多大のご示唆を受けた。≫(「認識理論の創造への出発」(一九六五、十一・十七)、本書冒頭に所収)
という記述にありました。しかし、ここで誤読したようです。そう気がついたのは、三浦つとむの追悼集(横須賀壽子 編『胸中にあり 火の柱──三浦つとむの遺したもの』明石書店 二〇〇二)に収録されている庄司論文「体系的な理論づくりを学びとる」を何気なく再読していたら、当時が以下のように回想されていたことに気づきました。
≪「段階」の一事におどろく/問題解決の論理構造、その図式的発見で、コトワザの世界が、新たな文化遺産として、わかってきたとき、このことを三浦さんにつたえたいなあと思いました。/そこで、そのことを綴ったプリント類を送りましたところ、多大の教示をいただきました。≫(前掲書 一四三頁)
たしかに前者には「お渡しした」と書いてあっても、「手渡しした」とは書いていません。後者にはハッキリ「プリント類を送りました」と書いてあります。ウーン、またやってしまったかという落胆が襲ってきて、また「鵜呑みの半助」的性格が出てしまったかと、という思いもやってきましたが、しばし考えているうちに、四種類の資料は郵送したと考えるほうがスッキリすると思い直しました。
というのは、資料③「言語教育と科学教育についてのMemo」と、同じ日付けになっている資料⑤「言語教育の体系化の歩み」(一九六五、九・二九)の関係を解釈するうえで無理がないと思えたからです。当初、私はこう想像しました。庄司は、九月二九日に書き終えた資料③を他の資料ともども、その日のうちに三浦に会いました。そしたらその助言によって、自分の「体内の組織がえ」が一挙に遂行されるような深い共感を得たために、その日のうちに資料③を改稿して資料⑤を作成することになった、と。しかし、資料⑤には三浦と会ってその助言に大きな示唆をうけたことが記述されていてもおかしくないのに、その痕跡がないのを不思議に思っていました。しかもこの資料は三浦に「渡した」なかには含まれていないわけですし・・・。
しかし、九月二九日に資料①~④を郵送したと考えればすっきりします。庄司は送ったその日に、資料の③を、資料④「テキスト:試案」ともども改稿したのだと考えられます。そして、一九七〇年に本書『コトワザの論理と認識理論』を編集する際に、第三部の「言語教育試論と小学生のコトワザ観」の第1章に資料②(「付記」で資料①)を当て、第2章に資料③④を改稿した資料⑤「言語教育の体系化への歩み」を当てたわけです。本書におけるこの論文は一九六五年九月二九日の日付けがありますが、本書への掲載に際して、以下のような「付記」が一九七〇年二月六日付けで、加えられています。
≪「付記」/以上のごとき、おぼえがき的な展開と次に示す実践の中途から、Ⅰの視点〔同資料⑤「言語教育の体系化への歩み」の第Ⅰ節「コトワザの教育への展望をもつ」〕に立ちつつ直接的にコトワザを中核とする言語教育へと収斂していくのである。その教育体系は、第二部の第6章「コトワザの教育過程の体系化」に掲げてみたとおりである。(1970.2.6)≫(本書 七六頁。〔 〕は尾﨑の補足)
この引用から分かるのは、資料⑤にしたがい言語教育構想(「言語教育試論」)を授業にかけている途上で、おそらく、三浦つとむからの「助言」が届き、コトワザを中核とする教育実践へと修正・展開したのだと、いう可能性です。だとすれば、私が縷々綴ってきた「三浦つとむからの学び、その核心」は、まさに庄司の教育実践の渦中で生まれ、その後の展開に活かされたと考えることができます。かえって、その意義深さが腑に落ちたという気がしました。(・・・・紆余曲折ばかりのブログですみません。)