前回(11/16)は、ハナシの発生に関する経済的事情を知りましたが、結局それは室町期における御伽衆などハナシで職業をたてる人々が誕生するなかで生まれたという議論でした。しかし、彼らが苦心して集めた話のネタが、すぐに古くさくなり二度話すと風邪を引くなどと言われたしなめられたことが、世間話がハナシの一派として生まれるキッカケになりました。私は先走って、御伽衆などの面々がハナシのネタを内部から外部に求めるようになることがその契機になったと書きましたが、それが当っているかどうか。これも含めて柳田國男は「世間話の研究」をどう締め括ろうとしているか。最終の第五節を読んでみることにしましょう。
≪(たとえ世間話が上のような契機で生まれたとしても)少なくとも世間話という名は当っている。セケンは実際の日本語においては、今の社会という新語よりも意味が狭い。これに対立するのは土地または郷土で、つまり自分たちの共に住む以外の地、弘く他郷を総括して世間とは言っていたのである。そういう未知の天地に対しては、昔から大きな好奇心はあった。それが最初のうちは昔の昔のその昔に対すると同じく、かなり奔放なる空想を働かして、たとえば孫悟空の『西遊記』を見るように、どんな法螺(ホラ)話でも包容する余地があったのである。ところが遠征が行われ人の往来が時とともに繁くなると、今まで聴いていた話のどれだけまでが本当であり、自分たちの判りきった生活と比べて、どれほど違っているのかにまた新たなる興味が生じた。詳しく説かずとも、近世の欧米に対する我々の知識欲がそのよい例である。これを四五百年前には国内の各地が、互いにゆかしがり(行きたがり)また間違って教えられていたのである。曾呂利新左衛門の逸話中にも多いように、どうじゃ近頃かわった話は聞かぬかなどと、顔さえ見れば先ず尋ねるのが、あの時代の「有識階級」の普通の癖であった。手前が今朝出て参りまする路で、木の鑵子(かんす)で茶をわかしている者がありましたとか、または昨晩は何とか坂の下で、恐ろしいものを見ましたとか、また例のその方がでたらめであろうなどと、けなしながらもそのような話を面白がって聴いていた。この放縦(ほうしょう:わがまま)なる聴衆の笑いずきが、せっかく発達しようとした世間話の若芽を、惨(みじめ)たらしく折りさいなんだ損失は大きかった。茶坊主が野幇間(のだいこ:芸のない素人の幇間ホウカン)となりまたただの取り巻き連となってしまうまで、金のある者のわがままはずっと続いていた。彼らさえ真面目に好い話を求めたならば、いくらでも新しい経験は自分の耳目を煩わさずに、外から供与し得られる時代になってからも、人は代物を払う以上は楽しまされなければ損だという考えがあって、常におおよそ見当のついた書物を買おうとし、または半ば期待し得る講演ばかり聴こうとしていた。そのためにこれほど出版物が多く、誰も彼も饒舌(じょうぜつ)になったにもかかわらず、存外この方面からは自分の養いになるものを得なかった。
ただ今日はもう求めても得られなかった時代とは違っている。以前は引っ込んだ田舎の村々に、世間話を運んで来る人の種類が限られていた。たまたま一人で長旅をして、戻って来た者があっても、そういうのは話が下手であったり、または作り事をするのが容易に露(あら)われた。話には別に劫(こう:永い年月)を経た名人があって、それは行商とか遊歴文人とか行脚(アンギャ:諸国を旅する修行)僧とかの、先き先き世話になり宿主の機嫌を取り結ぶべき者、または旅芸人などのほとんと軽口を専業にしている者であった。どんな話が村の人たちには喜ばれ、もしくは目を円くされるかを知り抜いている上に、まことしやかに地名や人名を取って附ける術はよく解していた。従うて地方の世間話は、いつまでも古い型を脱し得なかったのである。今日はもちろん人文地理の教育も進み、そんな事があるものかという制限は多くなったが、なお根柢(こんてい)において「何か変った話」を聴こうとする態度が跡引くゆえに、せっかく金をやって視察をして来たり、または歴史に伝わるような戦争に出た者が戻ったりしても、彼等もまた努めて奇事珍談のいたってありふれたものを説くに苦心して、まったく聴衆の意外とするような、真実の話を後に残すのであったのである。(次回に続く)≫(「世間話の研究」一九三一、ちくま文庫版『柳田國男全集』第九巻 五二六~八頁)
ここまで来てようやく柳田が短篇「世間話の研究」に何を求めていたのかが分かります。そこを判読するには、引用末尾に見える「何か変った話」」と「まったく聴衆の意外とするような、真実の話」の二つの世間話、両者の質的な相違を読み取る必要があります。前者は、未知の天地に対する大なる好奇心や、世間と郷土の違いに興味をもつ人々に対してその欲求をみたすだけの世間話、または御伽衆として権力者を笑わせる話、あるいは近世に下ると奥まった村々にまで行商・遊歴文人・行脚僧・旅芸人などがもたらす「変った話」などの世間話を意味しています。後者はそのような単に内部にいる者が興味関心を満たすだけの世間話ではなく、「自分に養い」になる世間話です。どのような世間話が我々の「養い」になるというのでしょうか。それは「まったく聴衆の意外とするような、真実の話」のことです。これが柳田の求めていた世間話なのです。自分を養い・聴衆が意外とする・真実の話です。私はこのような世間話とは、人間の様々なかつ真実の生き方が表れている話のことではないか。こう予想して次回の第五節の後半を読んでみたいと思います。














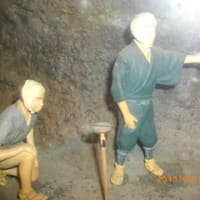




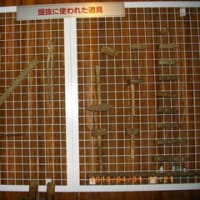
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます