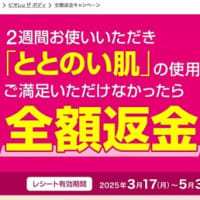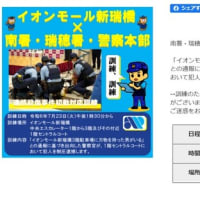東京都立川市の英断 指定喫煙所廃止を決めた
izaより 引用 この記事は 喫煙所撤去が
けしからんという視点でかいてる。
駅前から喫煙所をすべて撤去 東京・立川市の功罪
立川は多摩地区の主要都市として目覚ましい発展を遂げ、
中央線のほか南武線や青梅線、多摩モノレールも通る。
駅周辺にはルミネ、伊勢丹、高島屋といった百貨店、
大型家電量販店などが建ち並び、常に人で賑わっている
ことから、“リトル新宿”と呼ぶ人もいる
立川駅から徒歩10分も歩けば、東京ドーム40倍の広大な
敷地を有する国営の昭和記念公園がある
休日ともなると地元住民のみならず来街者数も膨れ上がる。
立川駅前から指定の喫煙場所が廃止されたのは、2016年7月11日。
立川市は2008年6月に施行した
「立川市安全で快適な生活環境を確保するための
喫煙制限条例」に則り、市内全域での 歩きたばこや
ポイ捨てを禁じてきた。また、立川駅周辺を中心とした
半径250メートル以内の区域と、西国立駅を中心とした
半径150メートル以内では、立ち止まっての路上喫煙も禁止。
2008年より駅前の南北2か所ずつに
指定喫煙場所を設けた。
立川市環境下水道部環境対策課の五十嵐智樹氏がいう。
「条例ができる前は、駅周辺での歩きたばこ喫煙率が
(歩行者全体に対して)2.6%程度だったものが、
喫煙所の整備と啓発活動によって0.15%前後に
まで下がり、ポイ捨てもかなり減りました」
まさに、喫煙者と非喫煙者が共存できる理想的な
駅前環境を整えた、はずだった。ところが、
渋谷区と同じく行政サイドの想定を超える人が
喫煙スペースに押し寄せ、逆に受動喫煙の
被害を訴えるクレームが多く市に寄せられた。
「1か所の喫煙所でピーク時には30~40人が同時に
たばこを吸うため、その大量の煙がビル風によって
近くのバスロータリーや、場合によっては駅の
コンコースの中にまで入り込んでいました。
来街者の方から『立川は駅を降りたらすぐに
たばこの臭いがしたのでイヤな思いをした』
といった苦情もいただくほどでした。
確かに駅のあちこちで見られた歩きたばこや
受動喫煙の対策は、喫煙所を設置することで
一定の効果がありましたが、たばこを吸わない方々の
許容する喫煙者数と煙の量を遥かに
超えてしまったのです」
清水庄平市長が、〈喫煙所からたき火のような
煙がもうもうと上がるのは、この街にふさわしくない〉と、
街のイメージアップの意味も込めて
喫煙場所の閉鎖を決めた-というのが一連の経緯である。
「もちろん、替わりとなるような場所も探しましたが、
適当な場所がありませんでした」と説明し、決して
喫煙者を“排除”しようとしたわけではないと繰り返したが、
結果的には喫煙所に集まっていた人たちの
行き場を失わせることになった。
毎日片道50分かけ、満員電車に揺られて
都内の会社に通っている立川市在住の40代スモーカーが嘆く。
「慌ただしい通勤の行き帰りに駅前の喫煙所で
一服して気分を落ち着かせるのが日課だったので
、吸える場所がなくなって正直ストレスは溜まっています。
喫煙スペースのある喫茶店や百貨店に行けばいいのでしょうが、
朝から喫茶店に入ってコーヒーを飲んでいる時間的な余裕は
ありませんし、帰りも店が開いている時間に帰って
こられるとは限りません。そもそも寄り道をしてまで
たばこを吸うぐらいだったら、
家まで我慢したほうがいいですしね」
市では、前述した駅周辺から半径250メートルの
「特定地区」を外れれば、路上でも周囲に配慮しながら
立ち止まって喫煙することを認めている。特定地区の範囲を
記した地図は駅周辺に多数掲示されてはいるものの、
東西南北どこから先が喫煙可能なのかが分かりにくい。
地元に土地勘のない来街者はなおさらだ。
「路上喫煙禁止地区である旨の路面表示シートを設置し、
その境界線はシートの向きを変えるなど工夫している」
(五十嵐氏)とはいえ、そこまで
足元表示に気を留める人は少ない。
市区町内をすべて路上禁煙、あるいはエリアを細かく区切って
禁煙にしているような自治体に比べれば、まだ立川の方針は
理解しやすい。つまり、駅周辺の人口密度が高いエリアは
受動喫煙の恐れが増すので路上禁煙にし、それ以外の場所
であればマナーを守って自由に喫煙できる。その点では
喫煙者の権利も尊重されている。
「立川モデル」も今後どこまで確立できるかは不透明だ。
厚労省が法制化を目指す受動喫煙防止対策は、
飲食店などを中心に屋内禁煙の範囲を広げ、
屋内を全面禁煙にするのでは、と見られているからだ。
屋内からすべての喫煙者を締め出せば、
屋外で吸える場所を探してさまよう
“喫煙難民”は増える一方だ。
神奈川県・横浜駅の「みなみ西口」付近では昨年末、
それまで17人しか入れずポイ捨ても横行していた
喫煙スペースを大改装し、70人分のスペースを確保し
高い仕切り板もつけた喫煙所に生まれ変わらせた。
歩道には季節の花の鉢植えも並ぶ。
西区長の吉泉英紀氏は、〈これまで横浜市の玄関口として
恥ずかしい状況だったが、きれいに整備することで
汚しにくくなるのでは〉と話した。喫煙者のニーズに
応えることで、むしろマナー向上や街の
イメージ改善に繋げようと期待を寄せている。
一方、国はどうだろう。東京オリンピックに向け、
屋内の喫煙環境に規制をかけることだけにとらわれ、
屋外はいわば自治体任せ。もちろん、人々が多く
集まる駅周辺は、地域住民や来街者も含めた
生活拠点として重要な役割を担う。屋内・屋外の
喫煙環境をどうバランスよく整備していくかは、
受動喫煙防止の観点ばかりでなく、各自治体
による街づくりの根幹に関わる一大事である。
歩きたばこはしない、他人に煙がかからないよう配慮する、
携帯灰皿を持ち歩く--といった最低限のマナーを守った
うえでの路上喫煙の是非、そして屋外での喫煙可能エリアの
基準などについても、今後、国民全体のコンセンサスを
得なければならない問題だろう。ただ喫煙者を
排除するだけでは、何の解決にもならない。
izaより 引用 この記事は 喫煙所撤去が
けしからんという視点でかいてる。
駅前から喫煙所をすべて撤去 東京・立川市の功罪
立川は多摩地区の主要都市として目覚ましい発展を遂げ、
中央線のほか南武線や青梅線、多摩モノレールも通る。
駅周辺にはルミネ、伊勢丹、高島屋といった百貨店、
大型家電量販店などが建ち並び、常に人で賑わっている
ことから、“リトル新宿”と呼ぶ人もいる
立川駅から徒歩10分も歩けば、東京ドーム40倍の広大な
敷地を有する国営の昭和記念公園がある
休日ともなると地元住民のみならず来街者数も膨れ上がる。
立川駅前から指定の喫煙場所が廃止されたのは、2016年7月11日。
立川市は2008年6月に施行した
「立川市安全で快適な生活環境を確保するための
喫煙制限条例」に則り、市内全域での 歩きたばこや
ポイ捨てを禁じてきた。また、立川駅周辺を中心とした
半径250メートル以内の区域と、西国立駅を中心とした
半径150メートル以内では、立ち止まっての路上喫煙も禁止。
2008年より駅前の南北2か所ずつに
指定喫煙場所を設けた。
立川市環境下水道部環境対策課の五十嵐智樹氏がいう。
「条例ができる前は、駅周辺での歩きたばこ喫煙率が
(歩行者全体に対して)2.6%程度だったものが、
喫煙所の整備と啓発活動によって0.15%前後に
まで下がり、ポイ捨てもかなり減りました」
まさに、喫煙者と非喫煙者が共存できる理想的な
駅前環境を整えた、はずだった。ところが、
渋谷区と同じく行政サイドの想定を超える人が
喫煙スペースに押し寄せ、逆に受動喫煙の
被害を訴えるクレームが多く市に寄せられた。
「1か所の喫煙所でピーク時には30~40人が同時に
たばこを吸うため、その大量の煙がビル風によって
近くのバスロータリーや、場合によっては駅の
コンコースの中にまで入り込んでいました。
来街者の方から『立川は駅を降りたらすぐに
たばこの臭いがしたのでイヤな思いをした』
といった苦情もいただくほどでした。
確かに駅のあちこちで見られた歩きたばこや
受動喫煙の対策は、喫煙所を設置することで
一定の効果がありましたが、たばこを吸わない方々の
許容する喫煙者数と煙の量を遥かに
超えてしまったのです」
清水庄平市長が、〈喫煙所からたき火のような
煙がもうもうと上がるのは、この街にふさわしくない〉と、
街のイメージアップの意味も込めて
喫煙場所の閉鎖を決めた-というのが一連の経緯である。
「もちろん、替わりとなるような場所も探しましたが、
適当な場所がありませんでした」と説明し、決して
喫煙者を“排除”しようとしたわけではないと繰り返したが、
結果的には喫煙所に集まっていた人たちの
行き場を失わせることになった。
毎日片道50分かけ、満員電車に揺られて
都内の会社に通っている立川市在住の40代スモーカーが嘆く。
「慌ただしい通勤の行き帰りに駅前の喫煙所で
一服して気分を落ち着かせるのが日課だったので
、吸える場所がなくなって正直ストレスは溜まっています。
喫煙スペースのある喫茶店や百貨店に行けばいいのでしょうが、
朝から喫茶店に入ってコーヒーを飲んでいる時間的な余裕は
ありませんし、帰りも店が開いている時間に帰って
こられるとは限りません。そもそも寄り道をしてまで
たばこを吸うぐらいだったら、
家まで我慢したほうがいいですしね」
市では、前述した駅周辺から半径250メートルの
「特定地区」を外れれば、路上でも周囲に配慮しながら
立ち止まって喫煙することを認めている。特定地区の範囲を
記した地図は駅周辺に多数掲示されてはいるものの、
東西南北どこから先が喫煙可能なのかが分かりにくい。
地元に土地勘のない来街者はなおさらだ。
「路上喫煙禁止地区である旨の路面表示シートを設置し、
その境界線はシートの向きを変えるなど工夫している」
(五十嵐氏)とはいえ、そこまで
足元表示に気を留める人は少ない。
市区町内をすべて路上禁煙、あるいはエリアを細かく区切って
禁煙にしているような自治体に比べれば、まだ立川の方針は
理解しやすい。つまり、駅周辺の人口密度が高いエリアは
受動喫煙の恐れが増すので路上禁煙にし、それ以外の場所
であればマナーを守って自由に喫煙できる。その点では
喫煙者の権利も尊重されている。
「立川モデル」も今後どこまで確立できるかは不透明だ。
厚労省が法制化を目指す受動喫煙防止対策は、
飲食店などを中心に屋内禁煙の範囲を広げ、
屋内を全面禁煙にするのでは、と見られているからだ。
屋内からすべての喫煙者を締め出せば、
屋外で吸える場所を探してさまよう
“喫煙難民”は増える一方だ。
神奈川県・横浜駅の「みなみ西口」付近では昨年末、
それまで17人しか入れずポイ捨ても横行していた
喫煙スペースを大改装し、70人分のスペースを確保し
高い仕切り板もつけた喫煙所に生まれ変わらせた。
歩道には季節の花の鉢植えも並ぶ。
西区長の吉泉英紀氏は、〈これまで横浜市の玄関口として
恥ずかしい状況だったが、きれいに整備することで
汚しにくくなるのでは〉と話した。喫煙者のニーズに
応えることで、むしろマナー向上や街の
イメージ改善に繋げようと期待を寄せている。
一方、国はどうだろう。東京オリンピックに向け、
屋内の喫煙環境に規制をかけることだけにとらわれ、
屋外はいわば自治体任せ。もちろん、人々が多く
集まる駅周辺は、地域住民や来街者も含めた
生活拠点として重要な役割を担う。屋内・屋外の
喫煙環境をどうバランスよく整備していくかは、
受動喫煙防止の観点ばかりでなく、各自治体
による街づくりの根幹に関わる一大事である。
歩きたばこはしない、他人に煙がかからないよう配慮する、
携帯灰皿を持ち歩く--といった最低限のマナーを守った
うえでの路上喫煙の是非、そして屋外での喫煙可能エリアの
基準などについても、今後、国民全体のコンセンサスを
得なければならない問題だろう。ただ喫煙者を
排除するだけでは、何の解決にもならない。