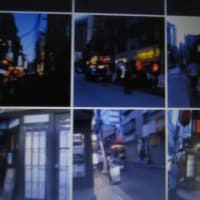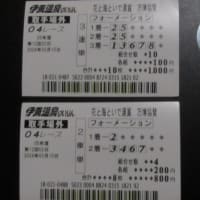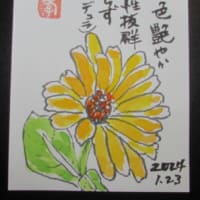過去数十年で最も景気が良い時に政権与党が敗北する。すべての政党がエリートを攻撃する選挙運動を展開し、選挙前よりもエリート主義的な議会が誕生する――。
最近の政治は筋が通らないことばかりだ。いったい何が起きていて、それはなぜ起きているのか。本書は、手垢のつくほど語られてきた民主主義の危機について比較分析から迫る試みだ。
徹底的に歴史とデータを洗う中で、前例なき事態がいくつか見えてくる。
ひとつは、幾多もの戦争や経済危機があったにもかかわらず、過去200年の歴史で30年間にわたって平均所得が減少したことは一度もなかったということだ。これは文明的な規模での変容と言える。
もうひとつは、伝統的な政党制の崩壊であり、弱い政党による激しい党派性だ。
ポピュリストの不満がいくら正当化されるといっても、一時しのぎにすぎない。私たちは依然として他の誰かに支配されなければならず、自分が好まない政策や法律に従わなければならないという避けがたい事実にぶつかる。「何が起こり、何が起こりえないのか」について世界的権威が掘り下げた結論!
[目次]
まえがき
第一章 イントロダクション
Ⅰ 過去――民主主義の危機
第二章 全般的なパターン
第三章 崩壊と生存の歴史
第四章 歴史の教訓——何に注目すべきなのか
Ⅱ 現在――何が起きているのか?
第五章 危機の兆候
第六章 考えられる原因
第七章 何に説明を求めるべきか
第八章 何が前例なきことなのか
Ⅲ 未来は?
第九章 民主主義の機能
第一〇章 隠密な変化
第一一章 何が起こり、何が起こりえないのか
訳者あとがき
人名索引/文献/註/図表一覧
著者について
アダム・プシェヴォスキ(Adam Przeworski)
1940年生まれ。ポーランド出身の政治学者。専門は、政治経済学、政治体制論、民主化研究。ワルシャワ大学卒業、1966年にノースウェスタン大学で博士号取得。ポーランド科学アカデミー研究員、ワシントン大学准教授、シカゴ大学教授を経て、現在、ニューヨーク大学政治学部教授。1991年にアメリカ芸術科学アカデミーの会員に選ばれ、2010年には「ヨハン・スクデ政治学賞」を受賞。主な著書に『それでも選挙に行く理由』(白水社)などがある。
吉田徹(よしだ・とおる)
1975年生まれ。慶應義塾大学法学部政治学科卒業、東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了(学術博士)。北海道大学大学院法学研究科教授、パリ政治学院客員教授などを経て現在、同志社大学政策学部教授。専門は比較政治学、ヨーロッパ政治。主な著作に『ミッテラン社会党の転換』(法政大学出版局)、 『アフター・リベラル』(講談社現代新書)、『くじ引き民主主義』(光文社新書)、『居場所なき革命』(みすず書房)他。
伊﨑直志(いさき・なおし)
1998年生まれ。東京都立大学(旧・首都大学東京)都市教養学部卒業。現在、同志社大学大学院総合政策科学研究科博士前期課程。専門は比較政治学。
1940年生まれ。ポーランド出身の政治学者。専門は、政治経済学、政治体制論、民主化研究。ワルシャワ大学卒業、1966年にノースウェスタン大学で博士号取得。ポーランド科学アカデミー研究員、ワシントン大学准教授、シカゴ大学教授を経て、現在、ニューヨーク大学政治学部教授。1991年にアメリカ芸術科学アカデミーの会員に選ばれ、2010年には「ヨハン・スクデ政治学賞」を受賞。主な著書に『それでも選挙に行く理由』(白水社)などがある。
吉田徹(よしだ・とおる)
1975年生まれ。慶應義塾大学法学部政治学科卒業、東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了(学術博士)。北海道大学大学院法学研究科教授、パリ政治学院客員教授などを経て現在、同志社大学政策学部教授。専門は比較政治学、ヨーロッパ政治。主な著作に『ミッテラン社会党の転換』(法政大学出版局)、 『アフター・リベラル』(講談社現代新書)、『くじ引き民主主義』(光文社新書)、『居場所なき革命』(みすず書房)他。
伊﨑直志(いさき・なおし)
1998年生まれ。東京都立大学(旧・首都大学東京)都市教養学部卒業。現在、同志社大学大学院総合政策科学研究科博士前期課程。専門は比較政治学。
2023年8月7日に日本でレビュー済み