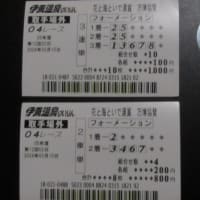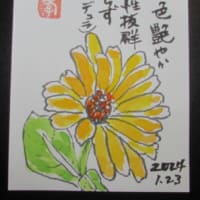三島由紀夫が太宰治を嫌いな理由「顔、田舎者のハイカラ趣味、適しない役を演じた」
文学は「好き」か「嫌い」かに読者を二分してしまう。
近親憎悪、とでも言ったらよいだろうか。
三島がこれほどまでに太宰を嫌ったのは、実は何によりも三島自身がこうした<弱さを演じる強さ>の秘密を熟知してからにほかならない。
近代文学において「自己」を否定してみせるというのはどういうことなのか―安藤宏 東京大学教授
小説家の三島由紀夫が太宰治を大嫌いだったという話はよく知られている。
三島由紀夫が太宰に面と向かって「僕は太宰さんの文学は嫌いなんです」と言い放ったエピソードはあまりに有名である。
これは昭和21年12月のこと、三島が21歳、太宰が37歳の時だという。
三島は「小説家の休暇」で、太宰治を嫌いな理由として3つの理由を挙げている。
私が太宰治の文学に対して抱いている嫌悪は、一種猛烈なものだ。第一私はこの人の顔がきらいだ。第二にこの人の田舎者のハイカラ趣味がきらいだ。第三にこの人が、自分に適しない役を演じたのがきらいだ。女と心中したりする小説家は、もう少し厳粛な風貌をしていなければならない。
引用:三島由紀夫『小説家の休暇』(新潮文庫、昭和57年)17頁
さらに三島は、太宰のもっていた性格的欠陥の少なくとも半分は、冷水摩擦や器械体操や規則的な生活で治せるもので、いわば、けして宿命的なものではないとする。
この箇所の言い回しも面白い。
生活で解決すべきことに芸術を煩わしてはならないのだ。いささか逆説を弄すると、治りたがらない病人などには本当の病人の資格がない。
引用:三島由紀夫『小説家の休暇』(新潮文庫、昭和57年)18頁
さらに三島は太宰の文学と文体について抱く印象を語っている。
太宰の文学に接するたびに、その不具者のような弱々しい文体に接するたびに、私の感じるのは、強大な世俗的な徳目に対してすぐ受難の表情をうかべてみせたこの男の狡猾さである。
この男には、世俗的なものは、芸術家を傷つけるどころか、芸術家などに一顧も与えないものだということが、どうしてもわからなかった。
自分で自分の肌に傷をつけて、訴えて出る人間のようなところがあった。
引用:三島由紀夫『小説家の休暇』(新潮文庫、昭和57年)18頁
そしてこの箇所の最後で三島は、被害妄想というものは相手の強大さをかえって過小評価させるもので、太宰は被害妄想的であったがゆえに、目前の化物のような岩に頭をぶつければ消えると思ってぶつけた結果、自分の頭を砕いてしまったと述べているが、この洞察はやや難解に感じる。
ここではその時の状況を主に三島の「私の遍歴時代」から引用してご紹介する。
また、この「小説家の休暇」は昭和30年ごろ、「私の遍歴時代」は昭和39年ごろ書かれているので、次の「遍歴時代」の自己分析の方が丁寧で公平という印象を受ける。
「稀有な才能は認めるが田舎くさい野心に耐えられない」
「私の遍歴時代」では三島が題名通り、過去を回想しながら文学的キャリアを築くまでのことを書いており、その中で太宰治との有名な面談の話が出てくる。
これは別の記事で引用してまとめたので割愛するが、さらにその前段で三島の太宰への印象論と、当時一大ブームを巻き起こした太宰治の小説「斜陽」に関する批評を書いている。
まず「私の遍歴時代」で三島は、太宰の「虚構の彷徨」の3部作(左翼運動での失敗と心中未遂を題材にした作品)、「ダス・ゲマイネ」(作中に主人公ではない人物として「太宰治」が登場する珍しい作品)といったものから作品にふれたが、太宰のものを読み始めるということは「私にとって最悪の選択だったかもしれない」と語る。
それらの自己戯画化は、生来私のもっともきらいなものであったし、作品の裏にちらつく文壇意識や笈(きゅう)を負って上京した少年の田舎くさい野心のごときものは、私にとって最もやりきれないものであった。
もちろん私は氏の稀有の才能は認めるが、最初からこれほど私に生理的反発を感じさせた作家もめずらしいのは、あるいは愛憎の法則によって、氏は私のもっとも隠したがっていた部分を故意に露出する型の作家であったためかもしれない。
従って、多くの文学青年が氏の文学の中に、自分の肖像画を発見して喜ぶ同じ時点で、私はあわてて顔をそむけたのかもしれないのである。
しかし今にいたるまで、私には、都会育ちの人間の依怙地な偏見があって、「笈を負って上京した少年の田舎くさい野心」を思わせるものに少しでも出会うと、鼻をつままずにはいられないのである。
引用:三島由紀夫『太陽と鉄』(中公文庫、1987年)「私の遍歴時代」146、147頁
三島由紀夫の『斜陽』批判
また三島は、太宰治の出世作となった没落貴族の女性を主人公にした小説『斜陽』について、当時ほかに娯楽のなかった世間の熱狂は大変なものだったと述べてから、そのころ自分が読んだ感想をこのように書いている。
私も早速目をとおしたが、第一章でつまずいてしまった。
作中の貴族とはもちろん作者の寓意で、リアルな貴族でなくてもよいわけであるが、小説である以上、そこには多少の「まことらしさ」は必要なわけで、言葉づかいといい、生活習慣といい、私の見聞していた戦前の旧華族階級とこれほどちがった描写を見せられては、それだけでイヤ気がさしてしまった。
貴族の娘が、台所を「お勝手」などという。「お母さまのお食事のいただき方」などという。これは当然「お母さまの食事の召上り方」でなければならぬ。
その母親自身が、何でも敬語さえつければいいと思って、自分にも敬語をつけ、
「かず子や、お母さまがいま何をなさっている・・・・・・か、あててごらん」
などという。それがしかも、庭で立ち小便をしているのである!
引用:三島由紀夫『太陽と鉄』(中公文庫、1987年)「私の遍歴時代」147、148頁