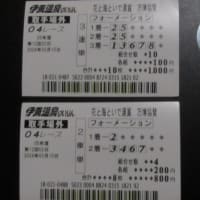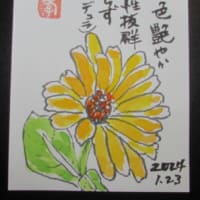生活保護者なのに、3日でその金の大半を失ってしまう男が身近にいる。
パチンコを中心に、現代日本における電子ギャンブルが住民たちの日常生活にどのような影響を与えるかを検討するものである。
電子ギャンブルとはパチンコ、スロットマシンやオンラインギャンブル等、電子機を通したギャンブルのことである。
具体的には、都市空間、ホールの建築やパチンコ機のデザインに目を向け、パチンコ利用者にギャンブル依存を引き起こし、その状態を維持するメカニズムを考察する。
現在、日本は世界の最も大きなギャンブル市場である。
2013 年にパチンコホールの売上は約 27 兆円であった(総務省 2014)。
パチンコホールは道路貨物運送業(23 兆円)や病院(21 兆円)を超える巨大な産業である。
多くの住民が頻繁に利用するコンビニエンスストア産業より規模が三倍近く大きい市場なのだ(コンビニ業界の売上は 2013 年に約 9.4 兆円だった)。
しかし、2014 年の調査によればパチンコ業界の利用人口は 1000 万人も達していない。
日本人口の 8%しか対象になっていない市場であるにもかかわらず、コンビニの売上を上回ることは、遊戯者一人当たりの使用額が非常に大きいということを示すのだ。
パチンコはパチンコ利用者の日常生活に深く浸透しているため、パチンコやパチスロへの依存が原因で、借金、離婚、鬱病、自殺といった深刻な問題に陥いっている遊戯者が多い。
厚生労働省の調査によると、日本の成人人口の約 4.8%は病的ギャンブラーの疑いがあるのだ。
一応違法であるにも関わらず日本はギャンブル大国である。
だが、日本の電子ギャンブルに関する研究が現在まで少なかった。
その上、ギャンブルに関する殆どの研究は心理学の視点から精神病や病的ギャンブラーの精神状態にしか目を向けてこなかった。
日本の電子ギャンブルの考察に当たって社会科学的なアプローチをし、依存を生み出す原因としてモノや空間の役割には注目する研究はない。
Schüll はアメリカのギャンブル機やカジノを研究上で、ギャンブル業界がモノのデザインを通じ人々に依存を引き起こしていることを明かした。
ギャンブルへの依存は個人の本質的な精神状態によって生じるのではなく、人と環境との触れ合いによって生じるため、環境におけるメディアの刺激等に注目すべきである。
日本において、都市空間、建築や機械のデザインはどのようにギャンブル依存を引き起こし、どのように依存を維持させるかを検討する。
日本のパチンコホール店舗数は 11,000 軒以上だ。
ファミリーレストランより多く、また、5軒のコンビニに対して 1 軒のパチンコホールがある?
パチンコホールがない都道府県はなく、全国に広まっているため、多くの日本住民には日常的にパチンコホールへ行くことが可能である。
その上、パチンコホールは住民の生活空間に浸透するような場所に位置している。
多くのパチンコホールは駅と商店街の近くにあるため、通勤、通学や買い物のとき、パチンコホールの前を通る住民は多い。
例えば、筆者がフィールドワークをした京都市では、平日にパチンコホールが混み始めるのは 6 時以降である。
それは明らかに仕事帰りの時間なのだ。パチンコをやめたくても、駅を出るとパチンコホールがあり、その前を通る。そして、我慢できず、つい入ってしまう。
このような人々は少なくない。パチンコホールは日常生活空間において、避けられない場所にあるのだ。
全日遊連はこのほど、6月末時点の組合加盟パチンコ店数を発表。営業店舗数は6,559店舗と5月末時点に比べ、29店舗減となった。
6月の新規店舗数は2(前月同様)、廃業店舗数は40(前月比9店舗減)、休業店舗数は162店舗(同11店舗減)。遊技機の設置台数はパチンコが195万2,834台(同5,141台減)、パチスロが122万493台(同485台減)、総台数が317万3,327台(同5,626台減)となっている。
今年上半期(1~6月)の推移は、営業店舗数が298店舗減、新規店舗数が18、廃業店舗数が322。遊技機の設置台数はパチンコが55,654台減、パチスロが5,566台減、総台数が61,220台減となった。
過去5年の10店舗以上の企業数は、2018年末は194社(4,529店舗)、2019年末は186社(4,412店舗)、2020年末は174社(4,174店舗)、2021年末は164社(3,970店舗)、2022年末は153社(3,695店舗)。そして2023年末は148社(3,571店舗)となりました。
ランクから落ちた社数は9社、10店舗以上の企業で店舗数を増やした企業は26社。店舗を増やした企業は去年に比べて倍増(13→26社)。
この数字だけで見れば、10店舗以上企業の一部は精力的に出店を重ねているといえます。
今年、最も店舗を伸ばしたのはデルパラグループ。
デルパラグループはバージン、VIPから複数店舗を一挙に取得。中国地方で活発に出店。買収店舗のグランドオープンもこれから控えてますし、まだまだ店舗を伸ばしていきそうな匂いがぷんぷんしてます。
次点はNEXUSとハリウッドチェーンでNEXUSは去年と大きな変わりはなく、九州中心に店舗拡大。南九州でディーステーションの知名度はぐんぐん上がってます。
ハリウッドチェーンはM&Aした山口のRITZをGW前に同時グランドオープン。年末も岡山駅前へ新築出店していて、こちらもデルパラ同様、中国地方で活発に出店中。
そしてランキング初登場は低貸の雄、USEI。ほぼ低貸オンリーで運営して新店もオール低貸でグランドオープン。プレオープンを長期間実施、そこから店休で新台入替を行う入念な準備を経てグランドオープンしたのは記憶に新しいところ。個人的にはグランドオープンのロールモデルだなと感じたグランドオープンでした。
そしてランク入り復活したリベラ・ゲーミング・オペレーションズは関東駅前店の買収を重ね、滑り込みランクイン。駅前ノウハウを活かしてこれからの動きが気になる1社です。
そして出店関係のトピックスで避けて通れないニュースは敬愛の全店撤退とガイア民事再生の2つ。
敬愛は今年初頭にあった15店舗を閉店。主要店舗はダイナムがM&A、その他店舗も別法人で営業は続いてます。確か承継が流れたって話もありましたね。その店舗はどうなったんでしょ。
そして世間を賑わせたガイアの民事再生。今のところは営業は継続して従来の営業スタイルは維持できている模様。近年のネガティブイメージが先行している中、色々な意味での信用回復が期待されます。