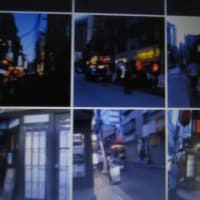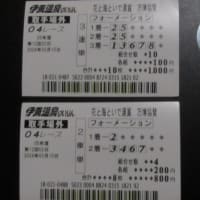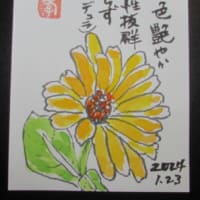直観脳 脳科学がつきとめた「ひらめき」「判断力」の強化法 (朝日新書)
人は何かを決める時に、どのように判断しているのしょうか。
経験やデータをもとに判断する、それとも、直観で?
直観というと、非論理的、非科学的と思われがちです。
しかし、最近の脳科学から、広い範囲の脳を使い、無意識下にある、記憶同士がつながった時、「直観」として優れた意思決定ができることが分かっています。
直観はどのように働いているのか、高めるためにはどうしたらいいのか。
最新の脳科学からみた「直観・ひらめき」について、皆さんに知ってもらいたく近著「直観脳」を出しました。
脳は、集中して時は働いて、ぼーっとしている時には休んでいると思っている方が多いかもしれません。
しかし、脳は休むことなく、いつでも働いています。
最高の意思決定を生み出す極意を、科学的に解説!!
最新研究で、直観を導く脳の部位が明らかになった。
優れた判断をしたいなら、「集中すること」は厳禁。
直観力を高めるためには、むしろ意識を「分散」させることが重要となる。
これまであいまいとされてきた直観のメカニズムを、脳の専門医が解説。
直観を駆使し、「創造力」を発揮するための実践的な思考法も紹介する。
◆本書の構成
第1章:直観を導くメカニズム
第2章:集中してはいけない
第3章:直観をたぐり寄せる「記憶のネットワーク」
第4章:論理的思考を超える
第5章:AI時代の脳の使い方
第6章:直観力を発揮する
私は脳を「予測マシン」として活用する方法を考えているので、本書はとても参考になりました。
まずは脳の記憶について話しましょう。
脳に入力された情報は「海馬の歯状回」へ先ず保存されます。その期間は2~4週間です。
海馬の保存期間中に、その情報が何度も使われると、脳はその情報が「重要な情報」と判断して「側頭葉」の長期記憶に移動します。
長期記憶は4つのカテゴリに分類されます。
・エピソード記憶(固有名詞や出来事の記憶)
・意味記憶(理解したことの記憶)
・手続き記憶(動作に関する記憶)
・情動記憶(情動と結びついた記憶)
これら4つの記憶はさらに陳述記憶(言葉で表せる記憶)と非陳述記憶(言語化しにくい記憶)の2つに大きく分けられます。
・陳述記憶━エピソード記憶と意味記憶
・非陳述記憶━手続き記憶と情動記憶
脳が記憶を処理して予測を行うときには、おもに《集中系》と《分散系》の2とおりの処理活動を行っています。《集中系》と《分散系》を明瞭にカテゴライズできたのは、本書を読んだおかげです。
《集中系》はおもに入学試験、レポート提出、ラブレター作成など意識下で集中して行う脳作業です。
一方、《分散系》はいままで脳に保存された重要な長期記憶をフルに活用する無意識での脳作業です。
こちらの方が圧倒的に多い情報量ネットワークを誇っています。無意識ですから、ある意味ブラックボックスにお任せですから不安もあるでしょう。
不安を解消するためには、日常からゴミ情報を避けて、良質な情報のみを厳選して読んだり、聴いたりしましょう。
ただし自分好みの情報に偏らないような工夫として、反対意見の情報にも同時に耳を傾けたり、自分好みの情報でもクリティカルシンキングつまり批判的な視点を忘れずに耳を傾けましょう。
余談ですが私は来年70歳ですから、若い時と違って忘れることを前提に、情報を脳の外に保存する工夫をしています。
たとえば以下のような
・Kindleで読書中にハイライト機能でマークする。
・本を読み終えたら、ハイライトした個所を「読書ノート」に書き写す。
・読書ノートへ書き写したら、それを基にレビューを作成してAmazonへ投稿する。
・読書やニュース情報、YouTube情報を基に、自分が興味のあるテーマでまとめて、週に約1回のペースでSNS(フェイスブック)へエッセイを投稿する。
こうすると、何かの度に書き留めたアウトプットを読み返して、脳のネットワークを強化することができます。
なお、「海馬の歯状回」では90歳まで新しい神経細胞が誕生しているそうです。そしてひとつの神経細胞を通るネットワークがひとつの情報を「記憶」として保存します。
《分散系》が働いているときは、脳の広い部分が活性化することによって、遠い記憶どうしを結びつけて、新たなものの見方や新しい発見が生まれやすくなります。
脳が「予測マシン」として無意識化で能動的推論を行っていることはご存じだと思います。
私たちは「意識」して意思決定をしていると思い込んでいます。
しかしリベットの有名な実験では、私たちが「意識」する前に、脳がすでに電気信号を発していることが判明しています。私たちは20ミリ秒くらい遅れて、現在起こっている世界を経験しています。
脳を有効に活用するために、私たちは「意思決定」にコミットするよりも、むしろ日常の「情報収集」にコミットした方がよいでしょう。
脳における「記憶の更新」はベイズ・ルールに基づいていることはほぼ間違いありません。
脳は膨大な情報量を計算するために並列計算(パラレル計算)を行っています。
ところが、意識システムでは逐次計算(シリアル計算)を行っています。
本来ならすべての情報を利用するのが最善ですが、なぜでしょうか?
それは意識のネットワーク(パイプライン)はとても狭いので、並列計算を逐次計算に変換して処理しているのです。順番に処理するために、ここでは時間というタイムスタンプ方式がとられています。
各情報の相対的な時間間隔がわかれば、因果性を推論できることになります。
脳は新しい情報を仕入れながら、そのたびに振り出しに戻って大本のデータから見直すなんてことはせずに、新しいデータを加えたら確率予想をアップデートしています。それまでの結論を軌道修正しているのです。
ここにベイズ・ルールが働いています。
科学が発展してきた理由も、ベイズ・ルールと深くかかわっています。
厳密な「時間軸」がなければ、現象が時間発展する力学もその解法である微分方程式も確立されることはなかったでしょう。
ここで思い出してください。
宇宙の小さな領域、例えば地球上で時間を作り出しているのは「エントロピー」と呼ぶ物理量であることを。
エントロピー増大の「時間の矢」によって、全ての事象は過去から未来へ、「秩序」から「無秩序」へ移行しているのです。
つぎに脳のメンテナンスの話をしましょう。
先ずは睡眠です。
脳は睡眠中に「シナプスの刈込み」を行っています。余分な記憶を消去しています。
そのためには起きているときに、しっかり学習しましょう。
次に学習です。
学習をすると、省エネで情報処理ができるようになります。
さまざまな課題で学習すると、「フレーム・オブ・レファレンス(参照系)」が拡がって、脳が活性化すると同時に、思わぬ”ひらめき”が得られることがあります。
とくに脳はリザーバー計算に長けています。私たちの脳はボーっとしているときでも活発に働いています。
「メタ学習」はリザーバー計算を人為的に利用している学習方法です。
いくつかのタスクを脳のネットワークに学習させると、学習によりダイナミズムを獲得して、新しいタスクに対しても高い計算性能を示すようになります。
高度な数学、外国語学習、脳科学、コンピュータサイエンス、これらを学習することによって、多様性と再現性の刺激が脳のリザーバー機能を高めることができます。
つぎにリラクゼーションについてです。
脳が”ひらめく”タイミングは、散歩しているとき、ボーッとして海を眺めているとき、シャワーを浴びているとき、いわゆるデフォルト・モード・ネットワークのときに起こります。
眺めの良い部屋と静かな環境は欠かせないでしょう。
環境といえば、個人的にはできれば気候ストレスも避けたいと思っています。
今年の冬から沖縄での避寒生活が始まります。
音楽もいいですね。
歌詞があると注意が行ってしまうので、読書や思考中にときどきジャズのインスツルメンタル音楽を聴いています。
ほかに小川のせせらぎや小鳥のさえずりなどのリラクゼーションミュージックも有効です。
こうした自然界にある音には振動数に反比例、つまりf分の1揺らぎが多く存在します。
f分の1揺らぎは脳にとって倍音構造を生じやすくなり、心地よくなれることが分かっています。
そうそう、木々の木漏れ日にもf分の1揺らぎは見られますよ。