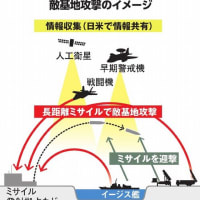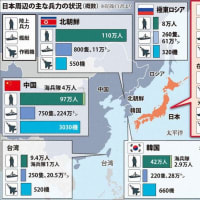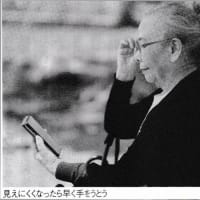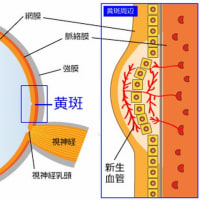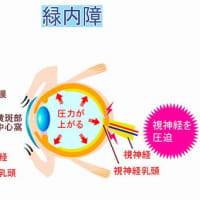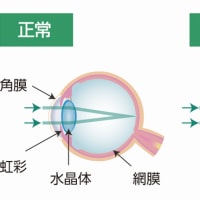小堀 遠州(政一)
小堀 遠州(政一) 大名、茶人、建築家、作庭家。備中松山藩第2代藩主
大名、茶人、建築家、作庭家。備中松山藩第2代藩主 松山で柚子を使い、ゆべしを考案、銘菓となった
松山で柚子を使い、ゆべしを考案、銘菓となった BS11「国宝を訪ねて南禅寺塔頭金地院より」より引用
BS11「国宝を訪ねて南禅寺塔頭金地院より」より引用






小堀遠州(ネットより引用)
 小堀遠州の生涯
小堀遠州の生涯 豊臣秀吉の給仕を務め、利休とも出会っている
豊臣秀吉の給仕を務め、利休とも出会っている 秀吉直参となり伏見に移り、遠州は古田織部に茶道を学ぶ
秀吉直参となり伏見に移り、遠州は古田織部に茶道を学ぶ 秀吉が死去後、徳川家康に仕え、関ヶ原の戦の功により備中松山城を賜う
秀吉が死去後、徳川家康に仕え、関ヶ原の戦の功により備中松山城を賜う 修築の功により、従五位下遠江守に叙任され、以後この官名小堀遠州で呼ばれるようになる
修築の功により、従五位下遠江守に叙任され、以後この官名小堀遠州で呼ばれるようになる 晩年は、伏見奉行を務めながら茶の湯三昧に過ごし、伏見奉行屋敷にて69歳で死去
晩年は、伏見奉行を務めながら茶の湯三昧に過ごし、伏見奉行屋敷にて69歳で死去 小堀遠州の建築&庭園等の作事
小堀遠州の建築&庭園等の作事 公儀作事の主な業績は、松山城の再建、駿府城修築、名古屋城天守、宮中や幕府関係の作事奉行の働き
公儀作事の主な業績は、松山城の再建、駿府城修築、名古屋城天守、宮中や幕府関係の作事奉行の働き 準公儀として、品川東海寺、水口城、伊庭御茶屋、大坂城内御茶屋も作事している
準公儀として、品川東海寺、水口城、伊庭御茶屋、大坂城内御茶屋も作事している 京都の寺では、南禅寺塔頭金地院内東照宮や方丈側の富貴の間、茶室および庭園、庭園など準公儀の作事
京都の寺では、南禅寺塔頭金地院内東照宮や方丈側の富貴の間、茶室および庭園、庭園など準公儀の作事 他に遺構建築物は、妙心寺塔頭麟祥院の春日局霊屋、氷室神社拝殿他多数あります
他に遺構建築物は、妙心寺塔頭麟祥院の春日局霊屋、氷室神社拝殿他多数あります 小堀遠州の庭園の作風
小堀遠州の庭園の作風 織部の作風を受け継ぎ発展させ、特徴は庭園に直線を導入したことである
織部の作風を受け継ぎ発展させ、特徴は庭園に直線を導入したことである 御所で実施した築地の庭や桂離宮の輿寄の「真の飛石」が小堀好みです
御所で実施した築地の庭や桂離宮の輿寄の「真の飛石」が小堀好みです 種々な形の切石を組み合わせた、大きな畳石と正方形の切石を配置した空間構成です
種々な形の切石を組み合わせた、大きな畳石と正方形の切石を配置した空間構成です 小堀遠州茶の湯
小堀遠州茶の湯 茶の湯は、現在ではきれいさびと称され、遠州流として続いています
茶の湯は、現在ではきれいさびと称され、遠州流として続いています 和歌や藤原定家の書を学び、王朝文化の美意識を茶の湯に取り入れました
和歌や藤原定家の書を学び、王朝文化の美意識を茶の湯に取り入れました 茶室においては、織部のものより窓を増やし明るくしました
茶室においては、織部のものより窓を増やし明るくしました 生涯で約400回茶会を開き、招いた客は延べ2,000人以上と言われる
生涯で約400回茶会を開き、招いた客は延べ2,000人以上と言われる 小堀遠州の華道
小堀遠州の華道 美意識は、華道の世界にも反映され、江戸時代の後期に特に栄えました
美意識は、華道の世界にも反映され、江戸時代の後期に特に栄えました 流儀は、正風流・日本橋流・浅草流の三大流派にその規矩が確立された
流儀は、正風流・日本橋流・浅草流の三大流派にその規矩が確立された 流派は、花枝に大胆で大袈裟な曲をつける手法という共通した特徴があります
流派は、花枝に大胆で大袈裟な曲をつける手法という共通した特徴があります